| |
 |
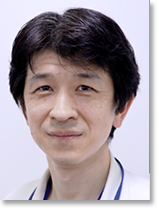 |
Y-CIRCLEの代表を務めます上木(じょうき)と申します。2022年4月より、この研究会の創立者で前代表である高橋竜哉先生から引き継ぎました。皆様、どうぞ宜しくお願いします。
この横浜脳卒中・リハ連携研究会、略してY-CIRCLEですが、2008年1月31日に横浜市立大学附属市民総合医療センター(当時の事務局)と連携して回復期リハビリテーション病棟を持つ4つの病院とで第1回の世話人会が開催されました。このとき制定された会則には、「医療連携の強化、臨床に関する情報交換の場の提供、市民への疾患啓発、合わせて会員の親睦を図ることを目的とする」とあります。当時は急性期病院が事務局の病院1つしかありませんでしたが、急性期病院の参加施設が増えた現在でもこの目的の本質は変わりません。2009年4月に事務局が横浜医療センターへ移動となり、複数の急性期病院と連携する回復期リハビリテーション病院、地域のクリニックの先生方にも御参加いただき、現在に至っております。
参加医療機関が増加し、研究会の参加人数も増えた現在でも、変わらないこの研究会の目的は具体的に以下の通りです。
① 急性期病院と回復期リハビリテーション病院とが、脳卒中
患者に対してどのような医療、ケア、リハビリテーション
がなされているのかをお互いに知ることにより、より円滑な
連携を実現すること。
② 医師のみならず、看護師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、
言語聴覚士、社会福祉士など様々な職種の人に幅広く参加して
もらい顔の見える医療連携を実現すること。
③ 多職種が顔を合わせる場を提供することにより生じた様々な
交流を通じて、地域の医療水準を上げることに寄与すること。
④ 最終的には円滑な連携や地域医療の水準上昇を地域の患者や
市民の皆様に還元すると同時に、脳卒中について市民の皆様
に広く知っていただくこと。
上記目的のために、現在、年に2回の研究会と年に1回の市民公開講座を開催しています(注: 現在はコロナ禍の影響で、市民公開講座の開催を中断しております)。
脳卒中の医療を取り巻く環境はめまぐるしく変わっています。急性期治療としてはt-PAを用いた血栓溶解療法や血栓回収療法などの治療により脳梗塞の予後は大きく向上しましたが、そのためにはいち早く治療を始めることが大事であり、一般市民の皆様が発症にいち早く気付くこと、救急搬送体制を整えること、病院の受け入れ体制や院内体制の整備、必要に応じて急性期病院の連携体制など、様々な体制作りがおこなわれてきました。急性期治療を経て後遺症が残っている場合には速やかに回復期リハビリテーションへ移行し、日常生活や社会生活への復帰を目指します。自立が難しい場合でも退院後の生活の場の環境調整をおこないます。このような脳卒中患者の退院に向けた支援をおこなうため、日本脳卒中学会が認定するPSCコアと呼ばれる一次脳卒中センターの中核施設では、脳卒中相談窓口の設置が2022年度以降、順次進んでいます。
また、脳卒中は予防も大事です。高血圧、糖尿病、脂質異常症などの管理に加えて、脳梗塞を既に発症した方の場合には抗血栓薬(血液を固まりにくくする薬)も必要となります。特に心房細動と呼ばれる不整脈は心原性脳塞栓症の原因となり、しばしば重度の後遺症を残すので予防は重要です。これには脳神経外科や脳神経内科だけではなく、関連する診療科、そして普段はかかりつけの先生に総合的に診ていただく必要があります。
これらは1つの医療機関でできるものではなく、また医師だけでできることでもありません。複数の医療機関(急性期医療機関、回復期リハビリテーション病院、かかりつけ医)、複数の職種(医師、看護師、薬剤師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士、介護支援専門員など)が連携を取ることで初めて実現できます。そのためには普段から顔の見える連携が大切であることを現場の医療従事者は実感しています。そのための礎となるべくこの研究会の活動を継続していきますので、今後とも宜しくお願いします。 |
|
|
|

