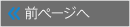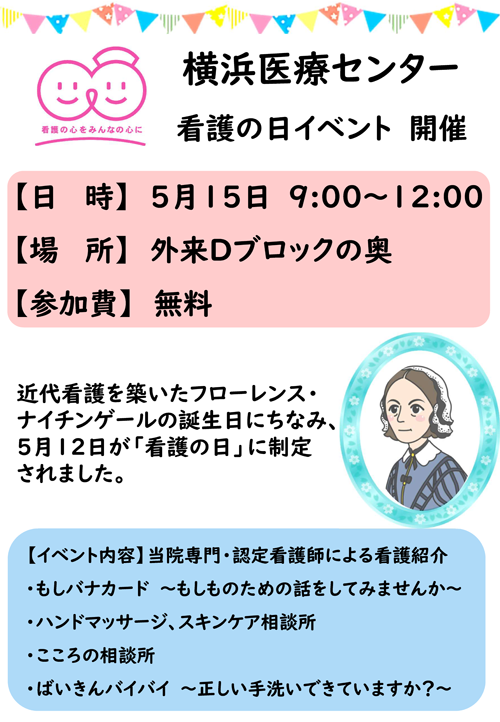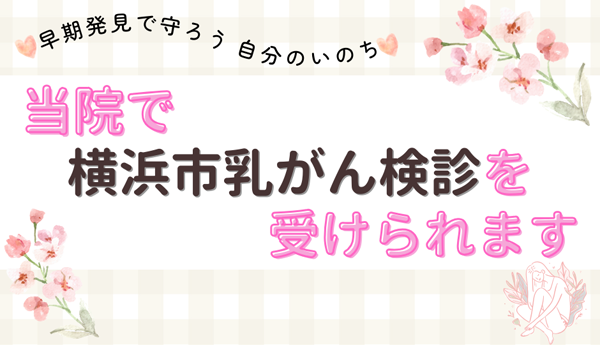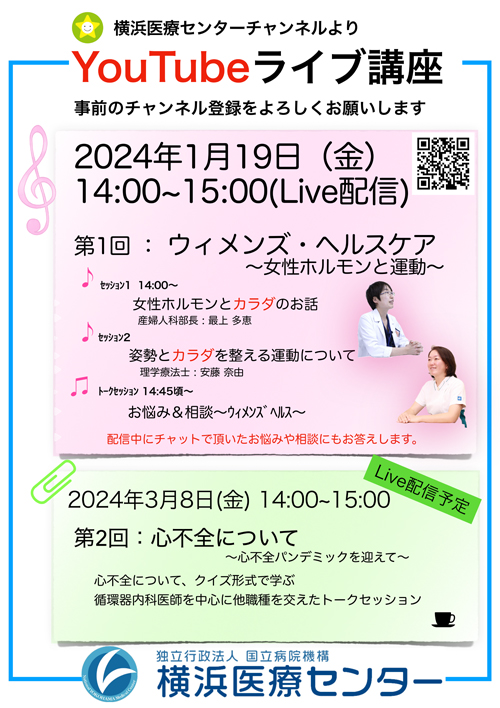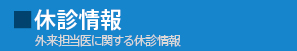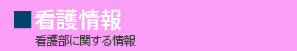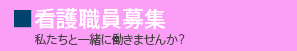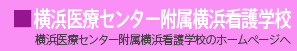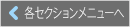
横浜医療センター ブログ
以下のカテゴリーをクリックしていただくとそのカテゴリーのブログを閲覧できます
■新型コロナ ■病気・けが ■診療 ■医師 ■看護師・助産師
■コメディカル ■チーム医療 ■ホスピタリティ
■地域医療連携 ■地域交流 ■研修・講演・公開講座 ■看護学校 ■時事

病院で働く人たち(地域医療連携室事務のお仕事)
2026年02月20日
こんにちは
気が付けば2月も半ばを過ぎました。先日の週末には雪が降り病院の敷地にもふんわりと白い雪が積もりました。
普段はあまり雪が積もらない地域なので、朝に真っ白な景色を見ると、少し特別な日を迎えたような気持ちになります。

週末にあれだけ白く染まっていたのに、月曜にはすっかり日常の景色に戻っていて雪の解ける速さには本当に驚かされます。
さて、今回のブログでは、地域医療連携室にスポットを当てて病院の日常をお届けします。
地域医療連携室は、その名の通り、地域における医療の連携のために必要な業務を行う部署です。事務職、看護師、医療ソーシャルワーカーが配属され、医師等と連携しながら働いています。その中で今回は事務のお仕事を紹介します。
私たちは、地域住民の皆さんの症状悪化時などに、地域のクリニックから救急受入依頼を受け、当院医師へのつなぎの窓口や受診調整などを行っています。患者さんの症状が落ち着いた後は、患者さんがご自分に適した医療機関を受診することができるよう、地域の病院やクリニックと連絡を取り合って、受診の調整をし、必要であれば紹介状の申込み受付や発送するなどしています。
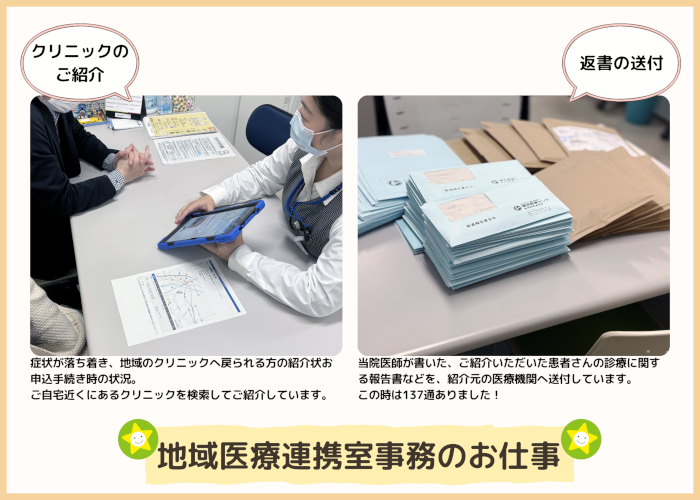
また、患者さんにとってわかりやすい案内を行うため、当院ホームページにある「かかりつけ医を探す」の検索ページを充実させ、院内でも患者さんご自身やご家族がかかりつけ医を探せるように、パンフレット棚やチラシを随時更新しています。
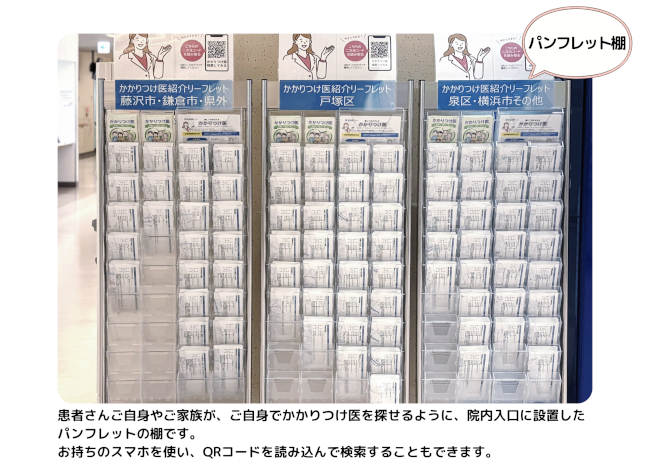
私たちは、紹介された患者さんの入口、出口のサポート役として円滑な受診・治療につながるように、日々業務に取り組んでいます。
かかりつけ医が見つからないなどでお困りの際にはぜひご相談ください。
連携室全員で、皆さんのお力になれるよう一緒に考えていきます!
これからもいろいろな病院のお仕事をご紹介していきます。
次号もどうぞお楽しみに。
病院で働く人たち(庶務係のお仕事)
2026年02月06日
こんにちは。
新しい年が始まってひと月ほどが過ぎ、ようやく日常のペースが戻ってきた頃でしょうか。
とはいえ寒さはまだまだ続きますので、どうぞお身体にはお気をつけください。
さて先日、当院では職員を対象とした献血を実施しました。
約2時間の実施時間の中でしたが、12名の職員が献血に協力することができました。

検査の結果、基準に達せず献血ができなかった職員もいましたが、自身の健康状態を見直す良い機会となりました。職員一人ひとりが自分の健康と向き合うことは、安心・安全な医療を提供するための大切な土台でもあります。
当院では今後も、職員の健康を大切にしながら、地域医療や社会への貢献を続けていきたいと考えています。

こうした病院の取り組みや日々の医療活動は、医師や看護師だけでなく、さまざまな職種の職員によって支えられています。
今回はその中から、私が所属している「庶務係の仕事」について紹介いたします。
私の仕事は、設備に不具合が起きたときの調査や修理の手配、病院スタッフが出張に行くための交通費の計算、院内での患者さんの呼び出し放送など、病院が円滑に機能するためのサポートを行うことです。
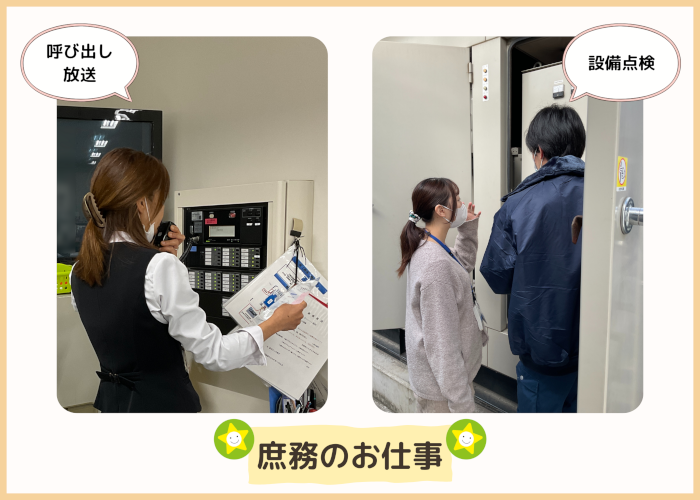
仕事で大切にしていることは、「現場で働く人の声に耳を傾けること」です。医療従事者の方々が安心して患者さんと向き合えるよう、困っていることや改善したいことを一緒に考え、少しでも働きやすい環境を作ることを心がけています。
患者さんと直接お話しをする機会は少ないですが、病院に来院された際に安心して過ごしていただけるようにこれからも裏方からサポートしていきます。
医療スタッフだけではない人たちが病院を支えていることを少しでも思いだしていただけると嬉しいです。
病院のお仕事紹介はまだまだ続きます。
次号もぜひ読んでください。
病院で働く人たち(広報部のお仕事)
2026年01月23日
こんにちは。
1月も早いものでもう半ばですね。
お正月飾りや鏡餅などを片付けるといよいよ本格的に新しい一年が始まった気がします。
さて当院では、先日消防訓練を行いました。病棟で火災が発生した想定で、対策本部の立ち上げや避難誘導、担架での搬送など、声を掛け合いながら真剣に訓練に取り組みました。

今年もこれまで同様、病院を身近に感じていただけるよう働いている人や部門を紹介していきたいと思います。
今回は、その中から「広報部」をご紹介します。
広報部は、宮崎副院長をはじめとした6名で構成されています。
ホームページやブログ、各種SNSの更新、広報誌の発行など、病院の“今”を様々な媒体に載せて発信しています。
院内でカメラを持って歩き回っている職員がいましたら、おそらく広報部ですので、お気軽にお声掛けください。

これからも、皆さまに病院の情報をわかりやすく、楽しくお届けしていきますので、ぜひご期待ください!
2026年 明けましておめでとうございます
2026年01月09日
お正月が明けて最初の週末を迎えました。
皆さま、年末年始はどのようにお過ごしになられましたか?
元旦はよく晴れて暖かいお正月でしたね。
箱根駅伝では、当院近くの戸塚中継所を通るので、職員の中にも応援に行った!という人やテレビで中継を見ていたという人も多くいました。
お正月気分から抜け出せないところですが、少しずつ日常に戻れるように体を慣らしていきましょう。
また、年末年始はおいしい食事を食べたりお酒を飲む機会が沢山ありました。
こちらも普段の食生活のリズムに戻して、体を動かすなどして整えていきましょう!
本年も当院の様々な情報を発信していきますので、横浜医療センターブログをよろしくお願いいたします。

2025年 ありがとうございました!
2025年12月26日
先週12/17に当院附属の看護学生が、入院中の患者さんへクリスマスカードを届けにきてくれました💌
その後、全学年の学生がグループに分かれ、各階のデイルームにて和やかな雰囲気の中で「あわてんぼうのサンタクロース」と「サンタが街にやってくる」の2曲の歌のプレゼントを贈ってくれました。
最後は患者さんから「パワーをもらえた!」などとお礼の言葉をかけていただき、みんなが笑顔になれる楽しいイベントとなりました🎄
学生の皆さん、ありがとうございました。

そして12/19には当院の職員が利用する院内保育園で少し早めのクリスマス会が行われました。
保育者が「先生サンタさんを探してくるね!」と言って廊下を探しに出ていくと「あれぇ~サンタさんが来てくれたよ!!」とサンタさんが登場し、子どもたちは固まって視線は一点集中!
サンタさんが「みんなにプレゼントを持ってきたよ」と子どもたち一人ずつにクリスマスプレゼントを渡してくれました。驚いて泣いてしまうかな?と思われましたが、泣かずに足早にプレゼントをGETしていました。園長先生が「サンタさん、握手してもらっていいですか?」というと子どもたちも続いて握手をしてもらうことができました。
プレゼントのお礼に、「あわてんぼうのサンタクロース」を歌ってもらうと、子どもたちの上手な歌声にサンタさんもつられて一緒に歌っていました。

特別なクリスマス会を終えてたっぷりお昼寝したあとは、こちらもまた大興奮のおやつバイキング!普段は保育園で食べられないおやつも食べることができて、子どもたちは大喜びの1日でした。
皆さんはどんなクリスマスをお過ごしになりましたか?
(当院のクリスマスの様子はXでも投稿しています。併せてご覧ください)
本ブログをいつもご覧いただきありがとうございます。
年内の診療は本日までとなり、新年は1月5日から通常診療を行います。
どうぞ良いお年をお迎えください。
地域医療をつなぐ大切な一日――「病病・病診連携の集い」を開催しました!
2025年12月19日
11月27日(木)、横浜医療センター附属横浜看護学校にて、年に一度の「病病・病診連携の集い」を開催しました。
この会は、当院と連携する病院や診療所の先生方をお招きし、講演や懇親会を通じて交流を深める場です。今回は100名以上の方々にご参加いただき、当院からも医師・看護師など50名以上が参加しました。

横浜医療センターの取り組み
横浜医療センターは、横浜南西部地域の中核病院として、患者さんに最適な医療を提供することを使命としています。地域の医療機関に対しても、様々な症例研究会などを開催したり広報誌等を発行するなどして、当院の専門性(強み)や現状の取り組みなどを発信しています。
また、当院は完全紹介制の医療機関であり、地域のかかりつけ医等の先生方からのご紹介で患者さんに受診いただいています。普段は書類や電話でのやり取りが中心ですが、こうした対面での交流は、より良い連携を築くためにとても重要だと考えています。
第1部:講演会
第1部では、当院脳神経内科部長・上木英人医師が「これからのMCI・認知症診療と地域医療連携」をテーマに講演しました。
認知症の一歩手前の状態であるMCI(軽度認知障害)の時点での対応の重要性、また仮に認知症になっても急に何もできなくなるわけではなく、正しく理解して対応することで希望を持って自分らしく暮らし続けられるんだという考え方など、地域全体で医療・ケア体制を構築する必要性についてお話ししました。


第2部:懇親会
講演後の懇親会では、医師だけでなく看護師、メディカルソーシャルワーカー、事務職員など、幅広い職種の方々との交流を楽しみました。ざっくばらんな会話を通じて、日頃の連携をさらに深めることができた有意義な時間となりました。
ご参加いただいたみなさま、本当にありがとうございました。

今後に向けて
横浜医療センターは、これからも地域医療の発展に向けて、さまざまな取り組みを続けてまいります。患者さん、地域の医療機関、そして地域住民のみなさまに信頼される病院であり続けるために、情報発信や連携強化を進めていきます。
今後ともご支援・ご協力をよろしくお願いいたします。

褥瘡勉強会(MDRPU)を実施しました
2025年12月12日
今週月曜日に毎年恒例の正面ロータリーのイルミネーションが点灯しました✨
外来ロビーにはクリスマスツリーが飾られ、クリスマス仕様になっております。


さて、今日は当院の褥瘡対策委員会が主催した勉強会についてご紹介します。
「褥瘡」とは皆さんご存じかもしれませんが「床ずれ」のことをいいます。褥瘡委員会では入院患者さんの褥瘡予防を目的に勉強会を開催しています。具合が悪くて動けないとき、同じ場所が圧迫されることによって皮膚の血流が途絶え褥瘡になりますが、これ以外にも入院中の患者さんは数々の医療機器を使うため、その圧迫でも褥瘡ができてしまうことがあります。医療機器による褥瘡は「医療関連機器褥瘡:MDRPU」と呼ばれています。当院は急性期病院であるため、褥瘡・MDRPUの発生率が高い状況です。
私たちの身近なところだと、マスクの着用で耳の付け根や鼻の頭が痛くなったご経験はありませんか?マスクのゴムの圧迫やノーズフィットなどで肌が荒れたりしてしまうこともMDRPUの一つです。
看護師はこの皮膚トラブルの見分け方や、発生した場合の対策やケアについて正しい知識をもつことが必要です。また実際に装着・体験することで患者さんの気持ちや苦痛を理解し看護に生かすことも目的としています。
また、過去にもご紹介してきましたが当院には患者さんの様々なご不安・お困りごとに対して、各分野を得意とした資格をもつ専門・認定看護師が存在しており、褥瘡の分野においても「WOCナース:皮膚・排泄ケア認定看護師」が活躍しています。
今回はWOCナースを中心に院内の看護師に向けて勉強会を開催し、職員たちは日々アップデートされている情報を再確認し、学ぶことができました。
今後も患者さん一人ひとりの状況に合わせて医療関連機器を活用し、適切なケアができるように知識を高めていきたいと思います。

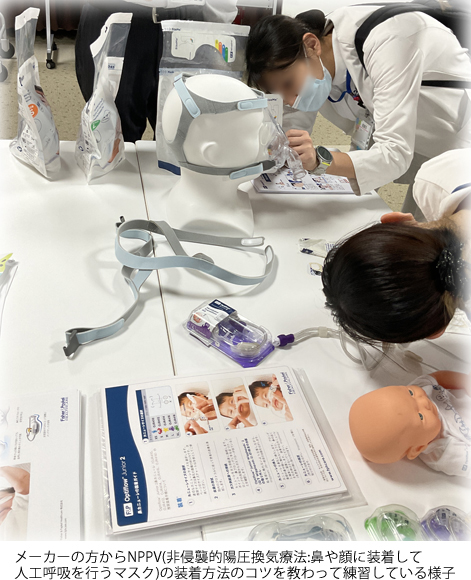
看護部就職説明会を実施しました
2025年12月05日
12月に入り、今年も残り1か月となりました⛄
少しずつ大掃除を始める方もいるかと思いますが、ケガや事故などなさらぬようお気を付けください。
さて、学生の方々はそろそろ就職活動を意識する時期でしょうか。
来年から本格的に始まると思いますが、どんなスケジュールで就職活動を進めていくのか下調べをしておくと安心ですね。
当院では看護部が附属の看護学生に向けて就職説明会を実施しました。
当院からは6名の看護師が参加し、複数のグループ病院にもご参加いただきました。

当院附属の看護学校であっても、学生のみなさんの進路は様々ですので、横浜医療センターの魅力をしっかりお伝えしてきました!


事前に学生に行ったアンケートの質問に看護師が答える時間があったのでこちらの内容を少しご紹介します。
【業務でわからないことはすぐに聞くことができる環境ですか?】
⇒看護師2年目でまだまだわからないことがありますが、すぐに聞くことができる環境です。自分から聞くことはもちろんですが、先輩からも大丈夫?わかる?と気にかけてもらえるので相談しやすいと感じています。
【精神的にきついと感じることはどんな時ですか?】
⇒仕事をしていても勉強は必要になるので大変だなぁと感じています。1年目で慣れていないときは帰宅してすぐに眠ってしまう日々でした。横浜医療センターでは病院にいる間の時間に勉強会や研修を行ってくれるので家に持ち帰ることなく時間を有効に使えています。
その後、グループに分かれて看護師としての知識や心得についてはもちろん、気になる通勤方法や夜勤制度、人気の病棟は?寮はきれい?など素朴な疑問にも先輩看護師にたっぷり教えてもらい説明会を終了しました。

これから就職活動を控えている皆さん、体に気を付けて頑張ってください😊
当院に興味がある方、是非お待ちしています✨
採用情報はこちら
国立病院総合医学会に参加しましたin金沢
2025年11月28日
11月も終わりの頃となり、二十四節季では静かに冬の到来を告げてくれる時季となりました。
寒い日がだんだんと増えてきたので、暖かくしてお過ごしください。
さて11月7日~8日にかけて国立病院総合医学会が開催され、全国の国立病院(国立病院機構、国立高度専門医療研究センター及び国立療養所等)の施設から約6000名の職員が参加し、様々な発表や討議が行われました。

当院からは5名が座長として参加し、42名の医師、看護師、薬剤師、事務職員がそれぞれの分野について発表を行うため参加しました。
参加した広報室長からコメントをいただきました。
「今回の学会では、最新の医療技術や診療体制の改善に関する発表のほか、最近のトレンドでもある生成AIやRPA(Robotic Process Automation)を活用した業務の効率化に関する発表も多かったです。
今回の学会で得られた知見を活かし、より良い医療提供体制の構築に貢献していきたいと考えています。」
金沢の会場へ行かれた職員の皆さま、おつかれさまでした。
毎年恒例のお土産写真をご紹介します📸
なお、当院公式Xでも#室長レポートで金沢カレーや学会中の様子の写真をUPしました✨
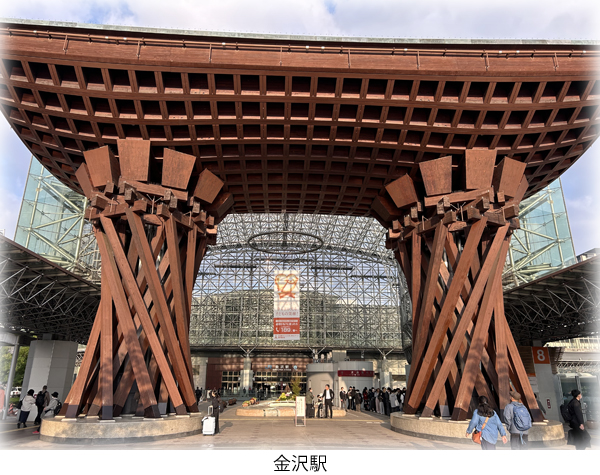




秋のイベントがひと段落して体調を崩している方を多く見かけます。
また例年よりも早い段階でインフルエンザが流行しています。
気持ちの良い気候が続いているので外出の機会も多く、街の中も賑わっておりますが引き続き感染対策をしていきましょう。
【過去のブログはこちら】
・国立病院総合医学会に参加しましたin大阪
・国立病院総合医学会に参加しましたin広島
院内イベントを開催しました!
2025年11月21日
先週11月14日の「世界糖尿病デー」にちなんで当院ではイベントを開催しました。
「世界糖尿病デー」は、糖尿病の脅威が世界規模で拡大していることを受け、予防や治療の重要性についての注意喚起を目的として国際糖尿病連合と世界保健機関によって制定されています。
当日の外来では血糖値測定や握力測定などを実施し、特に血糖値について「やってみたい!」と多くの方が興味をもって参加されていました。


また、午後には主に入院患者さんを対象に講義を行い、「糖尿病になったからと言ってお先真っ暗という時代は少し前の話です。現在は糖尿病で日ごろから通院されている方のほうが他の病気に早く気付くことができます。また、病気と付き合いながら長生きされている方も多くいます。これは今までに糖尿病を患った患者さんが治療を頑張って続けていることが蓄積されたデータで分かってきていることです。糖尿病の治療の目標は血糖値を下げることではなく、病気がない人と同じように皆さんが楽しく人生を歩むことです」とお話されました。
続いて、今週11月19日にはがん患者サロン「たんぽぽ」を開催しました。
理学療法士が「がんに負けない体づくり」について患者さんやご家族の方と交流を行い、おしゃべりをしたり簡単な運動をしたりしました。
スタッフたちも一緒に楽しんで盛り上がりましたよ。
その中でも深呼吸については「意外とできていないかも?」と言われており、心配や不安な気持ちを落ち着かせることができるので良い方法だと教えていただきました。病気や年齢に関係なく自律神経を整えることや頭痛の改善にもつながるとのことですので皆さんも試してみてはいかがでしょうか。
呼吸を整えることは、患者さんにとって大切なことのひとつで、前向きな気持ちを持つことにつながり、「体を動かしてみよう!」という気持ち作りにも効果的だそうです💪
日ごろから取り入れられる体操をたくさん教えていただいたので、またブログでご紹介したいと思います。

今後も、患者さんの健康促進に貢献できるようなイベントを積極的に実施していきたいと思います。
ブログやXで随時お知らせしていきますので、チェックしていただけると嬉しいです😊
戸塚ふれあい区民まつり参加レポート
2025年11月14日
2025年11月3日(月・祝)に戸塚ふれあい区民まつりに初めて参加させていただきました。
来場者数やグラウンドいっぱいに展示されるブースなど、予想以上の規模に驚くことばかりでした。準備していた配布グッズも、すぐに配り終えてしまうほど、多くのみなさんにブースにお立ち寄りいただき、とても楽しい時間を過ごすことができました。
暖かい声をかけてくださった方々ありがとうございました。
また、ご協力をいただいた関係者の皆さまへ感謝申し上げます。

今回のイベント内容ですが、横浜医療センターのブースでは病院にまつわるクイズを4問出題しました。産科ブースでは手形足形アートなどを行い、約130名のお子さんにご参加いただきました。看護学校ブースでは赤ちゃん抱っこ体験が人気で「なつかしい重み」、「これから孫が産まれます」「兄弟が産まれるので抱っこの練習をしてみたい」など様々な年齢の方に体験いただきました。
ご参加いただいた方には当院のオリジナルグッズを配布しました。
是非ご活用いただけると嬉しいです✨
ドタバタと駆け抜けてきましたが、これから改善点をあげて次年度以降、また参加できるように取り組んでいきたいと思います。
今後とも横浜医療センターをよろしくお願いします。

院内イベントのお知らせ
2025年11月07日
今週11/3に無事に「戸塚ふれあい区民まつり」への初参加を終えました。
沢山の方にご参加いただきありがとうございました。
引き続きイベントが盛り沢山なので、こちらの様子はまた後日レポートしていきたいと思います。
ご協力いただいた関係者の皆さま、ありがとうございました。

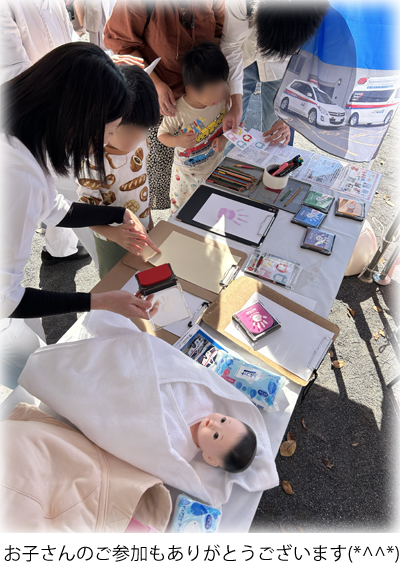
📢11月の院内イベントのお知らせです。
■2025年11月14日(金) 10時~13時「糖尿病デー」
ご来院の際にはお立ち寄りください。
■2025年11月19日(水) 14:00-15:00
がん患者サロン「たんぽぽ」~がんに負けない体づくり~
理学療法士が講義を行いながら簡単なストレッチを行う予定です。
がん患者さんとそのご家族の方ならどなたでも予約不要でご参加可能ですので是非ご参加ください。
また、本日から石川県金沢市にて「国立病院総合医学会」が開催されています。
毎年全国の国立病院機構から6000人ほどが集まる大きな学会です。
当院からも多くの職員が演題発表を行うために参加しています。
ここ最近は発表の準備で院内もバタバタと賑わっておりました。
皆さんの発表が大成功に終わりますように!!
公式Xでも国立病院総合医学会の様子を投稿していきますので是非のぞいてみてください🎵
市民公開医療講座「100年元気プロジェクト」開催報告
2025年10月31日
気が付けば10月も終わりですね。病院敷地内のイチョウも少しずつ色づいています。
朝晩は冷え込むようになりましたのでくれぐれもお体にはお気をつけてお過ごしください。
さて、10/26(日)に当院で、市民公開医療講座を開催しました。
あいにくのお天気で、同日開催を予定していた「とつか原宿ふれあい祭り」が中止となり非常に残念でしたが、多くの方にお越しいただきとても嬉しく思いました。
ご参加いただきありがとうございました。


地域の方々との交流を目的として、当院での会場では初めての開催となりました。
第一部の整形外科部長伊藤医師の講演では、「いつまでも健康で楽しい生活を送るために」という内容で、平均寿命と健康寿命の比較など興味深いお話をしていただきました。

第二部の館理学療法士の講演では「転ばないための健康体操」をテーマにクイズをしたり、みんなで一緒に簡単な体操を行いました。
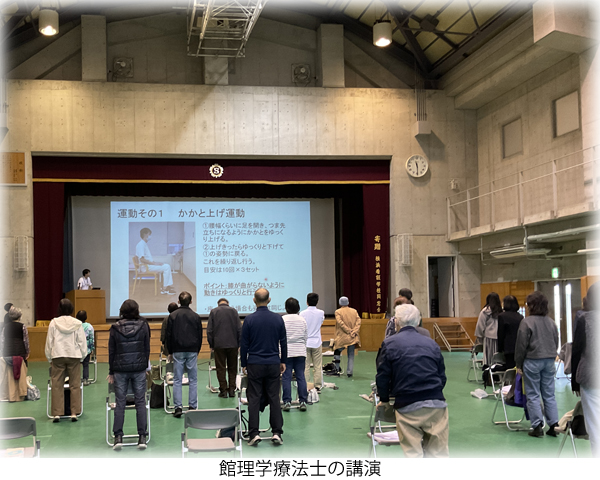
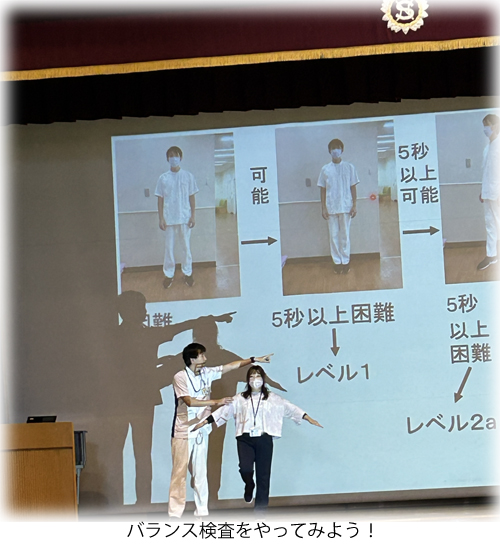
最後は、今回の会場となった附属横浜看護学校の出来立てホヤホヤの紹介動画を特別に初お披露目させていただきました。
ご来場いただいた方にはオリジナルグッズをプレゼントしました(*^^*)

アンケートで寄せられた改善点を次回に活かし、今後もイベントの企画や地域のイベントに積極的に参加していきたいと思います。
原宿商店街の方を始め、ご協力いただいた皆さまのご支援に感謝申し上げます。
次回11/3(月・祝)戸塚ふれあい区民祭りに初参加します!
横浜医療センタークイズや産科コーナーでは手形・足形アートなどを行う予定です✨
皆さまのご来場を是非お待ちしております!
JMS開催報告
2025年10月24日
先週、10/19(日)に当院で、JMSプログラムを実施しました。
JMSプログラムは毎年10月の第3日曜日に全国で乳がん・マンモグラフィー検査が受診できる取り組みです。
当院では全員女性の医師・技師が対応しており、患者さんからのアンケートでもメリットに感じていただける患者さんが多くいらっしゃいました。
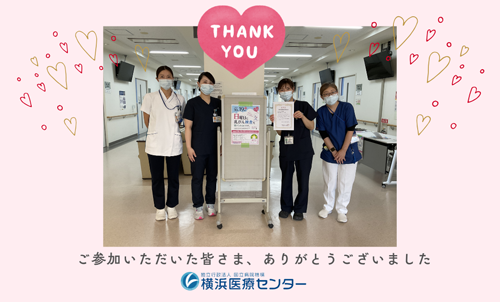
また、アンケートの中ではこれまでJMSプログラムの取り組みについて知らなかった方もいらっしゃいましたが、地域の回覧板を始め、院内ポスターやホームページ等、様々な広報媒体で知っていただけたことがわかりました。
皆さまの健康を促進する情報ツールとして、今後も広報部では地域の方のお力をいただきながら必要な情報を発信していきたいと思います。
なお、今年のJMSプログラムは終了となりますが、引き続き多くの方に受診いただけるように当院では平日毎週月曜日と金曜日に受診が可能ですのでこちらもご覧ください。
JMSプログラムにご参加いただいた皆さま、関係者の皆さま、ご協力いただきありがとうございました。
\最後に今週末のイベントのお知らせです/
■2025.10.25(土) 看護学校「楓葉祭」10:00-14:00
■2025.10.26(日) とつか原宿ふれあい祭り10:00-14:00 ※雨天中止
当院から、栄養ブースでは健康相談、産科ブースでは赤ちゃん抱っこ体験や手型・足型アート(未就学児対象)、ドクターカーブースでは乗車体験ができます。
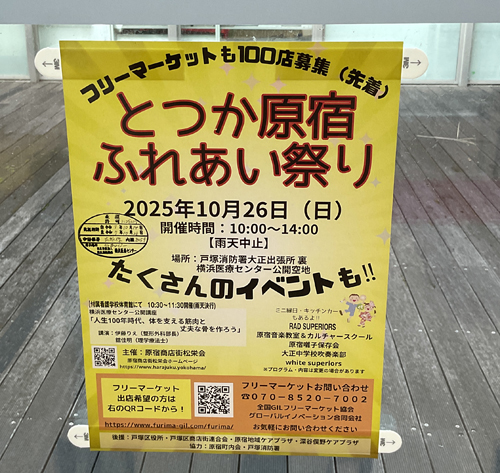
■2025.10.26(日) 市民公開医療講座『100年元気プロジェクト』10:30-11:30 ※雨天決行
お天気が心配されますが、沢山の方のご来場をお待ちしております❣
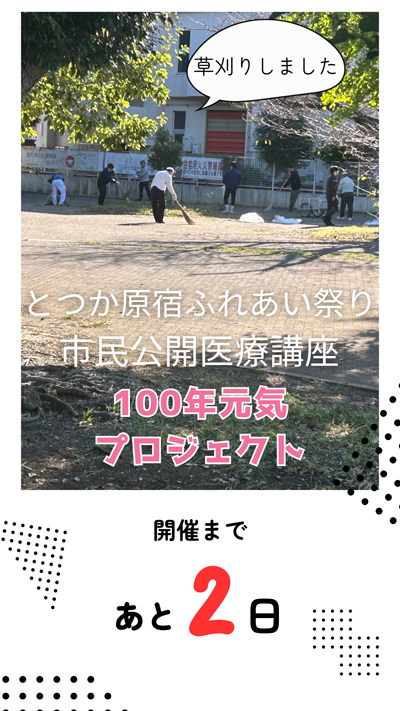
マイナ保険証のスマホ対応を始めました
2025年10月17日
今週はスッキリしないお天気の日が多かったですね。
気圧の影響で体調を崩されている方も多いようですので頭痛やめまいの症状に注意していきましょう。


さて、当院ではスマホ対応のカードリーダーを設置しました。
マイナ保険証については、使い慣れてみると便利さを実感されている方もいらっしゃるのではないでしょうか?
そして今回のスマホ対応により、マイナ保険証が不要となり、簡単に利用できるようになりました。
とは言っても、まだ開始されたばかりなのでやり方がわからないという方も多いと思います。
現在広報部ではiPhone版とAndroid版の2つのショート動画を作成中です。
「え、全部同じじゃないの?」と思われますが、それぞれ異なる操作方法ですので近日中に公開できるように準備を進めています。
無事にUPできた際にはまたお知らせしていきますので、是非チエックしてみてください。
また、市民公開医療講座「100年元気プロジェクト」の開催まであと9日となりました。お時間ある方は是非ご参加ください。お待ちしています。(詳細は10/10のブログをご覧ください)
“X”でも最新情報をUPしていきますので是非よろしくお願いします!
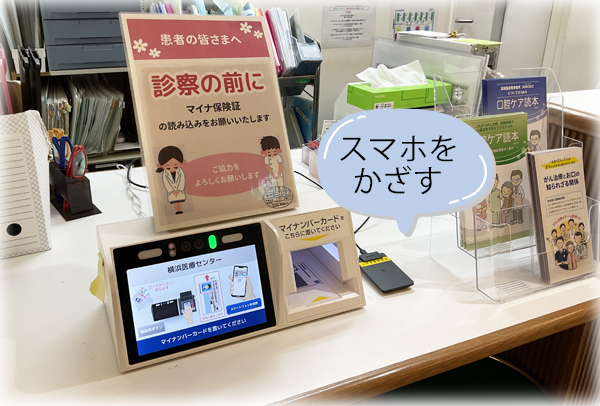

イベントのお知らせ🎈
2025年10月10日
敷地内の木々が色づき始め、夕方になると綺麗な夕焼けが見られて気持ちの良い秋になってまいりました。
週末は各地で秋のイベントや運動会が開催されており賑わっていますね。
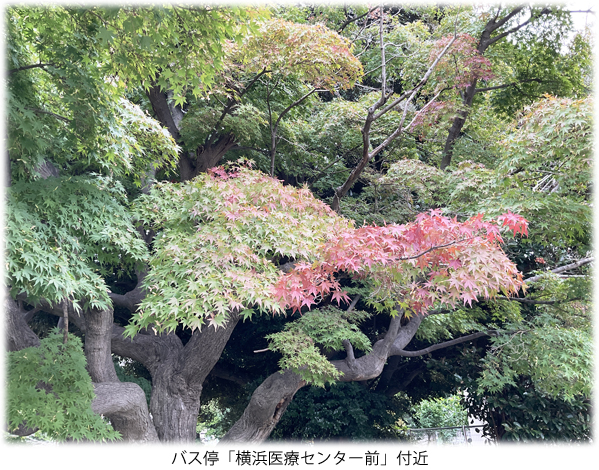

当院でも10/25(土)看護学校「楓葉祭」、10/26(日)原宿商店街主催「とつか原宿ふれあい祭り」が開催されます。
とつか原宿ふれあい祭りでは、当院のブース出展を行います。
ブースでは、栄養管理室:栄養相談、産科:手型・足型アート(未就学児対象)、赤ちゃん抱っこ体験、車両展示:ドクターカー乗車体験を行います。
また「とつか原宿ふれあい祭り」コラボ企画として、敷地内にある附属看護学校の体育館で公開医療講座を開催します。(*雨天決行)
当院整形外科医師による、人生100年時代に備えて丈夫な骨をつくるための秘訣や理学療法士による隙間時間でできる健康体操を実演で紹介します!
ご参加される方は動きやすい服装でお越しください。
現在、広報部ではイベント開催に向けて準備が大詰めです。
地域の皆さまと楽しく交流できることを楽しみにお待ちしています。
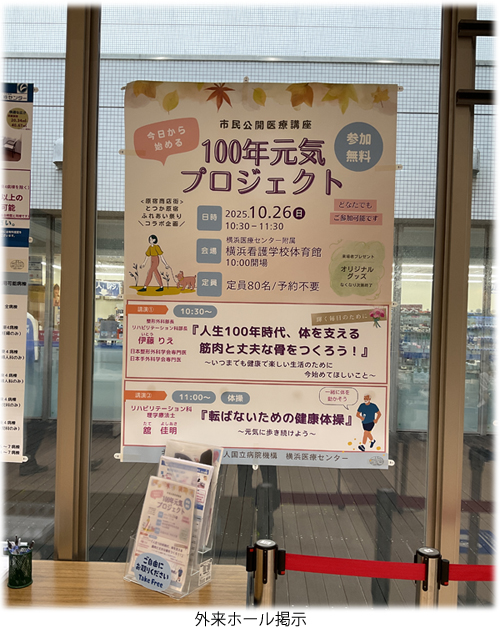
そして、11/3(月・祝)には「戸塚ふれあい区民祭り」に初参加します。
こちらの情報は順次お知らせしていきます。
“X”でも情報発信中です!是非チェックしていただけると嬉しいです。
新人看護師研修vol.2
2025年10月03日
10月に入りました🍂
1日を通して涼しい日が増えてきていますが、まだ昼間は季節外れの暑さになる日もあるようなので屋外で長時間過ごされる方は引き続き注意していきましょう。
さて、今回の新人看護師研修のテーマは「酸素療法・モニター管理・輸血療法」についてです。
盛り沢山の研修内容だったのですが、「酸素療法とモニター管理」について学習する様子をブログでご紹介します。
現在、新人看護師たちは患者さんの受け持ちが始まっており、先輩看護師の元で指導を受けながら、より高度な技術が必要になってくる時期です。
酸素療法については、4月のオリエンテーション時に講義は行ったものの、実演は行っていなかったので教育担当看護師長の発案で今回の研修に組み込まれました✨
医療酸素ボンベは誤った方法で扱うと、破裂や火災事故の原因となり、患者さんや看護師もやけどを負う危険性があるため、適切な取り扱いの知識が必要です。
グループごとに分かれて医療メーカーの方から直接説明と指導を受けました。


同時に、酸素は24時間つけているからOKではなく、心電図や酸素飽和度などのモニター管理を行って異常の早期発見に努めることが重要です。
新人看護師は技術の面や判断が必要な場面で悩むことや不安に感じることが多いといわれているので、毎月の研修は理解度を確かめられる良い機会です。
今後も安全な医療の提供を行えるように看護師のレベルに合わせた教育研修を定期的に行っていきます。

【循環器内科】生活習慣病の予防について
2025年09月26日
毎年9月は厚生労働省で『健康増進普及月間』と定めて各地で様々な活動が行われています。
出典:「スマート・ライフ・プロジェクト」(厚生労働省健康づくりサポートネット)
今回は生活習慣に着目して、当院の循環器内科医師に「高血圧」についてお話を聞いてみました。
Q1.「日本人に高血圧が多い理由にはどのような原因がありますか?」
A.高血圧には様々な要因が関与していますが、特に日本人では食塩摂取量が多いことが知られています。2019年の調査では10.1g/日と諸外国と比較し3g/日程度多くなっており、味噌や醤油など塩分を多く含む調味料が多いことが要因になっています。また最近では食生活の変化に伴い、肥満による高血圧も増えてきています。
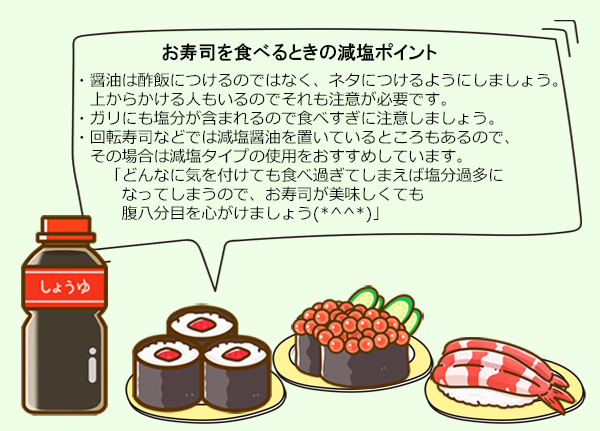
Q2.「急に血圧が上がる原因とはどのような時ですか?怒ってイライラしたり長距離運転など一時的に緊張してドキドキしたりは血圧に関係しますか?」
A.痛みや不安、緊張で交感神経が刺激されると人間の血圧は高くなります。一過性の血圧上昇はよくあることで、30分程度の安静で改善します。むしろ一過性の高血圧で治療を行うことは推奨されていない上、降圧薬の効果も乏しいです。ただし何の誘因もなく急激な血圧上昇をきたす疾患もありますので、頭痛や発汗を伴うような血圧上昇がある際は病院の受診が望ましいです。
Q3.「高血圧は放置するとどのような病気になりやすいですか?」
A.高血圧は血管に負担をかけ動脈硬化を起こす、脳卒中、冠動脈疾患の最大の危険因子です。脳血管病死亡の約40%が120/80mmHgを超える血圧高値に起因していると推定されています。また認知症、慢性腎臓病、心不全や心房細動のリスクも上昇します。
Q4.「予防・改善につながる食べ物、運動について教えて下さい。」
A.まず減塩を心がけることが大切です。カリウムを多く含む野菜や果物、低脂肪牛乳等の摂取もおすすめです。野菜は1日350 g、果物なら1日200 gが目標です。不飽和脂肪酸の摂取もリスク減少効果があるので、肉類より魚を主とするのが良いでしょう。ただし糖尿病や慢性腎臓病などの加療中の方は推奨されないものもありますので、主治医の指示に従ってください。また節酒、禁煙も効果的です。
運動は、息ははずむが会話できる程度の強さのウォーキングなどの有酸素運動を毎日30分以上、少なくとも10分以上継続し、150~300分/週を目標にしましょう。あわせてスクワットなどのレジスタンス運動を1日20分、週に2~3回取り入れるのもよいです。
Q5.「立ち仕事、座り仕事など高血圧に注意が必要な仕事はありますか?」
A.立ち・座りにかかわらず、長時間の同じ姿勢や睡眠不足、ストレスは高血圧発症リスクを上げます。また夜勤従事者は高血圧リスクが高いことが知られています。6時間以上の睡眠を心がけましょう。
Q6.「塩分のとりすぎは良くないと言われていますが、実際の食事での摂取量の把握のコツや工夫できることはありますか?」
A.塩分の目標は6g以下です。スーパーやコンビニで売っている食品には食塩相当量が記載されていますので、そちらを参考に計算して調整しましょう。加工食品や外食は塩分が多く、注意が必要です。塩分が少ないと最初は物足りなく感じるかもしれませんが、レモンや香辛料で味を工夫すると続けやすくなります。

高血圧はそれだけでは症状に乏しく、普段から意識することが難しいかもしれません。ただ収縮期血圧を10mmHg下げることで脳卒中、心臓病が2割減ると言われており、適切な血圧コントロールが将来のあなたの助けになることは間違いありません。私達もお手伝いしますので、ぜひ血圧について一緒に考えていきましょう。お気軽にご相談ください。

キルギス共和国 研修プログラムに協力しました
2025年09月19日
9月も半ばとなりましたが残暑が続きます。
長く感じられる夏ですが、少しずつ日の入りが早くなり、秋への変化が感じられます。
最近は秋バテという言葉を耳にしますので、猛暑を乗り越えたからだをしっかり休めて秋支度をはじめましょう🍂
さて、少し遡りますが今年の春に、キルギス共和国の保健省職員や国立循環器治療センターの医師ら7名と国際協力機構(JICA)関係者5名の皆様が横浜医療センターに来訪されました。
初めに宇治原院長から、「医療は国境を越えて人々の健康を守る重要な役割を果たしています。キルギスの皆様と知識と技術を共有し合うことで、世界中の患者さんにより良い医療を提供できると信じています。どうぞ私たちの施設を自由に見学し、スタッフと交流し、たくさんの質問をしてください。皆様の学びが深まり、今後のキルギス国の医療活動に役立つことを心から願っております」と挨拶をしました。

その後、当院の森診療部長から『日本の三次救急における循環器内科医の役割』について講演を行い、研修員が自国・自院の発展のため、様々な質問をしていた姿が印象的でした。
講義前に行われた森診療部長からの挨拶では、キルギス国は、日本人と顔つきがそっくりと言われ親日国と知られていることから、「今日、お会いしてみて、非常に日本人と顔が似ている」と話すと、それまでは到着したばかりで緊張されていた研修員の皆さんが笑いに包まれ和やかな雰囲気になりました。

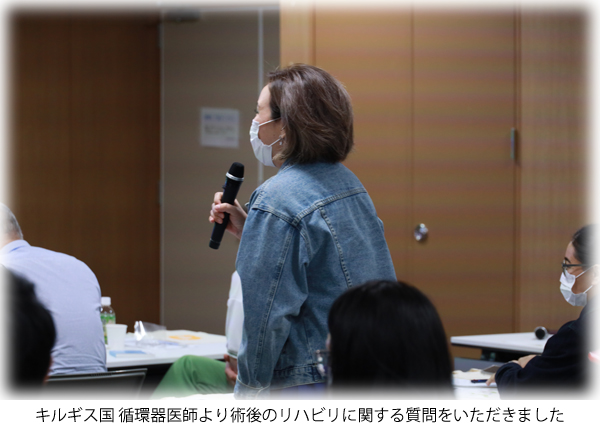
そして、ICU、カテーテル室、初療室を見学いただきました。
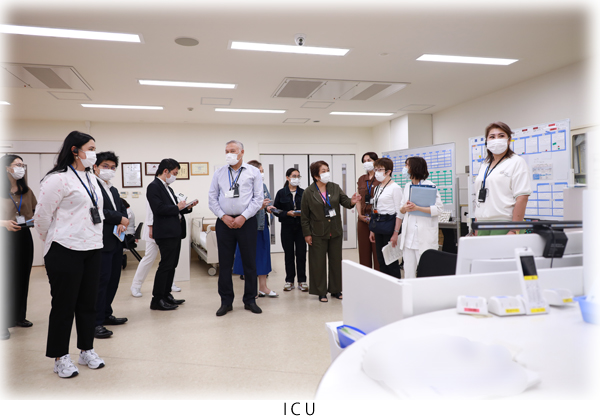


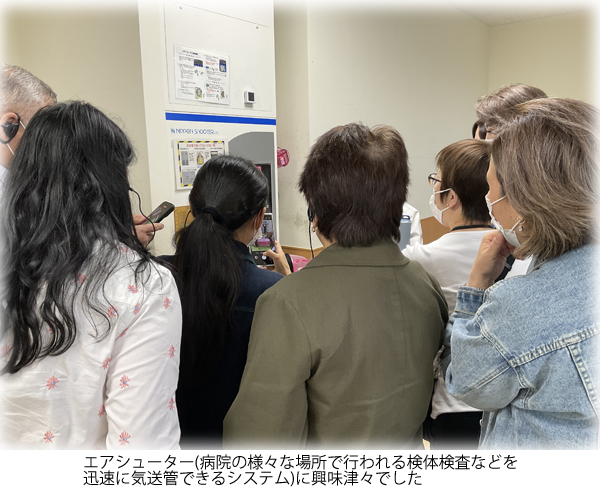
日本のリハビリテーションは知見が広いということから、手術後からどのくらいの日数でリハビリを始めているかなど、回復期の過ごした方や退院後の行き先(リハビリ施設)についてとても関心を持たれていました。
最後は記念品として、キルギス国のお土産を頂戴するなど、我々も貴重な時間を過ごしました。


今後の研修員の方々の活躍とキルギス国の医療の発展を心より祈念しております。

処方箋の有効期限に要注意⚠
2025年09月12日
先週の金曜日は大雨となり、地域によっては避難指示が発表され、不安に思われた方もいらっしゃったのではないかと思います。
最近はまとまって雨が降ることが多いので、いざという時のための行動を考えておきたいですね。
さて明日から3連休です。
当院ではお薬での治療が必要な外来患者さんには、保険薬局でお薬を受け取っていただく処方箋(しょほうせん)を発行しています。
この処方箋ですが、「有効期間」があるのをご存じですか?
処方箋は「交付日を含めて4日間」が有効期間(有効期限)と国のルールとして定められていますので、診察を受けて処方箋を受け取った日が1日目となります。
例えば、今日受け取った処方箋は、今日(1日目)、明日(2日目)、明後日(3日目)、明々後日(4日目)までが有効期間です。
4日を超えてしまうと「失効」。
これはつまり、お薬をもらうことができなくなってしまうことを意味します。
しかも、この4日間には「土曜日」「日曜日」そして「祝日」も含まれているんです。
多くの保険薬局は「土曜日」「日曜日」「祝日」がお休みです。ですが、処方箋の有効期間はそんなことは関係なく減って行きます💦
つまり、今日処方箋を受け取った方は今日中に処方箋を提出いただかなくてはなりません。
処方箋は、全国どこの保険薬局でもお薬の交付を受けられることにはなっていますので、「土曜日」「日曜日」「祝日」でも開いている保険薬局にお願いすることもできますが、かかりつけではない保険薬局ですと、おくすりの在庫がなく取り寄せになってしまうこともあります。
診察後で疲れていたり、最近は暑さもあるのであとで行こうかなと思っているうちに失効してしまわないように処方箋はその日のうちにかかりつけ薬局へ提出いただくことをおススメいたします。
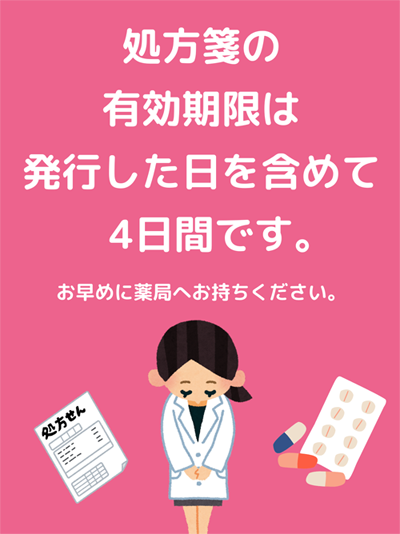
慢性心不全認定看護師にインタビューしてみた!
2025年09月05日
9月に入りました。
街中ではハロウィンの飾り付けを見かけるようになりました。
これから秋の行事を楽しみたいですね🎃
さて、今回は当院の認定看護師を紹介します。
認定看護師とは、患者さんの色んな分野のお困りごとに対して、その分野を得意とした資格をもつ看護師のことです。
今回は横浜医療センター歴13年目の慢性心不全認定看護師にお話を聞いてみました。
Q.慢性心不全認定看護師を目指した理由やきっかけを教えてください
A.入職した当時、たまたま循環器科に配属となり、勤務して過ごしているうちに楽しいと興味を持ったのがきっかけです。また、心不全チーム医療の立ち上げに関わり、後々のことを考えて認定看護師を目指そうと思いました。
Q.慢性心不全認定看護師としての役割・活動を教えてください
A.慢性心不全は、一生付き合う必要がある病気です。しかし、病気を理解してコントロールすれば長生きできる可能性があります。そのため、主に入退院を繰り返す患者さんの生活調整を行っています。2022年からはチーム医療を発足し、多職種の職員の架け橋として調整業務にあたっています。また、患者さんがご自宅へ戻られてからの生活で、ご家族が困らないようにサポートを行っています。
Q.慢性心不全認定看護師になってよかったこと、やりがいはなんですか?
A.心不全チームで患者さんがどのような生活をしていきたいかを多職種で話し合った時に、方向性が合致して協力し合って患者さんの対応ができることにやりがいを感じます。
患者さんの理想の生活に近づけるための答えはいつもないので、自分が患者さんと対話して患者さんの想いを引き出すこができると心を開いてもらえたような気がして嬉しい気持ちになります。
また、少し話はそれますが、自分自身の看護観に変化がありました。
認定看護師になるまでは「患者の命は俺が救うんだ!」と自分本位な考え方でした。
それが認定学校に通っている間に、患者さんが主体であることに気づきました。
心不全の患者さんの多くは食事制限がありますが、患者さんのこれまでの生活や嗜好を聞いて理想の生活に近づけること、折り合いをつけて病気と向き合っていく方法を一緒に考えることが今のやりがいにつながっていると思います。
常に、患者さんがより良い生活を送れるように何が最善かを模索し続けています。
「最後に、これから慢性心不全認定看護師やキャリアアップを目指される方に向けてメッセージがあればお願いします✨」
「慢性心不全に限らず、認定看護師になると、多職種の職員と関わる機会が増えます。
大人になって社会人になると、決められたことの中で解決していくことが多いと思いますが、青春時代のように仲間と一緒に熱意をもって仕事ができると、とてもやりがいが感じられます。また、認定看護師として周りからも認められて活動ができるので自身のモチベーションアップにもつながります。多職種の職員間でみんなをまとめていくので、リーダー気質の方は向いていると思います。
慢性心不全認定看護師は2011年からスタートしたので、まだできて間もない職種です。
このブログを読んで、患者さんと医療従事者をつなぐ「慢性心不全認定看護師」に興味を持っていただけると嬉しいです😊」
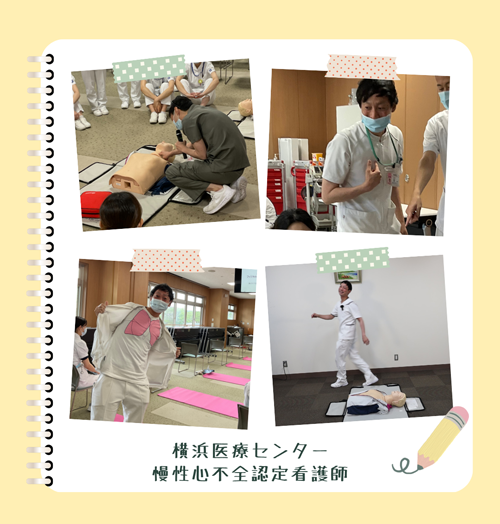
【歯科口腔外科】夏の口腔ケア
2025年08月29日
8月最後のブログです。
8月は「歯並びの日(8月8日)」や「歯ブラシの日(8月24日)」など、歯に関連する記念日が多くありましたが、皆さんはご存じでしたか?
そこで今回は歯科口腔外科医師にブログを執筆いただいたので、改めて歯と口の健康について考えてみましょう。

夏は、気温の上昇や生活習慣の変化により、口腔内のトラブルが増えやすい季節です。
そのため脱水症状になりやすく、全身のさまざまな臓器へ影響します。
そもそも、脱水とは、体内の水分が不足した状態を指します。夏に多量の汗をかいたり、水分補給が不足したりすると、体内の水分量が減少して脱水状態になります。
体内の水分量が減少すると、唾液腺での唾液の生成量が減少し、結果として口腔内が乾燥します。この状態を口腔乾燥と呼びます。健康な状態での1日の唾液の分泌量は、成人で一般的に1.0~1.5リットルと言われています。この膨大な量の唾液が、日中の食事や会話、そして就寝中も含めて、私たちの口腔内の健康を支えています。
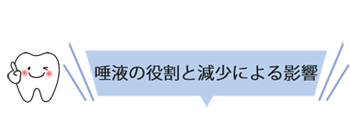
唾液は単なる水分ではなく、口腔内の健康を維持するための重要な役割を担っています。
🔷自浄作用:唾液は口の中の食べかすや細菌を洗い流し、口内を清潔に保ちます。唾液量が減ると、これらの洗浄作用が弱まり、細菌が繁殖しやすくなります。
🔷抗菌作用:唾液に含まれるリゾチームやラクトフェリンといった酵素には、細菌の増殖を抑える抗菌作用があります。唾液量が減少すると、この抗菌作用も低下し、虫歯や歯周病のリスクが高まります。細菌が作り出す揮発性硫黄化合物(VSC)が増加することで、口臭が悪化します。
🔷再石灰化:唾液に含まれるカルシウムやリン酸は、初期の虫歯で溶け出した歯の表面を修復する再石灰化を促します。唾液量が減ると、この修復機能が低下し、虫歯が進行しやすくなります。
🔷pH緩衝作用:唾液には、食後に酸性に傾いた口腔内を中和するpH緩衝作用があります。唾液量が減ると、酸が中和されにくくなり、歯が溶けやすい状態が続きます。
このように、脱水は単に口が渇くだけではなく、本来1日1リットル以上も分泌されているはずの唾液の量が減少し、口腔内の健康バランスを大きく崩す要因となります。
特に夏場は意識的な水分補給が、全身の健康だけでなく、口腔ケアにおいても非常に重要です。
✅夏の口腔ケアのポイント
夏の口腔トラブルを防ぎ、健康な口内環境を保つためには、以下の点に注意しましょう。
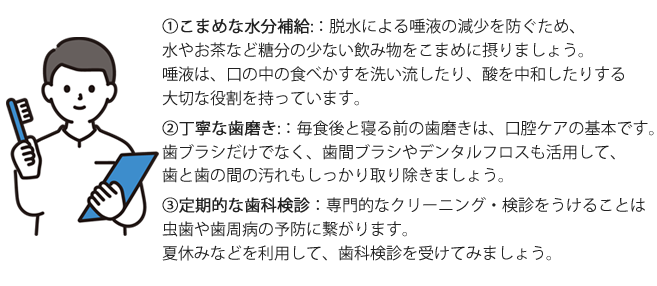
お口の健康に意識し、暑い夏を乗り切りましょう!
いかがでしたか?
夏というと、熱中症が思い浮かびますが、口腔ケアにおいても水分補給がとても大切なことがわかりました!
まだまだ暑さが続いていますので、生活の様々なタイミングで水分補給する習慣をつけましょう✨
👩高校生対象の看護体験を実施しました👨
2025年08月08日
暦の上では「立秋」を迎えました。
年々厳しい暑さが続き、秋にはまだほど遠く感じられますが、秋に向かっていく変化を見つけて楽しみたいですね。
ちなみに当院敷地内では、トンボがたくさん飛ぶ姿が見られます。
さて、7/29と8/5に高校生対象の1日看護体験を実施しました。
毎年実施していますが、申し込みが多数あるため、今年は2日開催として人数枠も増やしました!
白衣に着替えた後に、オリエンテーションを行い横浜医療センターについて紹介し、その後看護体験をしてもらいました。

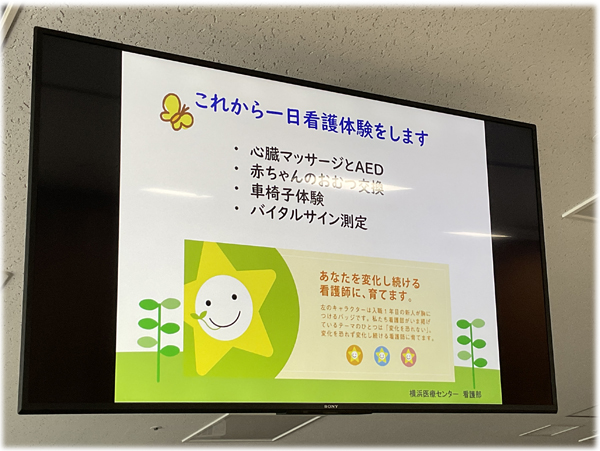

その後、敷地内の附属看護学校をご案内し、終了後に全体で意見交換会をして、感想や質問をいただきました。

高校生から「体験の中で、看護師の方が気さくに話かけてくれて会話をすることができて、看護師になった自分の将来像が見えた気がした」という感想がありました。
また、看護師への質問として「看護師になりたいと思ったきっかけは?」「看護師をやっていてよかったことは?」「働いていて大変なことは?」などが挙がり現役看護師たちが生の声を届けました。
当院の附属看護学校を目指している学生さんも参加してくれていたので、是非またお会いできることを楽しみにしています🤗
参加してくれた皆さん、暑い中お越しいただきありがとうございました。
今後の病院イベント情報はホームページや、ブログ、”X”で随時情報発信していきますので、興味のある方はチェックしてみてください✨
附属看護学校ブログ、学校Instagramもよろしくお願いします❣
看護部インターンシップ実施中です!
2025年08月01日
8月に入りました🌻
梅雨明け以降、毎日厳しい暑さが続いていますが、この暑さの中でもツバメのヒナたちはすくすく成長しています。
毎朝通りかかると4羽のヒナたちが大きな口を開けてエサを待つ姿を見かけます。
巣立ちまでもう少しのようですが、見守っていきたいと思います🐣

さて、当院では6月~12月まで看護部インターンシップを実施しています。
看護学生向けの職業体験なので、各地から沢山の学生が当院に足を運んでくださっています。

先日開催された際に、小児科病棟での勤務を希望している学生から、「産まれた時は未熟児でNICUに入っていたが、今は無事に大きくなって健康に過ごしているので、今度は自分がご家族に寄り添ってNICUにいる赤ちゃんを助けたい」と看護師を目指す気持ちを伺うことができました。
自身の経験から誰かの役に立ちたいという志がとても印象的でした。
看護を学ぶ学校で看護知識を身につけて、当院の仲間としてまたお会いできることを楽しみにしています✨


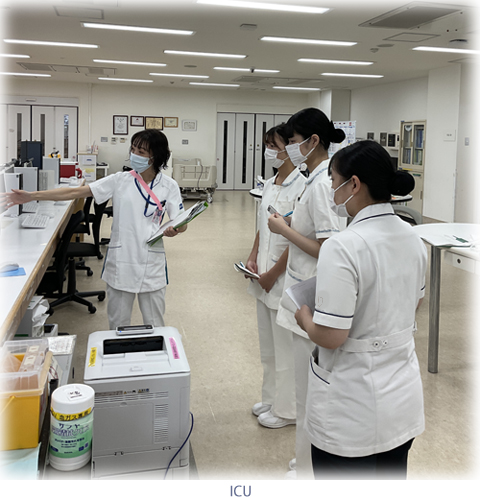
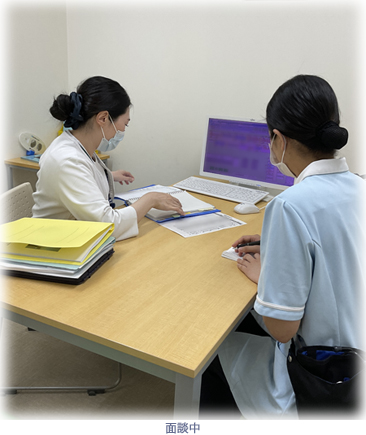
9月以降も実施予定ですので当院に興味のある学生さんのご参加をお待ちしております🤗
📝お申し込みはホームページをご覧ください。
看護師・助産師免許が届きました✨
2025年07月29日
今月、新人看護師47名のもとに看護師・助産師免許が届き、一人ずつ看護部長から受け取りました。
国家試験合格後から看護師免許の申請手続きや、就職と落ち着かない日々だったかと思いますがようやく手元に届いて安心した様子でした。
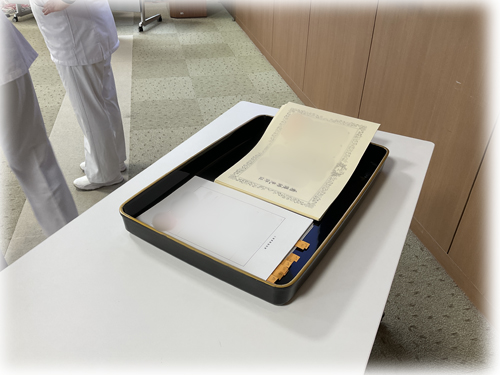

看護師のコメント💭
『看護師になった実感がわいて嬉しかったです』
『これからもっと気を引き締めて頑張ろうと思いました』
『看護師になった実感がわき、これからも頑張っていこうという気持ちになりました』
『嬉しさと看護師になって患者の命を預かるという責任を感じました』
助産師のコメント💭
『小さい頃から目指していた助産師になれたことを改めて実感したと同時に、母児の命を守り、寄り添える助産師を目指したいと思いました。』
『幼い頃からの夢が叶ったという喜びを感じるとともに、助産師という仕事に責任を持ってこれからも頑張っていきたいと思いました。』
【産科病棟看護師長より】
「二人とも緊張した面持ちでしたが、免許を受け取った感想を聞くと笑顔が見られ『助産師になったのだと自覚した』と話してくれました。初心を忘れず、これからも母児のために助産師として与えられた役割を全うしてほしいと思います。」
皆さんが頑張った証明でもあり、これから看護師として活躍するための大切な証明です。
大切に保管をして、ご家族の方にも見せてあげてくださいね!
新人看護師の皆さんおめでとうございます😊
看護フェスティバル開催レポート
2025年07月25日
先週7/19(土)11:00~16:00にゆめが丘ソラトス2階と3階のイベントスペースをお借りして看護フェスティバルを開催しました。
天気に恵まれた三連休の初日と言うこともあり、たくさんの方にご参加いただきました。
病院職員23名、看護学校職員2名の計25名で地域の皆さんをお迎えし、看護の魅力を体験できるブースを準備しました。
2階ブースでは、もしバナカード、ハンドマッサージ、正しい手洗い、認知機能チェック、聴診器体験コーナーなどのブースを出展しました。聴診器で自分の心臓の音やお母さんの心臓の音を聴いて、「すごい!」とつぶやいたお子さんのキラキラした眼がとても印象的でした。
また、ドクターカーブースは、医療ドラマを見たことのあるお子さんたちに人気で、トランシーバー体験やユニフォームの着用などを楽しんでいただきました。一次救命処置体験として、心臓マッサージのやり方やAEDの操作説明は、大人から子どもまで多くの方が立ち寄られました。
3階ブースには、こころの相談コーナー、母子医療センターの看護師・助産師による白衣の着用や赤ちゃん抱っこ体験・妊婦体験コーナーを設けました。
当院で出産したお母さんがお子さんと一緒に遊びに来てくださり、こんなに大きくなりました!と元気な姿を見せてくれてとても嬉しかったです🤗



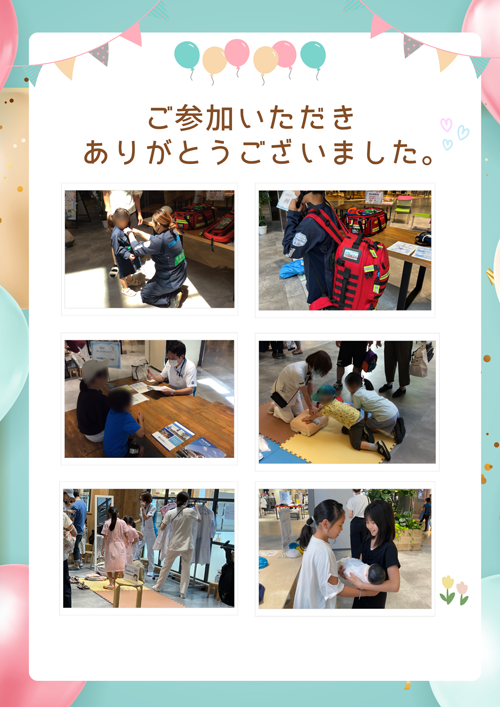
イベントを通して地域の皆さんと触れ合うことができ、ご来場いただいた方々と楽しい時間を過ごすことができました。
ご参加いただいた皆さま、開催にあたりご協力いただいた関係者の皆さまに改めてお礼申し上げます。
今後も地域の皆さんに信頼される病院を目指して、地域貢献できる機会を企画していきたいと思います。
【泌尿器科】7月と水分補給
2025年07月18日
今週は台風の影響で暴風や大雨の地域が多かったですが、関東ではようやく晴れ間が戻り、梅雨明け間近となってきました。
真夏日が復活しそうなので、お出かけ予定の方は熱中症に気を付けてお過ごしください。
さて、今日は泌尿器科医師にブログを執筆いただいたので最後までお読みいただけると嬉しいです。
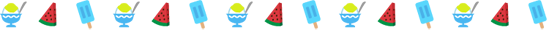
泌尿器科で夏といえば尿路結石が定番という泌尿器科クリニックさんのブログを見かけます。
四季がある地域では夏季に通常よりも尿路結石発作が起こりやすいということや、急に低気圧になった場合には発作が多くなることも言われており、そのうち季語に加えられたりすると文芸界も盛り上がりましょうか。 ちなみに、夏の季語には、〝日射病〟〝暑気あたり〟〝夏風邪〟〝水あたり〟〝赤痢〟〝脚気〟・・・・・などあるようですが、AIに聞いても尿路結石症を季語とした俳句は見当たらないということでした。
そこで新作傑作選3句
・救急車 いななき響く 夏の夜
・痛みこそ 身を削りつつ 石は月
・汗と涙 しぼる嘆きの 夕茜

夏井先生に一度、採点+解説していただきたいです。というわけで、今回のお題は水分補給と7月ということでしたが、水分摂取量と関係の深い尿路結石症もメタボリック症候群のひとつで、食習慣、運動習慣などによる予防についてもう少し我々も、患者さんも力を入れるべきかもしれません。
ひと昔前の泌尿器中心の日本泌尿器内視鏡/体外衝撃波結石破砕学会で、皆手術成績にばかり目が行っているのをみかねたのか、 学会長が“石割って終わりじゃダメだろう、予防にも目を向けるべきじゃないの?”という趣旨のことを言われ感動を覚えました。
これだけ、いろいろな研究がなされてきたのに予防医学に活かされていないのはもったい無い気もいたします。(生活習慣が原因でないものもありますので、念のため)。
こちらは川柳ですが(ネットからこっそり拝借)
「ジャンピング! 管に詰まった 石落とす」
今も似たようなことを言うことがありますが、ビール飲んで縄跳びしなさいみたいな指導が泌尿器科界では一般的でした(近場だけだったかもですが・・)。

尿路結石の話をしておいてなんですが、自分にとっての最近ヒットの水出しコーヒーについて少しだけ。 味もまろやかで、甘味を感じられて良いなあと思いましたので、利点を探したところ少しカフェインが減ることに加えて、尿路結石成分の王者として君臨している“シュウ酸”の含有量はホットと比べると減少するそうです。
最後にしたいと思いますが、最近祖父母の住んでいた築100年以上の平屋の借主さんが決まったこともあり、色々と整いましたということで謎かけをひとつ
“救急車で来院される尿路結石症の患者さん”とかけまして、“24年誰も住んでいなかった家”と説きます、そのココロは ・・・・・・
どちらも”イタミが激しい”でしょう! 伊丹幸雄でした~💛
(ちなみに俳句3選はいずれもAI作成ですが、謎かけはねずっちさんがしばらくはAIより強い気がします・・)
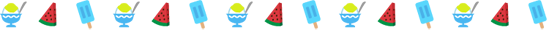
いかがでしたでしょうか。
夏は気温が高く、汗をたくさんかくため、体内の水分が失われやすい状態になります。
こまめな水分補給で夏にかかりやすい脱水症状や、尿路結石などの病気を予防できるので意識しておきましょう。

さて、明日7/19(土)は看護フェスティバル当日です🎊
ゆめが丘ソラトスのイベントスペースをお借りして、大人の方からお子さんまで楽しめる看護体験を実施します!
無料でご参加いただけますので、お気軽にお立ち寄りください😊
【栄養管理室より】夏の食中毒について🍱
2025年07月11日
蒸し暑い日が続き、『危険な暑さ』について連日報道されていますね。引き続き、熱中症から身を守る対策をして夏を乗り切りましょう。
今週始めの7月7日、七夕の日に入院中の患者さんへ行事食を提供しました。

~献立メニュー~
・ちらし寿司
・白身魚・コーンフライ
・添え)しめじ・ピーマンソテー
・サラダ
・オクラおかか醤油和え
・スイカ
・七夕ゼリー
スイカやゼリーで見た目も涼しく、季節のメニューをお届けできればと思います。
さて、暑くなってくると気を付けたいのが「食中毒」です。
特に一般家庭では「お弁当」を作る機会も多く、食中毒対策についてお困りの方もいらっしゃるかと思います。
今回は、お弁当作りでの注意点についてお話したいと思います。
食中毒防止には「つけない」・「ふやさない」・「やっつける」の3原則が大切です。
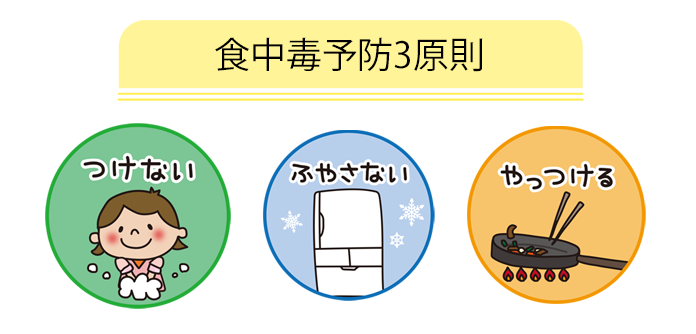
そして、十分な手洗いと、きれいな調理器具・弁当箱・カップの利用で細菌の付着防止をしましょう!
細菌の増殖を防ぐポイントとしては、おかずの水気を切る・粗熱を取ることです。
悩みがちな夏のお弁当のおかずには焼物・揚げ物がお勧めです。
加熱はしっかりしていただきたいので、卵は半熟より固ゆで、生食出来るハムやかまぼこも加熱しましょう。
持ち歩く際には保冷剤や保冷バッグ、保管は冷蔵庫を利用し早めに食べましょう。
入院患者さんの中には体力や免疫力が低下している方もいらっしゃいますので、当院栄養管理室では大量調理施設衛生管理マニュアルに準拠した管理を行っています。
①使用する食品の鮮度や消費期限を確認し適切な温度管理下で保管。
②調理に使用する器具類(箸・まな板・ボウル・食缶)は洗浄後、滅菌されたものを使用。
③下処理後の食品は、速やかに冷蔵保管。
④調理時には十分な加熱や冷却。中心温度計を使用し、調理温度を確認。
⑤出来上がった料理は、速やかに盛付け、調理から盛付までの時間を短くし細菌の繁殖を防止。
⑥お食事は温冷配膳車を使用し、適切な温度管理のもと「温かい料理は温かく、冷たい料理は冷たく」提供。

皆様、ご家庭でも日頃から気を付けていらっしゃるとは思いますが、食中毒の防止策として当院の取り組みを参考にして頂けたらと思います。
📝当院の衛生管理については過去のブログをご覧ください。
2年目看護師研修を実施しました
2025年07月04日
7月に入りました。
外来ホールには今年も職員が七夕の飾り付けを行いました。
それぞれの色の短冊に願い事がつづられて飾られています✨

さて、今日は新人看護師から2年目になった看護師のその後の様子をご紹介します。
当院看護部の教育研修では看護師2年目も定期的に集合形式で研修を行っています。
今回の研修の内容は「摂食・嚥下ケア」についてです。
摂食・嚥下障害とは、食べ物を食べたり、飲んだりすることが困難になる状態です。
当院の摂食・嚥下障害看護認定看護師が講師を担当し、看護師が患者役となって実際に様々な形状の食事を体験し、介助の方法を学びました。

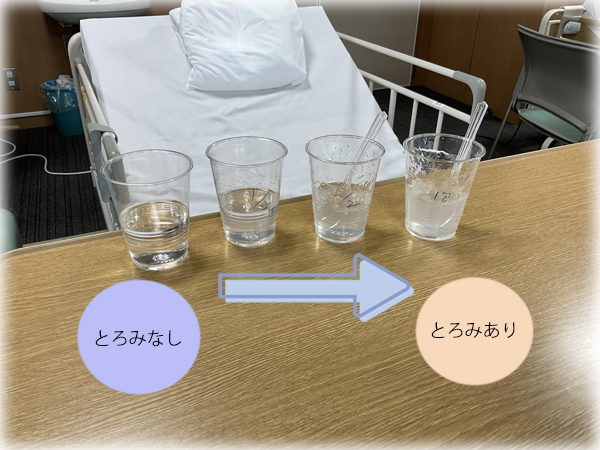


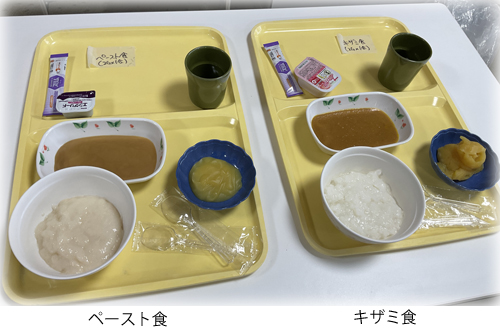
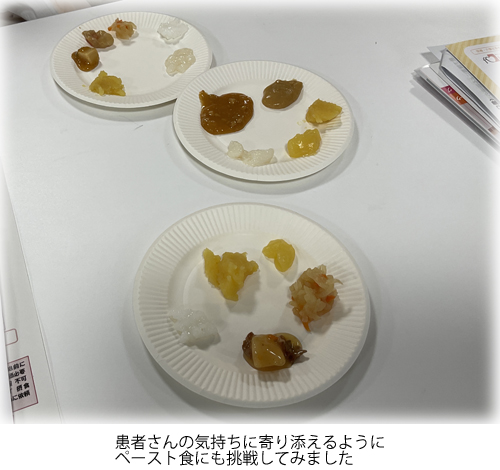
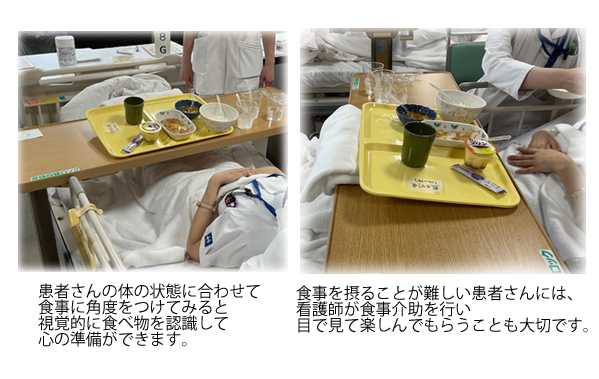
2年目看護師は、昨年の1年間で日々知識をつけてきたので講義がすんなりと吸収しやすい時期です。
また、日ごろの患者さんとの関わり方を見直す良い機会にもなりました。
成長中の2年目看護師を引き続きみんなでサポートしていきたいと思います😊
最後にお知らせがあります。
2025年7月19日(土)に、当院の看護部が“ゆめが丘ソラトス”にて『看護フェスティバル』を開催します❣
皆さまのご来場を心よりお待ちしております。
【放射線科】核医学(RI)検査装置を更新しました~知られざる放射線検査の世界~
2025年06月27日
当院では、2025年5月に核医学検査装置を更新しました。
皆様は核医学検査をご存じでしょうか?
別名でRI検査とも言われますが、レントゲンやCT、MRIに比べてなじみの少ない検査だと思います。

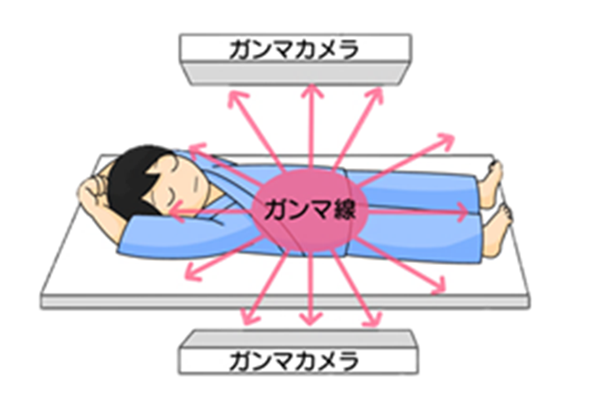
RIはラジオアイソトープ(RadioIsotope)の略で、直訳すると放射性同位元素といいます。放射性同位元素は、種類によってアルファ線、ベータ線、ガンマ線などといった、様々な放射線を発生させます。物体を通過する能力(透過力)の高い順にガンマ線>ベータ線>アルファ線であり、透過力の高いガンマ線が核医学検査で主に使われます。
このガンマ線を多く出すRIを、脳や心臓、骨といった目的の臓器によく集まるお薬と合成したものを放射性医薬品といいます。放射性医薬品を体内に入れると、目的臓器に集まりながらガンマ線が放出されますので、それを専用のカメラで計測することで、目的臓器のRIの取り込み具合を画像にすることができます。

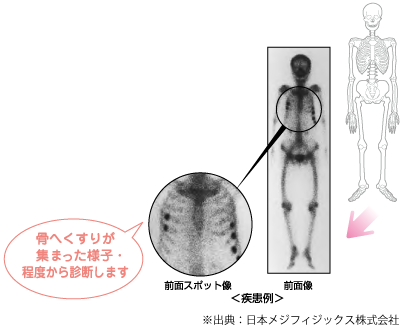
ガンマ線を検出するカメラなので、核医学検査装置はガンマカメラとも言われます。
体内に放射線源を入れる!!ということで被ばくについてご心配されるかもしれませんが、体内のRIは数日で体から排泄されますので、すぐに体に影響が及ぶようなことはありません。
被ばくにつきましては当院のHPに専用の説明ページがありますので、こちらをご覧いただければ幸いです。
さて、実際に核医学検査ではどんなことがわかるのでしょうか。
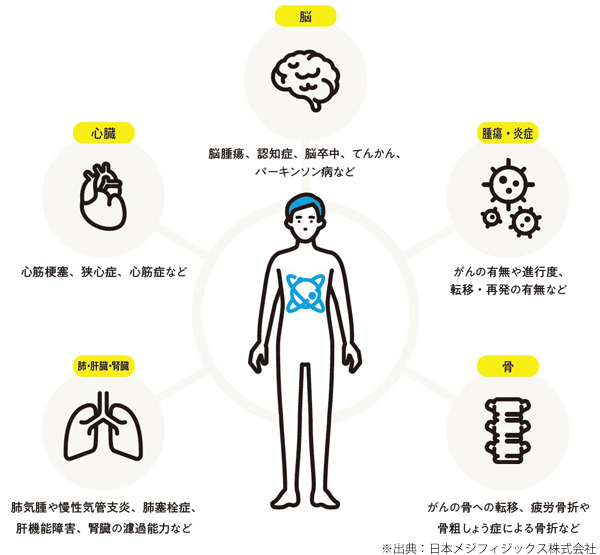
代表的なものでは、脳血流検査による認知症の診断や、脳血管治療前後の評価。
心筋血流による心筋梗塞リスクの評価。
他には腫瘍の性質評価や転移検索、腎臓の排泄機能評価、脳変性疾患であるパーキンソン病の診断にも使用されます。
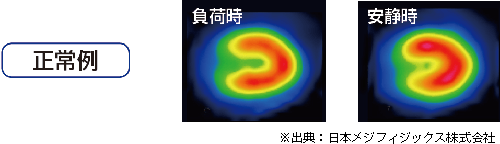
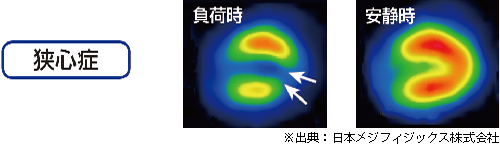
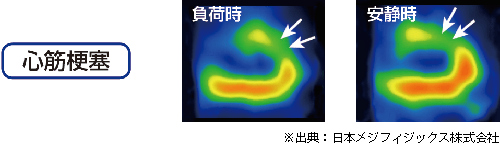
※出典:日本メジフィジックス株式会社(https://www.nmp.co.jp/)
レントゲン、CT、MRIは形態画像といって、形の変化や位置関係をみる検査であるのに対し、核医学検査では体の機能をみる検査であることがご理解いただけたと思います。
当院では様々な領域の核医学検査に幅広く対応しております。検査時間は長めのものが多いですが、苦痛になることのないよう、スタッフ一同いっそう気を配って参ります。
副院長ブログ「休日の過ごし方」
2025年06月20日
今週は梅雨時期とは思えないような暑さでした。
まだ体が暑さに慣れていないので、この時期でも熱中症になる可能性があります。
しっかり暑さ対策を行っていきましょう!
今回は第4弾となる副院長ブログです😊
駄文を書いても良い、と言われてしまい、嬉々としてネタ探しに明け暮れていますが、家と病院の往復な毎日では、そうそう見つかるものではありません。
でも、当直明けの土曜日に帰り道で、ゼッケン付けて国道1号線をゾンビの様に歩く人たちを見かけていて、なんだろ?と思っておりました。調べてみると、小田原から東京有明まで100㎞を歩くイベント。
むむ、これは、と思っておりましたが、ようやく参加することができました。
当日はそのゼッケン付けた皆さんが、雨対策に追われていました。天気は雨、しかも荒れ模様、私も傘と合羽を着こんで小田原城から朝8時半ごろ出発となりました。足が濡れるのが最大の懸念ですが、仕方がありません。
自転車なら小田原はツーリング程度の距離ですが、歩くのは率直に言って、のろい。傘をさしているので、バランスが悪くなかなか厳しい。相模川河口では吹き飛びそうな暴風で、走っちゃいけないルールでしたが、走り抜けちゃいました。
幸いに途中で雨は上がり、43㎞地点の原宿の交差点では病院を眺め、戸塚駅へ下ります。保土ヶ谷で夜を迎えましたが、コスモクロック(観覧車ですね)はビューティフルに点灯中、みなとみらいはデート中の皆さんが沢山、こちらはようやく2/3…足が濡れているので気分も2/3以上ブルーです。
20時間32分で到着しました。途中でおにぎりを6個食べ、カレーパンを一つ、一口羊羹を二つ、魚肉ソーセージを1本、おつまみチーズをちょっと食べて、3Lくらい水をのみ、トイレに行き、とまぁ、一日過ごしたわけでした。歩数は14万歩くらい、でも携帯の万歩計は99,999歩で振り切れていました。
とっても面白い体験でしたが、とにかく1時間に5㎞も進まないので、走りたくて仕方がない(走るのは別の筋肉なのか、ちょっと走ると体がほぐれる)、濡れた足では靴ずれができる。60㎞超えるとさすがにしんどく、誰にでもお勧めする、とは行かないなぁ、とは思いました。でも30-50kmの大会もあるそうです。それならほとんどの人が歩けると思います。
しかし、思いもよらない故障が。なんと、左右のお尻の間が擦りむけるのですよ。いたた。
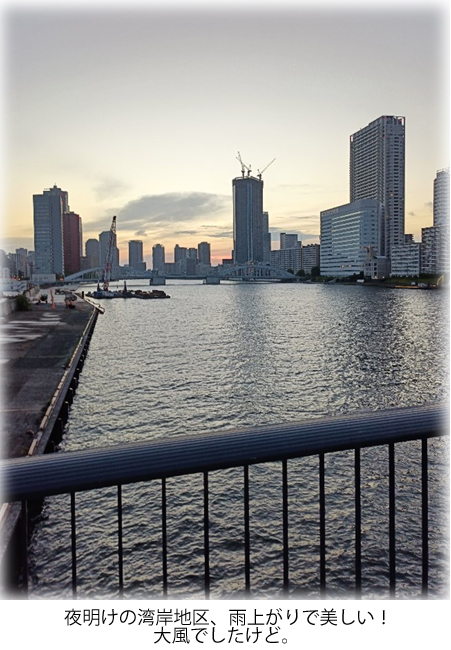

100Kmを無事に歩いたあとは、始発のゆりかもめに乗って帰宅し、翌日は通常通り自転車で当院に通勤したそうです。過去の「休日の過ごし方」でもマラソンやサイクリングとタフなお話がありましたね。「第2弾:フルマラソンのお話」「第3弾:サイクリングのお話」
いつもながら、そのアクティブすぎるエピソードに驚かされてしまいます。
故障も完治したそうで、安心しました。
副院長の「休日の過ごし方」は今後も不定期で掲載していく予定です🤗
新人看護師研修vol.1
2025年06月13日
先日、梅雨入りの発表がありましたね。
スッキリしないお天気の日が多くなりそうですが、この時期の楽しみを見つけて過ごしていきましょう。
公開空地のあじさいが先週よりも沢山咲いていました。


さて、4月のオリエンテーションを終えてから、新人看護師たちは各病棟へ配属され、病棟業務を習得しているところです。
先輩と一緒に患者さんのケアを行い、1日の流れが少しずつイメージできる時期になりました。
今回の新人看護師研修では、採血の演習を行い、安全に正確に行うためのポイントを確認しました。

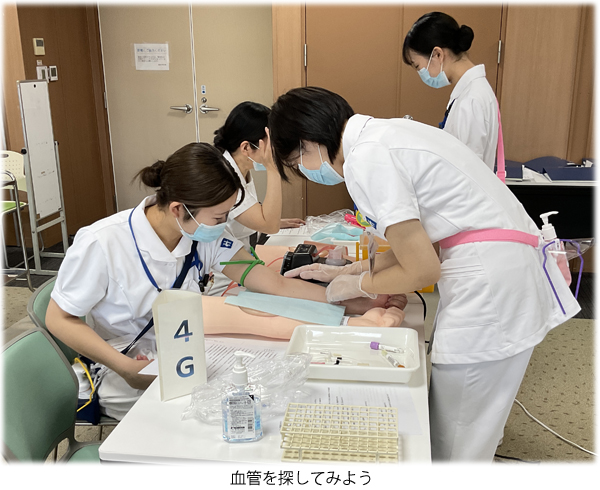
患者さん役の相手へ声がけをしながら演習を進めました。
採血の技術以外にも、針を刺した後は片手が離せなくなるので、手元に必要なものを先に揃えておくなどの手順も大切だと再認識できました。
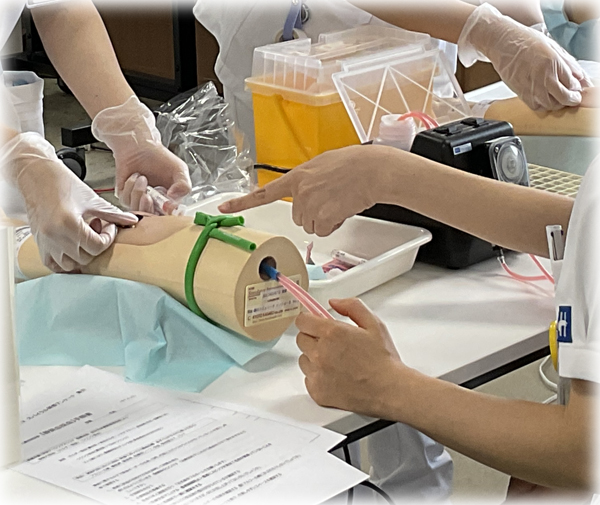
同日、シリンジポンプの使用方法についても医療機器メーカー担当者から直接指導を受けました。
安全に使用できる知識を得られるように頑張っていきたいと思います。
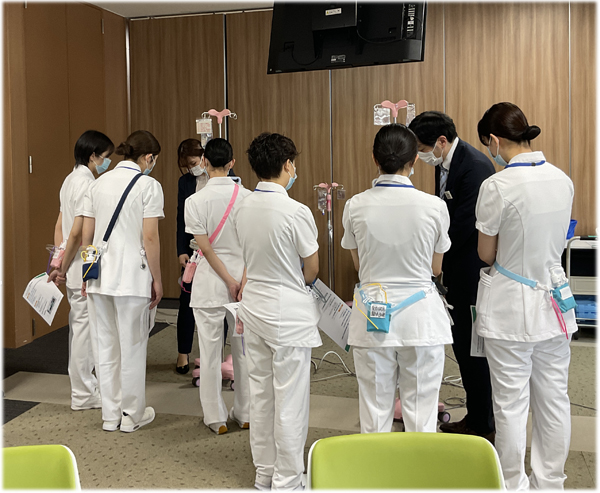
今後もブログで新人看護師の成長していく様子をUPしていくので温かく見守っていだけると嬉しいです😊
映画『ドールハウス』の撮影に協力しました🎥
2025年06月12日
明日、2025年6月13日(金)に公開される映画『ドールハウス』の撮影に当院が協力しました。
主演の長澤まさみさんと瀬戸康史さんより、サイン色紙をいただきました。
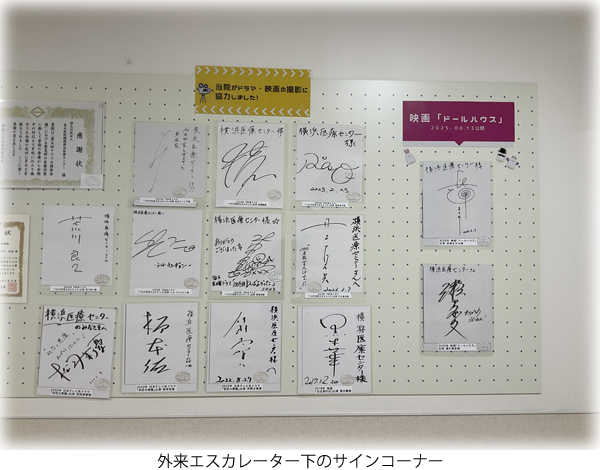
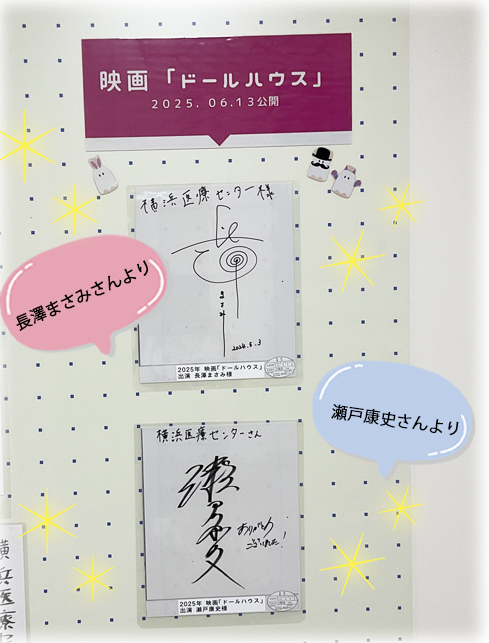
当院施設がどのような撮影シーンで使用されているのかを楽しみに探して見てみたいと思います。
ゾク×ゾクのドールミステリー‼
公式の映画ホームページ等で情報が公開されていますので是非チェックしてみてください😊
【耳鼻咽喉科】6月は「天気病」に注意!
2025年06月06日
6月に入りました。
公開空地にはあじさいが咲き始めています。


そろそろ梅雨入りの発表が気になりますが、体調管理にも気を付けたい時期です。
今回は当院の耳鼻咽喉科医師に「天気病」について教えていただきました。
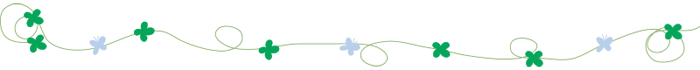
天気病(気象病)は、気圧や天候の変化によって体調が悪くなる症状のことです。
具体的な症状としては、頭痛、めまい、肩こり、関節痛、などがあげられます。
気圧の変化を感じる人体のセンサーは内耳だと言われています。
詳細な部位についてはまだはっきりわかっていません。
気圧の低下と、ストレス・睡眠不足などの要因が合わさって症状の悪化を起こすとされています。
耳鼻咽喉科で治療する、メニエール病やめまいを伴う片頭痛の方は、気圧の変動でめまいや難聴の増悪を起こすことがあります。
通常、気圧変化が大きいのは季節の変わり目で春と秋ですが、今頃の梅雨の時期にも症状が出やすくなります。
男性より女性のほうが多く起こるようです。
ご自身で行う予防や対策としては、睡眠をしっかりとる、リラックスする、生活リズムを整える、などがあります。
治療薬としては、五苓散(ごれいさん)、苓桂朮甘湯(りょうけいじゅつかんとう)などの漢方薬が有名で、実際に内服されている方も効果を実感されているようです。
季節の変わり目などに起こるめまいなどの耳症状については、耳鼻咽喉科にご相談ください。
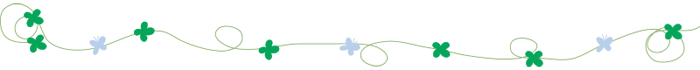
いかがでしたか?
天気病の症状はなかなか他人にわかりづらく、我慢してしまいがちです。
梅雨時期は、ご自身に合った解消法を見つけておき、無理なく過ごせるように注意しておきましょう。
耳鼻咽喉科YouTube動画「耳鼻科に来ない耳鼻科の病気」も是非ご覧ください。
MSWとして歩んだ20年、そしてこれから
2025年05月30日
最近はツバメがヒナにエサをあげている姿をよく見かけます。
当院には毎年、救急外来入り口にツバメの巣ができています。
ヒナが巣立つ8月頃まで見守りたいと思います🐣


さて、当院では先日5/28に永年勤続表彰伝達式を執り行いました。
今回受賞された職員のうち、医療ソーシャルワーカー(MSW)よりコメントをいただきました。
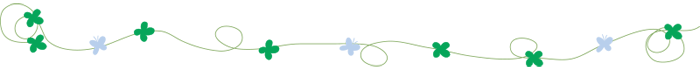
このたび、永年勤続20年の表彰をいただきました。
医療ソーシャルワーカーとして歩んできたこの年月を振り返り、改めて「もう20年が経ったのか」と実感しています。

「あっという間」だったとは言いませんが、国立病院機構に入職した日のことはいまも鮮明に覚えており、まるで昨日のことのように思い出されます。
この20年間、ずっと病院の現場で、患者さんやご家族と向き合いながら仕事をしてきました。多くの方と出会い、支え、支えられてきたことは、私にとってかけがえのない時間です。
一般的には「20年も勤めればベテラン」と言われることもありますが、私自身はまだまだ半人前の部分も多く、課題も尽きません。けれどもそれは、これからさらに成長できる「伸びしろ」が残っているということだと思っています。
これからも、よりよい支援を目指して、一歩ずつ進んでいきたいと思います。
そして、何より嬉しかったのは、長年にわたりともに時間を過ごしてきた宇治原院長から、直接表彰状を頂けたことでした。これまでの歩みを共に見守ってくださった方からの言葉は、特別な意味を持ち、胸に深く刻まれました。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

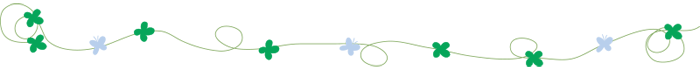
この度ご受賞された14名の職員の皆さま、おめでとうございます。
今後、益々のご活躍をお祈りいたします。
看護の日レポート
2025年05月23日
先週当院では「看護の日」のイベントを実施しました。
前回のブログでご紹介した認定看護師・専門看護師たちが各ブースで患者さんとゆったりと楽しいひと時を過ごしました。
~看護の日イベントの様子~
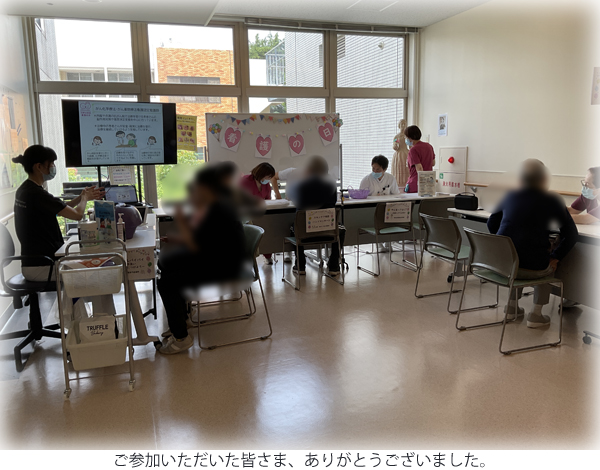
【ばいきんバイバイ~正しい手洗い身につけよう~】
お子さんを対象に手洗い動画の歌を聞きながら、手の洗い残しをチェックできる機械(グリッターバグ)で正しい手洗いの方法を楽しく学びました。

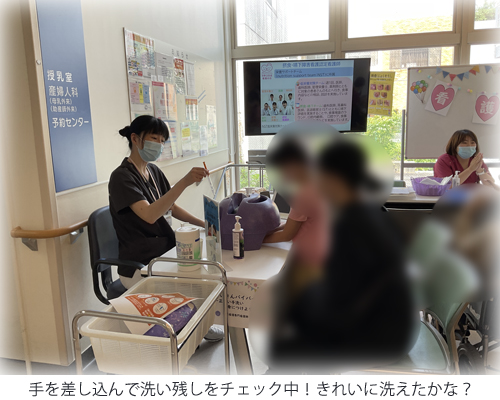
【スキンケア相談・ハンドマッサージ】【せん妄ってなに?】

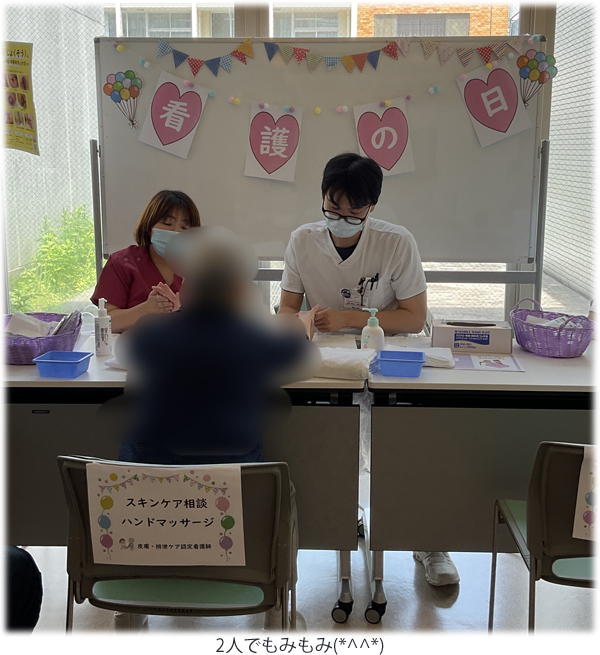
【こころの相談所】
怒りのタイプ診断を受けていただきました。。
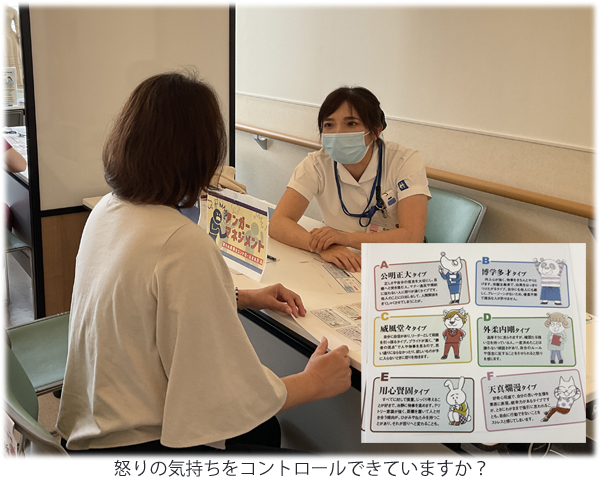
【もしバナカード】
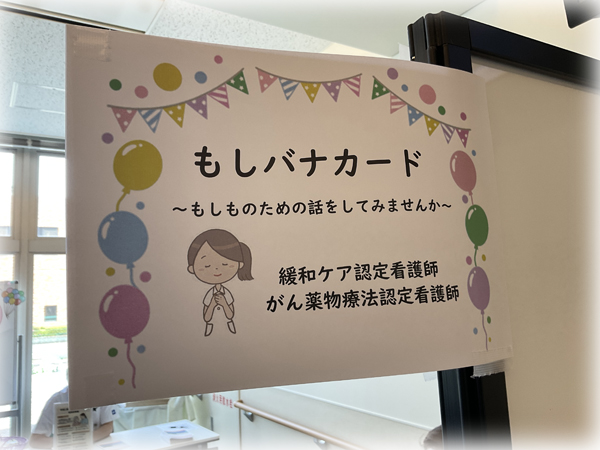
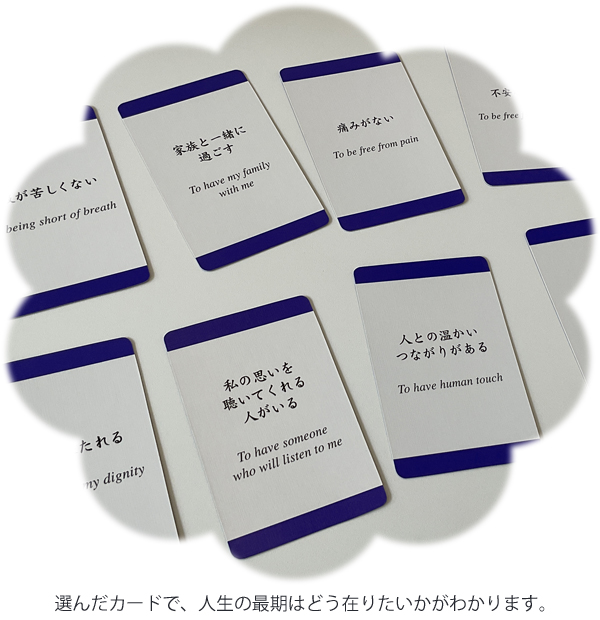
参加した職員より
久しぶりのイベントが開催できて嬉しいです。看護の日を通じて普段は患者さんの対応で間違ってはいけないと緊張していますが、今日はイベントなので楽しい気持ちで参加することができました。通院中の患者さんや入院中の患者さんが遊びに来てくれて嬉しかったです😊
今後も横浜医療センターでは、地域の皆さんと関われるイベントを開催できるように、積極的に企画を行っていきたいと思います。

看護の日
2025年05月16日
今週始めの5/12は「看護の日」でした。
看護週間とされる5/11~5/17の期間中は各地で様々なイベントが開催されていますが、当院でも昨日(5/15)イベントを開催しました!
当日のレポートはまた後日UPしたいと思います😊
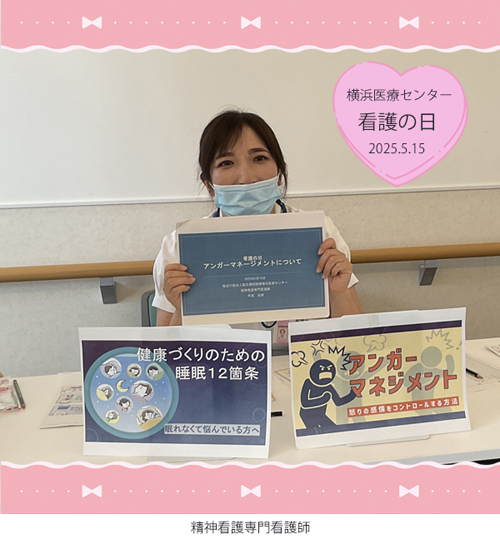
さて、「看護の日」ということで、皆さんは看護師のお仕事って聞くとどういったイメージを持っているでしょうか?
医療ドラマでよく見るような、病棟で受け持ちの患者さんの点滴を替えたり、血圧を測ったりといったことをイメージされるでしょうか?
実は医療従事者の中でもあまり知られていないのですが、患者さんの色んな分野の困りごとに対して、その分野を得意とした資格をもつ認定看護師と専門看護師が存在します。
医師も様々な科の専門医がおりますが、その専門医の看護師バージョンといったところでしょうか。
当院では、「皮膚・排泄ケア認定看護師」、「感染管理認定看護師」、「緩和ケア認定看護師」、「がん化学療法看護認定看護師」、「救急看護認定看護師」、「摂食・嚥下障害看護認定看護師」、「慢性心不全認定看護師」、「認知症看護認定看護師」と多くの種類の看護師が活躍しています✨
私は精神看護という専門分野を得意とした看護師になります。
どういった患者さんに対応しているかと言いますと、一番多い依頼は、高齢の患者さんがなりやすい、せん妄という一時的な混乱状態の対応です。せん妄は急な入院による環境の変化や、入院前から物忘れがある人、手術後で体が弱っている状態の人がなりやすく、自分が今病院に入院しているという状況が分からなくなってしまいます。そうなると、パニックになってしまい、大声で叫んだり、点滴の針を自身で抜いてしまったりします。
せん妄は予防することが重要なため、患者さんがせん妄にならないための対応について、病棟スタッフに教育を行ったりもしています。
他にも、いきなり癌告知などの重い病気の診断を受けてショックを受けたり、病気や加齢によって身体が思うように動かせなくなって気持ちが落ち込んでしまったり、不眠になってしまった患者さんの対応もしています。
また、統合失調症やうつ病といった精神疾患を持った患者さんが入院して身体の病気の治療を受ける時に、精神面のケアを行ったりしています。
直接患者さんの対応をすることもありますし、病棟のスタッフに対応をレクチャーしたりしています。
また、職員のメンタルサポートや、看護スタッフの倫理観を育てる研修を実施したり、付属の看護学校や外部の学校で精神看護について授業を行ったりしています。
看護師と聞くとみんな同じ職種のようにも思いますが、看護師の中でも助産師など、その分野の専門が役割を担って患者さんの健康を支えています。
年に一度の「看護の日」を通じて、今後も皆さんに看護活動を知っていただく機会をつくり、スタッフも日々の看護の大切さを再確認して患者さんと関わっていきたいと思います。

こどもの日🎏
2025年05月09日
ゴールデンウイークが明け、日常風景が戻ってきました!
当院敷地内ではつつじが見ごろを迎え、敷地内で散歩をしたり、写真を撮る人の姿を見かけます🎵


連休中にはこどもの日があり、戸塚区近辺でもこいのぼりが泳ぐ様子が見られましたが、皆さんもごらんになりましたか?
当院では入院中の患者さんにこどもの日の行事食を提供しました。
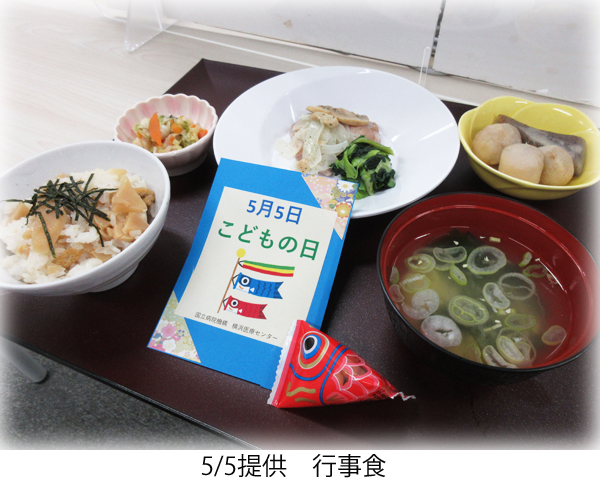
たけのこ御飯 / 鶏モモ風味ソテー / 添え)チンゲン菜 / 田楽(里芋・コンニャク) / 白菜人参生姜和え / 味噌汁(ワカメ・長葱) / こいボーロ
少しでも患者さんに病院食を楽しんでいただけるように、今後も季節を感じていただける行事食を取り入れていきたいと思います。
また、当院の職員が利用する院内保育園ではこども達がこいのぼりをイメージして保育制作を行いました。

0歳児クラス:手形アートでは、小さなかわいい手を頑張って「パー」に広げてペタッと手形をとりました。
1歳児クラス:目のシールを張ってもらうとそれぞれ違う表情のこいのぼりが出来上がり、こども一人一人の個性溢れる作品に仕上がりました。
2歳児クラス:にじみ絵をして、じんわりじんわり色が広がっていく様子を不思議そうに見ながら制作を楽しみました。
最後に当院からイベントのお知らせです📢
2025年5月15日(木)に『看護の日』のイベントを実施します。
以下の詳細をご確認の上、ご来院の際には是非お立ち寄りください😊
春は環境の変化に注意【後編】
2025年05月02日
前回のブログではこの時期に起こりやすい体調の変化についてお話しましたが、今回は予防と対策について、精神看護専門看護師に引き続きお話を聞いてみました。

Q.健康を維持する対策などがあれば教えてください
A.まずは生活リズムを整えることです。睡眠時間をしっかり確保して、食事もバランスよく食べましょう。まず朝起きたらカーテンを開けて日の光を浴びて体内時計を整えて下さい。日中はウォーキングなどの軽い運動をすることで良い睡眠が得られます。
眠れないからと飲酒をすることはいけません。飲酒をすると眠りが浅くなり熟睡感が得られなくなります。リラックスするために、半身浴やストレッチ、アロマ、マッサージなど自分に合ったリラックス方法を生活に取り入れてみてください。
また休日は大事なリフレッシュタイムです。オンとオフの時間を切り替えるようにしてみてください。インドアでゆっくり読書をして、映画鑑賞や丁寧に家事をするのも良いです。アクティブにスポーツをしたり、旅行をしたり、美味しい物を食べに行ったり、楽しみ方は人それぞれです。自分が楽しいなぁ、心地よいなぁと思えることを見つけておくとそれが活力になります。
いつもの仕事や学校のコミュニティ以外の人と話す場を作ることも大事です。
普段とは違う人間関係を作っておくと、普段のコミュニティで嫌なことが起こったときに気分転換することができます。
なんとなくで生活していると、自分の心が疲れているのかどうか気づきにくくなります。
以前は楽しめていたことが楽しめているかな、好物の物を美味しいと思えているかなと自分の気持ちを定期的に振りかえってみて、身体と同じように心も大事にしてみてください。
Q.気づかずに放っておくとどんな病気になる可能性がありますか?
A.そのままにしてしまうと、適応障害という病気になってしまい、対応をしないままだとうつ病に進行してしまう可能性が高まります。
適応障害は誰でもなる可能性のある病気であり、早期に対応できればそのあとのリカバリーも早いので、早めに対応することが必要です。
前編の記事で述べたような症状がある場合は、早めにメンタルクリニックを受診することをお勧めします。メンタルクリニックに対して、精神科は怖い、依存する薬を処方されるといった悪いイメージを持たれている方もいますが、最近は明るい雰囲気のクリニックが増えており、薬も改良が進んで依存性のない薬が処方されています。風邪をひいたときのように、悪くなる前に受診しようといった気持ちで受診して欲しいなと思います。
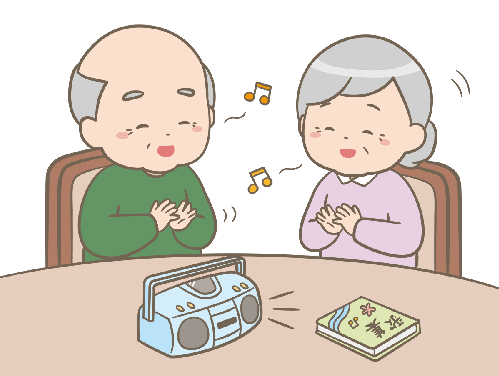
いかがでしたでしょうか。
明日からGWですが、リフレッシュをして気持ちよく連休明けを迎えられるように今から身体と心を整えておきましょう!
春は環境の変化に注意【前編】
2025年04月25日
新年度が始まり、早1か月が経とうとしています。
新しい生活に少しだけ慣れ始めてきた頃は体調不良が起こりやすい時期です。
今回はこの時期に注意が必要な体調の変化について当院の精神看護専門看護師にお話をきいてみました。

Q.春に不調を感じやすい季節といわれるのはなぜですか?
A.新年度が始まり、入学や入職、転勤や引っ越し等、人生の中での大きな変化が起こる時期です。新しい環境での慣れない通勤・通学、学業や仕事、初めての一人暮らし、新たな人間関係を作らなければいけない状況と、緊張や不安が続きます。
そしてGWが明ける頃に、気分が落ち込み心身の不調をきたしやすくなります。
Q.不調にはどんな症状がありますか、年齢は関係ありますか?
A. 遅刻や欠勤をしたり、表情が暗く笑わなくなってしまったり、声をかけても反応が薄かったりします。また、眠れなくなったり、食事が食べられなくなったり、集中力が落ちてしまってミスが増えたり、やる気がでなくなってしまったりします。
見た目で言えば、それまで綺麗に髪型や服装、お化粧といった身なり整えていた人が、髪型や服装を気にかけず、お化粧をしていないなども気持ちに余裕がなくなっているサインの一つです。
頭痛や腹痛、吐き気、発熱といった症状が出る人もいます。精神的な不調が身体の症状として表れることも多く、本人は心が疲れていることに気づいていないことが多いのです。
どの年齢というよりは、環境の変化があったのか、その変化に対応できているかが関係してきます。

次回【後編】では、環境の変化に左右されずに健康的に過ごすための予防や対策についてお話します。
研修医にインタビューしてみた!
2025年04月18日
今年のお花見は雨や強風でタイミングが難しく、あっという間に葉桜となってしまいました。
最近の暖かい日は桜の花びらが風に乗ってひらひらと舞ってきれいな様子が見られます。最後まで桜を楽しみたいですね。

さて、少し遡りますが3月28日に研修医修了式が行われました。
2年間の研修を経て、修了証を授与した後に宇治原院長からメッセージが贈られました。
「これから医者の卵から医者になります。医者になるということは主治医になり、責任の重さを負うことになります。チーム医療の中で他の職種を背負って日本の医療の発展を支えていってほしいと思います。」
また、教育研修部長からは「2024年の研修医の制度改革の過渡期の中、自身も学ぶ中で大変だったと思いますが、研修1年目の後輩のことも手厚く支えていただいたことを讃えたいと思います。医療の中では失敗させてあげることは難しいが、“変化できるものが生き残る”という言葉があるように、失敗を恐れず成長していってほしい。」とエールが贈られました。
研修を担当した各科の医師や、研修医が選んだ最優秀指導者の救急科の医師からも激励のコメントが贈られました。
現在、初期研修を終えた研修医は、専攻医としてさらに専門とする分野の道へ進んでいます。
今回は引き続き当院で専攻医として勤務する先生方に以下の2つの質問についてきいてみました。
①どんな医師になりたいですか?
②当院で専攻医になろうと思った理由を教えてください
【救急科専攻】
①周囲とのコミュニケーションを大切に、患者さんや他の医療スタッフに安心感を与えられるような頼もしい救急医になりたいと思います。
②2年間の初期研修を通して、医師としての基礎的な技術や考え方の多くを学ぶことができました。どの診療科の先生も大変教育的で、診療科間の垣根も低く今でも悩んだ時にはすぐに相談できる環境があります。専攻医としてまた新たな道を歩み始めるときにそうした基盤があることは大変心強く、自身の成長につながることであると確信したため当院で専攻医になりたいと希望いたしました。
【消化器内科専攻】
①幅広い知識や技量を持ち、それらを適切なタイミングで発揮することのできる医者やどんな頼まれごとをまずはやってみる!の精神で患者に対して向きあっていく医者になりたいです。
②研修医から専攻医になる上で、環境の変化が研修に与える影響は大きいと考えていました。2年間慣れ親しみ、そして育ててくださったこの病院でさらに研鑽を重ねて成長していくことで初期研修を行ってくださった恩を返すつもりでこの病院で働かせていただきたいと考えております。
【循環器内科専攻】
①どんな時でも慌てることなく対応でき、患者さんの予後や退院後の生活も考慮しつつ協力して検査や治療を行える医師になりたいと思います。
②初期研修ではどの診療科・病棟でも雰囲気よく丁寧に指導していただき充実した2年間でした。3年目も引き続き当院で働かせていただくことで、シームレスに知識や手技の獲得に向けて勉強を続けることができる点が魅力と考えました。


研修医修了式後は職員食堂でお疲れ様会が開かれていました!
皆さん、お疲れ様でした😊

新採用者対象のオリエンテーションを実施しました
2025年04月11日
今日は先週行われたオリエンテーションについて、一部紹介します。
【辞令交付式・院長挨拶】
新採用職員の代表者は、堂々と辞令を受け取り、頼もしさを感じさせる場面でした。
辞令交付後、院長からは当院の概況や、地域における中核病院としての役割などについて講義がありました。
そして、新採用職員の皆さんに向けて、「「この病院で働いてよかった」と職員自身が誇れる病院にしたい」という院長ポリシーや、「良いことも、悪いことも報告してほしい」と意見が言いやすい、働きやすく安心できる職場環境であることをお話しいただきました。

【縫合研修(研修医向け)】
当院の形成外科医師が講師を担い、「縫う箇所が一直線じゃなかったらどう縫う?」など常に研修医のテーブルを回って声をかけ、気さくな雰囲気の中で研修が行われました。
研修医からも、講師に対して質問が出るなどコミュニケーションも活発にあり、とても実のある研修となりました。
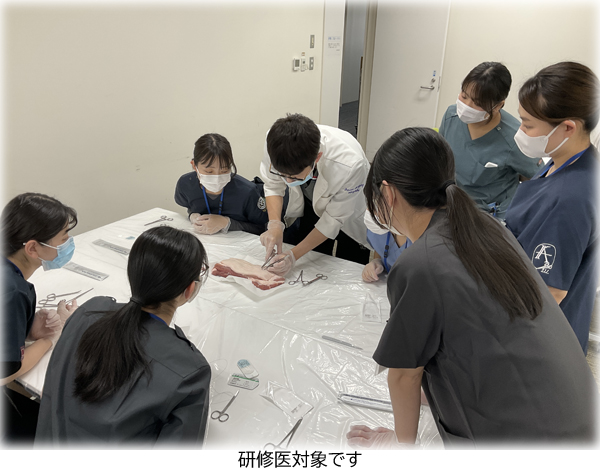

【ネットワークセキュリティについて】
この講義では、情報管理は他人任せにするのではなく、患者さんの個人情報を扱う組織であり、職員一人一人が情報管理の重要性を認識する「リスク管理の必要性」や「機密性の取扱い」についても説明しました。
お昼休み明けでお腹いっぱい、更に部屋も暖かかったので眠ってしまうかな?と思いきや新採用職員の皆さんは、真剣かつ慎重な面持ちで聞いていました!

また今回は、当院の隣にある大正消防署の署長にもオリエンテーションにご参加いただきました。
併せて、ブログをご覧いただいている皆様へのメッセージを頂戴しました。
「電気火災や放火など、最近戸塚区で火災が増えています。燃えやすいものを近くに置かないなど、日ごろから身の回りの整理整頓を心掛けましょう!」

以上、オリエンテーションのほんの一部ではありますが紹介させていただきました。
現在、新採用職員の皆さんは各現場に配属され業務がスタートしています。
慣れない中でも、一生懸命前向きに取り組む姿は、既存の職員に対しても良い影響を与えています。
我々も、新採用職員の皆さんをしっかりサポートしていきますので、今後の活躍をみなさまにも応援していただけると嬉しいです。
看護部については、今年度も新人看護師研修の様子をブログにUPしていく予定です。
今後とも横浜医療センター病院ブログをよろしくお願いします😊
当院で横浜市乳がん検診を受けられます
2025年04月04日
新年度が始まりました!
あいにくの天気でのスタートでしたが、今週中はオリエンテーション期間として手続き関係や、当院の概況やルールなどの説明を行いました。
新しい環境となると何をするにも疲れてしまいますが、季節の変わり目でもありご自身の体調管理もしっかり行いながら、ゆっくりと職場に慣れていただきたいと思います。
オリエンテーションの様子はまた後日のブログで更新したいと思います。

さて、先日当院ホームページに乳がん検診のご案内を掲載しました。
乳がんは定期的な検診を受けることで早期発見につながり、早期に治療を行うことで完治する可能性が高い病気といわれています。
通常は何か気づきがあって受診する方が多いと思いますが、自覚する前の発見が大切なので医療機関等で早い段階で見つけるためにも定期的な検診をおすすめします。
当院乳腺外来では、毎週月曜日10:30・13:30と金曜日13:30の検診予約枠を設けております。
検診では女性の乳腺外科医師と女性検査技師が担当しています。
当院におかかりでない方もお気軽にお問い合わせください。

横浜市乳がん検診についてはこちらをご覧ください。(横浜市ホームページ)
桜咲く季節に、ありがとう🌸
2025年03月28日
各地で桜の開花の様子が見られます。
当院敷地内の桜は、今週始めはまだつぼみだったのですが水曜日に見に行ってみると花が咲いていました。(26日(水)は夏日のような暖かさでした☀)
今週末はまた天気は下り坂の予報ですが、長い期間お花見を楽しみたいですね。



さて、今回は今年度で定年退職を迎える産科病棟看護師長にインタビューしてみました。
Q1.これまでの歩み(横浜医療センターに入職されたきっかけ、当院で何年勤務されたか)を教えてください。
昭和61年3月に国立相模原病院に就職。
助産師になりたくて助産師学校を受験したが補欠合格。
欠員が出なくて入学できず、相模原病院の産科病棟に配属され、看護師として1年間実務と勉強をして、昭和62年は助産師学校に入学しました。
卒業後の昭和63年3月に今度は助産師として相模原病院に再入職。
その後、平成22年4月に国立成育医療センターへ出向し、看護師長に昇任。
平成30年4月に横浜医療センターへ転勤し現在に至ります。
横浜医療センターでは7年間お世話になりました。
最初の2年は、東7消化器外科病棟、その後東4産科病棟に配置換えとなって、5年間を過ごしました。
Q2.長く看護師を務めるにはどんなことが大切だと思いますか?
助産師が天職と思っているので、仕事を楽しめることが長く務めるためには必要かなと思います。(あとは、生活のためやむを得ずというところもあります)
Q3.これまでのやりがいにつながったエピソードなどがありましたら教えてください。
お産の介助は、いつになってもとても緊張するので苦手ですが、頑張るお母さんの姿や生まれた後の赤ちゃんとお母さんの姿を見ると、感動で一杯になります。これがやりがいに繋がっていると思います。
Q4.若手看護師に伝えたいことはありますか?
学ぶべき知識がたくさんあり大変ですが、学ぶことによりできることが増え、できることが増えると、患者さんが元気になったり笑顔が増えるので、「石の上にも3年」と思って励んでほしいです。
Q5.これから看護師を目指す方へメッセージをお願いいたします。
看護師・助産師の仕事は、奥が深くて飽きません。一生続けられる仕事なので、しっかり学んで、目指してほしいです。
母子医療センターInstagram(@yokohamahahako)の開設等、我々広報部もお力添えをいただき大変お世話になりました。
病棟の雰囲気も和やかで、いつも親身に相談を聞いてくださったり、プライベートなお話もしてくださり、楽しいひとときでした。
新たなスタートを心よりお祝い申し上げます✨
横浜医療センターの職場環境ってどんな感じ?
2025年03月21日
ここ最近のお天気は交互に訪れる季節外れの暖かさと寒さでなかなか落ち着きませんが、卒業式に向かう華やかな衣装のお子さんたちを見かけて清々しい気持ちになりました。
これから新しい環境になる方も多いと思うので、今日は当院の職場環境についてご紹介します。
当院には約1000人、そのうち看護師600人ほどが勤務しており、職員同士の仲が良く、職場は穏やかな雰囲気です。
実際のところどうなのか、いろいろな職員に聞いてみました。
🔹病院によっては、「これは医師の仕事」「これは看護師の仕事」というふうに、職種ごとの線引きがはっきりしているところもありますが、当院はそういう壁があまり感じられなくて、みんなで協力しながら、患者さんにとって最善のことをしようという意識がすごく強いと感じます。
🔹とても働きやすい環境だと感じています。診療科や部門間の垣根が低く、どこにでも相談しやすい雰囲気が特徴です。
また、職員の半数以上を占める看護部では副看護師長たちの取組で職員のモチベーションを向上させる「もっとほめられ隊」というグループが活動を行っています。
「もっとほめられ隊」の取組の一つとして、院内でほめる文化を作り、みんなが仕事にやりがいを感じ、より円滑な人間関係を築けるように、サンキューカードを導入しました。日々忙しく、頑張っている看護部の同僚へ、ありがとうの気持ちをサンキューカードに記入し、各部署に設置したBOXに入れてもらいます。BOXに入れられたカードは、看護師長等を通じて本人に贈られます。受け取った職員からは、「看護師長から手渡されて驚いたしうれしかった」という感想をいただいています。
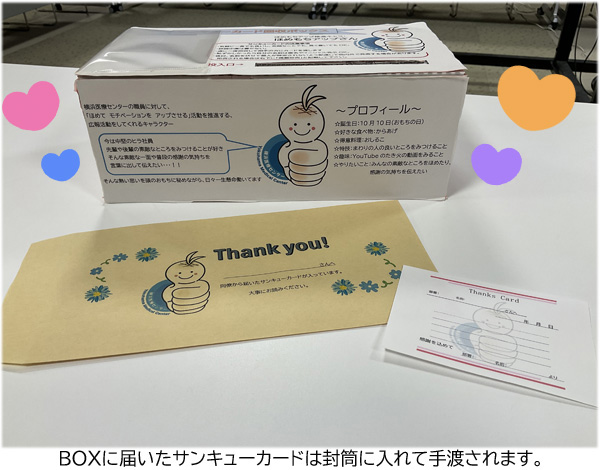
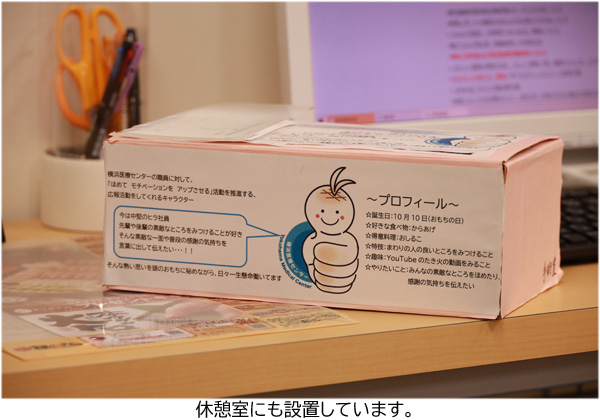
ありがとうの思いが直接伝わることで、仕事のモチベーションアップにつながると嬉しいという思いで活動に取り組んでます。
もう一つ、職員へ活動を広めるにあたり、サポートしてくれる新キャラクターが誕生しました!その名も「ほめもちアップさん」です!

モチベーションの「モチ」から「おもち(餅)」を連想し、アップの時の指の形と組み合わせています。
ぷうっとふくれた頭の中は、『みんなのいいところを見つけて、ほめてあげたい』という思いでいっぱいです。そしてそんな思いがどんどんふくらんでいく…みんなを応援したい!と思っているキャラクターです。
すべては患者さんに寄り添った医療や看護の提供のために、当院では今後も、モチベーションや向上心が高まるような職場の環境づくりを大切にしていきたいと思います。
新人看護師研修vol.5
2025年03月14日
昨日は久しぶりに晴れて暖かい1日でした🌤
当院ではピンクに色づいた桜のつぼみが見えました。
開花まであと少しのようです♪
だんだんと暖かくなってきて、春になったらやりたいことを考える方も多いのではないでしょうか。その一方で、花粉やアレルギー症状だったり、新しい生活のストレスを感じたりすることもありますので、心や体と相談しながら楽しく過ごしたいですね🍵

さて、このブログでもお伝えしてきた新人看護師研修ですが、2月に最後の研修を行い、総まとめとして看護の振り返りを行いました。
1年を振り返って「今後どのような看護をしていきたいか」について各自レポートにまとめ、グループで発表しました。発表を終えた後は、グループワークでさらにまとめを行い、全体で発表をしました。
最後に新人看護師たちへ、教育担当看護師長、教育担当看護師長と副看護師長、副看護部長から激励のメッセージが贈られました✨
💌1年間お疲れ様でした!初めのうちは業務を覚えることで忙しかったと思いますが、今では患者さんの想いを汲み取ることまで考えた看護を提供していて1年の研修が形になったと思います。
💌新人の時に想った気持ちは今も変わらないので、今の時期に芽生えた看護観を大切にしてください。
💌患者さんのケアの方法などについて、カンファレンスで発言していると聞いて頼もしいと感じています。2年目になるとまた忙しくなると思いますが今の気持ちを忘れずに看護を続ければ、気持ちが患者さんに届くと思います。今後も期待しています!
💌本当にみんなよく頑張りました!!お互いを褒め合って自分のことも褒めたたえてください。そして4月からは新たに入職する新人看護師を今度は皆さんが支えてあげてください。
新人看護師の皆さん、学びの多い1年だったと思います。本当にお疲れ様でした🤗
2年目も一緒に頑張っていきましょう!
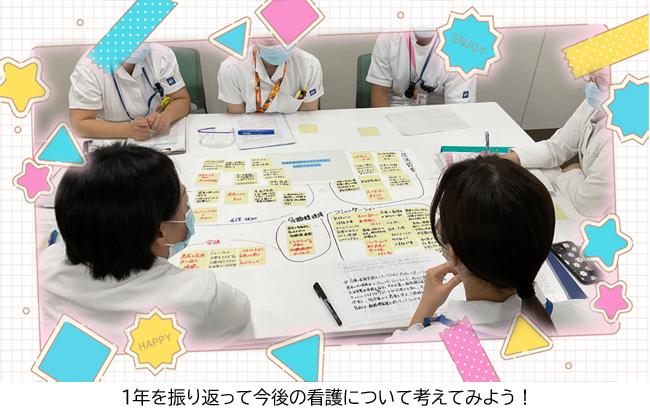
看護学生と交流会を実施しました
2025年03月07日
3月に入りました。
新たな年度を迎える準備が始まり慌ただしくなる季節ですね。
そして3月といえば卒業式。
当院附属看護学校でも3/4に卒業式が執り行われました。
卒業を迎えた皆さんおめでとうございます🌸

看護学校の1年生も着実に学習を進めており、初めての臨地実習を終えました。
実習先は国立病院機構グループの病院が多く、当院でも受け入れています。
実習の直前には不安を解消するため、当院の看護部が企画を行い、実習指導者である看護師と学生の交流会を実施しました。交流会の中で、学生からの質問に看護師が答える場面がありましたので、今日はこちらの内容をご紹介します。
~Q&A✨~
Q1. 患者さんとのコミュニケーションのコツは?
A.「学生さんの傾向として、どうしても情報を集めなければいけないと思ってしまい、情報収集に一生懸命になってしまうところがあるので、そうではなくて患者さんに興味を持って話してみるのがいいと思う」
Q2. 実習の事前学習でどのようなことをしておいたら良いか
A.「バイタルサイン測定を初めて実施すると思うので、しっかり練習してきてほしい」
「患者さんが安全・安楽に過ごす療養環境について勉強してきてほしい」
Q3. 実習指導者への報告のタイミングや、話しかけたらダメなタイミングは?
「指導者は、学生から声をかけてもらうのを待っています。何か実施する前や実施後などはすみやかに報告してほしいし、考えていることをしっかり伝えてもらえると、指導者も学生さんが経験できるように考えられるので、報告や相談をしてほしい」
Q4. 便利グッズを教えてほしい
「メモ帳&ボールペン:いつでもメモをとれるように準備しておきましょう」
「秒針付きの時計:患者さんの脈拍などを図るときに必要になるので、持っておくと便利です」
その後のレクリエーションではクイズ大会を行い、上位チームからプレゼントのドーナツをGETしました🍩


今後も当院では、学生が充実した実習を行えるようにサポートしていきたいと思います。
YouTubeで昨年度の交流会の様子もご覧いただけます。
「2024年看護学生と実習指導者の交流会」はこちらからどうぞ。
副院長ブログ「休日の過ごし方」
2025年02月28日
今日は、今回で第3弾となる副院長ブログをアップします。
宮崎副院長は、今年度より広報部長として広報全般を取り仕切っており、ブログ記事作成にとどまらず、難しそうな企画に対してもGOを出してくれるなど、当院の積極的な広報を支援してくれています😊
梅も満開になって、寒さの中にも春の様子が見られるようになりました。
年末から随分とカラカラ天気ですが、三寒四温の春の天気も間もなくでしょうか。
さて、その好天を利用して、先月の成人の日に、本当に久しぶりでしたが、自転車仲間と1日、初詣サイクリングへ出かけて参りました。
どこかの神社に、ではつまらない、ということで、相模国、一宮から五宮+総社(全部の神様がおられるそうで)を順に回る、という次第。ご存知の方も多いと思いますが、国府の置かれた周囲に格式順に神社があります。寒川神社から始まって、六所神社までで六つあります。
できるだけ一筆書きになるように、平塚をスタート、寒川町、二宮町、伊勢原市、平塚に戻り(平塚に二つあります)、最後は大磯町、と回って平塚に戻ります。
私は知らなかったのですが、二宮、三宮、四宮、ちゃんと地名になっていたんですね。合点がいきました。
幸いに寒さも緩んだ日だったので、絶好の日よりでした。この順番、というこだわりが走行距離をいたずらに増やします。さすが頭のネジが一本外れている人たちばかりが集まっただけのことはあります。
寒川神社はさすがにすごい人出でしたが、あとは落ち着いた、初詣に相応しい神社ばかりでした。成人の日とあって、晴れ着の若者を沢山見かけました。おめでたいですね。自身は40年前、と思うと遠い目になってしまいます。あちこちでお守りを頂き、各種の脅威から身を守る様にしておきました。

うちの病院にもきっとサイクリング好きがいるに違いないので、季節がもっと良くなったら、一緒に出掛けたいものです。 写真のお守り、六所神社は1カ所で5カ所の神様全員祭ってあるそうで、タイパ良しです。
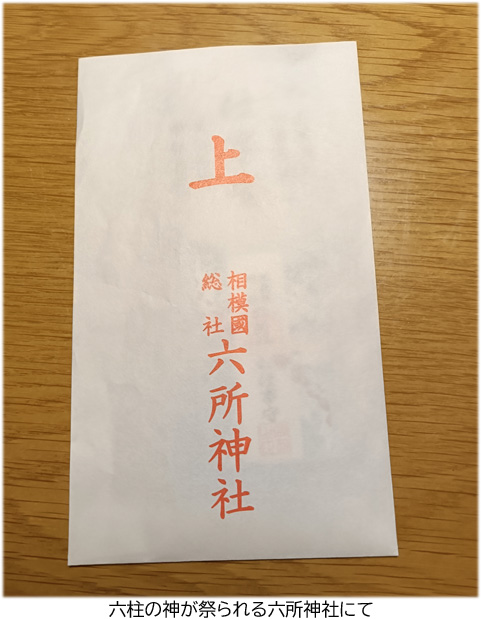
職員向けのグルメフェア企画を実施しました
2025年02月21日
寒さは相変わらず続きますが、夕方は少しだけ陽が伸びてきました。
当院正面には梅の花が咲いています。


そして毎年春に満開を迎える桜の様子は、まだ茶色くて硬そうですが芽がでているようでした。桜の開花までについて調べてみると、なんと秋頃にはすでに蕾が完成し、「咲くのは今じゃない!」と我慢しているそうです。そのためにも桜にとって冬の寒さは重要で、冬の風を浴びて咲くタイミングを待っています。
明日からの3連休も寒くなる予報ですが、季節はしっかりと春の準備が進んでいます。
さて、恒例となった職員食堂グルメフェア企画が1月に実施されました。
今回のメニューは、前回実施の際にアンケートでリクエストが多かった”韓国フェア”です!


この企画は看護部の副看護師長たちの取り組みで開催されており、以前までは、主に看護職員を対象にアンケート調査を行っておりましたが、今回は看護職以外の食堂利用者へ行ったアンケートの回答も参考にしながらメニューを決定したそうです。
テイクアウトしたランチを撮影させてもらいました😋

「見た目以上にキンパが大きくてお腹いっぱいになった!」
「チヂミが入っていてうれしかった」
などの感想を聞くことができ、今回も好評だったようです!
このイベントでは、看護師は夜勤勤務があるので、1日開催だけではなく、2日間の開催ができるようにこだわっているそうです。
そのため、実施回数が増えるたびに「今日はお弁当にしないで食堂のランチにしようと話していたの!」など盛り上がりを見せています。
今後も、当院で働く職員が楽しめるイベントの企画を充実させ、魅力ある職場作りを職員のみなさんと盛り上げていきたいと思います!
中学生職場体験プログラムを実施しました
2025年02月14日
当院では広報誌「はらじゅくかわら版」を年4回、発行していますが、ご覧になったことはありますか?
昨日、2025年冬号をホームページにアップしました!
2022年にリニューアル号を発行後は、表紙の写真については院内で公募を行い選出しています。
今号の表紙は「北海道で出会ったシマエナガ」が選ばれたので、撮影者の職員に少しお話を聞きました。
「北海道へ帰省した際に、シマエナガをウォッチングできるカフェがあり夫婦で訪れた時に撮影しました。カフェにいながら野鳥のシマエナガが登場するとお店の方が教えてくれるシステムで、その場から望遠レンズを伸ばして撮ることができました。可愛いシマエナガを皆さんにもお届けできると嬉しいです。」
さて、1月に当院近隣の大正中学校の2年生5名が職場体験に参加してくれました。
ユニフォームに着替えて看護体験スタート!
始めのオリエンテーションで副看護部長から「今日を楽しみに待っていました!皆さんも楽しんで看護体験してください🤗」と挨拶があり、それから簡単に当院の概況について説明し、クイズを行いました。
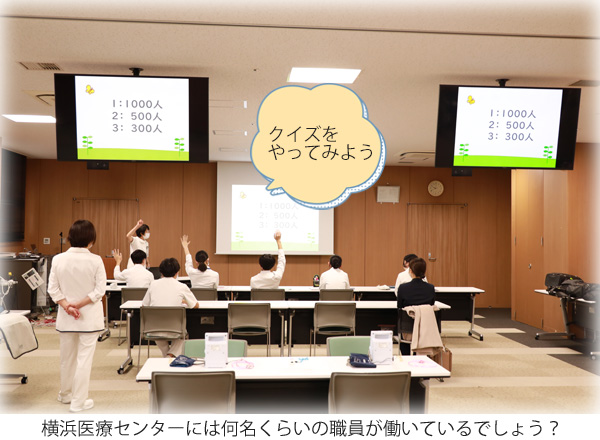
ちなみに当院では約1000人の職員が働いており、そのうち約半数が看護師です。
また、「病院にはどんな職種の人たちがいるでしょう?」と質問をしてみると、医師、看護師、栄養士と答えがあがりましたが、他の職種は皆さん思い出せない様子…。
司会の看護師が「みんなも病院にかかったらお薬もらわない?薬剤師という職種の人がいるよ!」と言うとみんな揃って「あぁ~‼」と気づき、意外と知っている職種がたくさんあることに興味を持ってその他の職種の紹介についてもお話を聞いてくれていました。
BLS(一次救命処置)の講師を担当する看護師からは、「自身も高校時代での職場体験がきっかけで看護師を目指したので、今日の体験が将来の職業選びのきっかけになってもらえると嬉しいです」と挨拶をしました。
その後、車いす乗車・健康チェック・BLS体験を行いました。




皆さん、真剣に体験を行っていただきこちらも嬉しく思いました。
今後も、看護師や病院の仕事に興味を持っていただくきっかけとなる取り組みを継続していきたいと思います。
ご参加いただいた皆さん、ありがとうございました😊
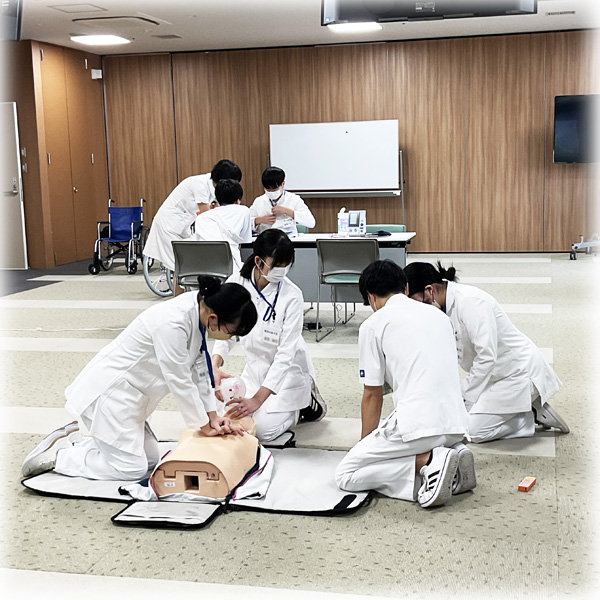
市民公開医療講座を開催しました
2025年02月07日
暦の上では立春を迎えましたが、春の気配はまだ遠いようです。
この冬最強寒波が襲来し、大雪の影響が出ている地域があります。
横浜も今週半ばからは路面凍結が見られました。
当院の敷地内でも、前日に降った雨の水たまりが凍っていました。週明けまで寒さが続く予報です。
春が待ち遠しいですね。
さて、1/9(木)に戸塚区役所3階の多目的スペースで市民公開医療講座を開催しました。
今回は当院の乳腺外科医師が「あなたのための乳がんセミナー」というテーマで講演しました。
日本での乳がんの患者数が増加傾向にあるという話から、発病のリスクや予防、診断の流れや治療方法まで詳しいお話をしていただきました。
またセルフチェックの方法も紹介があり、1時間強、皆さん真剣に先生のお話に耳を傾けてくださり、終了後の質疑応答も活発でした。


お話の中で、乳がんの発見は自身でしこりを発見して診断に至る、もしくは検診で見つかる場合がほとんど、とありました。また、今は自分で検索などをすればいろいろな情報を得ることができるが、ネガティブな情報も多く不安になってしまうこともあるので、病院などの信頼できるところから情報を得てほしい、との話もありました。
乳がんについてだけでなく、地域の皆さんに正しい知識を持ってもらうために今後もイベント等を通じて積極的に情報発信し、お役に立てればと思います。
医師からのコメント💭
今回はこのような機会をいただき誠にありがとうございました。
会場が予想外に広く圧倒されてしまいましたが、一時間という限られた時間で乳がんの診療について様々な内容をお話させていただくことができました。
検診については時間の関係であまり触れることはできなかったので、次回の機会があればまた違った視点でお話できればと思います。
お忙しい中、会場にお集まりいただいた皆様、関係者の皆様に心より感謝申し上げます。
「病病・病診連携のつどい」 を開催しました
2025年01月31日
強く冷たい風が吹く1週間でした。
週末には雪の予報が出ています⛄
また、来週は今季一番の寒波で厳しい寒さとなるようです。
天気予報を確認して早めに対策をしておきたいですね。
さて、少し前ではありますが、昨年末に、当院で「病病・病診連携のつどい」 を開催しました。
※病病:病院(当院)と他病院、病診:病院(当院)と診療所等の医療機関
講演や懇親会を行い、地域医療機関の先生方との連携を強化することが目的です。

当院は皆様ご存じの通り、地域の医療機関(かかりつけ医)の先生方からの紹介により受診することができる医療機関です。逆に言うと、医療機関の先生方が「横浜医療センターには患者さんを紹介したくない」となれば、当院に患者さんはいなくなってしまいます。
当院は地域の基幹病院として、様々な患者さんに最適な医療を提供できる病院と自負していますので、地域の医療機関にも「病病・病診連携のつどい」やその他の取組などにより、当院の専門性(強み)や現状などを発信していく必要があります。
当日、講演では、当院の宇治原院長より、地域の先生方から紹介いただいた患者数の報告や、当院の現状などを説明しました。
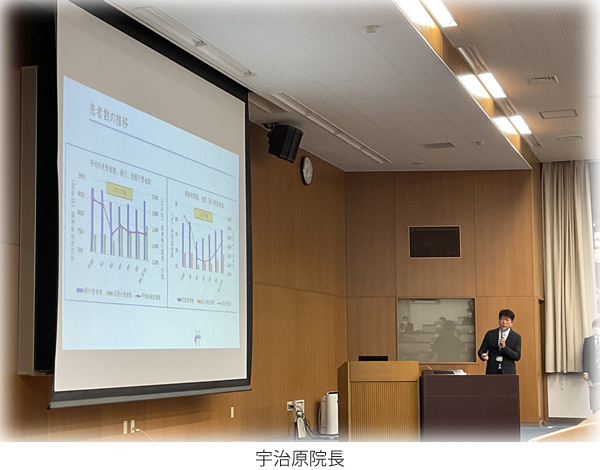
4月から認定された「地域がん診療連携拠点病院」のことや、コロナ禍以降の病院の様子についてもお話しました。
また、近く手術ロボットの導入予定があるため、泌尿器科部長の平井医師により、ロボット手術の種類や方法などの説明が行われました。

横浜医療センターは今後もさまざまな施策に取り組み、地域の医療機関や患者さんの信頼を高めていきたいと考えています。
マイナ保険証カードリーダーを増設しました
2025年01月24日
今週の日中は、厚手の上着がなくても過ごせるくらい暖かい日がありました。
ただ、日差しが出ていても風が吹くと寒く感じます。
横浜では微量ですが、すでにスギ花粉が飛散しているそうです。
花粉症の方は、そろそろ対策準備が必要になりそうです。
さて、マイナ保険証についてはすでに報道などで、ご存じの方も多くいらっしゃると思います。
当院では昨年12月に入り、マイナ保険証の利用者数が2000人を超え、既存のカードリーダーだけでは患者さんにマイナ保険証の読込みでお待ちいただく状況でしたので、スムーズに受診いただくためにカードリーダーを増設しました。
今回増設したのは、外来ブロックA~Dの各受付4か所です。

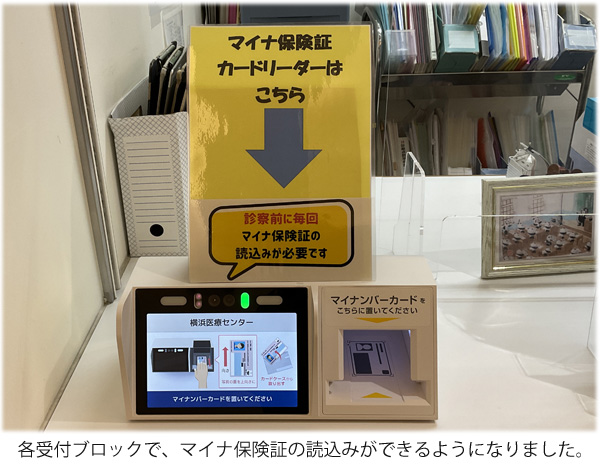
また、12/2以降は操作方法が簡単になり、2STEPでマイナ受付ができるようになりました。

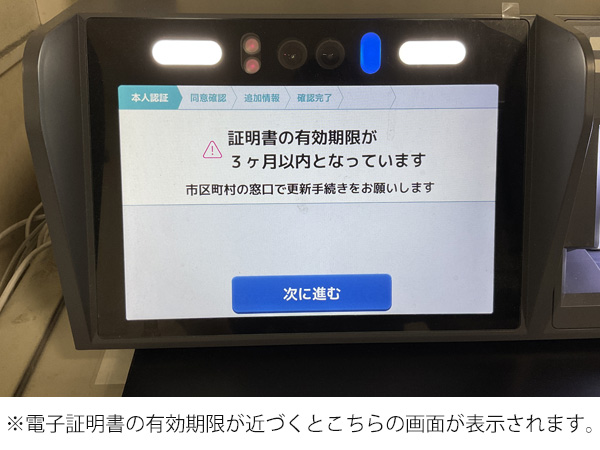
電子証明書の期限は5年。マイナンバーカードの期限は10年です。
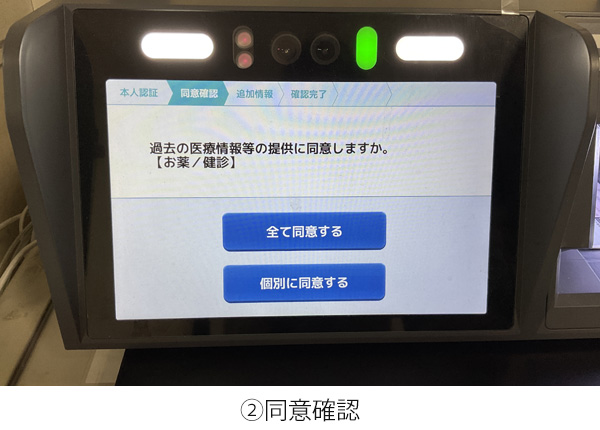
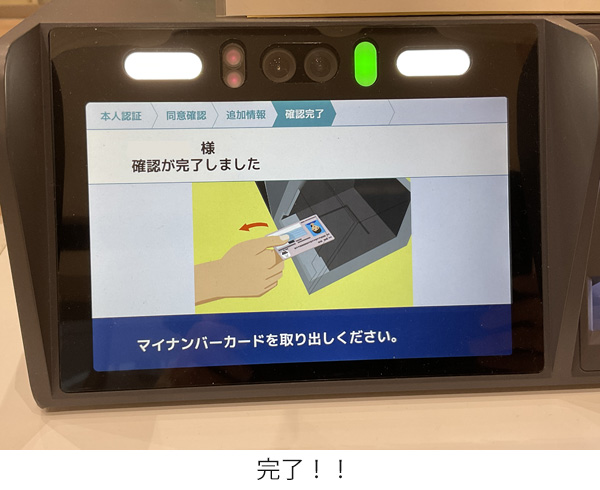
現在、定期的に外来ホールでマイナ保険証のご案内をしているところですが、患者さんからは『紙の保険証が使えなくなりますか?』や『紙の保険証しか持っていないけど、これからどうすればいいですか?』と多くのご質問をいただきます。
これは2024年12月2日以降、健康保険証の有効期限が切れても更新や紛失時の再発行ができないためです。
最長の有効期限の方でも、年内で紙の保険証は利用できなくなりますので、いざという時のために、マイナ保険証について、再度確認しておきましょう!
新人看護師研修vol.4
2025年01月17日
今朝も空気がヒンヤリとして冷え込みましたね。
寒さの中で、今週火曜日頃にはきれいな満月が見えました。
この時期ならでは冬の夜空を楽しみたいです。
暖かくしてお過ごしください。
昨年11月に、看護1年目の職員たちが静脈注射の講義を受け、12月に「院内認定静脈注射」の実技テストを受けました。

テストの順番待ち中のみなさんは緊張気味でしたが、教育担当の看護師長に「緊張するね!頑張って~!」と声かけをされて、少し笑顔が見られました。
テストは全員合格されたそうです!
その後は、各部署で先輩に指導を受けながら実践経験を積み、静脈注射ができる看護師として院内で認定されます。
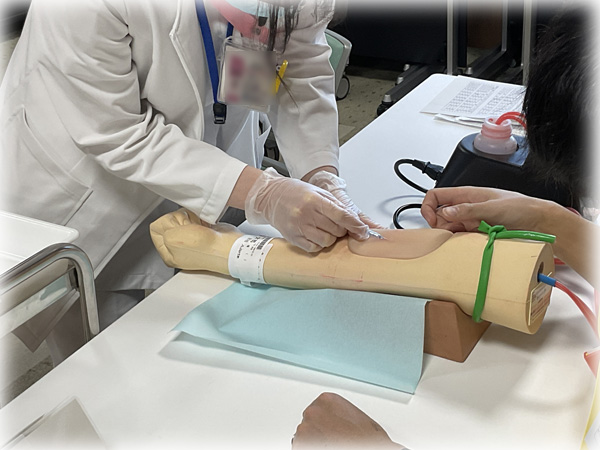
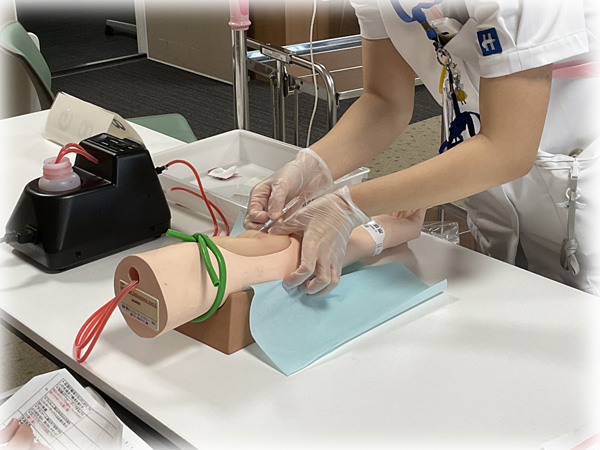
患者さんの身体に針を刺して薬液を入れる重要な行為なので、先輩たちの中で見守られながら慎重に、徐々に独り立ちできるよう取り組んでいます。
もうすぐ1年目研修の終わりを迎える時期となります。
これからより、1人前の看護師として業務を進めることが必要ですが今後も先輩看護師を始め、病院全体で見守っていきたいと思います。
なお、当院では1年目以降も様々な段階に分けて研修を行っています📝
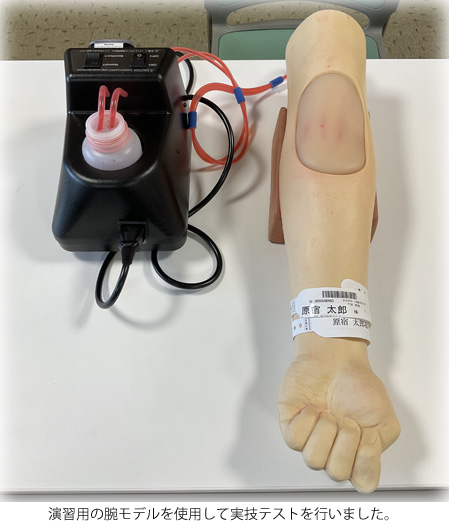
明けましておめでとうございます🎍
2025年01月10日
謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
今年は例年よりも長く、年末年始休暇が取れた方も多かったのではないでしょうか。長い休み明けに、切り替えがなかなかできなかったり、年末年始ならではのケガや、引き続き流行しているインフルエンザに罹患したりと体調を崩されている方を目にします。
無理をせずにご自愛いただけたらと思います。
さて、当院では仕事始めにあたる1/6に“仕事始め式”を行い、院長が今年の指針を掲げられました。
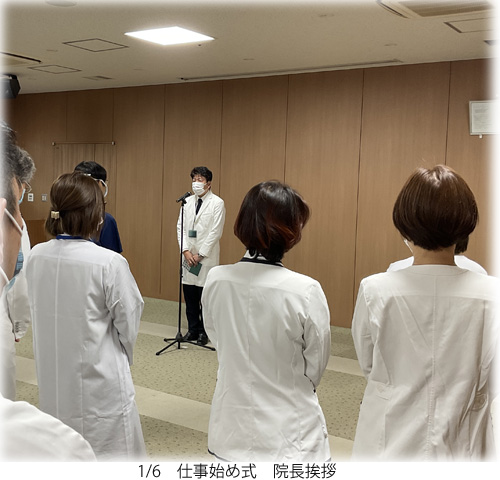
院長のご挨拶についてはYouTubeにて動画を公開中です。ぜひご覧ください。
また元旦には入院中の患者さんへお正月メニューを提供しました。

<食事メニュー>
・れんこんの赤しそ漬け
・帆立照り焼き
・ぶり照り焼き
・いか焼売
・ほうれん草の柚和え
・伊達巻
・かぶの黄菊和え
・紫芋きんとん
・たたきごぼう
・炊き合わせ
・結び湯葉
栄養管理室では、今年も季節を感じる行事食を取り入れてまいります。
楽しみにしていてくださいね。
そして昨年からお知らせをしておりました、「市民公開医療講座」を昨日(1/9)開催してきました。たくさんの方にお集まりいただき、ありがとうございました。
こちらのレポートはまた後日更新したいと思います。
本年も横浜医療センターならびに“病院ブログ”をよろしくお願いいたします。
年内最後のブログ更新です
2024年12月27日
前回のブログに続き、12/24のクリスマスイブには小児科病棟にサンタさんとトナカイ(医師)が登場しました!
クリスマスを病院で過ごす子どもたちの寂しさを少しでも和らげて、楽しんでもらえるようにおやつの提供時間にミニブーツのお菓子をプレゼントしました🎁


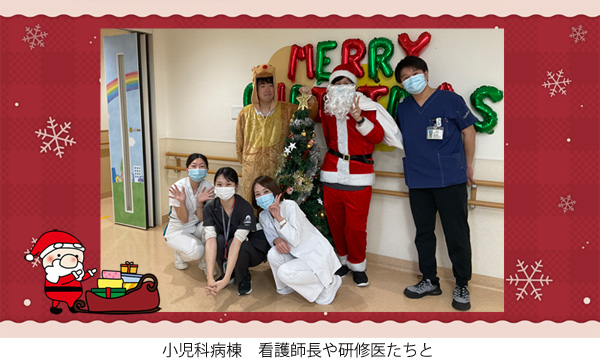
小児科看護師長より💭
「久しぶりのクリスマスイベントで、医師やスタッフたちも気合いを入れて準備をしていました。心待ちにしていた子どもの笑顔を見たときは、心がほっこりしました。
小児科病棟入院中も、子どもたちの大切なイベントを楽しく過ごせるようにしていきたいと思います。」
さて当院ではこれまでマイナ保険証について様々なご案内をしてきました。
■横浜医療センター 病院職員がマイナ保険証のメリットについて解説する動画
2024年12月以降は従来の健康保険証は新規発行が行われず、マイナ保険証への一体化への取り組みが本格的に進んでいます。
2025年3月からはマイナ免許証の運用も開始されると報道がありましたね。
来年からは、よりみなさんがご来院時にスムーズにマイナ保険証をご利用いただけるようカードリーダーを増設する予定ですので、ご安心ください。
設置場所などについては、また来年のブログでお知らせしたいと思います。
そして2025年1月9日(木)には市民公開医療講座を開催します。
乳がんは女性だけでなく、男性も発症する可能性のある病気です。この講演ではがん検診の受診や、もしがんになってしまった時の治療などについてお話しします。
1/6迄、下記のQRコードよりお申込みいただけます。
沢山の方のご来場をお待ちしております。
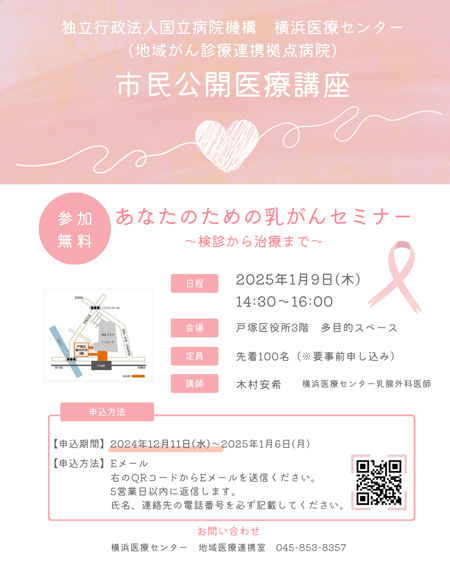
本ブログをいつもご覧いただきありがとうございます。
来年も当院の様々な出来事を皆さんにお知らせできるように更新を続けたいと思います。
年内の診療は本日までとなり、新年は1月6日から通常診療を行います。
どうぞ良いお年をお迎えください。
今年もサンタさんが遊びに来てくれました🎅
2024年12月20日
昨日は東京や横浜で初雪が降り、戸塚区ではコロコロとあられ雪が見られました⛄
年末年始にかけても厳しい寒さとなりそうです。
風邪などひかないように気を付けて、元気に年末年始を過ごしたいですね。
さて、クリスマスを来週に控え、院内はクリスマス仕様になっています。


そして今日、院内保育園では恒例のクリスマス会が行われ今年も保育園にサンタさんが来てくれました!
~保育園園長より~
「12月に入り保育園にクリスマスツリーやクリスマスの飾りが増えてくると、子どもたちもウキウキムードです。空を見上げてサンタクロースを探している2~3歳児さん、クリスマスツリーを見ながらクリスマスクリスマス!と叫ぶ1歳児さん。玄関のクリスマスツリーに興味津々で手を伸ばす0歳児さん。今日は少し早いクリスマス会🎄サンタさんは来てくれるかな?」

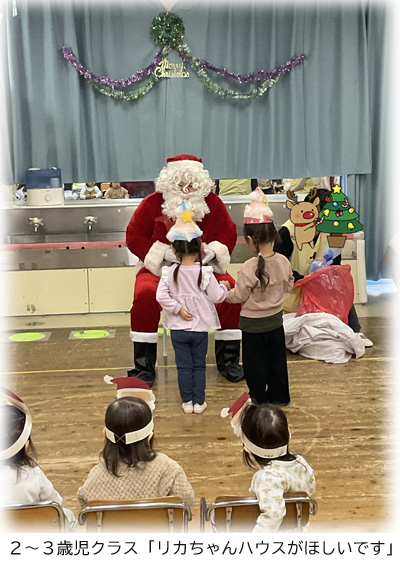
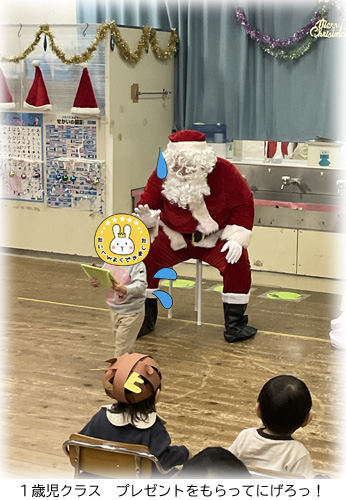

なお、当院敷地内のシンボルツリーのイルミネーションが今年も点灯中です。
癒しの灯を楽しんでいただけたら幸いです。

理学療法士にインタビューしてみた!
2024年12月13日
今回は当院の理学療法士(Physical Therapist)にお話しを聞いてみました。

🔸リハビリテーションに関わる職種はいくつかあるようですが、それぞれ教えてください。
当院のリハビリテーション科では理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が活躍しています。「理学療法士」とは病気やケガなどが原因で、歩く・寝る・座るなどの基本動作が困難な患者さんに対して、体の機能を取り戻すお手伝いをするリハビリの専門職です。
「作業療法士」は、基本動作の応用編で日常生活の動作(洗濯をする・ペンを持つなど)を実現していく専門職です。また、生活に必要な認知機能や高次脳機能にもアプローチして社会復帰に貢献する役割もあります。
「言語聴覚士」については過去のブログをご覧ください。
🔸理学療法士のお仕事について教えてください
よく患者さんから「今日はマッサージ師さんが来てくれた」と言われることもあるのですが、マッサージ師ではありません(笑)
その場で体をほぐして楽にするリラクゼーションの目的とは異なり、医学的に痛みの原因を考えながら、その人の普段の生活スタイルに合わせて体の機能を回復・維持させていくことが目的です。


🔸普段のお仕事内容を教えてください。
私は現在、15人ほどの患者さんを担当し、平日は毎日リハビリを行っています。時期によっては20人くらいの患者さんを担当することもあります。
(当院には現在、理学療法士は14名います。)
1日のほとんどは病棟へ出向き、患者さんの日々の身体面の変化や気持ちのケアも意識して患者さんと接しています。「今はそういう気分じゃない」「おなかの調子が悪い」となれば、予定の組み換えや運動量の調整をしています。
🔸急性期病院ならではの業務はありますか?
当院には比較的重症度の高い患者さんが多いので、病室でリハビリを行うことも多いです。身体の回復が第一なので、治療や処置を優先し、医師や看護師と連携を取りながら患者さんの体調に合わせてリハビリの計画内容を考え段階的に進めています。
急性期から回復期、在宅への切れ目のないリハビリを提供するために発症早期からリハビリを提供しています。また、次の転院先に移れるところまで状態を良くすることが望まれています。
🔸これから理学療法士を目指す方へメッセージをお願いします。
リハビリテーション科だけではないかもしれませんが、幅広い年齢層の患者さんと接する機会があるので、色々な会話の引き出しを持っておくと良いと思います。
医療の現場では患者さんとのコミュニケーションは欠かせません!
🔸おまけ
職業病なのか、電車やすれ違う人の姿勢や歩き方を見ると、自然に歩行分析を行い、この部分を改善できたら良くなるのに!と思ってしまいます(笑)
理学療法士からのコメント💭
「患者さんが心身ともに元気になって退院できるよう、スタッフと共に今後も患者さんとご家族に寄り添いながら一歩一歩リハビリを進めていきたいと思います。」

最後に当院からのお知らせです。
コロナで長らく開催できなかった市民公開医療講座を再開します。
今回のテーマは「あなたのための乳がんセミナー」で、乳腺外科の専門の医師が、乳がんの気になることについてお話しします。来年1月9日(木)の午後2時30分から、戸塚区役所の多目的スペースで開催します。無料でどなたでもご参加いただけますので、下記のQRコードよりぜひお申し込みください。
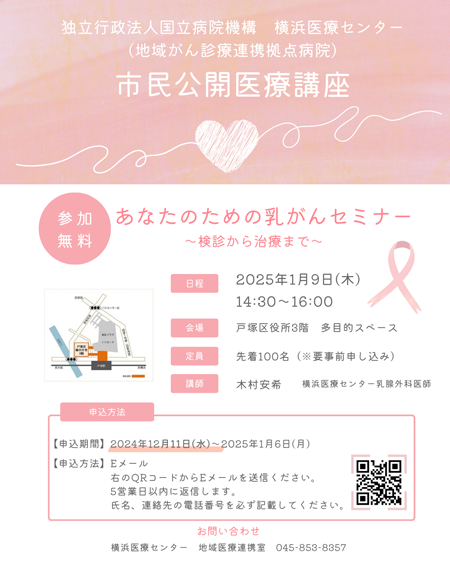
「薬剤師外来」がスタートしました🏥
2024年12月06日
初冬の候となりました。
当院では今週クリスマスツリーが飾られました。
入院中の患者さんやご来院の方々に、少しでも心穏やかな気持ちで過ごしていただけると幸いです。

さて、当院では11月から新たな医療サービスとして「薬剤師外来」を開設しました。
「薬剤師外来」とは、抗がん剤治療を受けられる患者さんに対して、薬剤師が直接お話を伺い、より安全で効果的な治療を支援する取り組みです。
当面は乳腺外科で注射・点滴による抗がん剤治療を受けられる患者さんを対象としています。診察の前に薬剤師がお話を伺い、前回の治療後に起きた体調の変化や気になる症状について詳しくお聞きします。時には医師には言いづらい些細な変化や不安なことも、薬剤師が丁寧にお伺いし、必要に応じて医師に橋渡しをさせていただきます。
また、必要に応じてかかりつけ薬局とも連携を図り、日常生活における体調管理や服薬管理について、地域全体でサポートする体制を整えていきます。実は、このような薬剤師による面談は、抗がん剤の副作用軽減に効果があることが確認され、今年の診療報酬改定で「がん薬物療法体制充実加算」として認められました。
薬剤師は薬の専門家として、これまでも入院患者さんの治療に関わってきましたが、今回の「薬剤師外来」の開設により、外来患者さんへのサポートをより一層充実させることができるようになりました。
当院は今後も地域の皆様により質の高い医療を提供できるよう、様々な取り組みを進めてまいります。
担当薬剤師からのコメント💭
「治療の際に気になることや不安なことがありましたら、遠慮なくお話しください。
患者さんやご家族の方々に、より安心して治療を受けていただけるようサポートさせていただきます。」

看護学生向けの就職説明会を実施しました
2024年11月29日
先月、当院附属の看護学生(2年生)を対象に看護部主催の就職説明会を行いました。
当院を含む県内の国立病院機構グループの5病院が参加し、学生は看護学校内の教室をローテーションして各病院の説明を聞きました。
今回のブログでは当院の説明会の様子についてご紹介します。
始めに、当院に勤務する4名の看護師から、「横浜医療センターに就職してよかったこと」を一言ずつ伝えました。

◽1年目看護師
・新人看護師はキラリバッチをつけているので一目でわかり、いろいろなスタッフに見守られていることを実感する。
◽2年目看護師
・附属の横浜看護学校から就職した同期がたくさんいて、1人で悩みを抱えることがない
◽病棟看護師(実習指導者)
・育児をしながら働いているが、時短勤務に理解があり働きやすい環境を作ってもらえる
◽病棟副看護師長(認定看護師)
・急性期病院なので重症の患者さんが、治療をして退院していく姿を見るとやりがいを感じられる
・様々な患者さんの看護は大変だが勉強になる。自分のキャリアアップアップに繋がることも嬉しい
その後グループに分かれて、4名それぞれの看護師に気になることを質問する時間がありました。
普段は聞きづらい勤務時間や病棟希望についてなど役立つ情報をたくさん教えてもらうことができて、和やかな雰囲気で皆さんとても楽しそうでした。


今回の説明会で、当院の良さが看護学生に伝わったと思います。
最後に当院の看護部長より、これから看護師を目指す方々に向けてメッセージです❣
「看護学生の皆さん、将来どんな看護師になりたいですか。〇〇になりたいと強く思い描いている人もいれば、どんな看護に惹かれるのかこれから探していく人もいるでしょう。入職したての私は、後者だったと思います。
横浜医療センターは救急医療、がん医療、周産期医療、他にも多くの役割を担っています。皆さんの夢を私たちと一緒に叶えてみませんか😊✨」
最後にお知らせです📄
この度、広報部の新しい試みとしてAIを活用して病院ブログの動画を作成しました。
このAI動画はこれまでに更新したブログをピックアップして定期的に当院の公式YouTubeチャンネルに掲載します。
これからも皆さんのお役に立てる情報を発信できる広報を目指して取り組んでいきたいと思います。
今後とも病院ブログ・ブログAI動画をよろしくお願いいたします。

CTとMRIの違いをわかりやすく解説!~知られざる医療機器の世界~
2024年11月22日
今週日曜日は半袖でも過ごせるくらいの陽気でしたが、月曜日に入ると真冬のような寒さとなり防寒なしでは出歩けないほど寒い日がありました。
また、横浜市内ではインフルエンザが流行しています。
引き続き、咳エチケットや手洗いでしっかりと予防していきましょう。
さて、今回は放射線科でCTとMRIの違いについて解説します!
わかりやすく説明しますので、細かい所は省きます😊
CTとMRIはどちらも似たような大きな機械ですが、実は仕組みや得意分野が違います。
どちらの撮影画像も似たような画像です。
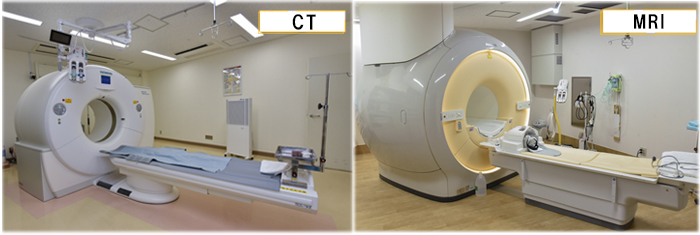
それではCTから解説していきます。
CTは、X線を使って体の内部を画像化します。
X線写真は基本的に白黒の画像ですので、X線が透過しにくい組織は白く、透過しやすい組織は黒く写ります。人体で言うと、X線が透過しやすいのが肺なので黒っぽく写り、透過しにくいのが骨なので白っぽく写ります。筋肉や臓器(心臓、腎臓、肝臓等)はその中間の灰色に写ります。
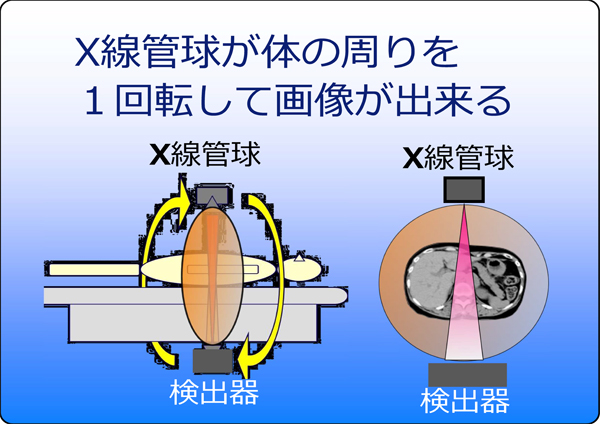
MRIは強力な磁力とラジオ波を使って、体内の水分や脂肪を画像化します。
放射線を使わないので、被ばくする事はないですが、装置は常に大きな磁力を発生しているので注意が必要です。組織の種類(筋肉、脂肪、血液など)によっても水分量や磁気的な特性が異なるため、MRI画像では異なるコントラストが得られます。たとえば、脳では組織によって異なる信号強度で写るため、詳細な脳構造を確認できます。
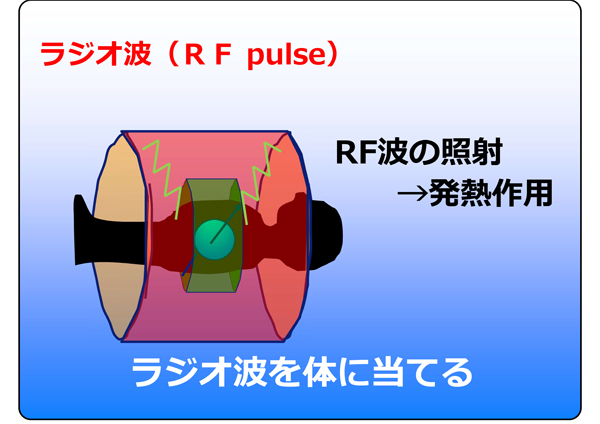
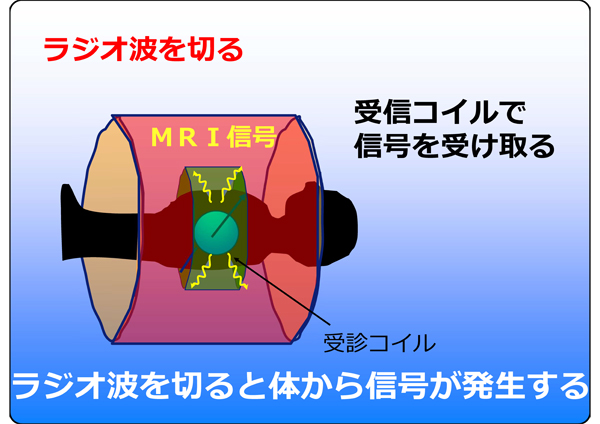
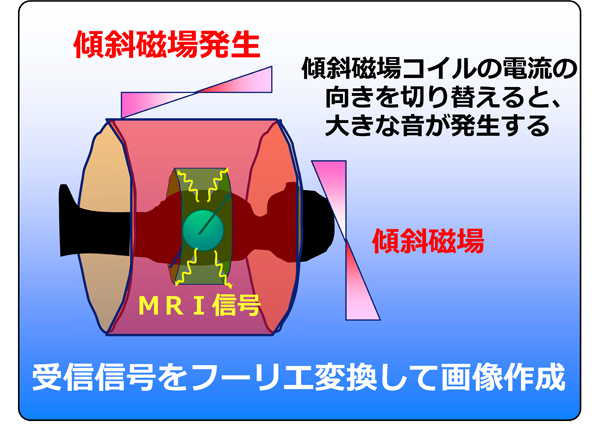
MRIについて詳しい解説はこちらの動画をご覧ください。
CTやMRIの検査をする場合は、それぞれの特徴を活かして使い分けていますが、X線被ばくによる影響や体内金属の有無なども考慮しなければなりません。
CTとMRI、それぞれに得意分野があります。CTは検査時間が短く、且つ広範囲を検査できます。しかし、X線による被ばくがあります。MRIと比較すると脳出血や骨折の描出が得意です。
一方MRIは検査時間が長く、検査範囲も限定的です。X線被ばくはありませんが、装置の特性上体内に磁性体がある方は検査が出来ません。また検査中は体温の上昇や非常に大きな音が発生します。CTと比較すると脳梗塞や四肢の筋肉や靭帯の描出が得意です。
今回は簡単にCTとMRIの違いを解説しましたが、YouTubeの横浜医療センター公式チャンネルには放射線検査の説明や検査による被ばくの説明の動画がありますので、ご興味のある方はこちらもご覧ください。
国立病院総合医学会 in大阪に参加しました
2024年11月15日
昨日、11月14日は「世界糖尿病デー」として、糖尿病の脅威が世界規模で拡大していることを受け、予防や治療の重要性についての注意喚起を目的として国際糖尿病連合と世界保健機関によって制定されています。
当院でも外来ホールにて「世界糖尿病デー」に関する掲示を行いましたのでポスターの内容を抜粋して皆さんにもお伝えします。
「糖尿病は生活習慣の乱れ・だらしないというイメージが強く社会的に疎外されて心苦しい思いをする方がいますが、遺伝的な体質の要素で糖尿病になる人もいるので、偏見を減らして新しいイメージを持つきっかけになってもらえると嬉しいです。」

さて、先月10月18日~19日にかけて国立病院総合医学会が開催され、全国の国立病院機構の施設から約6000名の職員が参加し、様々な発表や討議が行われました。

当院からも34名の職員が参加し、医師、看護師、薬剤師、事務職員がそれぞれの分野について発表を行いました。
我ら広報チームからも代表職員が、マイナ保険証の利用促進について、YouTube動画作成、院内職員に向けた広報誌作成についての取り組みについて発表を行いました。
発表では優秀な演題が各セッションから1つ選定されるのですが、今回「マイナ保険証の利用率向上」がベスト口演賞に選ばれました。
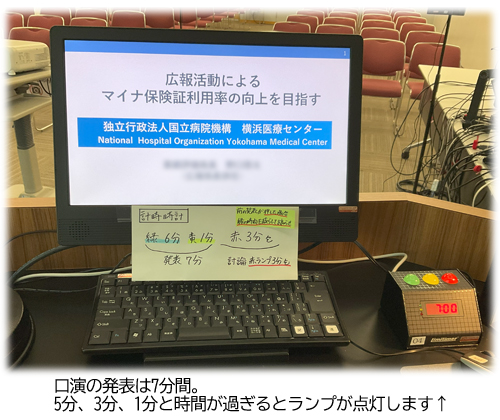
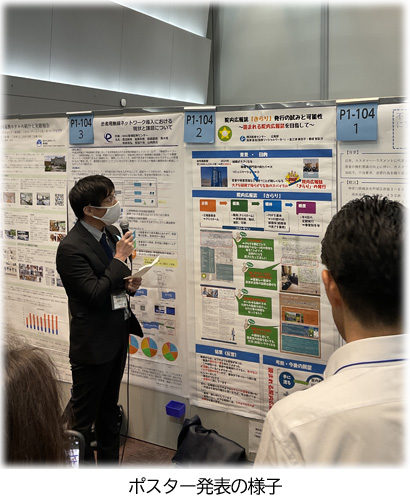
参加された職員の皆さん、お疲れ様でした!
職員からのコメント
「他病院の活動や課題解決に向けた取組など、見回れないほどのセッションが同時に行われ、非常に学びになる機会となりました。今後、学会で得た学びを活かしそれぞれの職種から関わる皆さんへ貢献していきたいと思います。」
職員からのお土産写真📷



副院長ブログ「休日の過ごし方」
2024年11月08日
立冬を迎え、暦の上では冬が始まりました。
昨日、東京都心では木枯らし1号の発表があり、まさに冬の訪れとなりました。
そろそろ冬のコートが必要になりそうですね。
さて、今回は副院長に休日の過ごし方についてブログ執筆いただいたのでこちらの記事をアップします。
休日をどのように過ごされるか、それぞれの方に持論があると思います。
私の場合は何かしら修理したり、整備したり、また数日前の新聞を読むことなのです。
でも、年に2回だけですが、フルマラソンに出ております。
ここしばらくはDr.ランナーとして横浜と佐賀の大会に出かけて、他のランナーに声掛けしながら走ったりしています。
毎年10月の終わりに横浜マラソンが開催されますが、これが2万人以上参加の巨大レースで、目の届く範囲ランナーばかりになります。高速湾岸線を封鎖して走るのが売りなのですが、実はランナーには不評ではないか、というコース設定。車で走っていると平坦に思いますが、微妙に上り下りがあり、またカーブが傾いているので、左右の足が均等にならないのです。風は強く、日差しを遮るものもありません。
今年は微妙に暑くちょっと厳しい条件でありました。歩いてしまうランナーには声掛けしながら走っていましたが、こちらも実は歩きたい気持ちでいっぱい、調子の悪そうな人には立ち止まって様子を見ますが、こっそり休んでいるのが本音です。人のために止まったのさ、自分のためじゃないんだよ、と言い訳できるのはDr.ランナーの特権かも知れません。
還暦を迎えて最初のレースでしたが、初マラソンよりは10分くらい早く戻ってきたので、もうちょっと、年2回の休日と筋肉痛を楽しめるのでは、と思っております。

大勢の人が一斉にスタートするのでスタート地点までにも30分くらいかかります。
私は写真の時間より、もう少し早くゴールできました。

副院長だけでなく院内の職員は、休日はしっかり休んで、患者さんへのよりよい医療の提供に努めています。
とはいえ、マラソンのような強い負荷の運動をしたら、休んだことにならないのでは?と思われる方がいるかもしれませんが、院内でマラソンをしている別の職員によると、体は疲れても、心がリラックスするとのことです。
とつか原宿ふれあい祭りに参加しました🎈
2024年11月01日
11月に入り、あっという間に秋も終わりに近づいてきたように感じます。
気象庁の予報ではこれから急激に寒くなるということです。
10月までは暖かい日もあったため、実際の気温以上に寒く感じるかもしれません。
急な冷え込みに体調に気を付けていきましょう。
さて、先週10/27(日)のとつか原宿ふれあい祭りに、当院附属看護学校と一緒に参加させていただきました。
当日は雨天中止ということで、お天気が心配されましたが少し暑いくらいでした。
当院はマイナ保険証と産科病棟のご案内、看護学校は学校紹介や看護衣試着、聴診器体験などについてブースを出展しました。
ブースには多くの地域の方々にお立ち寄りいただき、「息子を横浜医療センターで産みました!」や、「数年前に手術をしてもらって、この通り今は元気すぎるくらい元気なのよ!」など嬉しいお話をたくさん聞くことができました。
また着ぐるみのマイナちゃんが登場すると子どもたちに囲まれ、記念撮影されるなど、多くの方に楽しんでいただけました。
職員もマイナちゃんのサンバイザーを着用しながらPR頑張りました!





売店では焼きそばやポップコーン、お弁当などが販売されており、迷いながらも葉山牛コロッケをいただきました。
衣はサクサク、中はホクホクで美味しかったです。
ご当地の名産品が食べられることもお祭りの醍醐味ですね。

ご来場いただいた皆さま、そして原宿商店街松栄会の皆さまありがとうございました。
今回、コロナ禍以降、久しぶりにイベントに参加できました。これからも多くのお祭りやイベントで当院の情報を発信していきたいと思いますので、横浜医療センターを見つけた際にはお気軽にお声掛けください☺
YouTube動画撮影の裏側
2024年10月25日
もうすぐハロウィンですね👻
当院も職員が飾り付けを行い、ハロウィン模様となっております。

さて、今年後半に入りYouTube動画を続々と更新中ですが、皆さんご覧いただけましたでしょうか?
先日は我ら広報部から「マイナ保険証の解説動画」をUPしましたので、今日はこちらの撮影中の様子をお届けしたいと思います。

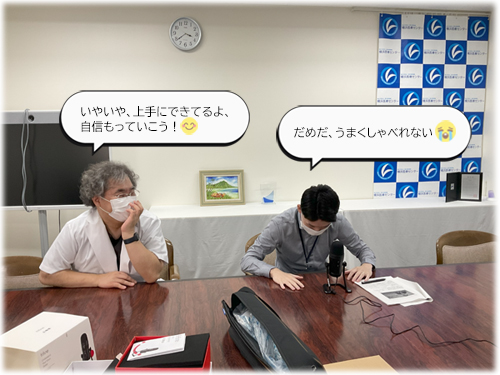
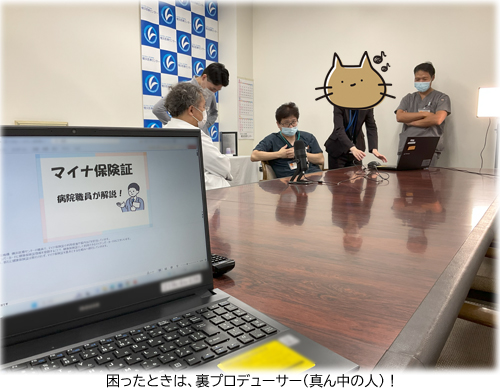
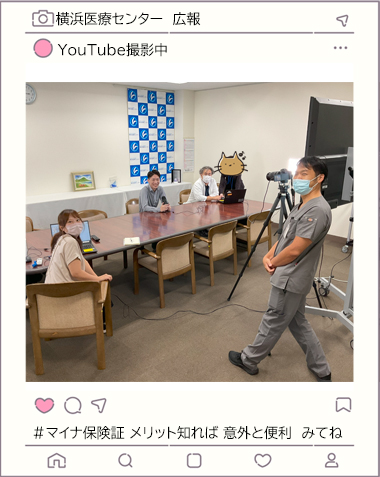

マイナ保険証利用については、正直よくわからない点が多いですよね。
動画の中では、マイナ保険証を使うと何が便利になるのかについて広報担当職員が解説していますので、使うメリットがわからない😥などのギモンをお持ちの方は是非ご覧ください。
~担当職員よりコメント~
「メンバーでスライドの構成やどんな具体例であればイメージしてもらいやすいかなど悩みながら、楽しみながら動画を作成しました。初めての撮影で緊張していますが、この動画を見て少しでもマイナ保険証のことを知ってもらえると嬉しいです。」
そして、あさって10/27は先日このブログでお知らせしたとつか原宿ふれあいまつりが開催されます。
今回、初の出店となり不安もありますが楽しいイベントとなるよう準備いたしましたのでお時間のある方は遊びにきてください!
職員向けのグルメフェア企画を実施しました🍝
2024年10月18日
昨日はスーパームーン🌕が見られ、当院職員がきれいなお月様を撮影してきてくれました。
特に今年の満月の中では最も大きく見られるとのことで、写真でも月の模様がよく見えます。皆さんはどんな模様に見えましたか?✨

さて、今年の1月のブログで職員向けのグルメフェア企画についてお話しましたが、毎回好評でその後も定期的に実施されています。今回は第3弾となり、2日間の実施期間中、職員食堂は大変賑わいました!

今回のメニューは2日とも提供された「大人のお子様ランチ~洋食プレート」と、1日ごとの日替わりメニューである「カレーピラフホワイトソースがけ&チキンレモン」、「ボスカイオーラ(ツナときのこのパスタ)&ミニサラダ」でした。
特に「大人のお子様ランチ~洋食プレート」は人気3大スターのエビフライ・ハンバーグ・カニクリームコロッケが盛りつけられ、見た目も豪華で大人気、2日目には売切れとなっていました。
テイクアウトをした職員が各自の席へ持ち帰ると、「それ食べたかった!」「まだ売り切れていないかな…」「何食べた、どっちにした?」など、職場で会話が弾んでいました。

広報も食堂にお邪魔してみると、いつもよりさらに混雑、でも厨房ではオーダーが入ると手際よく調理がされ、出来立てのあたたかい食事がすぐに提供されていました。

職員コメント💭
両日ともAランチ頂きました。
初日のエビフライは頭からしっぽまでサクサクに揚がっており、全て残さずに食べられました。2日目はエビフライとカニクリームコロッケが売り切れとなり、代わりにとんかつとから揚げになりました。
普段からメニューにはあるものですが、個人的にはごはんにはこちらのほうがあう!ので、結果おいしくいただきました。
普段から思っていますが当院の食堂の揚げ物のクオリティーはなかなかです!
病院で一緒に働いている職員が仲間の職員のために考えて実施してくれる企画で、職員みんながおいしいランチを食べることができ、元気に働く活力となります。
また、食事をした職員はみんなどのようなメニューが良いか、アンケート調査に協力してくれています。これにより、企画してくれる職員にとってもよいモチベーションとなりますし、よりよいメニューが提供され、それを食べた職員がさらに元気に働けるようになります。
これは1つの例ですが、当院では、病院全体で協力しながら、職員が活き活きと健康に楽しく働ける環境づくりに取り組んでいます。
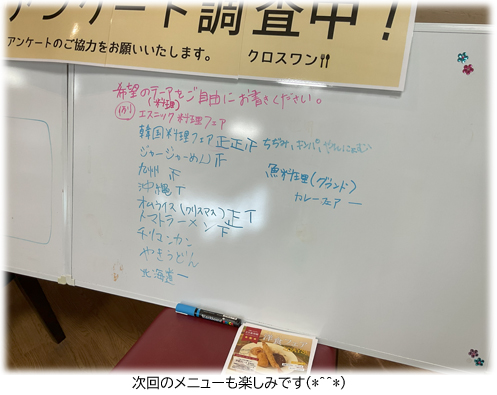
災害訓練を実施しました
2024年10月11日
二十四節気では寒露の候となり、朝晩は冷え込むようになりました。
最近は特に日の入りが早まり、さっきまで明るかったのに急に暗くなったと感じる方もいらっしゃると思います。徐々にではなく急に暗くなることで帰宅時間頃は事故が増えやすい時間帯といわれていますので、秋の夕暮れ時は周囲に気を付けてケガなどなさらないよう注意しましょう。
9/20のブログでお伝えした、災害訓練が9/28に実施されました。
当院をメインの訓練会場に、当院の職員やボランティアの方々に加え戸塚区・泉区役所や同区内の他病院の職員にも多数ご参加いただきました。
災害拠点病院は、災害発生時に災害医療を行う地域の医療機関を支援するという重要な役割があります。そのために、一定の指定要件に沿って非常事態に備えられた運営体制・施設となっており、被災によって機能不全に陥らないようにすることが求められています。
災害が発生した際には、本部となる当院に地域の被災状況が集約されるため、集約された状況から対応を考えて実行していく必要があります。
災害と一言で言っても、様々な事態が起こりうるので、毎年異なるシナリオを作成して訓練を行っています。今年は首都直下型地震発生翌日を想定した訓練で、被災内容や院内の状況の確認、多数の傷病者の受入を想定した病床の確保、様々な制限の中でどのように業務を継続するか、などの対応を行いました。また、院内で火災が発生したという想定もあり、通報や初期消火、避難などの訓練も同時並行で行いました。



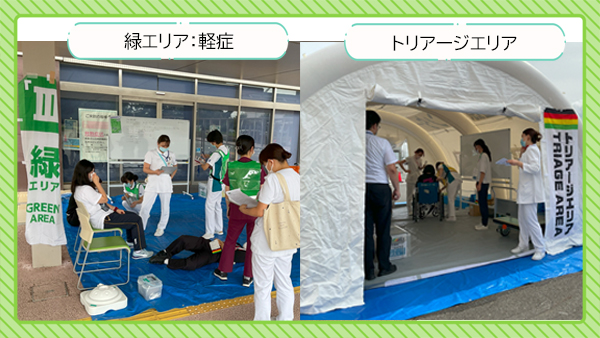
災害は起きてほしくはないですが、いつか必ず起こりますので、その際に対応できるよう今後も訓練を継続して行いたいと思います。
また、被害を少なくするためにも一人ひとりの防災に対する意識や対策は大切です。
皆さんも、ご家庭でできる備えについて確認をしてみてくださいね。
とつか原宿ふれあい祭りに参加します
2024年10月04日
10月に入りました🍁
昨晩は激しい雨が降り、不安定なお天気は来週も続きそうです。
日中はまだ気温の高い日がありますので油断せずに暑さ対策や食品の管理に気をつけましょう。
さて、今回は皆さんにお知らせが2つあります。
2024年10月26日(土)に当院附属看護学校の文化祭「楓葉祭」を一般公開します。
小さなお子さまにも楽しんでもらえるようなブースも企画しています。
看護学校に入れる機会はなかなかないので、興味のある方はぜひお越しください。
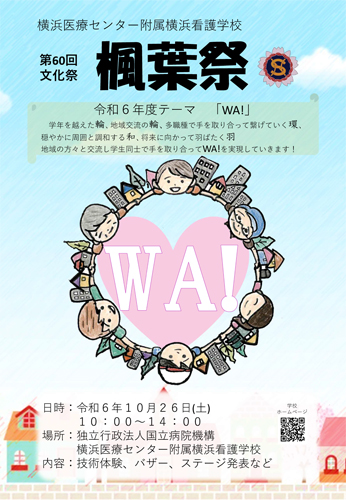
そして翌日、2024年10月27日(日)に当院の公開空地で開催される「とつか原宿ふれあい祭り」に当院広報部と看護学校が参加します。
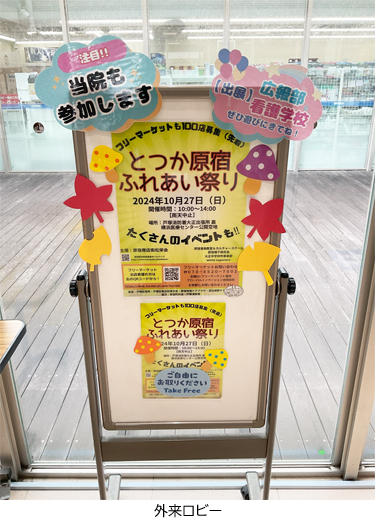
現在、絶賛準備中なのですが地域の皆さんに喜んでいただけるように進めておりますので、当日ふれあい祭りに行かれる方は覗いてみてください😊
来ていただけたら何か良いことがあるかもしれません…✨
たくさんの方のご来場をお待ちしております!
ICLS研修を実施しました
2024年09月27日
今週始めは、窓を開けて寝ていて朝「寒い!」、外に出て「涼しい!」と驚かれた方が多いのではないでしょうか。急に肌寒い気候になりましたので、衣類の調整などを工夫したいですね。
さて、今日はICLS研修についてです。
ICLSとはImmediate Cardiac Life Supportの頭文字をとった略語で日本救急医学会が開催している蘇生教育コースです。
医療従事者を対象としている研修で、今回は医師、看護師、救命士以外にも臨床工学技士や薬剤師、理学療法士、研修医などが参加しました。
これまでブログでも取り上げてきたBLSは医療従事者ではなくてもその場に居合わせた人が誰でもできる処置ですが、ICLSは医療従事者向けに心停止に即座に対応することに特化しているものです。
当院の臨床研究部長でコース開催責任医師のもと、資格を取得している職員がインストラクターとなり、院内で研修と試験を行いました。
ICLSの目標は「突然の心停止に対して最初の10分間の適切なチーム蘇生」を習得するとしているので、前半に一次救命、二次救命の復習を行い、その後設定したシナリオを想定して蘇生に必要な技術やチーム医療を身につけました。
後半に試験を実施し、その後修了式を行いました。

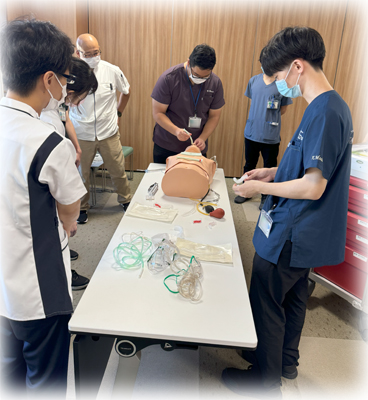

心停止は病院のどの部署においても起こりえるので、頭文字の「Immediate(すぐに、即座に)」処置が行えるよう、今後も職員が技術を習得できる機会を作っていきたいと思います。
災害時看護研修を実施しました
2024年09月20日
今週9/17は中秋の名月でした。
当院の近辺でもきれいな月を見ることができました。皆さんご覧になられましたか?
ちなみに来年の中秋の名月は10/6だそうです。
9月1日は防災の日でした。
当院では定期的に災害に備えた訓練や研修を実施しており、今回は看護部でリーダー的役割を担う看護師を対象とした研修を実施しました。
当院は災害拠点病院であるため、災害が発生した場合は、看護師たちは院内にいる患者さんの救護と同時に、地域で被災した傷病者を受け入れる体制を整える必要があります。
そのため、シミュレーションを通して災害看護の基礎知識を復習し、安全の確保やいつもと違う状況の中での治療、院内PHSが使用できない場合の連絡方法について再確認し、共通認識を持つことができました。
後半にはクイズ形式での講義や、災害時に各病棟で起こりえること、必要になることの議論を行いました。
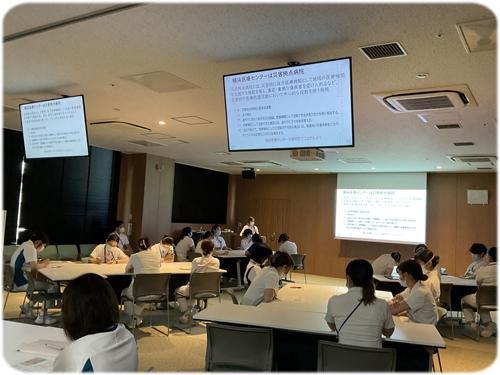


今後も病院機能を維持しながら、入院患者の安全確保と地域の中心となって地域被災者の医療救護活動を行うために、職員間で防災意識を高めていきたいと思います。
また、日ごろから準備を行うことは二次災害の予防にもつながります。
9月末には病院全体での災害訓練も実施予定ですので、こちらの様子も後日ブログでお知らせしたいと思います。
敬老の日
2024年09月13日
厳しい残暑が続いていますが、帰宅時間頃は少し涼しく秋の空が見えます。
秋は夕暮れといいますので、秋の景色を楽しみたいですね。

そして、今週末の連休には敬老の日があります。
院内保育園では祖父母の方々に向けてハガキ制作を行い、郵送しました。
子ども達は少しだけ敬老の日の意味を理解しながら、秋らしいコスモスをイメージして制作に取り組みました。
おじいちゃん、おばあちゃんに喜んでもらえるといいですね(*^^*)
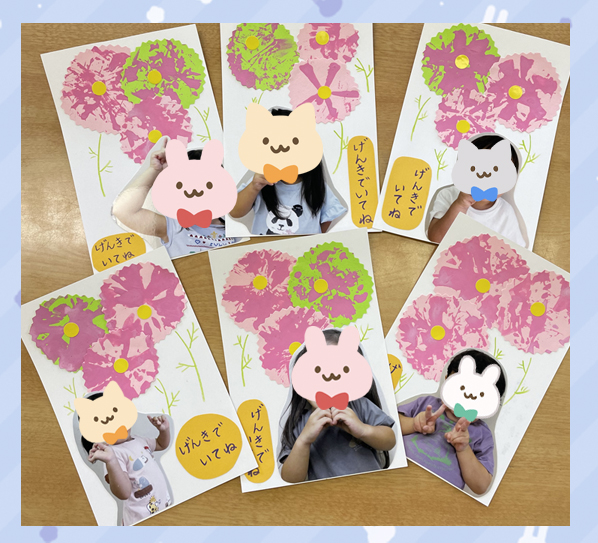
さて、当院では7月の新札発行に伴い、当院では精算機を準備中としておりました。
精算機に吸い込まれていく紙幣は一般的には、光を検知する「光学センサー」と磁気インクを読み取る「磁気センサー」で読み取ることにより、本物の紙幣かどうか判定します。
当然紙幣が変われば、紙幣の情報が変わりますので、この対応にどうしても時間がかかってしまいます。
この間皆さんにご不便をおかけしていましたが、8/21より新札も使用できるようになりました。
発行当初はなかなか出回っておらず、手元に新札が来ることがあまりなかったですが、最近は買い物のおつりなどで目にする機会も多くなりました。
体感としてはまだ新札が使えないところも多くあるように思いますので、当院での精算では活用してくださいね。

新人看護師研修vol.3
2024年09月06日
9月に入りました🍡
台風が過ぎ去り、ようやく秋の涼しさが感じられるようになりましたね。
秋の虫たちの鳴き声も聞こえ始め、長い夏の終わりが見えてきました。
さて、ブログで定期的にお伝えしている新人看護師研修について今回も皆さんにお伝えしたいと思います。
今回の研修は救急看護(BLS)です。BLSとは、「Basic Life Support」の略称で一次救命処置のことを言います。
休日や夜勤の際など看護師が少ない時に急変が起きた場合や、院内で人が倒れていた場合などに焦らずに手順通り一次救命処置が実施できるようイメージトレーニングをしておくことが研修の目的です。
帰宅中に駐車場で人が倒れていたら?廊下で職員が倒れていたら?ここから一番近くにあるAEDはどこ?など、様々な想定でどんな行動を取るべきなのかを3人1組で一連の動作のシミュレーションをして何度も練習しました。


研修の後半では、救急カートの説明と一次救命処置の次の段階で行われる二次救命のシミュレーションを皆さんに見ていただきました。
「今日学んだことをしっかりと復習して、二次救命に繋げられる環境を整えることも看護師の大切な役割であるということも覚えていただきたいです。」と新人看護師の皆さんへ伝えられました。
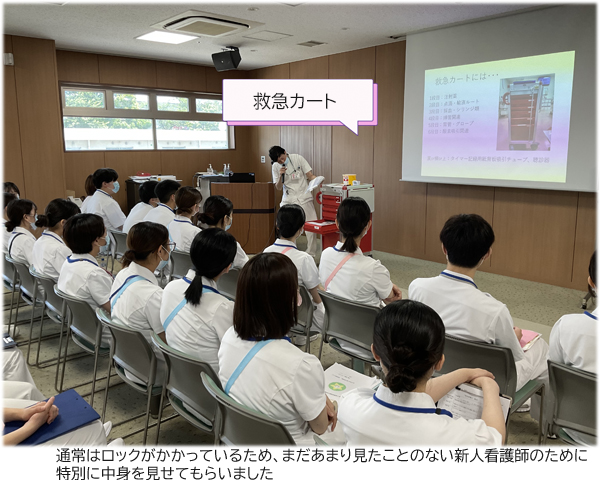

今後も、研修を通して復習しながらしっかりと手順を覚え、実際の現場で慌てることなく行動に移せる自信を持ってもらえるようにサポートしていきます。
【看護学校】体験学習プログラムに参加しました
2024年08月30日
各地の台風被害が心配されます。
関東では明日も大雨が続く見込みですので、引き続き注意が必要です。
当院附属の看護学校では、8月6日に横浜市で毎年実施している市内小学生を対象にした体験学習プログラム「子どもアドベンチャーカレッジ2024」に参加し、当日21名の小学生が集まってくれました。
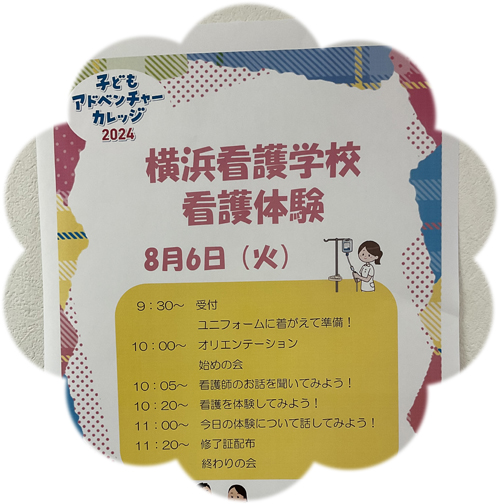
ユニフォームに着替えた後、初めの会を行いました。副学校長から「今日は体験学習です。看護師ってどんな仕事をするのか、そのためにはどんな勉強をしているのか、横浜看護学校ってどんな学校なのかを是非たくさん学んで感じて、有意義な時間にしていただけたら嬉しいです」とお話がありました。
そして、体験を始める前に看護のお仕事について説明がありました。

「看護」の漢字をよく見てみると、目で見て手で守る「保護する」とあります。
目の前の患者さんを観察して必要な処置などを行って、心も体も元気にすることが看護師の仕事です。また、将来看護師になるためには、たくさんの人と交流をもつこと、マナーやルールを守ること、自分の健康を守ることなど、皆さんが今からでもできることも教えていただきました。
そして、皆さんしっかりとお話をきいてから、グループごとに分かれて各コーナーの体験をしました。
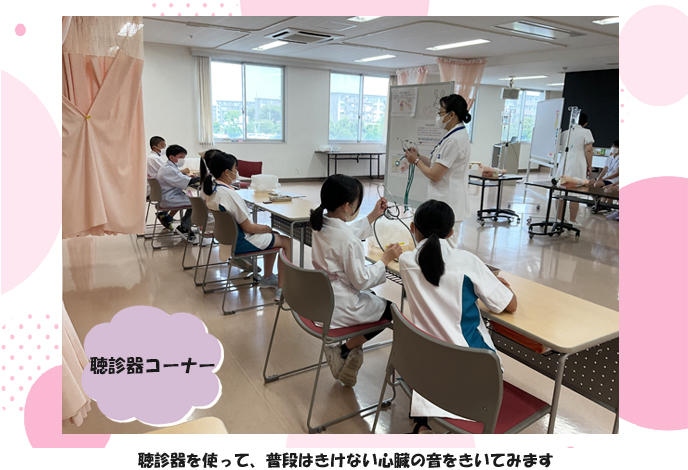

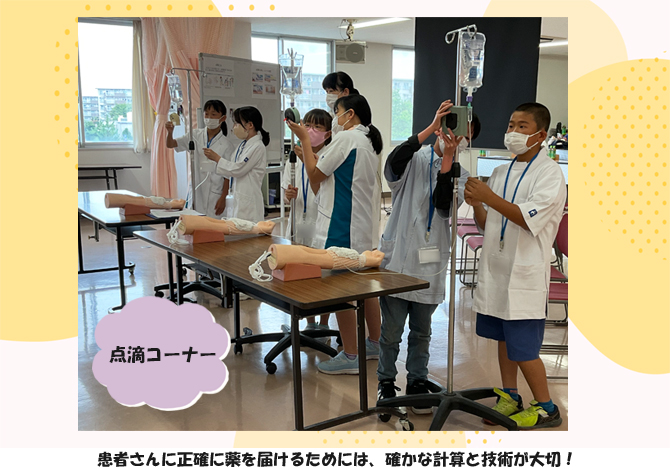

終わりの会では、修了証をお渡ししてグループで体験の振り返りをしました。
最後に教育主事より、看護師は患者さんと関係を築いても“また会おうね、また来てね”と言えない仕事です。中には残念ながら病院で最期を迎えられる患者さんもいます。だから私が思う良い看護を提供するためには「常に信頼してもらえる自分でいること」、そのために患者さんと向き合うその時その時を大切にしています、という貴重なお話を聞くことができました。
看護学校からのコメント💭
今回、初めて小学生の子どもたちへの体験学習を行いました。最初は初めての場所に緊張している子も多くいましたが、体験を通してたくさんの気づきや学びを得られたようでした。教員自身も、皆さんと一緒に看護について話すことができて、改めて看護のやりがいや魅力を感じられる時間となりました。
ありがとうございました!
高校生1日看護体験を実施しました
2024年08月23日
二十四節気では、処暑の候となりました。
少し前まで夕方6時を過ぎてもまだ明るいと感じていましたが、日々少しずつ日暮れが早くなってきましたね。息苦しい暑さも少し和らぎ、夏から秋への季節の移り変わりが感じられます。
先月7/22に高校生を対象にした1日看護体験を実施し、近隣の学校から16名の学生たちが参加してくれました。
白衣に着替えた後に病院紹介を行い、その後に看護体験を実施しました。
4つのブースをローテーションし、健康チェック、車いす乗車、BLS(一次救命処置)、小児おむつ交換を体験しました。
車いす乗車体験では自分が思っていたよりも操作の工夫や乗っている人への配慮が必要で難しかった、乗ってみたら今まで見ているものと全然違かった!という声が多くあがっていました。


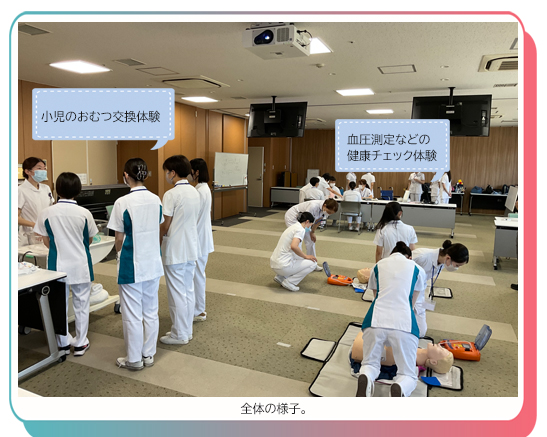
体験を終えた学生からの感想
「現場の看護師からしか聞けないことを、たくさん教わることができて本当に貴重な体験をさせていただきました、ありがとうございました。」
「看護体験は他施設でも参加したことがあったが、ここの病院は体験の時間が多くてよかったです。」
「今日の体験で、看護師になりたい気持ちがもっと強くなりました。」
と皆さんから感想をいただきました。
スケジュールの中では当院附属の看護学校で学校紹介も行われ、最後にBLS(一次救命処置)を実施している個人写真とお菓子などを看護部からプレゼントしました。

今日の体験で看護師や病院の仕事に興味をもつきっかけになっていただけると嬉しいです。
ご参加いただいたみなさん、ありがとうございました😊
副院長ブログです!
2024年08月09日
今回は、4月に就任した宮崎副院長に、この夏、どんな病気が増えているのかを執筆してもらいました!
宮崎副院長は、副院長になってもこれまでと変わらず夜間当直をし、救急外来でも活躍しています。
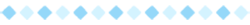
北日本では大雨災害が一段落したとはいえ、災害級の暑さは横浜周辺でも続いています。7月は史上最も暑かった、との報道もありましたし、以前に比べて平均で2℃気温上昇があったとか。かき氷が欲しい所です🧊🥵
さて、病院は世の中の写し鏡、みたいなところもあり、様々な病気や怪我が増えたり、減ったりします。
では、いまはどんな病気が増えているのでしょうか。
暑くなれば、昨今啓発が進んでいる熱中症の方がおいでになりますが、症状は様々ですがやはり動けなくなる方が少なからずいらっしゃいます。
この時期の地面はとても熱くなりますから、動けなくなると熱傷も生じます。
長時間かけて生じる熱傷なので、治療が難しくなりがちです。朝の涼しい時間、と思って庭仕事をしていて、動けなくなって救急車、は珍しくありません。お気を付けください。
もう一つニュースを騒がせているのはCOVID-19、新型コロナですが、19と言う数字は2019年に出現したから、というともう5年も経ったことになります。
いまだに悩まされておりますが、初期にみられた若年者の重症化はほとんどありません。しかし高齢者の方では重症化することが、わずかですが見られます。
65歳以上(一部の高リスク者は60歳以上)では定期接種対象で、自己負担額がありますが、接種で重症化が防ぐことができれば、心配は少なくなります。
ワクチンに危険が無い、とは言えませんし、あくまでご自身の判断ではありますが、この5年間で実感としてワクチンには効果がある、と感じております。
接種は10月からの様ですが、最新型のワクチンになるようです。ご検討ください。

敷地内の草刈りを行いました
2024年08月02日
8月に入りました。
連日猛暑が続き、記録的な高温になった地域もありました。
当院夏の風物詩のミストシャワーが7/23より設置されています。
見るだけで涼しくなる気がしますね😊

7月上旬に当院事務部の職員たちで敷地内の草刈りを実施しました。
今年は一段と暑さが増して、草刈り作業もとても大変そうでした。

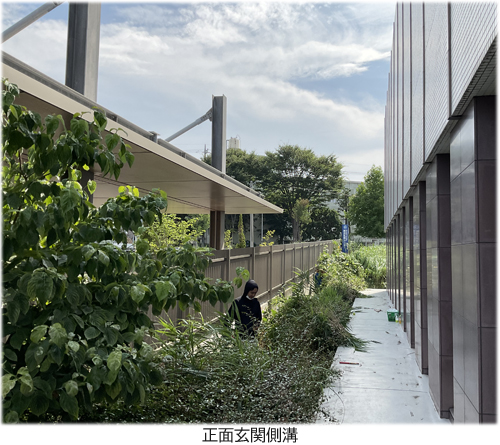


職員からのコメント
「普段は室内で仕事をすることが多い事務職ですが、外でみんなと作業することができ楽しかったです!」
今後も定期的に敷地内の環境整備に努めていきたいと思います。
【院内保育園】じゃがいも堀り2024
2024年07月26日
今週初めの22日(月)は二十四節季の大暑というとおり、息苦しいほどの暑さとなりましたが皆さん体調など崩されていないでしょうか。
少し前になりますが当院では七夕の時期、外来ホールに沢山の短冊が飾り付けされました。後日、皆さんの願いが込められた短冊は、職員が近隣の神社へ持っていきお焚き上げをしてもらいました。
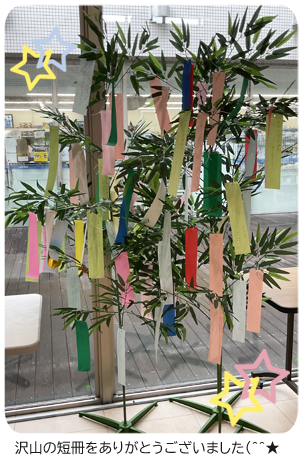
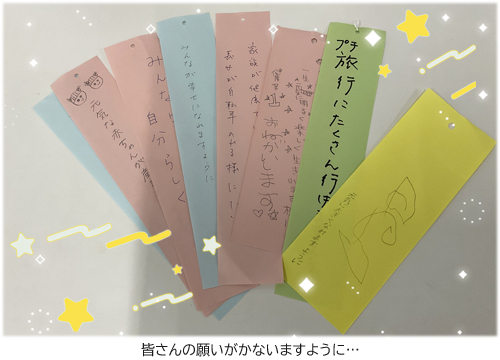
さて、今日は毎年恒例となった院内保育園のじゃがいも堀りの様子をお伝えします。
今年もお隣の大正地区センターの畑で育ったじゃがいもを館長さんのご厚意で掘らせていただきました。
📝昨年のじゃがいも堀りのブログはこちら
院内保育園園長より🐣
おいもの山の前にちょこんと座りおいも堀りのスタートです!ちらほら見え隠れするおいもを掘り当てると「みてみて!」と嬉しそうに保育士やお友達に見せていました。



沢山のおいもを掘るのは大変でしたが最後まで楽しんでいた子ども達です。

貴重な体験をさせてくださった地区センターの方に「ありがとうございました!」とみんなでお礼をして帰ってきました。

小児科医師にインタビューしてみました【後半】
2024年07月19日
昨日関東では梅雨明けが発表されました。
連日の猛暑でまだ夏じゃなかったのね…と思われる方も多いと思いますが、これからが夏本番のようです。さらに、熱中症対策をしていきましょう!
涼を探してみるとあじさいが咲いていました。

前回ブログの後半です。
病院では聞きにくいけど気になる素朴な疑問について、小児科医師に聞きましたので、夏のお出かけなどのお役立ち情報として知っていただけると嬉しいです。
🔷Q.「長時間の移動などでおむつかぶれしてしまった時の対処法は?」
🔶A.おむつかぶれしてしまった時はおしりふきでゴシゴシ拭くことは避けましょう。移動中に洗ってあげることは難しいので、おむつ替えの際にペットボトルや霧吹きを使用して少量のぬるま湯や水で便を洗い流すと良いです。水が使えないときはゴシゴシこすらずにおしりふきを押し当てながら優しく拭くと良いでしょう。
🔷Q.「授乳中に赤ちゃんが沢山汗をかいてしまって心配です」
🔶A.赤ちゃんはもともと汗っかきで、授乳時はお母さんの体温を感じながら一所懸命に飲むのでより一層汗をかきます。ただ、授乳でしっかり水分補給をしているので、授乳中に沢山汗をかいてしまっても気にしなくてよいでしょう。
🔷Q.「帽子をかぶせていると顔を赤くして頭も汗だくになるのですが帽子は必要?」
🔶A.今の夏は日差しが強いので日よけ帽子はかぶりましょう。前述のように赤ちゃんはもともと汗っかきで、夏場の日中はさらに大量の汗をかきます。外出の際には着替えを持参し、濡れタオルで汗を拭いてあげましょう。また紫外線も強いので、子ども用の日焼け止めを使用すると良いでしょう。体温調節や紫外線の観点から、日差しの強い時間帯の外出は気を付けましょう。
🔷Q.「のどが渇いたらジュースを飲ませてもいいの?」
🔶A.たまにジュースを飲むことはいいと思います。ただ、ジュースばかりたくさん飲んでしまうと満腹感が出て、母乳・ミルクや離乳食の量が減ってしまう可能性があります。また、何度も飲んでいると麦茶などの甘くない飲み物を飲まなくなる可能性もあるので気を付けましょう。
小さな子どもは、自分の体調をうまく伝えることができないので体調管理に気を付けて暑い時期を楽しく過ごしてください🎵

小児科医師にインタビューしてみました【前半】
2024年07月12日
久しぶりのブログ更新です。
ホームページ更新が停止の間、皆様にはご迷惑をおかけし申し訳ございませんでした。
今週よりブログ更新も復活しますので是非ご覧ください。
さて、ブログがお休みの間に関東では梅雨入り発表がありました。
平年より2週間以上遅い発表となったようです。
梅雨入りしてからさらに蒸し暑い日が続きますが、今回はこの時期にお悩みの方が多い「子どものお肌」に関する素朴な疑問について、小児科医師に話を聞きましたのでぜひ参考にしてください。

🔷Q.「子どもの皮膚トラブルでは、どのようなタイミングで受診したらよいでしょうか?」
🔶A.お手持ちの保湿剤を塗っても改善がないときや湿疹が増えじくじくするなど悪化するときは早めに受診しましょう。
🔷Q.「常に体がべたべたしていて、その後かゆがっているときの対処法は?」
🔶A.赤ちゃんは体温調節が未熟で新陳代謝も活発なので汗っかきです。汗でべたべたしている状態をそのままにすると、汗に含まれる様々な成分による刺激で肌がかゆくなります。汗をかいたらすぐシャワーを浴びるのが理想ですが、現実的には難しいので、汗をかいたらすぐに拭いたり、夏場はこまめに着替えさせてあげるなどしましょう。
🔷Q.「虫よけスプレーは小さい子でも使っても問題ないですか?」
🔶A.赤ちゃん用や幼児用の虫よけスプレーは使用して大丈夫です。スプレータイプの場合は直接噴霧すると目や口に入ることがあるので、大人の手のひらに出してから塗りましょう。塗りムラがあると虫よけがついていない箇所は刺されてしまうので、顔、腕、足にまんべんなく塗りましょう。
🔷Q.「蚊に刺された場合の対処法は?」
🔶A.市販の虫刺され軟膏を塗って大丈夫です。かゆみや赤みが強い場合は冷やすと症状が和らぎます。掻きむしると化膿してしまうこともあるので、虫刺され用パッチを貼るのも良いです。それでもかゆみや赤みが強く、腫れがひどくなる場合は受診しましょう。
そして、今の時期水分補給は重要です。汗をかいていないように見えても、皮膚表面から水分が蒸発しています。水分補給は麦茶、水を選びましょう。乳幼児用イオン水は下痢や嘔吐がひどい場合のために調整してあるので、元気な時の水分補給には向きません。赤ちゃん用ジュースも普段飲むことはいいですが、夏場の水分補給には向いていませんので適切な水分補給をしてあげましょう。 ・・・後半は次回に続きます。

ホームページ更新停止について
2024年06月14日
明日6/15(土)~6/25(火)までホームページ移行に伴い、当院のホームページ更新が停止となります。
なお、停止期間中でもホームページの閲覧は可能です。
📍更新停止期間
令和6年6月15日(土)~令和6年6月25日(火)
※来週6/21(金)のブログはお休みとなります。
更新停止期間中の病院からの大切なお知らせは当院公式YouTubeチャンネルにて更新いたします。
ホームページTOP画像をクリックしてご覧いただけます。

当院ホームページをご利用の皆さまには大変ご迷惑をお掛けいたしますが何卒ご理解の程よろしくお願いいたします。

新人看護師研修vol.2
2024年06月07日
6月に入りました🐌
関東ではそろそろ梅雨入りの時期ですが、今年は発表が遅れる見込みのようです。
暑さは日に日に増していくと予報がありますので、しっかり水分補給をしていきましょう!
さて、4月に続き5月も新人看護師研修を実施したので研修の様子をご紹介します。
今回は「フィジカルイグザミネーション」の研修です。
フィジカルイグザミネーションとは、視診・触診・打診・聴診を行い、看護師の五感を使って情報を手に入れる手段のことです。
正しい知識と正確・安全に行うための技術などを学びました。
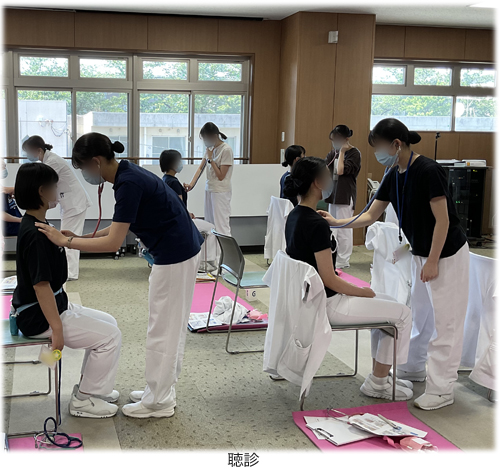

患者さんの診察を行う際には、このフィジカルイグザミネーションとともに、問診などを行い患者さんのことについて情報を集めます。
患者さんの状態について様々な情報を合わせて評価することを「フィジカルアセスメント」といいます。
症例を想定してシミュレーションを行い、フィジカルアセスメントを行って患者さんの身体にどのような異変が起きているのかを学習しました。

また、意識レベルと筋力評価方法についても学びました。
意識レベルの評価方法は、なんとなくではなく、共通レベルの指標のため、どのスタッフも共通に患者を把握することができるため大切です。
意識レベルを評価できることで、より正確に患者さんの状態を報告することができ治療に関わる高度な技術の実施が可能となります。


最後に、「今皆さんができることは、まず正確に患者さんを観察して手に入れた情報を報告することです。アセスメントが正しいかも先輩に確認してもらうことが大切です。急性期病院で必要な技術は周りの先輩がサポートしていきますのでこれから身に付けていきましょう!」と講師の病棟看護師からアドバイスがありました。
今後も、新人看護師が基礎の理解を高めながら看護経験を積んでいけるように定期的に研修を実施していきたいと思います。
日本医療マネジメント学会を開催しました
2024年05月31日
5月も最後の日となりました。
今朝は雨が強く降り、外に出てみると肌寒く感じました。
晴れるとまた気温が上がるので体調を崩されないようお気をつけください。
少しさかのぼりますが、2月のブログでふれた日本医療マネジメント学会神奈川大会が3月10日に鎌倉芸術館にて開催されました。
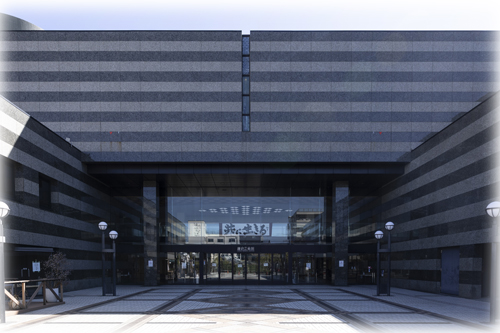
今回、当院の宇治原院長が学術集会会長を努め、テーマは『「医療提供体制の改革」に向けて』としました。
2024年度は様々な診療報酬の改定など、医療に関わる体制の改定が行われます。
また、医療DX、AI(医療ロボットなど)の活用に向けて様々な課題があります。これらについて医師・看護師をはじめ薬剤師、放射線技師や医療事務職まで多岐に渡る職種の参加者と議論することができました。



テーマの中にある医療DXは、皆さんがより良質な医療やケアを受けられるためにデジタル技術を用いて必要な診療情報を効率よく取得・活用して診療を行うことです。
最近よく目にするマイナ保険証も医療DXの取り組みです。
マイナ保険証については当院でもご利用いただけますので、マイナンバーカードをお持ちの方は、ご来院の際に是非ご持参をお願いいたします。
詳しくはまた別の機会のブログでお知らせしたいと思います。
今回の医療マネジメント学会に参加した職員からのコメント💬
「コロナ禍になって、丸4年が経過し、ようやく完全対面での学会が通常となりました。モニター越しに意見を交わすのではなく、生の声が飛び交う学会にあらためてポストコロナを感じました。やっぱり学会は学び(刺激)を得ることができます。この刺激を日々の業務に活かしていきたいと思います。」
世の中では様々な場面でデジタルが利用され便利になってきました。
当院でも患者の皆さまに、より質の高い医療を提供するために学会などを通じて情報を取り入れ、時代に遅れることのないよう成長し続けていきたいと思います。
「おくすりシートリサイクルプログラム」に参加しています🌏
2024年05月24日
夏日になるような暑い日があったり、そうかと思うと雨が降って寒くなる日もあったりと、最近はころころと気候が変わりますが、皆さん体調などお変わりないでしょうか。
当院では4月から、1階、夜間休日受付近くの自動販売機向かいに「おくすりシートくるりんBOX」を設置しています。皆さんがおうちなどで飲んだお薬の使用済みのシートをこの箱に捨てることができます。

おくすりシートは「プラ」の記載があることが多いので、その場合は横浜市では「プラスチック製容器包装」としてごみの分別をします。
しかし、記載がない場合などで、金属として燃やすごみに分類する場合もあるため、捨てるときに迷われる方もいるのではないでしょうか。
おくすりシートくるりんBOXの設置は、製薬会社が主催し横浜市なども協力している「おくすりシートリサイクルプログラム」という取組で、横浜市内の公共施設や病院などが参加しています。
回収された使用済みのおくすりシートは、プラスチックとアルミニウムが分離され、それぞれ再生素材としてリサイクルされます(なんと、おくすりシートは国内だけでも年間13,000トンが生産され、使われているそうです!)。当院は環境を守るこの取組の趣旨に賛同し、プログラムに参加しました。

おうちに使用済みおくすりシートがあったら、少しの量でもかまいませんので、当院や横浜市内の一部薬局、公共施設などのBOXに入れてくださいね。

看護の日
2024年05月17日
今週、5/12(ナイチンゲールの誕生日)は看護の日でした。
看護学校では「みんなで描こう 私たちが目指す看護」をテーマに学生全員でグループワークを行い、全員の想いを「絵」で表現しました。
ナイチンゲールは看護師が一人一人の患者さんに看護することを「芸術art である」と述べています。
学生たちは、ナイチンゲールの看護について理解を深めながら自分たちの目指す看護をイメージして制作に取り組みました。


制作後は体育館で絵の展示・投票を行い、最後に結果発表を行いました。
集計中はボランティア活動で敷地内の草刈りも行いました!
なお、当院では5/16まで外来サイネージにて、各病棟の看護師などを紹介する看護の日のコンテンツを放映しました。

【投票結果】
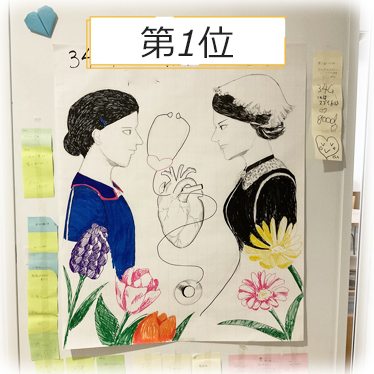
1位の作品へのコメント:ナイチンゲールの看護を私たちに受け継いでいくというイメージがすぐに浮かんで感動した!

2位の作品へのコメント:花の華やかさと鳥が飛び立つ開放感が快方に向かっていく様が伝わってくる

3位の作品へのコメント:患者さんの心の中にいる看護師のあたたかい看護が想像できて絵のイメージがわかりやすい
閉会式では副学校長から「今回の看護の日を心に、学生の皆さんに成長してもらえたら嬉しいです」と学生へメッセージがありました。
看護学校では、これから出会う患者さん一人一人を想い、今の時代に必要な看護技術を提供できるような学生の育成に努めていきます。

こどもの日🎏
2024年05月10日
ゴールデンウィークが明けて、多くの方はいつもの生活が戻ってきたでしょうか。
ゴールデンウィーク中にはこどもの日がありました。
晴れた空にこいのぼりが泳ぐ姿をあちこちで見かけましたが、皆さんもご覧になられましたか?
こどもの日は子どもの健やかな成長を願うと同時に、母に感謝するという趣旨があるそうです。
当院では入院されるお子さんやそのご家族の不安な気持ちを少しでも取り除けるよう、看護師がケアやサポートを行い、また、小児科病棟には様々な飾り付けがされています。

当院に入院中の子どもたちは看護師と一緒に病棟にある好きな絵本やおもちゃを選んで病室に持っていくことができます。
また、一人一人の好みや興味に合わせて医師や看護師が遊んで笑わせたり、話し相手になったりして、楽しく過ごすお子さんの姿も見られます。
そのような入院中の様子については、面会や荷物の受け渡しの際に看護師からご家族へ丁寧にお伝えしています。
離れている時間はずっと泣いているのではないかと心配なさるご家族の方からは、看護師さんたちが親身に子どもと関わってくれて安心して入院させられたとお話を聞くことができました。
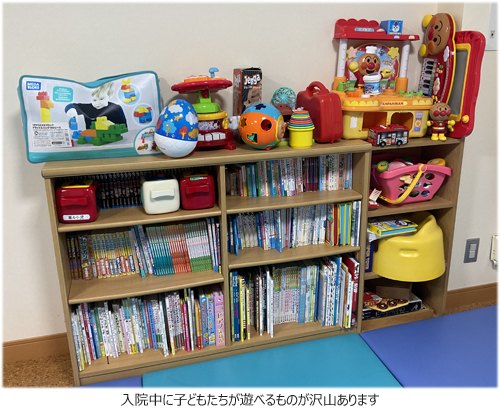
また当院では子育て中の職員たちが安心して子どもを預けて働ける環境づくりにも努めています。
敷地内にある院内保育園では、子どもたちがそれぞれ制作したこいのぼりを持って元気に走る姿が見られました。
保護者である職員からは土曜保育があったり、オンコール勤務(急患対応時)の日も保育利用ができたりするのでとても助かるといった声がありました。


今後も子どもたちの健やかな成長を祈りながらご家族に寄り添って、安心して受診や治療を受けられる環境づくりに努めていきたいと思います。

処方箋の有効期限に要注意⚠
2024年04月26日
いよいよゴールデンウィークですね。
まとまった休日を利用して行楽に出かける方、遠方の実家・親戚に帰省する方、あるいはその帰省を待ち受ける方、ご自宅でゆっくりとくつろがれる方、いろいろいらっしゃると思います。
横浜医療センターは暦通り(カレンダー通り)に外来診療いたします。
当院ではお薬での治療が必要な外来患者さんには、保険薬局でお薬を受け取っていただく処方箋(しょほうせん)を発行しています。
この処方箋ですが、「有効期間」があるのをご存じですか?
処方箋の有効期間=交付日を含めて4日間
処方箋は「交付日を含めて4日間」が有効期間(有効期限)と国のルールとして定められています。国のルール、とは「保険医療機関及び保険医療養担当規則」という、難しそうな名前のものです。
交付日を含めて、ですので、診察を受けて処方箋を受け取った日が1日目となります。
例えば、今日受け取った処方箋は、今日(1日目)、明日(2日目)、明後日(3日目)、明々後日(4日目)までが有効期間です。
4日を超えてしまうと「失効」。
これはつまり、お薬をもらうことができなくなってしまうことを意味します。
しかも、この4日間には「土曜日」「日曜日」そして「祝日」も含まれているんです。
多くの保険薬局は「土曜日」「日曜日」「祝日」がお休みです。ですが、処方箋の有効期間はそんなことは関係なく減って行きます💦
このゴールデンウィーク、処方箋の有効期間は事実上4日ではなくなります。
4月26日 や 5月2日は、その日のうちに処方箋を提出いただかないといけなくなっています。
処方箋は、全国どこの保険薬局でもお薬の交付を受けられることにはなっていますので、「土曜日」「日曜日」「祝日」でも開いている保険薬局にお願いすることもできますが、かかりつけではない保険薬局ですと、おくすりの在庫がなく取り寄せになってしまうこともあります。
ゴールデンウィーク前、ゴールデンウィーク中に発行された処方箋はその日のうちにかかりつけ薬局へ提出いただくことをおススメいたします😌
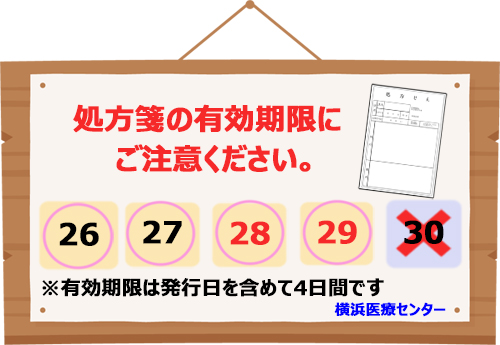
新人看護師研修が始まりました☘
2024年04月19日
暖かい日が続き、先週まで満開の桜でピンクに染まっていた当院の敷地は、葉桜が増え、また違った雰囲気になりました。
先週には見られなかった花も沢山咲いて、だんだん5月に向かっている様子が感じられますね🌺
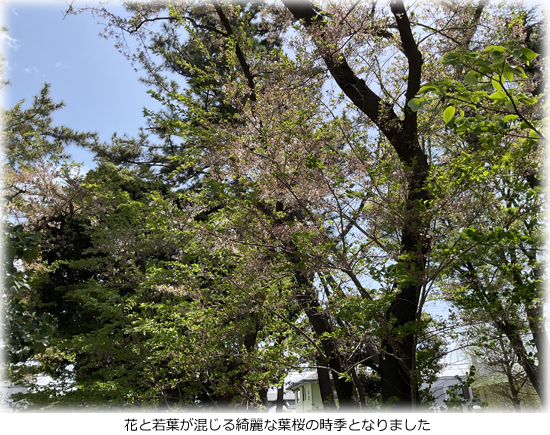

さて、当院では今年度も新人看護師研修が始まりました。
当院では教育プログラムを通して年間で研修を行っており、新人看護師が看護の基礎について理解を深め、現場で抱える不安を少しでも取り除けるようにサポートしています。
今回は「輸液ポンプ・シリンジポンプの取り扱いについて」と「体圧分散寝具・下肢血流観察」の研修を行いました。
正確に薬剤の投与をコントロールするための輸液ポンプやシリンジポンプは病院では良く用いられる器具です。正しい取り扱いと手順について確認しながら繰り返し実践を行いました。
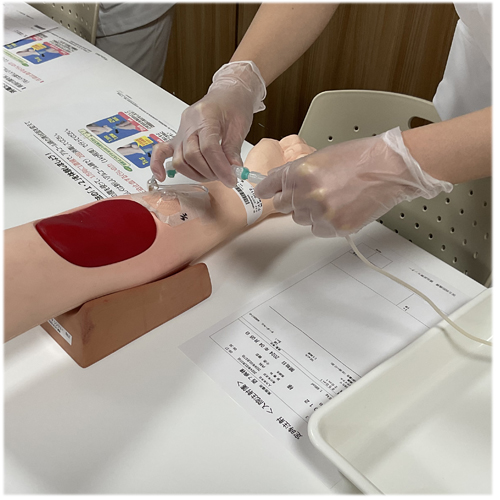
下肢血流観察では、いわゆるエコノミークラス症候群を予防する弾性ストッキングの正しい着用方法と、下肢(脚)の血流状態の観察について実際に体験しました。
ストッキングで筋肉を圧迫するため、着用していると血流の不足や、皮膚に障害が発生してしまうことがあるので、装着時にどのような注意が必要か考えました。
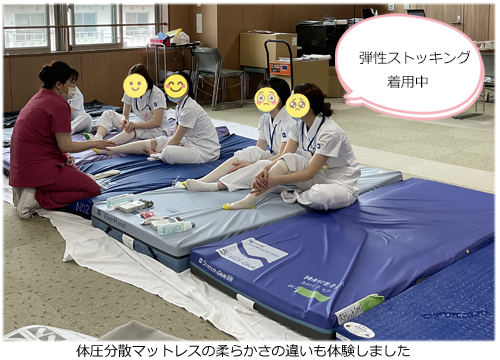
新人看護師の皆さんは、看護学校で教わったことに加えて急性期病院の現場で必要になる知識を学べる機会となりました。
今後も新人看護師が成長できるよう様々な研修を行っていきたいと思います。

横浜医療センターの春を見つけました🌼
2024年04月12日
今週始めの4/8(月)はとても良いお天気でしたね。
当院附属の看護学校では第62回生の入学式が行われ、57名の新入生を迎えました。
新入生代表は「国立病院機構及び社会に貢献できるような看護師を目指します」と宣誓しました。
これから同じ目標を持つ仲間の皆さんと一緒に頑張ってほしいと思います。


入学式の帰り道に敷地内を探索してきたので当院の春の様子をご紹介したいと思います。




新年度が始まり、新しい環境で過ごされている方も多いと思います。
だんだん疲れが出てくるといわれていますので休日は好きなことをしたりしてゆっくり過ごしてください🍵
新採用者対象のオリエンテーションを実施しました☘
2024年04月05日
4月に入り新しい年度がスタートしました!
雨や曇りの日が続いていますが気温は暖かくなって当院敷地内の桜も咲き始めています🌸
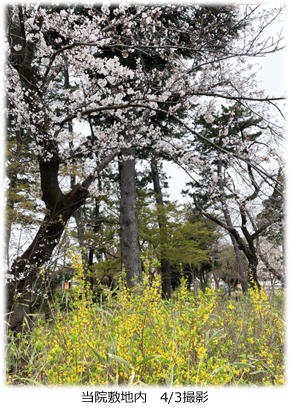
さて、当院では4/1~4/4まで新採用者を対象としたオリエンテーションが行われましたので、今回はこちらの様子をご紹介します。
初日は新採用者の方々の辞令交付式を行ったあと、宇治原院長より横浜医療センター紹介のお話がありました。

感染防止に必要な看護技術では感染管理認定看護師が講義を行い、注射針の取り扱いや防護具の着脱手順、感染性廃棄物の処理方法などについて説明がされました。
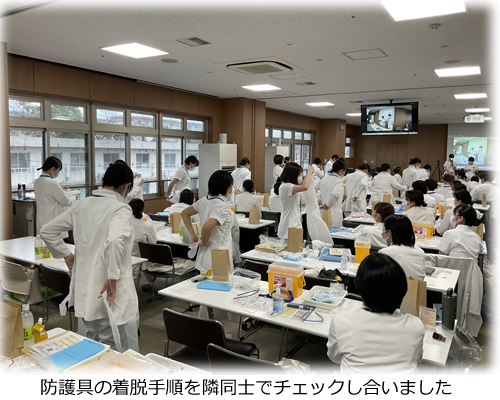

MRI室での吸着体験では身に付けている電話や時計など、全て吸着されてしまうので外してください!という事前説明を受け皆さん恐る恐るお部屋へ。
広報部も機材を持ち込めないのでMRI室手前のギリギリのところで撮影させてもらいました!
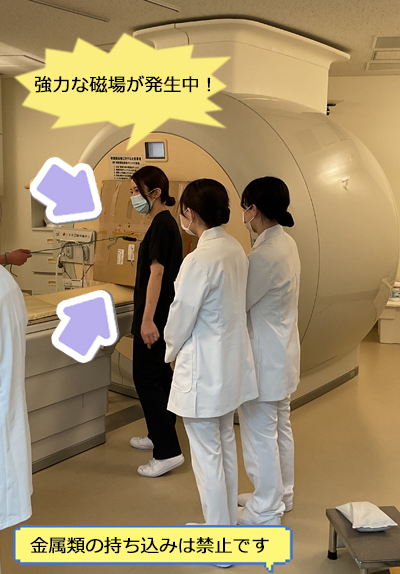
研修医対象の縫合練習では、4グループに分かれて指導医に教わりながら行いました。
女子グループの縫合が上手だったそうです✨

今年度も横浜医療センターの様々な様子を随時更新していきたいと思います。
是非ご覧ください😊
また、季節の変わり目は体調を崩しやすいので皆さんお気を付けてお過ごしください。
ご定年おめでとうございます🎉
2024年03月29日
3月も終わりを迎え、桜の花がちらほらと咲き始め、春の訪れを感じます。
当院では先週金曜日(3/22)に研修医の修了式が行われました。
研修を終える医師たちは全員修了が認定され、この日宇治原院長より修了証を授与されました。

研修医の皆さん、おめでとうございます✨
さて、本日は当院で定年退職を迎えた職員に対し辞令交付式を行いました。
長きに渡り、当院の診療や地域に貢献してきた定年退職者5名へ、院長から感謝の意をお伝えしました。
ご定年される職員のうち、松島副院長(消化器内科)と藤澤看護部長よりメッセージをいただきました。
松島副院長より💬
「私事ですが3月末をもって横浜医療センターを定年退職いたします。1991年に奉職後、30年あまりに渡って勤務を続けることができましたのは、地域住民の皆様ならびに連携いただいた医療施設の皆様のお力添えと、当院スタッフのサポートのお陰であります。
長らくの御厚誼に深く感謝申し上げます。今後は今までとは異なった立場で、微力ではありますが、医療に関わっていく所存です。皆様ありがとうございました。」
藤澤看護部長より💬
「このたび3月31日をもちまして横浜医療センターを定年退職となります。転勤を繰り返し、最後の4年間を横浜医療センターで勤務させていただきました。着任した当時は、新型コロナ感染症の対応に追われ大変だった記憶があります。しかし職員一丸となって毎日、どうしたら良いか話し合い、工夫して何度も訪れる危機的状況を乗り越えました。
横浜医療センターは本当に、職種間の垣根が低く、一つの目標に向けて全員が協力しあう病院だと思います。地域住民に信頼され、ますます発展することを願っております。お世話になり、ありがとうございました。」

ご定年を迎えられた皆さま、本当にお疲れ様でした。
温かいご指導を賜わりましたこと、職員一同感謝申し上げます。

戸塚駅・大船駅改札口からバス停(横浜医療センター行き)までのご案内🚌
2024年03月22日
この度、改札口から最寄りのバス停までの行き方が分かりづらいというご意見をいただきましたので動画を作成いたしました。 当院へお越しの際はぜひご利用下さい。
🚩戸塚駅から横浜医療センター編
🚩大船駅から横浜医療センター編
YouTube道案内動画は当院ホームページのアクセスからもご覧いただけます。
初めてご来院される方や新採用者の方々は、こちらを一度ご確認いただくとバスの乗り間違いや駅で迷ってしまうことも少なくなるかと思いますので是非ご活用ください😊
今後も皆さまのお役に立てるコンテンツをアップしていく予定ですので
引き続き横浜医療センター公式YouTubeチャンネルをよろしくお願いします🎵
看護学校 第59回生の卒業式を挙行しました💐
2024年03月15日
3/8のYouTubeライブ配信をご視聴いただいた皆さま、ありがとうございました✨
とっても盛り上がり、予定より40分ほど延長して配信を行いました!
お見逃しの方はこちらをご覧ください。
また機会があれば出演者のオフショットをご紹介したいと思います!
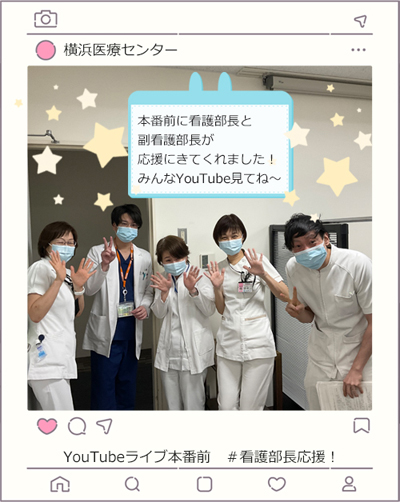
さて、3月5日、当院附属看護学校では卒業式が挙行されました。
第59回生の入学式や戴帽式はコロナ禍の影響で保護者の方の参加ができなかったのでこの卒業式が初めての保護者参加となりました。
また4年ぶりに当院の病棟看護師長も列席し、在校生や来賓関係者に見守られながら華やかな卒業式を迎えることができました。


学校長式辞では、当院院長でもある宇治原学校長より卒業生の皆さんへお祝いの言葉と応援のメッセージを述べられました。
「第59回生の皆さん、ご卒業おめでとうございます。これから多くの新入社員が経験すること以上に看護師の皆さんは新人とはいえ、人の命を預かるという重い責任を強く感じると思います。悩んだ時は先輩に相談してください。同じ経験をしたことがある周りの看護師が必ず助けてくれるはずです。」
卒業生あいさつでは先生方への感謝の思いとこれからの決意が述べられました。
「本校での学びを終え、卒業の日を迎えられたことに感謝の気持ちでいっぱいです。
臨地実習では私たちの学びになるように機会を与えて下さった患者さんに対し、知識や技術の不足、経験の少なさから看護ができているのかと不安や様々な感情が沸き起こる日々でした。コロナ禍の影響で周りの学校では臨地実習ができない中で1年生から実習の機会を提供してくださり全ての課程を終えることができたことは私たちの大きな強みであり、今後に生かすことができると確信しています。
大切な仲間とともにこれから看護師として1歩ずつ歩んでいきます。」

卒業を迎えられた皆さん、おめでとうございます🎉
これからの活躍を職員一同応援しています!
看護学生と実習指導者の交流会を実施しました🍩
2024年03月08日
3/3は雛祭りでしたね🌸
当院でも雛祭りをイメージしたお食事を入院中の患者さんへ提供しました。
今後も栄養管理室では患者さんに喜んでいただけるように季節に合わせた食事の工夫に努めていきます。

さて、実習施設でもある当院では看護学生の臨地実習を行っています。
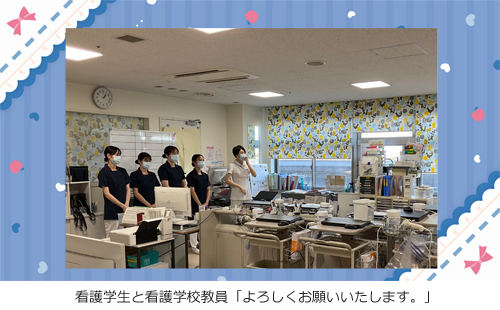
当院の初の試みとして、当院附属の看護学生と実習指導者の交流会を行ったので、今回はその様子をお伝えしたいと思います。
臨地実習は、看護学生が看護師になるために病院などの実践の場で学ぶ大切な授業のひとつです。
これまでの授業は学校で面識のある教員と一緒に学んでいましたが、臨地実習では実際の医療現場に身を置き、初めて受け持つ患者さんや臨床の現場で働く看護師と接するため、今まで体験したことのない緊張や不安を感じます。
そこで、実習指導者である看護師を中心に、看護学生との交流を持ち看護学生が実習に取り組みやすい雰囲気をつくろうと考えました。
交流会では指導者出演の看護学生の実習の1日のVTRを見たり、お互いの自己紹介やクイズ大会などを行い、とても盛り上がりました!

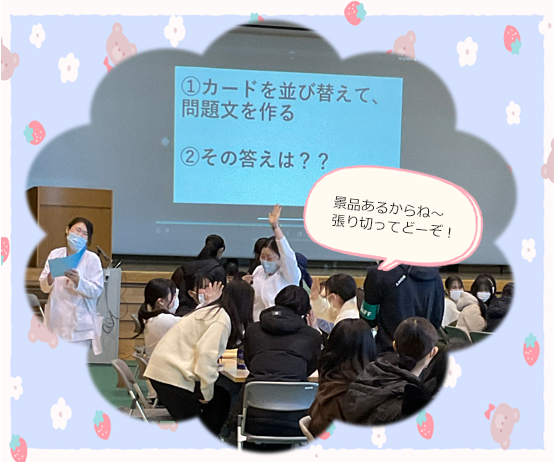


トークタイムでは実習指導者と看護学生のグループに分かれて、看護学生から質問コーナーの時間を設けました。
質問では、「病棟の雰囲気はどんな感じですか?」「どういう勉強をしておくといいですか?」「他病院の実習はどのような雰囲気ですか?」「ポケットには何を入れていますか?」などの質問がありました😊
翌日から各病棟で行った実習では、看護学生皆が良い緊張感の中で取り組めており、実習指導者も事前の交流を通じて学生と関わることができて良かったとお話してくれました。
交流会での楽しさを思い出しながら看護学生の皆が成長できる良い機会になっていると嬉しいです。
YouTubeライブの裏側😎
2024年03月01日
今日から3月がスタートです!
令和5年度も最後の月となり、当院でも来年度に向けた準備がバタバタと始まっております。

1/19に無事に皆さまに当院初となるYouTubeライブ『ウィメンズ・ヘルスケア~女性ホルモンと運動~』をお届けすることができました。
チャットでお悩み&相談コーナーはとても盛り上がりました!
ご覧いただいた皆様、チャットにご質問をお寄せいただいた皆様ありがとうございました❣
職員からは配信後に「YouTube見たよ!」「すごい面白かった!」などの言葉やお疲れ様の温かい拍手をいただきました😊
お見逃しの方はアーカイブ配信を是非ご覧ください。
今日はこのYouTubeライブの裏側を少しご紹介したいと思います。
YouTubeライブの撮影・配信チームは副診療放射線技師長(プロデューサー)、主任臨床工学技士(撮影カメラマン)、広報SE(配信担当)の3名が中心で、昨年の10月から配信場所の確保や機材準備、複雑な配信ソフトの設定や使い方の確認を本職の傍らに行ってきました。
実際の配信場所からYouTubeを介して音声を確認する動作などに苦戦したりしながら何回もリハーサルを行い、万が一のトラブル対応のためにカンペも用意して当日挑みました。
本番は通信不良などが起きずに最後まで予定通りに配信を行うことができて安心しました。

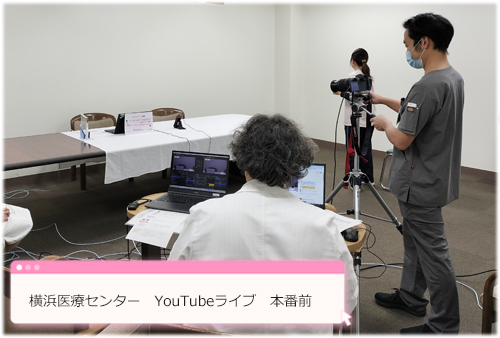

次回のYouTubeライブ『心不全について~心不全パンデミックを迎えて~』
🔊3月8日(金)14:00~15:00に開催します!
皆さんと一緒に楽しめるクイズ企画も行う予定ですので是非ご覧ください。

令和6年能登半島地震への第二次医療支援について
2024年02月22日
当院のこれまでの能登半島への支援についてご紹介いたします。
過去のブログはこちらをご覧ください。
2月11日(日)
医療班6名(副院長(救命救急センター長)・医師・薬剤師・看護師・専門職)を石川県輪島地区へ派遣しました。
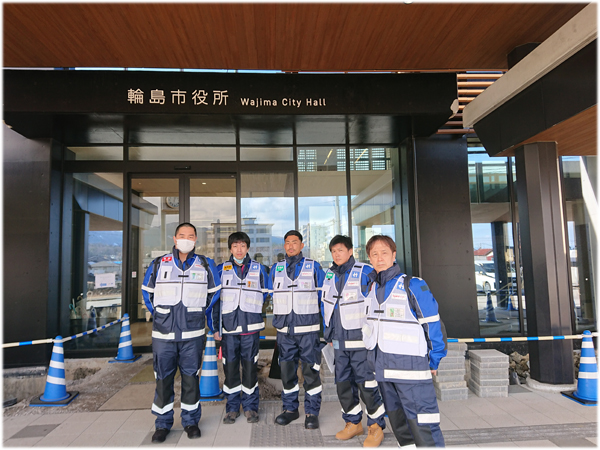
職場体験を実施しました☘
2024年02月16日
今週はバレンタインデーがありました❣
当院では2/14の夕食に入院中の患者さんへバレンタインをイメージした食事の提供を行いました。
皆さんに季節を感じて楽しんでいただけたら嬉しいです。

1月25日に当院近隣の大正中学校の学生5名が職場体験学習を行いました。
半日のスケジュールでしたが、白衣に着替えてオリエンテーションを受け、看護体験を行った後に病棟やリハビリテーション室へ見学に行きました。
オリエンテーションでは看護部長から学生の皆さんへ、
『これから20歳くらいまで学生生活が続くと思うけれど、それから就職すると今は人生100年時代だから70歳、80歳までも働くことができる。それを考えたらとても長い時間ですよね。学生生活よりも先の長い話だから自分に合った仕事、やりがいのある仕事じゃないと続けるのは辛いし、やりたくない仕事を続けるって大変だと思うでしょ?だから職業選択ってとても重要だと思います。
今日来てくれた皆さんが大人になった時に毎日楽しいと思えるような職業についていただきたいです。その中の一つとして、病院で働く人はこんなふうに働いているんだなぁと体験してもらえたら嬉しいので短い時間だけど是非頑張ってください。』とお話してくださいました。
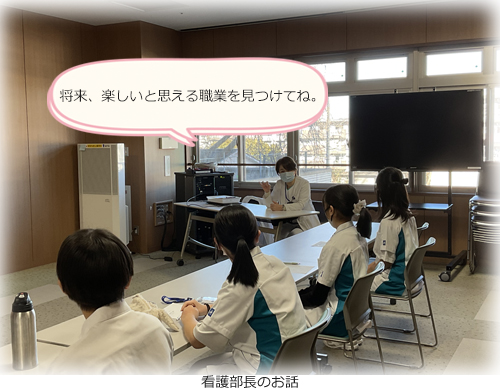


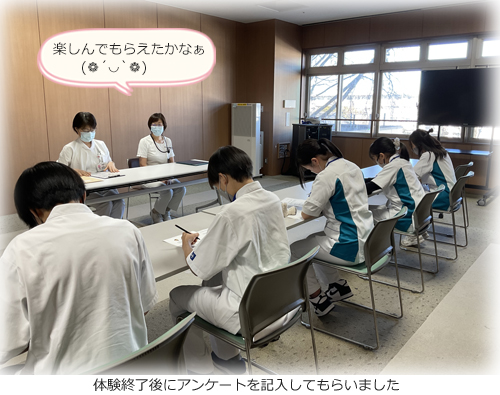
職場体験に参加した学生の感想💬
『とても忙しそうに見えたけれど、みんな笑顔で会話していたのですごいと思いました。』
『看護の仕事について色々教えてくれてありがとうございました。看護について興味を持てました。』
『今回の体験でここの病院で働いている皆さんが患者さんのことを一番に考えていてすごいなと思いました。』
そして最後に意見交換会を行い、記念写真をプレゼントしました✨

今回の職場体験で、看護師や病院の仕事に少しでも興味をもつきっかけになっていただけたら嬉しいです。
大正中学校の皆さん、ありがとうございました😊
院内研究発表会を開催しました📝
2024年02月09日
今週月曜日、関東では午後から雪が降り帰宅時間頃は交通に影響が出て大変でしたね。

昨年12月に院内研究発表会(第30回クリティカルパス大会)を開催しました。
過去のブログでもご紹介していますが、当院では各病棟や部門が、クリティカルパス(入院中の予定をスケジュール表のようにまとめた診療計画書:以下パス)を新たに作成したり、既存のパスの定期的な見直しを行い診療の質を向上する活動を行っており、その活動の成果を発表する場として、毎年パス大会を行っています。
なお、今回は、3月10日に開催される日本医療マネジメント学会神奈川大会(大会長:当院宇治原院長)を見据え、パス以外の研究も発表可能とし、発表の中には放射線科の誘導サインやトイレサインが分かりにくいという患者さんのご意見から改善を行ったという内容もありました。

また、第1回目パス大会は今から20年前の2003年12月に開催されたのですが、当時を知る宇治原院長から次のようなお話がありました。
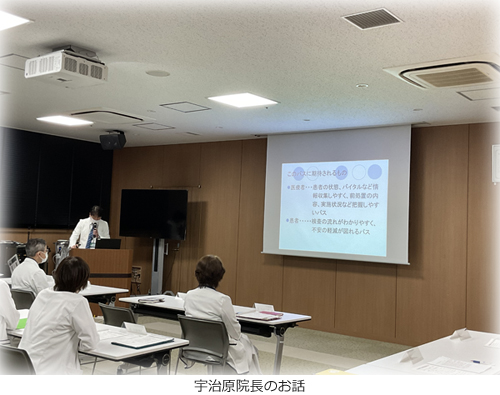
『2002年~2003年頃、全国の病院でパスの導入が始まりました。当院でもその時期にパスの運用を開始し全部署で発表を行うことによって、啓蒙してきました。
第1回目の大会では、糖尿病チームケアユニットの作成についての発表があり、そこから当院でのチーム医療が始まりました。当初はチームを作るために色々な部分で苦労しました。
パスの真髄は「連携」です。そのため、これからも常に患者さんと医療者をセットで考え、パスを通して医療の標準化を作ってほしいです。病院では医師や看護師が定期的に入れ替わります。標準化は必ず必要で医療安全にもつながります。』
今大会の優秀賞3部門🎊
🏅集中管理部「アンギオ室において迅速な業務対応を行うための医療材料・医療機器の整理整頓」
🏅栄養管理部「院内栄養管理体制の改定による栄養管理業務の効率化」
🏅西2病棟「統合失調症患者の疾病心理教育を導入して」
今後も定期的に院内研究発表会を開催し、当院の医療の質を高めていきたいと思います。

令和6年能登半島地震への当院の医療支援について
2024年02月02日
令和6年能登半島地震の被害に遭われた皆様へ心からのお見舞いを申し上げます。
今回は当院のこれまでの能登半島への支援についてご紹介いたします。
1月9日(火)
医療班5名(医師・薬剤師・看護師・事務職)を石川県輪島地区へ派遣しました。

1月20日(土)
横浜医療センターDMAT隊5名(医師・看護師・業務調整員)を石川県七尾市へ派遣しました。

次回の派遣は2/11を予定しており現在国立病院機構内で調整中です。
院内災害訓練・日本DMAT関東ブロック訓練を実施しました
2024年01月26日
令和6年能登半島地震の被害に遭われた皆様へ心からのお見舞いを申し上げます。
報道では、建物や道路、水道等にも甚大な被害のある中、被災地の病院では懸命の診療を続けているとのことで、当院としても医療班やDMAT隊の派遣を行っており、引き続き支援を行っていきたいと思います。
万が一の事態に備えるという点で、当院でも災害に備えるための訓練を定期的に実施しています。
昨年11月に大規模地震(首都直下型M8.2/最大震度7)発生を想定した災害訓練を実施していますので今回はその訓練について紹介します。
当院は災害拠点病院であるため、地域医療を維持するために必要な対応訓練を2つ行いました。
1つは『院内災害訓練』、もう1つは『DMAT訓練』です。
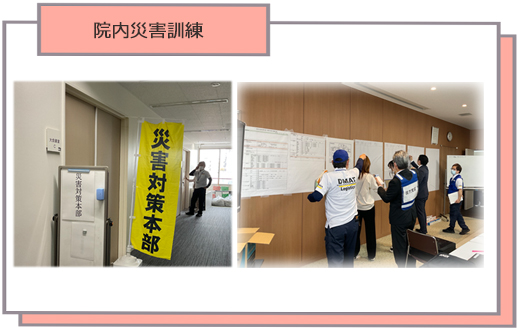
『院内災害訓練』では、災害拠点病院としての機能、診療体制・対応の確認を行いました。
実際に災害対策本部を設置し、院内の被災状況や職員の状況の把握、入院患者さんの状況などの情報集約を行いました。
また、トリアージエリアを設置し、多数の被災者が来院することを想定して当院附属の看護学生に搬送スタッフ・患者さん役として協力いただき訓練を行いました。
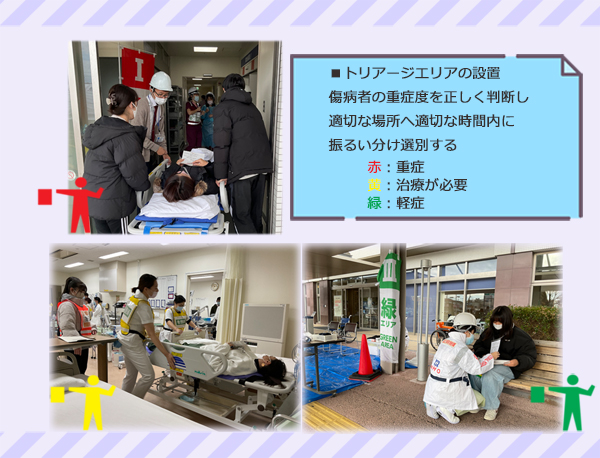


『日本DMAT関東ブロック訓練』では、1都6県のDMAT指定医療機関が参加し、神奈川県内全域が被災した想定のもと、当院を含む市内4病院に活動拠点本部を設置し実動訓練を行いました。
本部運営では、地域医療の被災状況の把握や情報収集・分析を行い、ライフラインに対する補給や適切な物資の支援、DMAT隊の派遣を行いました。
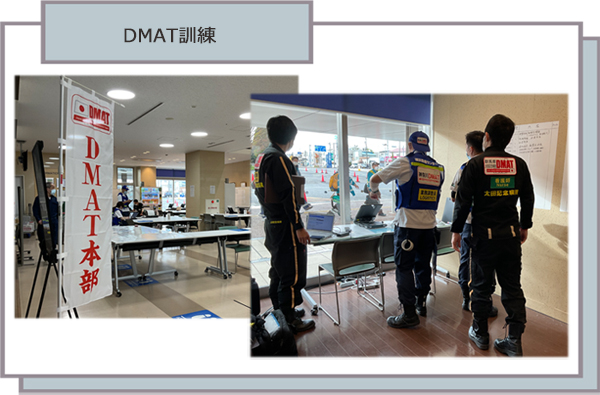
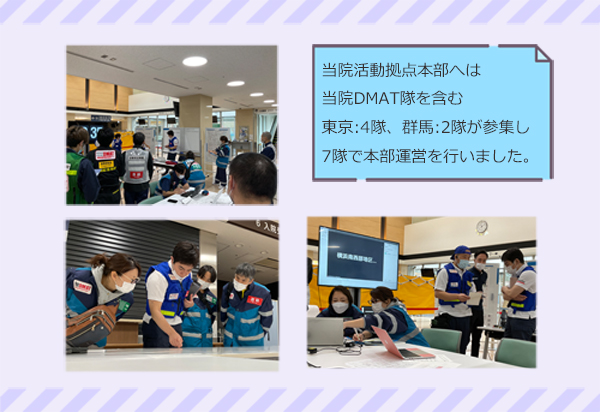
今後の課題や実施後の感想💬
■院内災害訓練
『今回の院内災害訓練は「災害対策本部運営訓練」と「多数傷病者受入訓練」の2本立てで実施しました。訓練内容は指揮命令系統の確立、情報収集、対策の決定が主となる訓練でしたが、災害用物品や初動対応、人員配置の不備・未整備を改めて認識することができました。またコロナの影響もあり、災害に対する意識が薄れていたことも否めません。ですが、当院は地域の災害拠点病院、戸塚・泉区医療の最後の砦であることを肝に銘じて、今後も災害訓練を継続的に実施し、職員一人一人が災害に対する意識を高め、災害に強い病院を目指していきたいと感じました。』
■DMAT訓練
『コロナの影響で約5年ぶりの実動訓練でした。そのため感染対策に配慮したDMATとしての本部運営の在り方を再確認する事が出来ました。災害に打ち勝つには地域の助け合いが不可欠なので、院内や地域の方々の協力を得ながら活動していくことは引き続き必要になる課題だと感じています。』
災害はいつ発生するかわかりません。
しかし、万が一に備えておくことは非常に大切だと再認識しました。
今後も訓練は継続し、私たちの使命を果たせるように対応していきたいと思います。
地域子育て拠点との共催の研修会を実施しました🍀
2024年01月19日
本日14:00~当院初の\YouTubeライブを配信/します🎊
お気軽にご参加ください✨
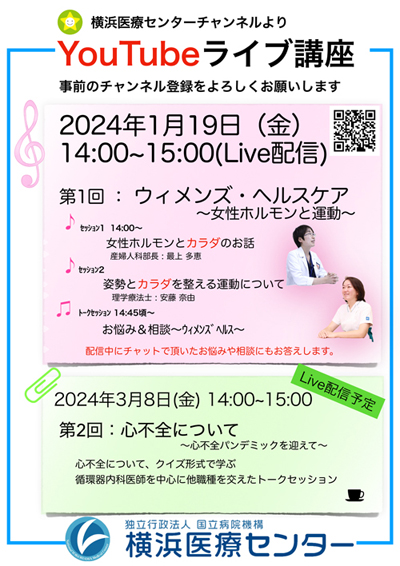
昨年、12月12日に地域子育て拠点「とっとの芽」で、「お医者さんに聞いちゃおう」という研修会を行い、当院から4名(小児科医、産婦人科医、助産師2名)が講師として参加しました。
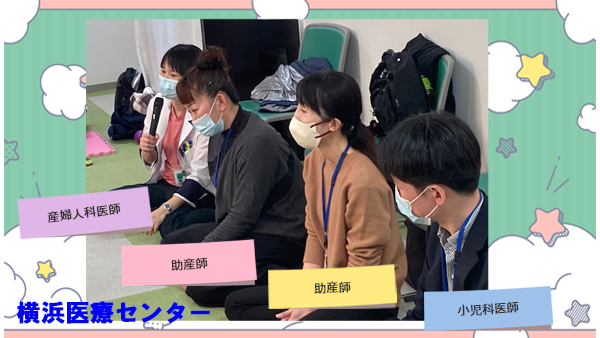
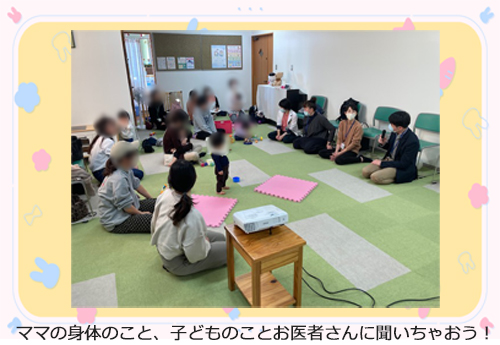
研修会といっても、お子さん・お母さん自身の質問を座談会(交流会)で話し合うものです。
母子参加の研修のため、親子で一緒に和やかな雰囲気で研修会は進みました。
研修は1時間を予定していましたが、参加されたお母さんからは夜泣きについて、離乳食のこと、2人目妊娠のタイミングのことなどについての質問があり、当院の医師、助産師が一つずつ丁寧に回答していると、あっという間に時間が過ぎてしまい、少し追加の質問を受け付け、研修会は終了しました。
参加者からは「とてもためになる内容であった」等の嬉しい言葉を頂けました。
今後もこのような地域交流を積極的に行っていきたいと思います。
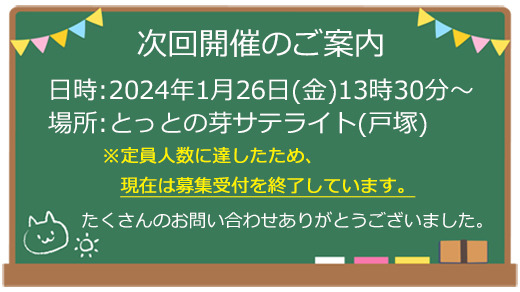
職員向けのグルメフェア企画を実施しました🍥🍜
2024年01月12日
当院看護部、副師長会のQC活動(※)チームからの発案でグルメフェア企画を実施しました。
横浜医療センターでやりがいをもって楽しく働き続ける職員を増やしたい!という思いから実施された企画で、職員向けに1/10・11の2日間、当院2階の食堂で日替わりの特別ランチメニューを提供しました。
※Quality Control=品質管理や改善のための活動

【1/10:醤油とんこつラーメン・ミニチャーハン】
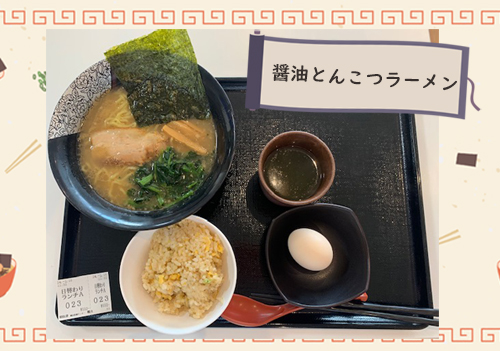
この日は全提供数164食のうち140食がこの限定メニューだったそうで、売り切れて食べられなかったという職員もいました。
【1/11:わらじかつ丼】


メニューは、看護部で希望メニュー投票を行い、結果をもとに食堂と話し合いをして決まったそうです。
この2日間、職員同士の会話のきっかけにもなり、おいしい食事でパワーを補充することができたようです😋
中にはボリューム満点の食事で、午後の仕事に支障が出そうだ…という声も😴
また第二弾も実施できるよう検討していきたいと思います!
さて、昨年のブログでお知らせしたタウンニュース元旦号(戸塚区版・泉区版)はご覧いただけましたでしょうか?

📑https://www.townnews.co.jp/0108/2024/01/01/712757.html(戸塚区版)
📑https://www.townnews.co.jp/0107/2024/01/01/712656.html(泉区版)
記事にありますように、今年は手術室の増室や放射線治療機器を最新機器へ更新を行う予定です。
時代のニーズに合わせて対応していけるよう準備を進めていきたいと思います。
新年のご挨拶🐉
2024年01月05日
謹んで新年のご挨拶を申し上げます。
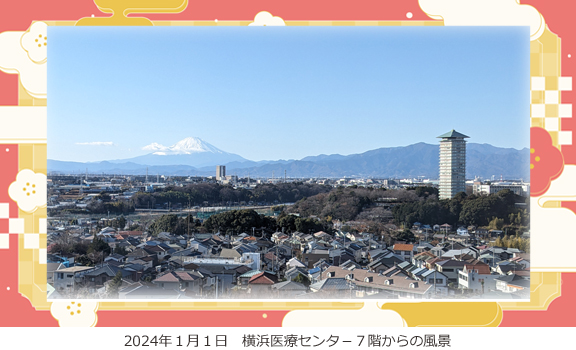
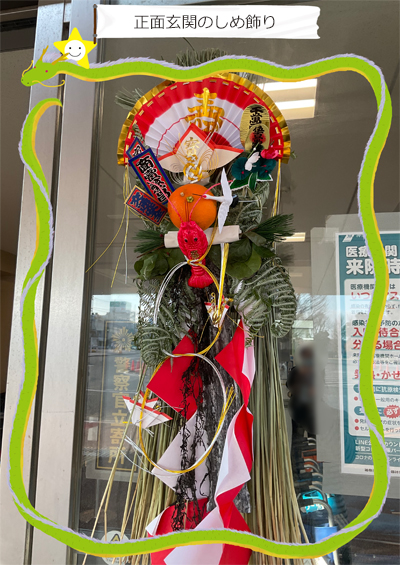
今年は「辰年」ですが、これにはどんな意味があるのでしょう。
干支は十干(甲・乙・丙…と1から10まで数える言葉)と十二支(皆さんご存知の12種類の動物)の組み合わせから成り立ち、60年で一周します。2024年は「甲辰」になりますが、甲は十干の始まりにあたり物事の始まりを意味し、辰は草木が成長する様子を表すとされています。
諸説ありますが未来に向けて物事を始めるのに良い年のようです。
当院も今年は新たな取り組みに向けて準備を進めていきたいと思います。
『院長メッセージ』はこちらからご覧いただけます。
入院中の患者さんへ毎年恒例の年末年始食事メニューを提供しました。
お正月を病院で過ごす患者さんたちに少しでもお正月気分を味わっていただけたら幸いです。





本年も横浜医療センター病院ブログをよろしくお願いいたします。
今年もサンタさんが遊びに来てくれました!
2023年12月27日
クリスマスがあっという間に過ぎ、今年も残りわずかとなってまいりました。
このブログも本日が今年最後の更新となります。
さて、少し前に戻りますが…先週12月22日に院内保育園では恒例のクリスマス会が行われ今年も保育園にサンタさんが来てくれました!
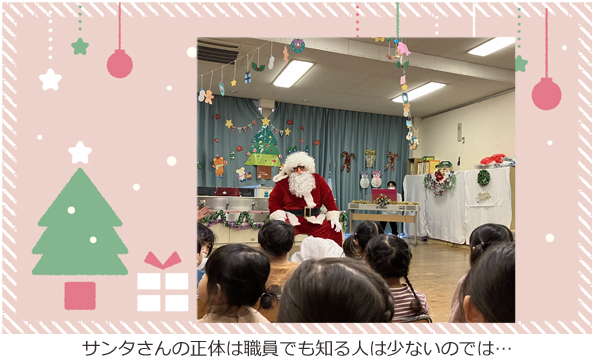
サンタさんを初めて見てびっくりしているお友達もいましたが、みんなで一緒にクリスマスソングを歌ったり、プレゼントをもらったりと、楽しく過ごしました。
午後はお楽しみのおやつバイキング🍭🍩
子どもたちは食べたいお菓子を自分で選んでたくさん食べることができてとても喜んでいました。

12月24日には入院中の患者さんへクリスマスをイメージした食事の提供を行いました。

**メニュー**
・エビピラフ
・グリルドチキン
・カボチャサラダ
・彩ピクルス
・ミネストローネ
・いちご
・クリスマスケーキ
食材費の高騰など様々な制約がある中でも、今までと変わらずに献立を提供できるよう栄養管理室の工夫が込められています。
クリスマスの贈り物や食事の提供で、沢山の患者さんの笑顔を見ることができて大変嬉しく思います。
本ブログをいつもご覧いただいている皆様、ありがとうございます。来年も当院の様々な出来事を紹介しますので、楽しんでいただけたら幸いです。
当院は年内28日まで、新年は1月4日から通常診療を行います。
どうぞ良いお年をお迎えください。

患者さんへクリスマスカードを贈りました🎁
2023年12月22日
もうすぐクリスマスですね。
今年は冬にも関わらず暖かい日が続いていましたが、週末は晴れても厳しい寒さとなる予報です。
急な寒さに気を付けて楽しい週末をお過ごしください。
今日は当院でのクリスマスの取り組みをご紹介します🎄✨


当院附属の看護学校では、学生たちが実習でお世話になっている入院中の患者さんに日頃の感謝の意味を込めてクリスマスカードを配布しました。
患者さんに心和むひと時を過ごしてもらい、季節感を味わっていただくということを目的に、看護学校のクリスマス委員の学生が中心となってクリスマスの企画を行いました。
そして、1、2年生全員で授業・演習の合間・放課後の時間を使って、心を込めてポスターやカードの作成を進めてきました。
そして本番の昨日(12/21)、クリスマスの音楽を流しながら各病棟を回って配布を行いました。

病院でクリスマスを過ごす一般病棟の患者さんや小児科病棟の子どもたちが学生や職員たちと一緒に楽しい時間を過ごす様子を見ることができて私たち広報部も嬉しく思いました。
また、先日小児科病棟の子どもたちへ全国共済神奈川県生活協同組合様より闘病中の子どもたちの一刻も早い回復を願い絵本が届きました。
温かいご支援を賜り心より感謝申し上げます。
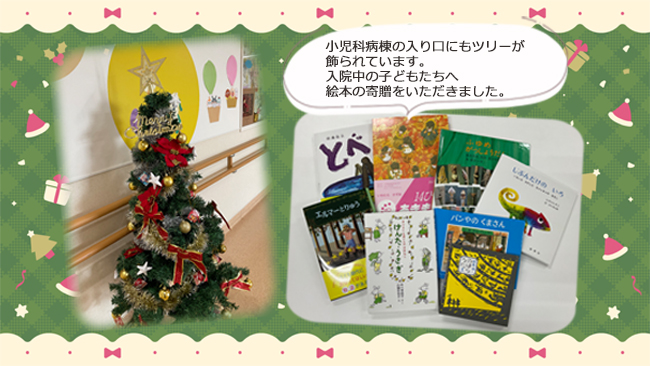
次回は今年最後のブログです。
引き続きクリスマスの様子をUPしたいと思います。
是非ご覧ください😊
言語聴覚士がブログインタビューに答えてみた!
2023年12月15日
※イルミネーションは令和6年2月15日をもって終了いたしました。
冬至に向けて、日の入りが早くなってきましたね。
冬の夜空に映える当院のシンボルツリーは今年度も「ソーラーパネル」蓄電によるイルミネーションを実施しています。

点灯期間は令和6年2月29日(木)までとなっています。
癒しの灯を楽しんでいただけたら幸いです。
さて、今日は言語聴覚士のお話です。
言語聴覚士とは「話す」・「聞く」・「食べる」といった人が生活する上でとても大切な機能の障がいがある方に専門性の高いサービスを提供し、自分らしい生活を構築できるように支援するセラピストです。
「Speech Language Hearing Therapist」の頭文字をとって院内では「ST」と呼ばれています。当院で勤務する2名のSTにインタビューを行いました。
🔸言語聴覚士になるにはどのような資格が必要ですか?
高校卒業後に大学・短大または専修学校(3~4年)へ行くか、大学4年を卒業後に専修学校(2年)を卒業し国家試験に合格する必要があります。
2人とも元々は教員や心理学の道を目指している途中でSTの職業を知り興味も持ちました。
🔸横浜医療センター(急性期病院)でのSTの業務を教えてください。
脳血管疾患や交通事故などで脳の一部を損傷したために、失語症・構音障害(高次脳機能障害)によりコミュニケーションに支障がある方への評価や訓練プログラムの検討を行っています。また、内科疾患等が原因で起こる嚥下障害で食べ物が飲み込めない方への訓練なども行います。
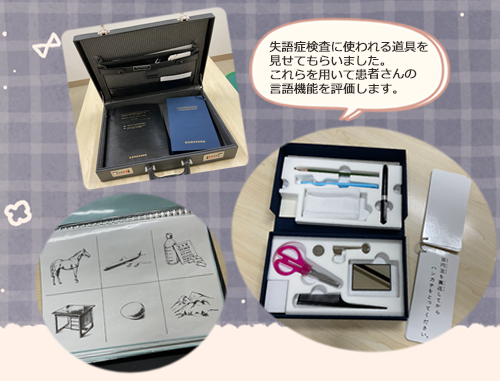
🔸仕事をしていて楽しいことや嬉しいことを教えてください。
精神的に1番大変な時期を乗り越える場所だと思うので、辛いリハビリを乗り越えて食事ができるようになったりして回復していく患者さんをみられることが嬉しいです。
🔸最後に言語聴覚士を目指す方へメッセージをお願いします!
専門のカリキュラムはとても辛いし、就職後も勉強は必要なので日々忙しいですが、患者さんに合わせたプログラムで訓練の成果が出た際には大きなやりがいが感じられます。
また、当院は土・日・祝はお休みなので子どもの習い事の付き添いや好きな場所へ出かけるなどプライベートも充実しています。
今回のインタビューを通してSTの方々が、患者さんやそのご家族へできることの可能性を増やし良い未来へ導くお仕事をされているということがとてもよく分かりました。
今後も当院では患者さんの「できた!」を多く増やせるように一人一人の気持ちに寄り添って支援を行っていきます。
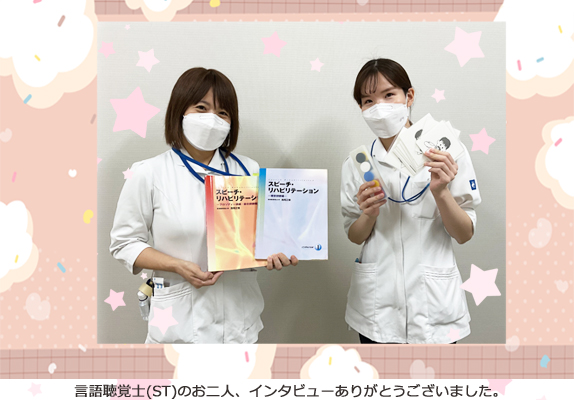
タウンニュース新年号の取材を受けました!
2023年12月08日
冬が近づくにつれ空気が澄んで景色が綺麗に見えますね。
当院敷地内からの風景を少しご紹介します。



だんだんと冷え込みも増し、風邪など引きやすい時期ですがこの季節こそ見ることができる景色もあり、まもなく当院で点灯予定のイルミネーションも楽しみです✨
点灯した際にはこのブログでお知らせしたいと思います。
さて、先日タウンニュースの記者の方から宇治原院長と栃尾産婦人科医長がインタビュー取材を受けました。
記事は2024年1月1日新年号に掲載される予定です。

内容についてはまだお話できませんが、当院の敷地内にある附属の看護学校や産婦人科に関わるお話について主に取材していただきましたので、こういった内容が掲載される予定です。 皆さんも新年号タウンニュースをご覧になって当院の記事を見つけていただけると嬉しいです。 是非お楽しみに🎵

YouTubeにてライブ配信準備中!
2023年12月01日
今日から12月です。もう師走ですね。
例年にない暖かさの11月でしたが、平年並みに落ち着いて来たように感じます。
さて、横浜医療センターのYouTube公式チャンネルを開始して1年が経ちました。もうご覧になっていただけましたか?
当院では新しい試みとして、来年から公開講座をYouTubeライブで配信します。
視聴者の皆さまのご意見も聞きたい!という思いから、リアルタイム配信を企画しました。
また、チャットを解放し、配信中に講師が質問にお答えします。
1月は“ウィメンズ・ヘルスケア”について、産婦人科の最上医師から“女性ホルモンとカラダのお話”、また、安藤理学療法士から“姿勢とカラダを整える運動”について実技を交えてお話します。
講座の最後には、2人がお答えする“お悩み&相談”のコーナーもご用意しています。
ぜひ、この機会にチャットでご質問をお寄せください。
3月は、当院の心不全ケアチームが中心となり様々な職種のスタッフを交えた講座を企画しております。
こちらは心不全について、クイズ形式で学べる講座となっていますのでご期待ください。
多くの方々に楽しんでいただけるよう各講師やスタッフが趣向を凝らして企画しております。
ぜひ、年明けからのYouTubeライブを楽しみにしてください。
横浜医療センター公式チャンネルの登録もお願いいたします!
職員の休日🎵
2023年11月24日
ようやく秋も深まってきましたね。
師走に向かって慌ただしくなってきますが、ふと見上げた空が高くて気持ちの良い季節です。
さて、このブログでは当院で行われた様々な行事の様子をUPしましたが、今回は当院職員の「秋の休日」をご紹介します。
既にご存じの方も多いかもしれませんが、宇治原院長はテニスが趣味です。
テニス好きの職員を集めて余暇活動としてテニスサークルを主催しています。
以前は定期的に開催していたテニス大会(通称:宇治様カップ🎾)が久しぶりに開催されました。
現職に限らず、退職された方も含めての活動です。
大会日程は9月でしたが、8月から事前練習会を行ってみんな気合十分!
もちろん、応援のみの参加も可能でした。

参加した職員に感想を聞いてみると「来年は優勝目指して頑張ります‼」というコメントがありました。
休日の気分転換に、カメラを携えて出かける職員も📷
~山中湖パノラマ台付近から見た風景~

~大山の風景~



休日時間を思い思いに過ごす職員の1コマ。素敵な作品ですよね。
医療従事者に限らずですが、仕事を長く続けるためには休息の時間や自身の健康管理も大切です☕
今後も質の良い医療が提供できるよう職員の心と体の健康維持に努めてまいります。
国立病院総合医学会 in広島に参加しました
2023年11月17日
10月20日~21日にかけて国立病院総合医学会が開催され、全国の国立病院機構の施設から約6000名の職員が参加し、様々な発表や討議が行われました。
昨年は規模を縮小して開催されましたが、今年は4年ぶりに特別講演・教育講演・シンポジウム・ポスター発表、一般口演(応募数2,115題)のフルバージョンでの開催となりました。

当院からもたくさんの職員が参加し、宇治原院長の「急性期病院の患者マネジメント-求められる運用と実践-」をはじめ、医師、看護師、薬剤師、理学療法士、臨床工学技士、事務職員がそれぞれの分野について発表を行いました。
我ら広報チームからも代表職員が、広報部の立ち上げに至った経緯や広報委員会発足について、また、広報としての新たな役割や実績をポスターにまとめて発表を行いました。
国立病院機構ではまだ馴染みのない「広報部」について、現地で質問を受ける場面もありました。
このブログも広報活動の一環です。
みなさんに「今」を届けられるよう継続していきたいと思っています。
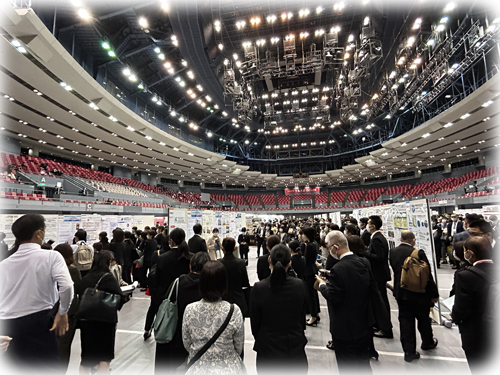

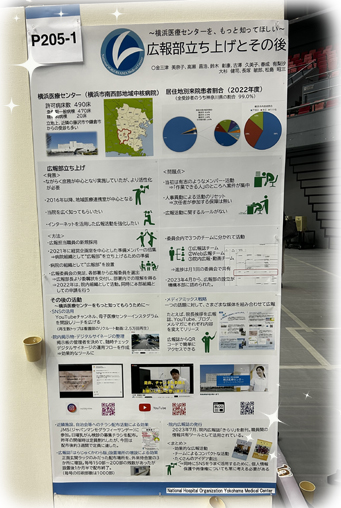
職員からのお土産写真📷


参加した職員からの感想コメント💬
・発表の準備は大変だがメーカー機器の出店ブースでロボット手術の操作を試すことができて良い機会になった
・様々な立場から意見交換が出来て刺激になる
・学会で学ぶ他に、仲間との絆を強めることができた
国立病院総合医学会は、職員にとって全国の仲間に再会できる良い機会です。
今後、学会で得た学びをそれぞれの業種から関わる皆さまへ貢献していきたいと思います。
第61回戴帽式を行いました
2023年11月10日
先日、看護学校で戴帽式が行われました。
当院の戴帽式はこれから本格的な実習を行う看護学生の1年生(戴帽生)が看護の道へ進む決意を表明する儀式です。

式では、学生一人ひとりが聖火をろうそくに灯し、全員で誓いの言葉を暗唱しました。
ろうそくの灯は、ナイチンゲールが暗い夜も患者さんのためにろうそくを灯して看護していたという言い伝えから看護の心の灯火とされています。


厳かな雰囲気の中、暗闇の会場内を、ろうそくを持って歩く場面もありましたが、緊張の表情ながら皆さんしっかり前を向いて堂々とした様子で臨んでいました。

戴帽生代表の挨拶では、両親への感謝の言葉を述べた際に保護者の方が涙ぐむ場面も見られました。

戴帽式を終えた皆さん、これから実習が始まりさらに本格的な授業が始まると思いますが頑張っていきましょう。
今回ご参列いただきました保護者、来賓関係者、祝電をいただいた皆様ありがとうございました。
📑戴帽式の様子はタウンニュース戸塚区版(2023年10月19日発行)にも掲載されています。
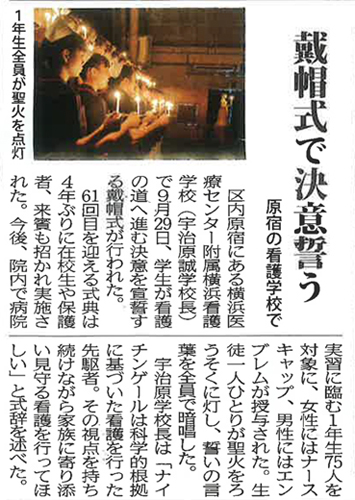
院内保育園親子レクリエーション
2023年11月02日
10/31はハロウィンでした。
当院でもハロウィンの飾り付けや入院中の患者さんには行事食の提供を行いました。
外来ホールの飾りつけ中に来院者の方から「気持ちが明るくなりますね😊」とお声がけいただき職員も嬉しく感じました。




さて、先日院内保育園の『親子レクリエーション』が看護学校の体育館で行われました。
第1部の親子レクリエーションでは、保護者と一緒に体操をしたり、かけっこをしたりと、親子の触れ合いの時間を楽しみました。


第2部の和太鼓体験・鑑賞では、栄区を中心に活動している団体【昇龍】による和太鼓演奏に、子どもも大人も太鼓のリズムに合わせて手拍子をしたり踊ったりして、楽しいひと時を過ごしました。

保護者アンケートで以下のような感想をいただきました。
・すべてが手作りで、アットホームな雰囲気の中、子どもたちをよく見て下さっているのが分かりました。
・リトミックなども、保育園でいろんな練習をしていることが分かり、子どもの成長が見られて、とっても楽しかったです。
・小さい子が多い中でも工夫されていて、楽しめました。和太鼓がとても良かったです。大人も楽しませてもらいました。
今後も院内保育園では保護者である看護師などの職員たちが安心して仕事に取り組めるよう日々の保育や親子で楽しめる行事の企画に努めていきたいと思います。
J.M.Sプログラムに参加しました
2023年10月27日
今日は、先週実施された「ジャパン・マンモグラフィー・サンデー(J.M.S)」の報告です。
J.M.Sとは、子育て・介護・仕事など多忙な平日を過ごす女性のために「10月第3日曜日に全国でマンモグラフィー検査が受診できる環境作り」を目指し、日本乳がんピンクリボン運動(認定NPO法人J.POSH)が全国の医療機関に呼びかけ、2009年から開始した取り組みです。
当院では今年で3回目の参加となり今年度は10月15日(日)に開催されました。
今年はさらに多くの方に知っていただくために、自治会・町内会の皆様にご協力いただき、当院近隣にお住いの方々への開催案内チラシの回覧をさせていただきました。
また戸塚駅周辺のPRボックスへも開催案内チラシを配架させていただきました。
たくさんのご予約をいただきありがとうございました。
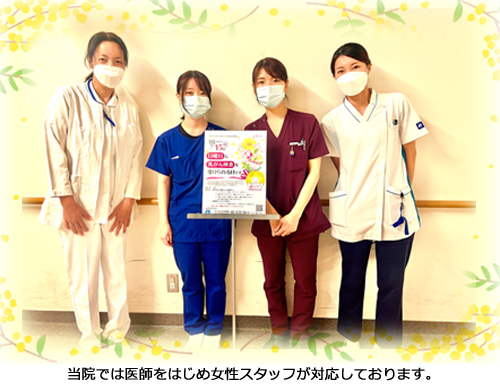
乳がんについて乳腺外科の先生にお話を伺いました。
🎗乳がんについて教えてください
「乳がんは女性がかかるがんの中で一番多く、年間約9万人の人が乳がんと診断されます。早期発見すれば治る可能性が高いため、定期的な検診受診と自己触診をお勧めします。」
🎗年齢的に注意した方がいい年代はありますか?
「近年は高齢の方の乳がんも増えてきていますが統計的には40歳から60歳代に罹患率のピークがあります。そのため、40歳以上の方は積極的に検診を受けていただきたいと思います。なお、30歳代の方の乳がんも増えてきていますので、血縁の方に乳がんの既往がある場合などは積極的な検診受診をお勧めします。」
【受診された方からのアンケート】
・女性限定で安心して受診できた
・平日受診できないので日曜日で良かった
などの感想をいただきました。
平日多忙でなかなか病院に行くことができない女性の方々にこの活動を知ってもらい、さらに多くの方に参加していただけるよう、取り組んでいきたいと思います。
【チーム医療の活動紹介10-1】心不全ケアチームが学会発表しました
2023年10月20日
秋晴れの日が続いていますね。
10月に入り様々な行事が開催されています。
当院でも先週から院内保育園のイベントやJ.M.S(ジャパン・マンモグラフィー・サンデ-)プログラムが開催されました。
また本日20日(金)~明日21日(土)まで国立病院総合医学会(広島)が開催されますので、順次開催の報告をブログで更新したいと思います。
さて、今日のブログは10月6日(金)~8(日)に開催された「第27回日本心不全学会学術集会」の参加者からの報告です。

心不全とは心臓のポンプの力が弱いために息切れやむくみが起こり徐々に悪化して生命を縮めることがある病気です。
心不全は、がんの次に死因として多い疾患で、心不全患者は毎年1万人ずつ増えている傾向にあります。
当院では、心不全の入院患者さんが病気と折り合いをつけて生活していくために昨年多職種のメンバー6名からなる「心不全ケアチーム」が発足して活動しております。
今回の学会では、心不全ケアチームでの活動報告として、各メンバーが、活動の中で得られた成果や、学んだことを形にするというコンセプトをもとにチームメンバー6名(循環器内科医師、慢性心不全認定看護師、理学療法士、退院調整看護師、栄養士、薬剤師)全員が発表しました。
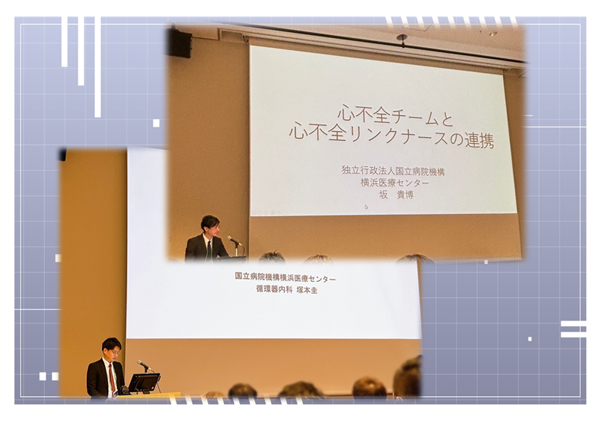
学会では毎年新たな知見が発表されるので診療に関する情報をアップデートすることができてチーム一人一人のモチベーションや熱量も上がったようです。
また、近年の心不全患者の増加により地域全体で患者を看ていく方向性に変わってきていることも訪問看護師や在宅介護士など多くの地域の医療関係者の参加により実感したそうです。
今後もさらにチームの活動の精度をUPさせて診療に取り組んでいきたいと思います。

心不全ケアチームのみなさん、日々の業務の中での学会準備・発表お疲れ様でした😊
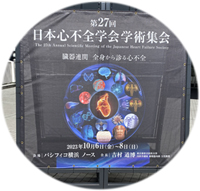
小児科病棟入口扉のデザインをリニューアルしました🌈
2023年10月13日
患者さんから小児科病棟(4階)への入口がわかりづらいというご意見をいただき、東4病棟全体の誘導サインと小児科病棟入口扉のデザインをリニューアルしました。
変更①:エレベーターを降りた際に目に入るサインを産科・小児科への方面をわかりやすく変更。

変更②:エレベーターを降りて左に曲がった壁面のサインを産科と小児科を色分けして表記。

変更③:産科病棟スタッフステーションのカウンター下に、奥に小児科病棟の入口があることを示すよう表記を追加。

変更④:小児科病棟入口扉のデザインをリニューアル。

リニューアル後、患者さん「見やすくなった」「わかりやすくなった」「明るくなった」とお声をいただいています。
病棟職員からも、これまでは小児科病棟までたどり着けない方を見かけることもありましたが、最近では迷わず小児科病棟入口までたどり着いている方が多いと感じるという声を聞けました。
また、小児科病棟師長からは「不安で入院してくるお子さんや保護者の方々に少しでも安心していただけたらいいなと思っています」とコメントがありました。

今後も皆さんからのご意見をもとに、安心して過ごせる環境づくりに努めていきたいと思います。
看護師免許証が届くまで
2023年10月06日
9月29日は十五夜でした。
必ず十五夜に実際の満月が重なるわけではありませんが、今年は綺麗な満月が見られましたね。
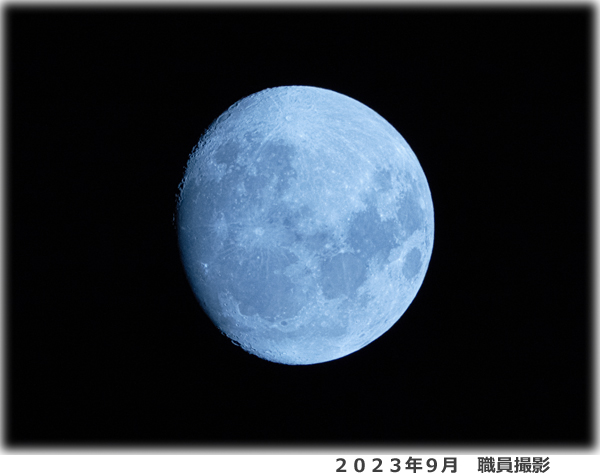
当日には入院中の患者さんへ行事食を提供しました。

~メニュー~
・炊き込みチャーハン
・鮪ソテーおろしソースがけ
・京がんも炊き
・キャベツ人参和え(ポン酢)
・十五夜デザート
少し暑さも和らぎ食欲がわいて患者さんには沢山食べていただけたようでした。
季節の変わり目を感じながらお月見を楽しんでいただけたら嬉しいです。
今年3月、看護師国家試験に合格後、看護師免許証の申請を行っていた新人看護師たちの元に看護師免許証が届きました。
申請から実際に厚生労働省より発行され、届くまでに数カ月の期間を要するため免許証が手元に届くまでは登録済み証明書用はがきを免許証代わりとして、看護師として勤務することが可能です。
そのため看護師として働くためには、試験に合格して終わりではなく免許を取得するための申請が必須となります。
※産科の助産師は助産師国家試験と合わせて看護師国家試験に合格する必要があります。

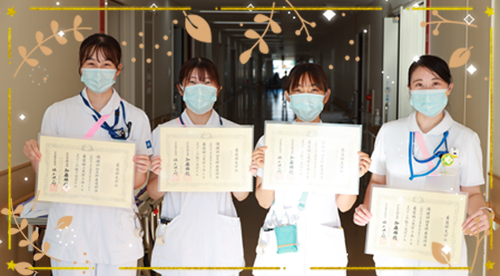
猛勉強の日々から国家試験、合格発表、就職と…手元に届くまで長い道のりだったと思います。
皆さんの笑顔からいろいろな思い出が詰まった大切な看護師免許証なのだと感じますね😊
撮影にご協力いただいた新人看護師の皆さんありがとうございました✨
新人看護師研修vol.4
2023年09月29日
今週始めの月曜日はさわやかな秋晴れでしたね。
ようやく秋の気配が感じられたと思ったら翌日からまた夏の蒸し暑さが戻ってしまいました。
日々の寒暖差も大きく体調を崩しやすい時期です。
また、市内ではインフルエンザが流行していますので引き続き感染対策を行っていきましょう!
さて、先日新人看護師研修が行なわれました。
今回の研修内容は看護職の倫理についてです。
看護師は相手の立場になって気持ちを理解することがとても大切です。
過去のブログでのお話にもありましたが、ドラマを見ると客観的にいろいろな人の気持ちがわかるのでいろんなジャンルのドラマを見ると良いと看護部長がお話されていました。
皆さんもドラマなどで、「自分の病状について誰にも言わないでほしい」、「家族の余命は本人に言わないでほしい」、と患者さんが言っていたり、本当にこれでいいのかな?と思うような対応をしたりする場面を目にしたことがあると思います。
そばにいる看護師は、どんな対応が患者さんにとって最善なのか思い悩むことがあります。このような時に「看護職の倫理綱領」という行動規範があります。
今回の研修では「看護職の倫理綱領」を確認しながら、患者さんが治療を受ける上で、患者さん本人や家族の思いを汲み取ったり、想像したりすることが、看護には大切であることを理解しました。
これからも定期的に研修を行って日々の看護業務を振り返りながら、患者さんやそのご家族の気持ちに寄り添った看護ケアができるように努めていきたいと思います。

敬老の日
2023年09月22日
最近の天気は急変が多く、傘を持たずに出かけたら突然大雨に見舞われた…とお困りの経験をされた方も多いのではないのでしょうか。
先週も、夕方帰宅する頃の時間は土砂降りでした。また雷にも注意したい時期です。
さて、9月18日は「敬老の日」でした。
街中ではお孫さんを連れたおじいちゃんおばあちゃんの姿をいつもより多く見かけました。
院内保育園でも子どもたちが敬老のハガキ制作を行い、優しいおじいちゃんおばあちゃんを思いうかべながら、手形をとったり、楓や銀杏の葉を貼ったりしました。


子どもたちは「おじいちゃん?ばーばにあげるの?」と保育士に聞くなど、届けられる姿を想像しながら楽しそうに作っていました。
その後制作したハガキは祖父母の方々へ届けられ、喜ばれたそうです😊
また病院では当日入院中の患者さんへ行事食が提供されました。

敬老の日メニュー🍴🌰
・栗ご飯
・鶏竜田揚
・ツナサラダ
・塩もみキャベツ
・清汁
・巨峰
多年にわたり社会に尽くされてきた皆様のご長寿をお祝いします。
当院では入院中も患者さんに楽しく笑顔で過ごしていただけるよう
今後も季節を感じられる行事食の提供を行っていきたいと思います。
お祝い膳の嗜好調査について🍽
2023年09月15日
9月中旬に入りましたが異例の残暑が続いています。
今週末は連休の方も多いと思いますが、連休中も暑さは続く予報なので油断せずに暑さ対策を行いましょう!
当院の栄養管理室では定期的に病院食の嗜好調査について実施しています。
病院食について沢山のご意見をいただいておりますが、今日は産科の患者さんからいただいた、出産後に提供する「お祝い膳」に関する内容をご紹介します。



🔸2018年に第一子を出産したときにお世話になりましたが全体的においしくなっていて
びっくりしました!予算など制約があると思いますが愛と工夫を感じ励まされました。
🔸妊娠後期、お腹が重くなってきて辛かったときに、インスタでお祝い膳のことを知り、正直この日のためにがんばろうと思ったほどでした😊
🔸横浜医療センターで3回目の出産になります。
洋食か和食か選べるようになっていたのは今回が初めてで洋食を選んだ時から今日のお祝い膳がとても楽しみでした。ボリュームもとてもあり、味もとってもおいしかったです。
🔸七夕のカードやお祝い膳の箸袋など、食事以外の心遣いを感じられて嬉しかったです。カードも箸袋も大切にもちかえります。
🔸和牛ステーキ、久しぶりに食べたので、嬉しいメニューでした。
柔らかくてとても美味しかったです。
🔸デザートのケーキですが、戸塚のケーキ屋さんのケーキだったらもっと嬉しかったかも!!
栄養管理室では嗜好調査の内容を踏まえて、日々入院中の患者さんに喜んでいただけるよう改善に努めています。
また、当院の母子医療センターのInstagram(@yokohamahahako)では生まれて間もない赤ちゃんの写真や妊娠・出産に関する様々な情報を毎週更新していますので是非ご覧ください❣
ママと赤ちゃんが一緒に撮影できるスポットも設置しましたので、今後当院での出産を検討されている方は是非ご利用ください🤗

タウンニュース人物風土記に掲載されました!
2023年09月08日
秋の虫の声が聞こえる時季となりました。
いつの間にか日が暮れる時間も早くなり、暑い風から涼しい風に変わってきている気がします。

8月に当院の宇治原院長がタウンニュースの取材を受け人物風土記(戸塚区版)のコーナーに掲載されました。
記事はタウンニュースのウェブサイトに掲載されていますので、こちらからご覧ください。
院長は取材の中で、地域の医療機関と顔の見える連携づくりを目指すことでさらに信頼される病院にしていきたいとお話していました。
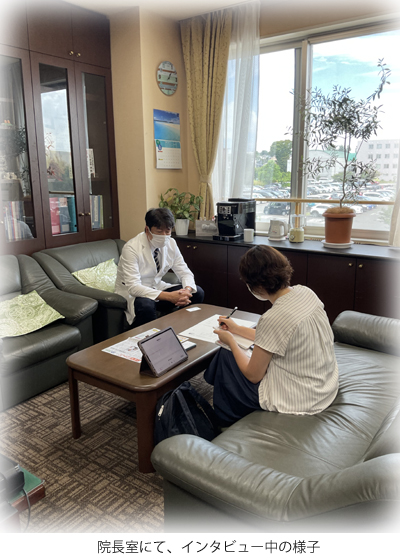
当院には地域医療連携室という部署があります。
地域医療連携とは、患者さんに身近な医療機関(かかりつけ医)と当院(高度・急性期医療を担う病院)が、症状に応じてそれぞれの役割を担いながら、連携して医療を提供するしくみです。
地域医療連携をしっかり行っていくためには、相互の関係性がとても大事です。
院長は、日頃から地域の医療機関へ地域医療連携室とともに訪問しています。
地域の医療機関の先生方と直接話し、顔の見える関係性を作ることで、安心して患者さんを任せられると思ってもらうことが大切です。
今後も患者さんの病状や生活に合わせて、適切な医療の提供が適切な医療機関からできるように地域で協力し合い取り組んでいきたいと思います。

防災の日
2023年09月01日
今日9月1日は防災の日です。
近年では、異常気象による水害や土砂災害などの気象災害が増えています。
この機会に皆さんのご家庭でも、災害の備えの見直しや災害対策についてご家族とお話されてはいかがでしょうか。
今日は当院の防災設備についての一部をご紹介します。
【非常電源装置】
駐車場の奥に囲いに覆われた建築物があります。
これは、生命維持装置や手術室の設備などが停電の発生時でも診療が中断することなく継続して診療が可能となるように、非常用自家発電装置を設置しているものです。
常時、3日間分の燃料備蓄設備も併設しています。

【備蓄倉庫】
病床数分の患者さんの3日間の非常食を備蓄しています。当院の病床数は490床ですので、1日3食の3日分というと、ものすごい量ですね。
当院での非常食は※ローリングストック法を取り入れ、賞味期限が切れる前に定期的に無駄がないよう消費し、その都度新しい非常食を補充し備えています。
※消費した分を買い足すことで常に新しい非常食を備蓄する方法
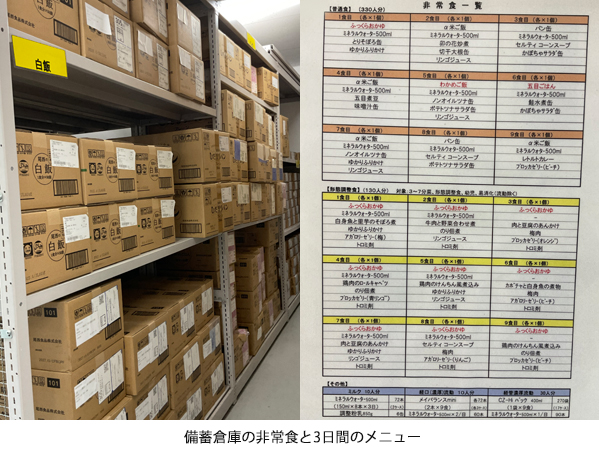
【免震装置】
平成22年の新病院建築時に免震装置を設置し、建物は免震構造となりました。
地震に見舞われても大きく被災しないよう、地下空間に約175個ある免震ゴムによって建物が支えられています。
大きな地震の際は出入り口にある境目が緩衝エリアとなり、足場が浮き上がることもありますのでご注意ください。
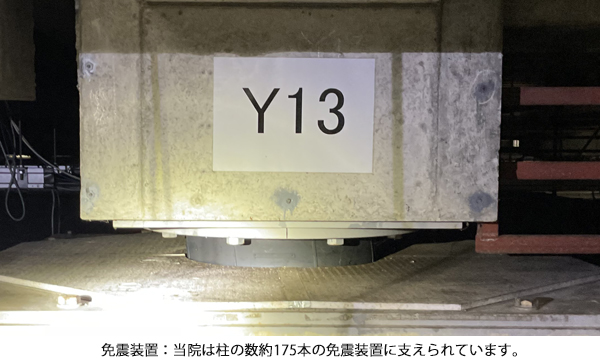
これらは災害時でも適切な医療を提供できるよう、災害拠点病院として指定されるための要件の一部であります。
また、当院にはDMATと呼ばれる災害派遣医療チームが救急医療担当副院長を中心に存在しています。
災害によって近隣の医療機関が機能できなくなった際でも専門的な訓練を受けたチームが現場対応できるようにしています。
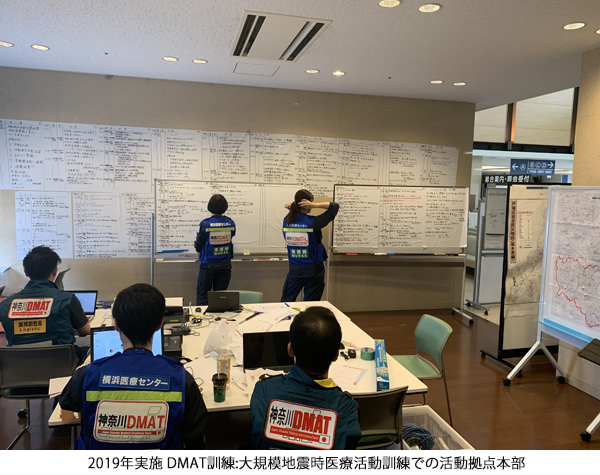
令和2年に発生した新型コロナウイルス感染症では、クルーズ船のダイヤモンド・プリンセス号にも当院のDMATが派遣され活動していました。
訓練活動にも積極的に携わっており、神奈川県の災害を想定した訓練では日本各地からDMAT隊員が当院に集まるといったこともありました。
今年の11月にも当院で訓練を実施する予定です。
東日本大震災の際には、地域が停電して暗い中、当院の照明が点灯しているのを見て地域住民の方から安心できたという声もあったそうです。
これからも日々の診療と共に、地域の皆さまにとって安心できる病院機能を維持できるよう役割を担っていきたいと思います。
熱中症にお気を付けください⚠
2023年08月25日
二十四節気では8/23から処暑の頃となり、秋に向かっているところです。
この時期は昔から台風がよく来ると言われているそうで、異常気象や突然の雷雨に注意したいです。


暦の上では秋に向かっているとはいえ、まだまだ暑さが続いています。
皆さんはしっかり水分補給できていますか?
昨年の9月の暑さ指数(日中)を調べると中旬までは厳重警戒の日が多く記録されていました。今年もしばらくは残暑が続きそうですので、引き続き熱中症対策が必要です。
当院に来られた際も、飲食等の制限がない方については待合の間にこまめに水分補給をするなど熱中症にならないように十分お気を付けください。
また、無理はできませんが暑さに負けない身体作りも大切です。
病院広報誌「はらじゅくかわら版」のリハビリ通信「ウォーキングで病気を予防しましょう」のコーナーではウォーキングのフォームや頻度の目安などを紹介していますので、ぜひご覧ください。
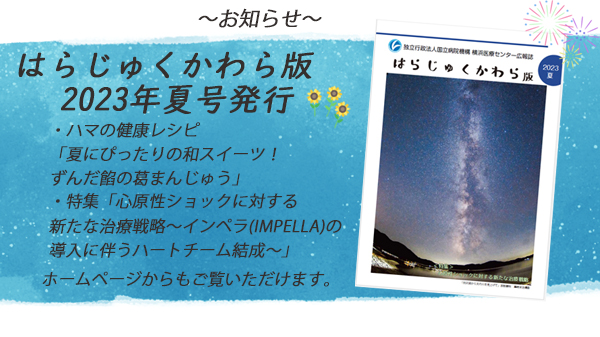
水分補給や暑さに負けない身体作り、服装で体温調節を行って、あと少しの夏を元気に乗り切りましょう!

高校生を対象に「一日看護体験」を実施しました🎀
2023年08月18日
台風が過ぎ、再び厳しい暑さになりました。
暦の上では秋となりましたが秋の涼しさまではまだまだ遠そうです。
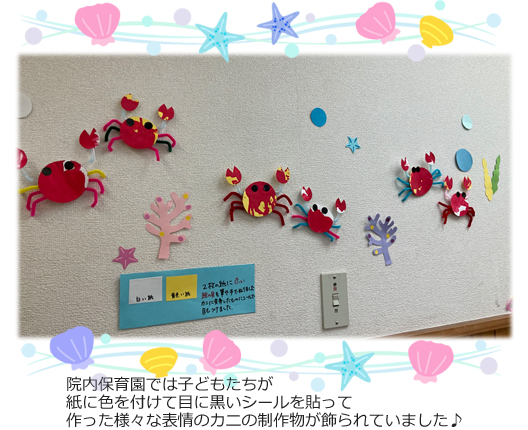
さて、今日は7月24日に行われた「一日看護体験」について報告したいと思います。
この体験には地域の高校から希望された9名の高校生が参加しました。
はじめに、院長、看護部長、事務部長から挨拶がありました。
「半日と短いがとにかく楽しんでもらいたい」、「職員たちがそれぞれの役割を担って運営しているということに気が付いてもらえると嬉しい」など話されました。

体験コーナーでは、「車いす乗車」、「血圧や酸素飽和度測定」、「小児のおむつ交換」、「一次救命処置」について各ブースに分かれて体験しました。
この企画の内容は、看護部の担当者が、高校生の皆さんと会うのを楽しみにいろいろと考えて準備しました。

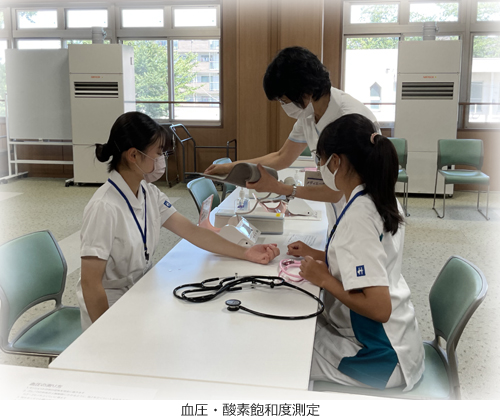


皆さん手際よく実施していたため、たまたま会場を通りかかった職員は、「高校生だとは思わなかった」と驚いていました。
体験を終えて、参加された高校生の皆さんから感想をいただきました。
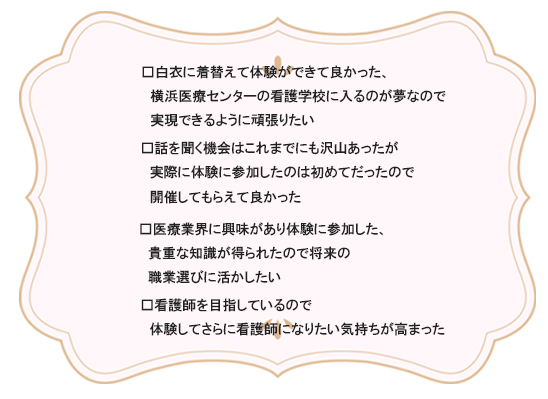
そして最後に看護部からプレゼントをお渡ししました。
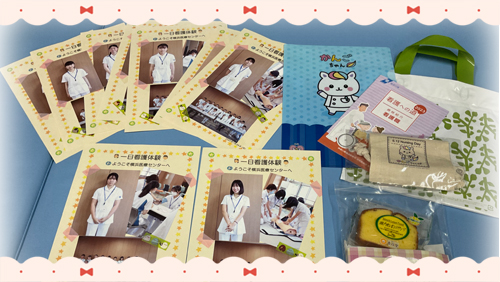
看護師を目指している方が多くいらっしゃったので、夢に近づくお手伝いや看護職に興味を持っていただくきっかけとなれたら嬉しいです😊
【チーム医療の活動紹介9-1】感染制御チーム(ICT)の活動
2023年08月04日
先週末の7/30(日)は土用の丑の日でした。
当院では当日に入院中の患者さんへ行事食を提供しました。
季節の変わり目を感じながら、暑い夏を乗り切っていただけると嬉しいです😊

今日は、感染症対策のために活動している多職種チームを紹介させていただきます。
コロナ禍で感染予防や感染症対策についての関心が高まりました。
「感染制御」に関する仕事は症状や病気を改善するための治療と異なり、感染を拡げないことを目的とするという特徴から地道で地味な仕事が多くを占めています。
華やかな印象ではないチームですが今日も院内感染撲滅のために邁進しています!

横浜医療センターには感染症対策を担う感染制御部が統括する二つのチームがあります。
『抗菌薬適正使用支援チーム(AST)』、『感染制御チーム(ICT)』です。
ASTは患者さんの病気に適切な抗菌薬が投与されているかを監視し適正な使用を促すチームです。
ICTは院内感染に関する実働部隊で病院中の環境を清潔に保ち、感染症を予防するための対策を講じて患者さんと職員を感染症から守れるように感染症に関する全般を一手に引き受けています。
感染制御部はAST、ICTを取りまとめる上部組織の役割をしています。
それぞれのチームは医師、看護師、薬剤師、検査技師、事務職という多職種で構成され、各々が力を発揮しています。
今回はICTラウンドについてご紹介いたします。
このラウンドは各部署が清潔に管理されているかをチェックするラウンドです。
チェックされる部署からは敬遠されがちですが…。
感染対策で大切な手洗いや手指消毒がしっかりできているかを確認しております。
病院にかかわるすべての方々を感染症から守るために心を込めて評価をしています。
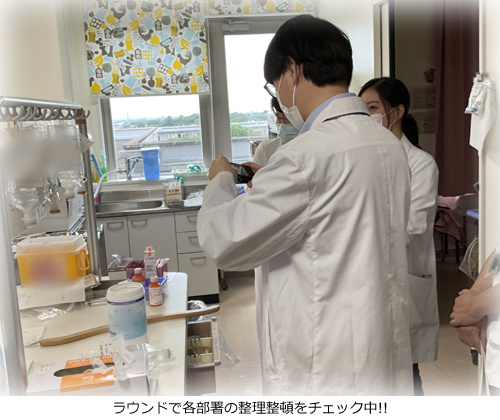
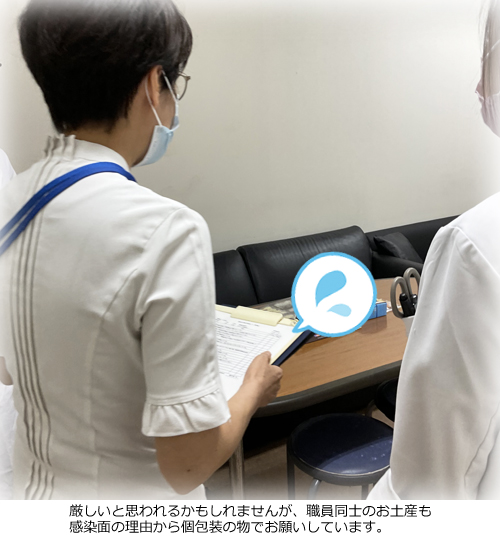
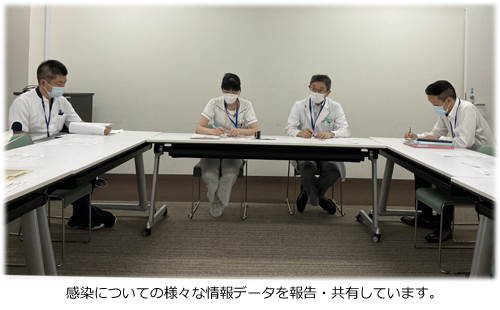
感染症対策の行き届いた病院で安心して診療を受けていただくために、今後も活動を続けて参ります。
こちらもご覧ください🎵
□YouTube すぐに役立つ感染対策教育動画
『手洗い編』
『N95マスク着脱編』
『アルコール手指消毒編』
『個人防護具着脱編』
□お知らせ
『専門・認定看護師出張講座』
新人看護師研修vol.3
2023年07月28日
梅雨もようやく明け夏本番ですね🌞
敷地内にはひまわりとコスモスが咲いていますが、ご覧になられた方はいますか?

さて、ブログで定期的にお伝えしている新人看護師研修について今回も皆さんにお伝えしたいと思います。
今回の研修は救急看護(BLS)です。BLSとは、「Basic Life Support」の略称で一次救命処置のことを言います。
休日や夜勤の際など看護師が少ない時に急変が起きた場合、焦らずに手順通り一次救命処置が実施できるようイメージトレーニングをしておくことが研修の目的です。
院内発生を想定に手順の説明を受けたあとに3人1組で一連の動作のシミュレーションを行いました。
慢性心不全看護認定看護師の講師からは、とにかくひたすら繰り返し練習しましょう!と指示があり、皆さん時間内に何度もシミュレーションを行いました。



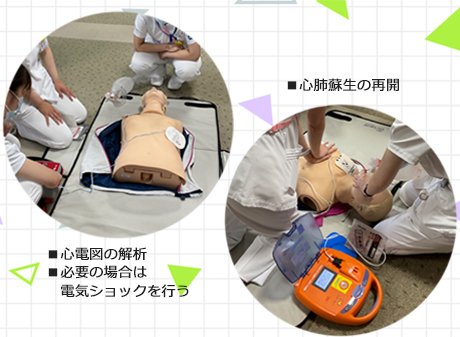
胸骨圧迫は質の高い圧迫ができるようにならなくてはいけません。
研修ではメトロノームの電子音が1分間に約100回のテンポでピッピッピッと鳴る中、そのテンポに合わせてひたすら圧迫を繰り返しますが、写真で見る以上にかなり体力勝負です💦
緊急時には、傷病者のご家族に蘇生処置中止希望の確認ができるまで、または、上司や医師が到着するまで胸骨圧迫を続ける必要があるので、一人で長い時間行うのはとても大変です。そのためチームで交代しながら圧迫を繰り返し、チームの重要性も認識できました。
終了後のアンケートでは、
「急変時の対応を頭では理解していても実際の経験がなかったので研修を行って応援要請やAED到着までの流れが実践できそうだと感じた」、「忘れないように振り返って実践できるようにしたい」、「難しいし疲れはたまるけど命をつなげるためにもっと自分を鍛えることが必要だと感じた」などの振り返りがありました。
今後も急変時に備え、慌てることなく命を救う行動に移せるように知識と技術の習得を目指して訓練していきたいと思います。

リフレッシュ研修を行いました❣
2023年07月21日
7月上旬に職員たちで敷地内の草刈りを行いました。
この暑さですでに青々とまた草が生えていましたが、草刈りの時には咲いていなかった花が咲いていました🌺

さて今日は、先日行われた既卒転勤者対象のリフレッシュ研修のお話です。
既卒転勤者とは看護学校を卒業している看護師経験者で別の病院施設などから転勤してきた方のことです。
すでに経験を積んでいることから、一般的に「経験者だからわかるよね。」と思われてしまうなど、本人と周囲の認識のズレから悩みを抱える看護師が多いようです。
特に当院は急性期病院なので緊急を要した患者の看護を行いながら、新しい職場に慣れるまで日々一生懸命です。
そこで今回、スタッフ想いの看護部長の企画でリフレッシュ研修が開催されました。

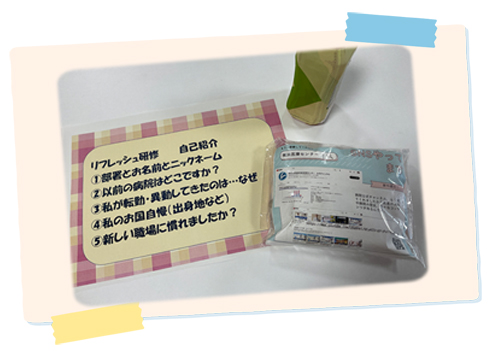
研修では、地方から転勤の看護師からの地域のおいしいものの話や、趣味の話、生活環境やキャリアプランについて、終始笑顔に包まれた和やかな雰囲気の中で盛り上がりました。
中には病棟スタッフ同士で仲良くツーリングに出かけたという話もあり、皆さん驚いていました。
今後も当院では看護師の働き方に合わせ、新人看護師に限らず、すべての看護師が成長できる環境づくりに努めていきたいと思います。

七夕🎐
2023年07月14日
厳しい暑さが続いていますね。
当院の正面玄関横にはご来院の患者さんに少しでも暑さをしのいでいただけるようにミストシャワーを設置しています。
屋外では2~3℃程度の冷却効果があるといわれており、暑い屋外でも空気がひんやりしていて涼むことができます。

さて、少し過ぎてしまいましたが、今日は当院で行われた七夕の様子をお伝えします。
7月7日まで、患者さんと職員が書いた願い事の短冊を外来ホールに飾りました。
世界平和や健康を願うものなど、たくさんの人々の願いが短冊に込められました。

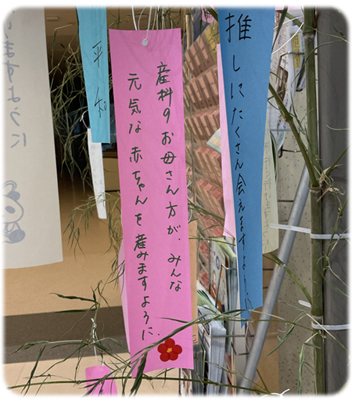
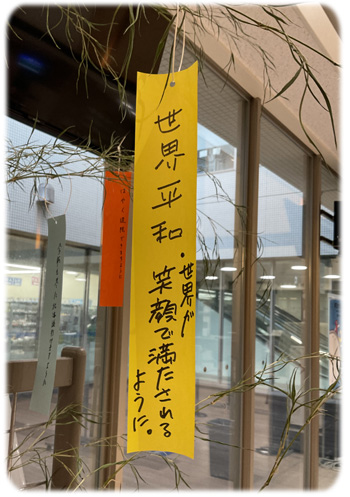
また入院中の患者さんには7/7の夕食に特別メニューを提供しました。

~メニュー~
・ちらしずし
・マグロのおろしソースがけ/オクラ添え
・冬瓜人参煮
・胡瓜昆布和え
・七夕デザート
・スイカ
入院中の患者さんやご家族の方々にとって思い出に残る夏の行事として楽しんでいただければ幸いです。
これから夏のイベントの時期です。
引き続き感染対策や熱中症対策をしながら夏を楽しみましょう🍧
【院内保育園】じゃがいも堀り2023
2023年07月07日
今週中頃、夕暮れ時に病院近辺でヒグラシの鳴き声が聞こえ始めました。
まだ梅雨明け前ですが連日の暑さもあり、夏がきたなぁと感じます。

さて、今日は院内保育園のお話です。
今年も、昨年に続き(昨年のブログはこちら)大正地区センターの畑で育ったじゃがいもを掘らせていただきました。
今年は女の子だけのじゃがいも掘りでしたが、隅から隅までくまなく掘って、泥んこになりながら、たくさん収穫できました。



収穫したじゃがいもで作った「はらぺこあおむし」のスタンプを押したり、小さいじゃがいもに絵具をつけてビー玉のように転がしたりして子どもたちが作成した素敵な絵を、感謝の気持ちを込めて大正地区センターの館長さんへお礼のメッセージと一緒にプレゼントしました。

普段できない体験ができて、子どもたちは大喜びでした。
また、小さな子どもたちのクラスにもお裾分けをして、各家庭でおいしくいただきました。

今日は七夕ですね。
園には保育士、子どもたち、保護者の願いごとが書かれた短冊が飾られています。

当院の七夕の様子は後日のブログでお知らせしたいと思います。
皆さんの願い事が叶いますように…✨
血液浄化センターが開設しました
2023年06月30日
今週は真夏日を思わせる蒸し暑い日が続きましたね。
今年は暑い期間が長くなると予想されていますので体調管理に気を付けて過ごしましょう。
さて、かねてより西2階病棟エリアの一部を改修、整備しておりました血液浄化センターがこの度竣工し、令和5年6月13日より新たにスタートいたしましたのでご紹介します。

当院ではこれまで血液透析等の治療は救急病棟の病室を利用して実施してきましたが、今回新たに血液浄化センターを開設することにより、救急病棟のすべてのベッドを救急患者さんのために活用することができるようになりました。

当院の血液浄化センターは入院患者さんの血液透析・血漿(けっしょう)交換などを行うためのお部屋となっており、窓が多くとても明るい環境です。
🔹血液透析…腎不全の患者さんに対して、機械(血液透析器)に血液を通し、血液中の老廃物や不要な水分を取り除き、血液をきれいにする治療です。
🔹血漿(けっしょう)交換…主に免疫の異常がある患者さんに対して、血液中に存在する病気の原因となる物質を除去するための治療です。血液中の血漿だけを交換するため、血漿交換と呼ばれます。

完成に伴い内覧会を開催し医師会の会長や近隣医療機関の先生方にお越しいただきお祝いのお花をいただきました。

内覧会では、宇治原院長、血液浄化センター長(腎臓内科部長)からのご挨拶や、横浜市立大学附属病院 田村主任教授のご挨拶、テープカット式が執り行われました。

今後も当院では、地域完結型医療の維持を目指し、診療能力を上げ続ける努力をしていきます。

病院食の衛生管理と家庭での食中毒予防について
2023年06月23日
今日は当院の栄養管理室長より食中毒予防についてのお話です。
食中毒は年間を通して発生していますが、梅雨から夏にかけて特に食中毒に注意したい季節となります。
当院の栄養管理室は管理栄養士10名と、調理師と調理員の6名の職員、委託職員の総勢51名で構成されており、毎回約300食の食事を提供しています。

当院では、HACCP(ハサップ)という世界で標準的に活用されている衛生管理の手法に基づき調理を行っています。HACCPとはアメリカのアポロ計画の中で宇宙食の安全性を確保するために発案された衛生管理の手法で、当院でも宇宙食の様に安全な食事提供を心掛け日々取り組んでいます。


気温が上がるこの季節、家庭で食中毒を予防するためには、「付けない」「増やさない」「やっつける」という3原則を守ることが大切です。
①「付けない」・・・お料理を作る時は、きちんと手を洗うことが大切です。また、お肉を切ったまな板をしっかり洗わず、続けて生で食べる野菜を切ったりする事で、お肉の菌が野菜に付着することになるため、切る順番を変えることで、菌の付着を防ぐことができます。
②「増やさない」・・・スーパー等で食材を購入後、寄り道をせず家に早く帰り、冷蔵庫や冷凍庫に入れ保管することで、菌の増殖を防ぐことができます。夏はかなり気温が上がるため、保冷剤や保冷バックの利用もお勧めです。冷蔵庫は10℃以下、冷凍庫は-15℃以下を保ち、冷蔵庫の詰め込み過ぎにも注意しましょう。
③「やっつける」・・・多くの細菌は、75℃以上で1分以上加熱することで死滅することができます。お肉は中心部までしっかり加熱することが大切です。火の通りにくい鶏肉やハンバーグは特に注意し十分に加熱しましょう。
また、夏に向けてバーベキューや焼き肉をする機会が増えますが、お肉の中心部までしっかり焼くことで細菌は死滅するので、よく焼くことを心掛けましょう。また、生肉を扱った菜箸やトングは、焼き上がったお肉やサラダを盛り付ける時に使用しないよう注意しましょう。
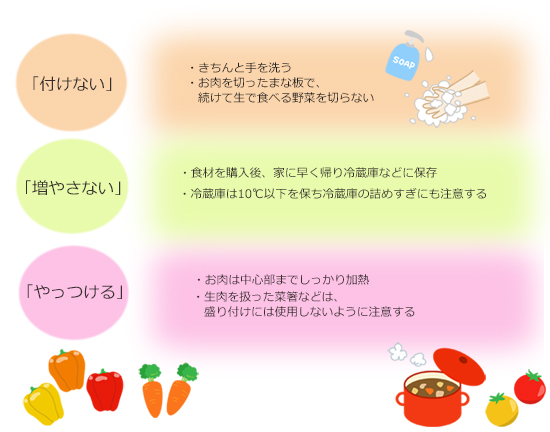

最後に、コロナ禍以降デリバリーやテイクアウトの利用が増えています。調理してから食べるまでの時間が長く、特に気温の高くなるこの季節は、食中毒が発生しやすいため、購入後は速やかに食べるようにしましょう。
夏は細菌性食中毒が増加する季節となります。普段以上に食品の取り扱いに注意しながら、バランスのよい食事を心掛け、暑い夏を乗り切りましょう。

新人看護師研修vol.2
2023年06月16日
曇りがちな梅雨の時期に、紫陽花が鮮やかに咲いていますね。
最近は夜も気温が下がらず、蒸し暑くなってきました。上手にエアコン等を使って室温管理をしたいですね。
さて、ブログ「新人看護師研修vol.1(2023年4月21日)」に続き、今回は「フィジカルイグザミネーション」について研修を行いました。
「フィジカルイグザミネーション」とは「視診・触診・打診・聴診」を用いて患者さんの状態を観察し、アセスメントすることです。
(アセスメント:情報収集し、分析を行って評価すること)
これは、「患者さんの観察を行うための知識と技術」として必要なので、早い段階で習得します。
集中ケア認定看護師が講師となり、視診・触診・打診・聴診の正しい手順と、意識レベルの評価方法について学びました。
視診・触診・打診・聴診は、正しい手順で行わないと正常なのか異常なのかわかりません。DVD等で正常と異常の見分け方を学びました。

意識レベルの評価方法は覚えにくいので、身体を使って覚え方の練習もしました。
例えば、意識レベルのうち、「発語」については、Vの1点(点数が少ないほど意識レベルが低い)=発語なし、というのを『シー』の指と1を連動して覚える、などを教わりました。
その他、症例から、患者さんの意識レベルはどのような状態なのかをみんなで考えました。
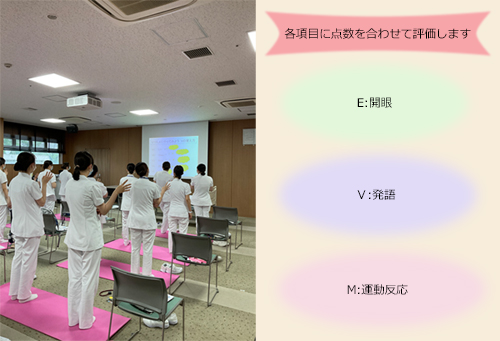
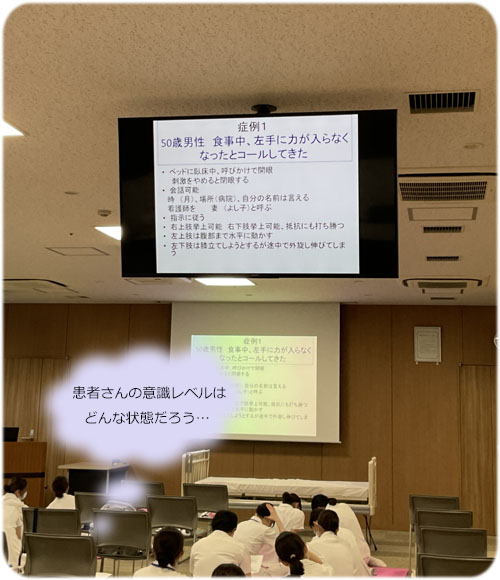
基礎的なことですがとても奥が深く、患者さんの異変を見逃さずに観察できるよう常にスキルを高めていく必要があります。
今後も定期的に看護や技術について研修を行い、新人看護師が一人前の看護師に成長できるよう努めていきたいと思います。

YMC YouTuber増殖中!(当院スタッフです。)
2023年06月09日
今週は梅雨入り前の貴重な晴れ間がありましたが、先週末に続き今朝も強い雨が降りました。
梅雨入りの発表もあり、ますます日々のお天気チェックが欠かせません。

さて、昨年開設し当院のブログでもたびたび紹介しているYouTubeチャンネルですが、5月は「耳鼻科に来ない耳鼻科の病気①(顔面神経麻痺)」を公開しました。
顔面神経麻痺は発症してからなるべく早く受診することが重要など、役に立つ情報が満載の動画ですので、是非こちらからご覧ください😊
当院のYouTuberは続々と増殖中で、現在は小児科の撮影を終え、近日中のUPに向けて編集中です。
6月は小児科の動画を2本UPする予定です。
病院情報や様々な診療科の動画コンテンツを随時更新しているので今後とも見にきていただけると嬉しいです🎵
チャンネル登録も👍よろしくお願いします!!

Instagram(母子医療センター)もやってます♡
※YMCとは…Yokohama Medical Centerの略です。
NICU看護師インタビュー ~看護の日のイベント②~
2023年06月02日
今週はスッキリしないお天気の日が続きました。
一日の中でも気温差が大きい日もあり、なんとなく身体が疲れやすい時期です💦
自分に合わせた体調管理をして、元気に乗り切りたいですね。
さて、先週に続き、今回は小児・NICU病棟からNICU担当の新人看護師にインタビューを行いました。

🔸NICU(新生児集中治療管理室)はどんな雰囲気の部署ですか?
NICUでは赤ちゃんやお母さんたちへの身体や心を気遣う優しい声かけで常にあたたかさに溢れています。
🔸小さな赤ちゃんが患者ということで、コミュニケーションをとるのが大変かと思いますが工夫されていること何でしょうか。
NICUにいる生まれたばかりの小さな赤ちゃんの表情や身振りはコロコロ変わり、身体全体で気持ちを表現しているので、赤ちゃんがどう感じているのかのサインを見逃さないように気を付けています。
🔸特別な小児用ベッドや医療器具があるようですが、それらについて教えてください。
小さく生まれた赤ちゃんには体温や酸素の管理が重要なので赤ちゃんの身体の機能に合わせたベッド(クベース・コット)があります。
また、黄疸の光線療法に使用するベッドや様々な種類の呼吸器もたくさんあります。
🔸NICUに入院されている小さな赤ちゃんの看護面で特に気をつけていることはどんなことですか。
赤ちゃんは急な状態の変化が起こる可能性があるのでベッドのアラームが鳴ったらすぐにスタッフが赤ちゃんの元に駆けつけ見守っています。
🔸赤ちゃんが元気に退院できるのが楽しみですね。
NICUから退院する赤ちゃんは生まれて初めて家族の待つおうちへ帰ることができます。
家族の元に無事に帰れるように、日々小さな命を大切にしています。

年に一度の「看護の日」、今回はデジタルサイネージを通じて、患者さんや、ご家族に看護活動を知っていただく機会をつくることができました。また、職員もそれぞれの活動を把握することができました。
今後もみなさんへ看護の心を知っていただく機会をつくり、スタッフも日々の看護の大切さを再確認して患者さんと関わっていきたいと思います。
手術室看護師インタビュー ~看護の日のイベント①~
2023年05月26日
これから梅雨の時期ですが強い日差しの日が続いていますね。
当院敷地内の木々たちもこの日差しで少し前より緑が増えました。
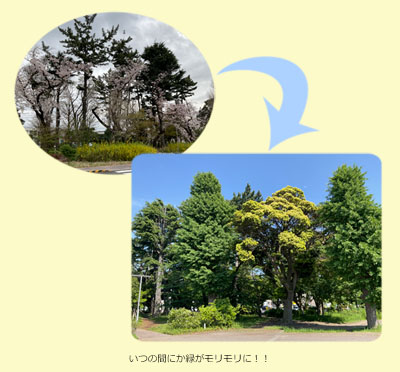
さて、5月12日は看護の日でした。近代看護を築いたフローレンス・ナイチンゲールの誕生日にちなんで国際看護師協会が定めています。
当院では5/10~5/16まで通院中の患者さんとそのご家族を対象に外来ロビーや外来待合等で、デジタルサイネージにて【看護活動の紹介】を掲示しました。
このたび、紹介された様々な看護活動の中から、『手術室』、『小児・NICU病棟』の看護師にインタビューを行いました。
今回は『手術室』の看護師3名に行ったインタビューブログです。

🔸ポスターにエキスパートナースが多数とありますがどんな専門的な看護師が所属されているのでしょうか。
手術看護認定看護師、特定行為看護師が所属しています。その他にも、中国語が話せる看護師が中国語のエキスパートナースとして活躍しています。手術を受けるのは誰でも不安ですし、違う国で手術を受けるなら尚更です。中国語のエキスパートナースが関わることで、「あなたがいて良かった」と喜ばれることがあります。

🔸看護師には、病棟看護師や手術看護師などに分かれているようですが、ポスターにあった手術看護師について教えてください。
病棟で勤務する看護師は日々の看護の関わりの中で信頼関係を築いていくと思いますが、手術看護師は、手術前訪問、手術中、そして手術後訪問という短い時間の中で信頼関係を築きます。
不安を感じる患者さんが多く、少しでも不安を軽減できるように関わりを持つことを心がけています。また、器械出し(手術室内で医師の近くに立ちメスなど手術で使用する器具を渡す役割)業務を行うためには、手術器具の名称を覚える必要があり、手術に関わる専門知識や技術も必要となります。さらに、当院の手術室では全科を受け持つので、様々な科の病態や手術手技についてのスキルも必要となります。
🔸一番やりがいを感じる時はどんな時ですか。
手術後の回復に向かう過程が見えた時です。
手術の現場に立ち会い、術後訪問で患者さんにお会いし、回復されている姿を見るとやりがいを感じます。また、手術後、患者さんから「あなたのおかげで安心して手術室に入れた」と言われた時、手術前の環境づくりや患者さんとの関わり方が間違っていなかったと気付き、やりがいが感じられます。
あと、手術は患者さんが起きている状態で行う手術もあるのですが、その際、手術看護師は、患者さんの不安を軽減するため、声掛けや手を握ったりすることがあります。手術後、その患者さんから「あなたがいてくれて安心できた」と話してもらえた時は嬉しかったです。
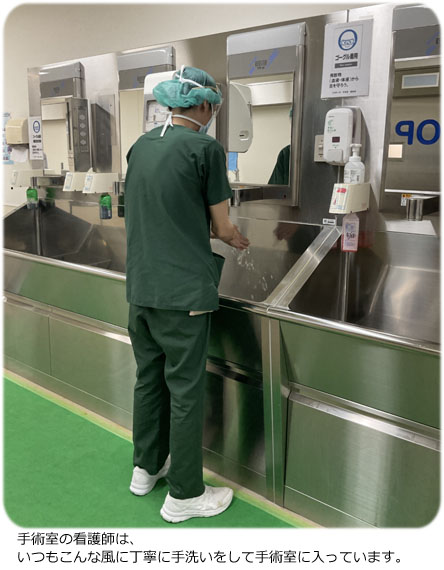
次回は『小児・NICU病棟』の看護師にお話を伺います!
是非ご覧ください😊
新院長密着レポート!
2023年05月19日
4月より新院長が就任して早1か月が過ぎました。
副院長時代とは違った大変さがあり日々診療・経営・幹部など様々な職種の方々との会議や、他院への出張で忙しくされています。
その中で少しだけ院長に密着してみましたので院長の1日をご紹介したいと思います!

<院長の1日🌼>
| 8:00 | 出勤、メールチェック📩 |
| 8:30~9:00 | 会議📑 |

| 10:00~11:00 | 資料作成など |
| 12:00 | ランチ🍙(おにぎり1個&ささみサラダ)おやつタイムがあるので控えめに… |
| 13:00 | 行事など🎈 今回は看護学校の防災訓練がありました。 |

| 15:00 | 来客応対や幹部との面談が多いそうです。 今回は戸塚消防署長と面談がありました。 合間にコーヒ-&おやつタイム☕ |


| 16:00~ | 会議📑 |
| 17:15 | お疲れ様でした! |

<読者の方へメッセージ>
ご覧いただきありがとうございます。
これから私は3つのポリシーを持って院長を務めてまいりたいと思います。
1.提供する医療の質の向上をはかります
2.働いてよかったと思える病院にします
3.職員の成長を支援します
どうぞよろしくお願いいたします。
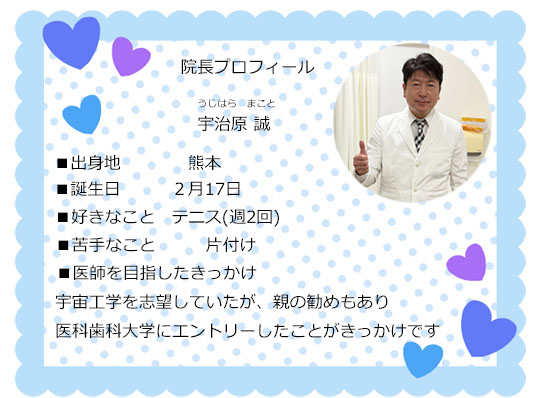
こどもの日🌈
2023年05月12日
新緑がまぶしい季節となりました。
5月に入り、今回が最初のブログです。
5月5日は「こどもの日」がありましたね。
今年も小児科病棟ではスタッフが壁面にこいのぼりなどの可愛い飾り付けをしてくれました。

入院中の患者さんには特別メニューを提供しました。
春らしいメニューでこどもの日の雰囲気を楽しんでいただいたようです。

~メニュー~
たけのこごはん
鶏木の芽焼き
付け合わせ(ベジタブルソテー)
田楽(里芋・こんにゃく)
白菜と人参の生姜和え
こいボーロ
甘夏柑
1階外来ホールの壁面時計前では子どもたちがプロジェクションマッピングの映像が映るのを楽しんで見て待っている姿も見られます。

また、こどもの日は院内保育園でもとても大切な行事です。
子どもたちがこいのぼり制作をして楽しみました。

子どもたちの健やかな成長を祈りながら、今後も当院ではお子さんが安心して受診できる環境づくりに努めていきたいと思います😊
薬剤師がブログインタビューに答えてみた!
2023年04月28日
こんにちは。大型連休が目前に迫っていますね。
今年はコロナ対策が緩和され、観光地では多くの人出が見込まれるようです。
みなさんのご予定はいかがでしょうか。
さて、当院の広報誌「はらじゅくかわら版春号」が来週完成する予定です。
かわら版に部署紹介として掲載されているのが、「薬剤部」なのですが、かわら版の完成に先駆けて薬剤部職員にインタビューを行いましたので、ブログに掲載します!
🔹インタビューよろしくお願いします。
かわら版に続いて、ブログでも取り上げていただきまして、ありがとうございます。
セルフメディアミックス状態ですね。かわら版にも書いていますが、あまり表舞台に出ることがないので、皆さんに知ってもらう機会をいただいてありがたく思います。
🔹当院の薬剤部の特色について教えてください。
横浜医療センターの薬剤部は26人の薬剤師で稼働していますが、仕事と家庭を両立している薬剤師が「いと多し」・・・そして「強し」・・・、いや、「頼もし」です。
🔹薬剤師はどんな性格の方が向いていると思われますか?
薬剤師に求められる役割が時代ごとに変わってきているので、向いている性格も変わってきたと思います。そんな中でも周りにどんな方が多かったかというと「マジメ」な方かなぁ。
「カタイ」方もいます。(悪口に聞こえたらごめんなさい💦)
ちなみに私はどちらにも当てはまらない「希少生物」のようです(笑)。
もっとも、薬剤師が働く職場は、病院以外にもいろいろなところがあるので、どの性格でもハマるところはあると思いますよ。

🔹薬剤師の業務で大変なことはなんですか?
実は体力勝負だということです。薬のイメージというと、錠剤とかカプセルとか湿布とかだと思いますけど、点滴・・・あれ液体ですからね。20本とか入った段ボールを運ぶ機会もたくさんあるのですよ。
あと、薬の名前はカタカナばかりで、増える一方なので、覚えるのが大変です。薬剤師だって、これには苦労しています。でも、だからといって漢方薬みたいに読めない漢字が並んだような薬が多くても、またそれはそれで困るのですが😅
🔹薬剤師を目指す方へメッセージをお願いします!
もし、薬剤師を目指している方がこの記事を見ていたら、2つ、伝えたいことがあります。
1つ目は「体力重要!マジ重要!」
2つ目は「勉強頑張れ!超頑張れ!」

普段見えないところにいる薬剤師ですが、高い専門知識と体力が必要な職種!ということがとてもよく分かりました。
また、進化していく医薬品に向上心を持って知識を磨き続けていることもわかりました。
当院では薬剤部を中心に、今後も安全に、そして適切に患者さんの元に薬がお届けできるように努めてまいります。

新人看護師研修vol.1
2023年04月21日
今週半ばは気温が上がって夏日のようでしたね。
当院の事務部でも扇風機をまわしたり、うちわであおいだりする職員の姿を見かけました。
だんだんと夏が近づいてきているなぁと感じます🌈
さて、当院の新人看護師が受講する「新人看護師研修」がスタートしました!
この研修は、新人教育プログラムとして毎月1回(8月を除く)開催されます。
今回の研修は皮膚・排泄ケア認定看護師が講師となり褥瘡(床ずれ)予防のための看護を体験しながら学びました。
研修では新人看護師が4つのブースに分かれ、体位変換や、オムツ装着、体圧分散マットレス、車いす用の除圧について、説明を受けながら実施しました。

寝返りをすることができなかったり、好きなように動くことができない患者さんは床ずれの原因になりやすいです。
そのため、これらの看護は予防や苦痛の緩和を図るためにとても大切です。

マットレスは同じように見えますが全て異なる素材のマットレスなので、どのような違いがあるのか皆さんで寝心地を確かめていました。
厚みや機能、寝心地など、様々な違いがあるようです。

また、車いす用の除圧クッションもあり、実際に圧がかかっていないかモニターで確認を行いました。

今後もさらにプログラム内容を充実させ、急性期病院で必要となる知識や技術の教育を行っていきます。
ブログでも新人看護師の成長を見守っていきたいと思います😊
ようこそ横浜医療センターへ
2023年04月14日
4月も中旬となり、気温の高い日が続いていますね。
先日、鈴木前院長が記念植樹を行った八重桜がきれいな花を咲かせました🌸

春は風が強く吹く季節でもあり、今週は中国大陸からの黄砂の飛来がニュースとなっています。
人によってはアレルギー症状や呼吸器疾患、循環器疾患を引き起こすこともありますので、マスク等での対策が必要ですね。
さて当院では今年度も新採用職員を迎えました。
4月3日に辞令交付式を行い、4月6日までオリエンテーションを行いました。
オリエンテーションのひとつ、「横浜医療センターの紹介」では、講義の3時間前に辞令を受け取り、新院長となった宇治原院長から当院の理念や診療機能、教育・研修についてお話がありました。冒頭で「院長ホヤホヤです。」と自己紹介のご挨拶があり、皆さんの緊張が和んでいました。
その後も、当院のさまざまな業務について講義形式でオリエンテーションが行われ、新採用職員の皆さんは熱心に聴いていました。
講義形式のほか、体験形式でも様々な研修を行いましたので、そちらの様子も写真でご紹介します。

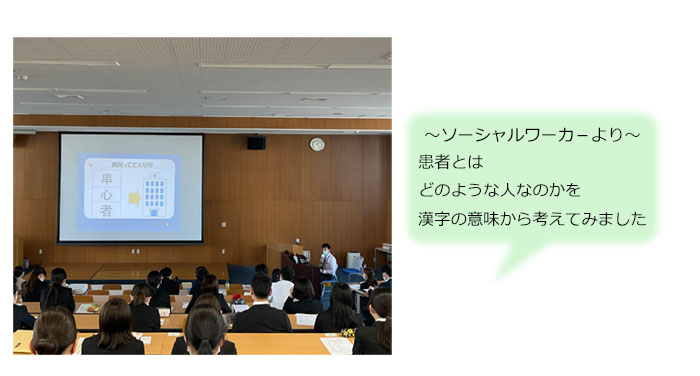

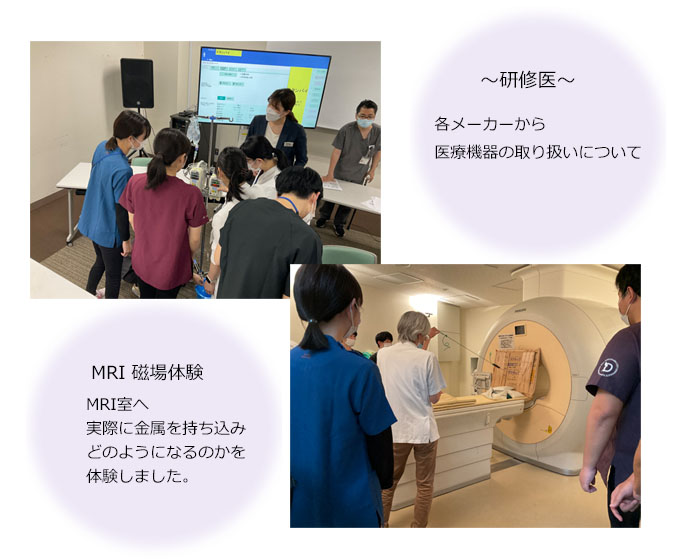
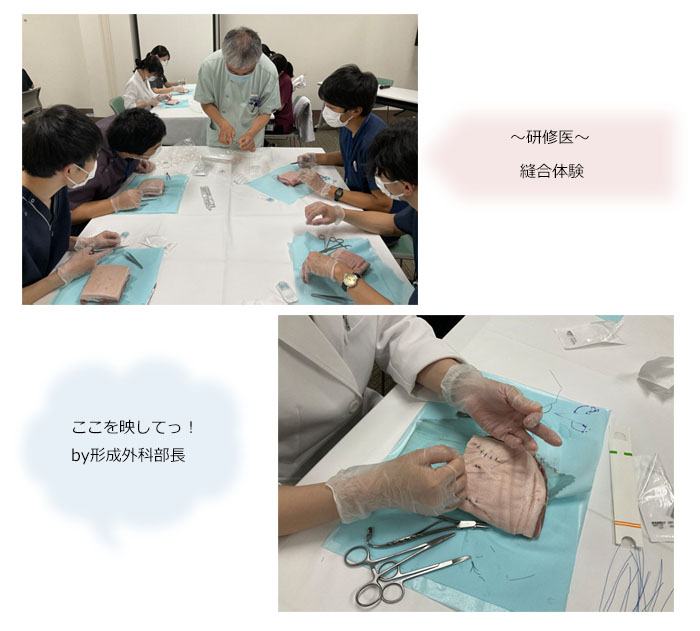
当初は不安な様子の新採用職員でしたが、少しずつ緊張も解けてきたように思います。
今の気持ちを忘れずそれぞれの部署で羽ばたいて欲しいです!
【チーム医療の活動紹介8-1】心不全ケアチームの活動~病気と共に生きていくために~
2023年04月07日
4月に入り、新入学や新入職員の皆さんの姿を見かけました。
早咲きの桜もまだ花が残り、あらたな1年の始まりに彩を添えていました。
私たちも気持ちが引き締まる思いです。

さて、新年度は「チーム医療の活動紹介」ブログでスタートします。
8回目となる今回は心不全ケアチームについてご紹介します。
心不全とは、心臓が悪いために息切れやむくみが起こり、良くなったり悪くなったりを繰り返して命を縮める病気です。
心不全のポイントは、完全に治る病気では無いことです。
生活習慣の乱れやお薬の飲み忘れ等が原因で、再び症状が出てきてしまうことがあります。
しかし、突然「あなたは心不全なので、生活習慣を改善しましょう。」と説明を受けても今までの生活リズムを変えることは簡単ではありません。
そのため当院では、患者さんが病気と折り合いをつけて生活していくために、医師、慢性心不全看護認定看護師、心不全療養指導士、薬剤師、栄養士、理学療法士、ソーシャルワーカー、退院調整看護師からなる「心不全ケアチーム」が、患者さんへの生活習慣改善のための教育や栄養指導、心臓に負担がかからない程度の運動の提案、ヘルパーや訪問看護などの社会資源の活用の提案などを行っています。
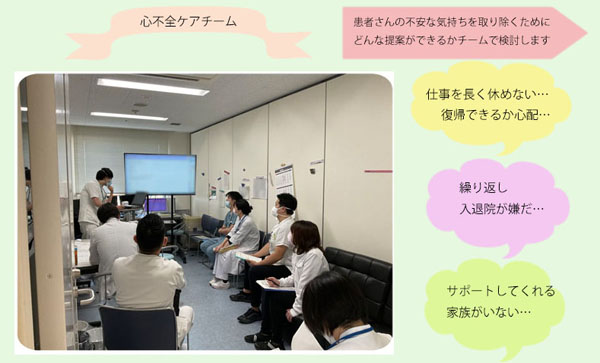
心不全というとあまり馴染みの無い病気と思われがちですが、実は、高血圧や糖尿病等の生活習慣病も心不全の予備軍になります。
息切れやむくみを自覚したら、心不全の可能性があります。
ご不安なことがありましたら、まずはかかりつけ医にご相談下さい。
今後も随時、チーム医療のご紹介をしていきます。
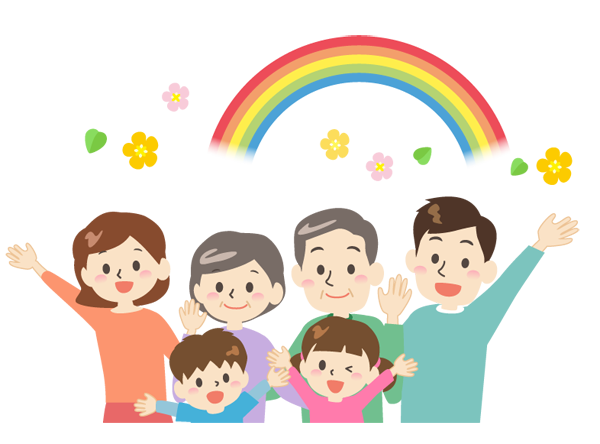
ご定年おめでとうございます🎉
2023年03月31日
桜のシーズンの時期ですが、皆さんご覧になりましたか?
先週末、当院敷地内の桜も見ごろを迎えました。
雨の影響が心配されていましたが、今年もきれいに咲きました🌸
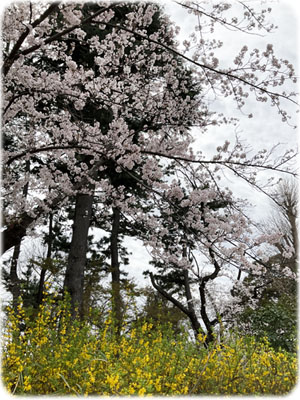

さて、今年度もいよいよ終わりですね。
本日、定年を迎える職員への辞令交付式が行なわれました。
長きにわたって、当院の診療や地域医療に貢献してきた職員7名に対して、院長から感謝の意をお伝えしました。
人生の節目を迎え、晴れ晴れとした表情で式に参加されていました。
皆さん本当にありがとうございました。そしてお疲れさまでした!
ご定年される職員のうち、小松臨床研究部長(消化器内科部長)からコメントを頂きました。
「このたび3月31日をもちまして横浜医療センターを定年退職となります。
東京女子医大消化器内科より、昭和63年6月、国立横浜病院消化器科医員として出向となり、その後約35年間、大過なく勤めさせていただけたのは、職員や医師会の皆様方の御指導による賜物です。深く感謝しております。
4月からは縁がありまして、近隣の「わかば医院」の院長として、勤務させていただくことになりました。これまでの病院勤務医とは違った立場で、微力ながら地域医療に貢献させていただければと思っております。今後ともよろしくお願いいたします。」

※なお、鈴木院長も定年退職となります。院長メッセージはこちら🌸

看護師と看護助手が一緒に取り組んでいます🌼
2023年03月24日
今週は暖かい日が続いていますが、週末にかけて天気は下り坂ですね。
晴れた日に敷地内を歩いてみるときれいに花が咲いていました。
他にもいろいろな草花が植えられているのでまたご紹介していきたいと思います😊

これまで当院では各病棟・部門に看護助手を配置し、看護師が担ってきた仕事を移譲し、「協働」して、それぞれの役割に特化したケアを行い、看護の質の向上に取り組んできました。
例えば、認知症やせん妄などの患者さんに対して、看護助手が定期的に散歩に付き添ったり、会話相手となることで、認知症状や不眠が改善したり、患者さんが活き活きとして、明るい表情が見られるようになりました。
適切なタスクシェアにより、看護師は医療的ケアに専念することができ、看護助手も患者さんから頼りにされ、その回復を見守ることで、やりがいを感じながら仕事に臨むことができます。
これまで当ブログで取り上げたように、当院では看護助手のスキルアップ研修を定期的に実施しているほか、事例発表会を行って各部門の好事例の共有を行うなど、協働の取組を一層充実させています。院内表彰制度でもこの取組が認められ、院長賞・優秀賞を受賞しました。
これからも、安心・安全な看護を提供するためにできることは何かを考えて、日々患者さんとの関わりを大切にしていきたいと思います。

静脈注射実務看護師研修と1年間の振り返り
2023年03月17日
各地で続々と桜が開花しているようです🌸
当院敷地内の桜の開花も楽しみです😊
さて、このブログでは看護師1年目研修について何度かご紹介してきましたが、研修プログラムも終わりを迎える頃となりました。
今回の研修では、静脈注射について講義・テストを受けたあと、演習用の腕モデルを使用して実技テストを行いました。

患者さんの身体に針を刺して薬液を入れる重要な行為なのでみな真剣です。研修後は、各部署で先輩に指導を受けながら実践経験を積み、静脈注射ができる看護師として院内で認定されます。
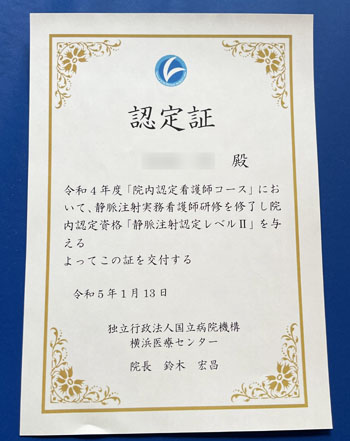
研修最後のプログラムでは、1年間の振り返りを行い、「その人らしさを支える看護とは」いうテーマでレポート発表を行いました。
それぞれが病棟で学んだ経験を皆で聞くことで「毎日成人を看護しているので小児科病棟の話が聞けて新鮮だった」、「同期同士で学んだことを共有できてよかった」などの感想や気付きが得られ、次年度の課題や目標を見つけることができました。
皆さん、2年目もがんばってくださいね🤗

テレビドラマに撮影協力しました!
2023年03月08日
こんにちは🌼
3月に入りグッと春めいてきました。
足元にはつくしやタンポポが見られるようになりました。
花粉さえなければ・・・と言う方も多いかもしれません。
さて、当院では1月からスタートしたTBSドラマ「100万回言えばよかった」(以下、「100よか」)に撮影協力をしていました。ご覧になった方からの反響が大きく、驚いています。
12月に当院で初めての撮影があり、つい先日まで土日を利用して複数回撮影をしていたのです。
主人公の悠依(井上真央さん)を事故に遭う寸前に助けたのが、医師の夏英(シムウンギョンさん)。
夏英の勤務先である大学病院が当院です。オリジナル脚本によるファンタジーラブストーリーで、詳しい内容はこちらで見ることができます。
今日は撮影の裏側をご紹介します。
早朝から正面玄関にたくさんの人。「え?何事?」と思い急いで院内に入ると、早めに到着していたエキストラの皆さんでした。それ以上にスタッフの人数の多さに、思わず「うわぁ」と声が出てしまうくらい驚きました。用意した控室に案内すると、てきぱきと支度が始まります。

衣装、ヘアメイク、撮影現場の設営、カメラマン、演出、監督など本当にたくさんの方々により、着々と「100よか」の世界が作られていきます。
日常との違和感がないように、細かい部分の作りこみもあります。張り紙やチラシなど「これもセットだったの?」と思ってしまうほどです。

2つ以上のシーンを撮影するときは、1つ目のシーンを撮影している間に次のシーンの設営をして、すぐに移動。スムーズに撮影ができるように準備されていました。
カメラテスト後に「じゃ、本番いきます!」「はい、本番!」の声が掛かると、その場の空気がキュッと引き締まります。

撮影は会議室や職員スペースの廊下、食堂、ロビー、診察室などさまざまな場所で行われました。最初は入り口から控室までの移動で迷子になるスタッフの方が続出していましたが、回を重ねるにつれ「いつもの場所ですね」と案内がいらないほど慣れていただきました。
そして、撤収がものすごく早いです。使わなくなった機材から順に台車などに積み込み、それぞれの役割をこなしてあっと言う間に片付いてしまいます。いつも最後まで残って現状復帰をする方もいます。

撮影を見ていて思ったのですが、演技をする俳優さんはもちろんのこと、それを支えるスタッフの皆さんのチーム力が素晴らしかったです。医療の世界も同じで、患者さんとその治療を行う医師、看護師やコメディカルでのチーム医療を行っています。職種が違っていても、チームで目指すゴールがあることは同じだなと感じます。
「100よか」はTBS系列で、毎週金曜日の22時から放送されています。先週第8話が放送され、いよいよストーリーもクライマックスに向かっています。ファンタジーラブストーリーですが謎も多く、どんどん惹き込まれていきます。
実力派の俳優陣が演じるそれぞれの役柄が本当にピッタリで、色々なドキドキを感じることができるドラマです。HPやSNSではこれまでのダイジェスト版を見ることもできますので、ぜひご覧ください✨
脳神経内科の動画「パーキンソン病について」を配信中!
2023年03月03日
3月がスタートしました!
気温も徐々に高くなり、春の気配が感じられます。
そして、今日は雛祭りですね🌸
今年も当院では外来ホールに雛人形を飾りました。
皆さんもそれぞれのご家庭で雛祭りを楽しんでみてください。

さて、当院の公式YouTubeチャンネルでは、先日ご紹介した脳神経外科に続き、第二弾として脳神経内科の動画「パーキンソン病について」を配信しました❗
「パーキンソン病」はボクシングのモハメッド・アリさん、映画俳優のマイケル・J・フォックスさんなど有名人が罹患したことで、聞いたことがある方も多いと思われますが、どんな病気かご存知ですか?
パーキンソン病は指定難病のひとつで、高齢者に多く、「手足が震える」「筋肉がこわばる」などの運動障害が起きる脳の病気です。
こうした症状を高齢のせいだからと思って受診をされていない方もいるようです。
動画では、具体的な症状から治療の方法まで、脳神経内科部長の上木(じょうき)医師が分かりやすく解説しておりますので、是非ご覧ください。
上木医師の素敵な笑顔の「いいね!」も見ることができますよ😊

当院の広報活動が表彰されました🎊
2023年02月24日
暦の上では雨水の時期となり、厳しい寒さが和らぎ始める頃ですね。
週末にあたたかな南風が吹いたと思えば、また北風に変わり気温の変化が著しいです。
春が待ち遠しいですね😊
さて、当院を含めて140の病院が所属する「独立行政法人国立病院機構」では、各現場で業務課題の解決に取り組む活動を「QC活動」と呼んでおり、グループ内の改善事例の共有を目的として、年に1回、事例募集・表彰を行っています。
このたび当院の広報活動の取組が「優秀賞(全国2位!)」として表彰されました。

昨年度このブログや登録医メールマガジン、プレスリリースの充実に取り組み、今年度からは体制を強化して広報誌のリニューアル、YouTubeやInstagramの開設など、一層の情報発信に取り組んでいることが評価されました。
地域の皆さん(今、このブログを読んで頂いているあなたも)に、当院のことをもっと知って頂き、地域から信頼される病院になれるよう、今後も広報活動を行っていきたいと思います。
YouTubeやInstagramは随時コンテンツの更新を行っていますので、ぜひご覧ください✨

放射線科の誘導サインをわかりやすくしました
2023年02月17日
先週末から寒暖差が激しいですね。
ほころび始めた梅の花も、心なしか寒そうに見えます。
放射線科では、紹介患者さん等のCT、MRI、RI検査や放射線治療を行なっています。
放射線受付で受付を済ませて、検査室前でお待ち頂くのですが、検査室までの順路で本来は曲がっていただくところを、真っ直ぐ進んでしまう人が多く、患者さんが迷ってしまうことがありました(イラストの赤で囲った場所です)。
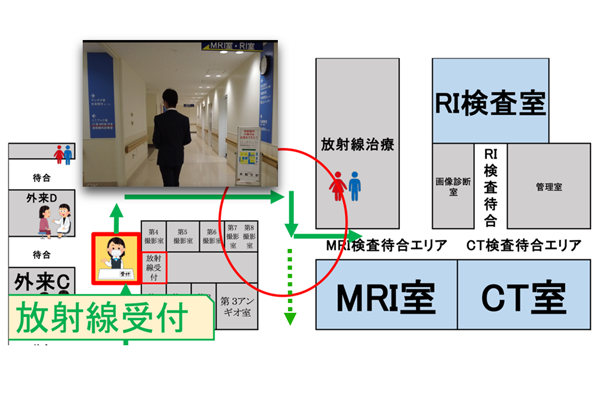
そこで今回、患者さんが迷わずに検査室までお越しいただけるよう、誘導サインを見直しました。

当院の誘導サインは、ブルーを基調として白文字で統一されていますので、このイメージを崩さないようにしつつ、各検査室を色で判別できるようなデザインに変更しました。
CTはオレンジ、MRIはグリーン、RIはピンク、放射線治療はブルーで表記されています。
この変更の後は、真っ直ぐに進む人もかなり減っている印象です。
これからも、患者さんにとって優しい病院になれるよう、こうした改善に取り組んでいきます。

こちらの案内動画もご覧ください😊
第29回クリティカルパス大会を開催しました🏆
2023年02月10日
本日はみぞれ混じりの冷たい雨が降っています。
このあと雪となるようですが、昨年のように積もるのでしょうか、心配です。
春の訪れまでもう少し時間がかかりそうです。
さて、1月30日に(先月末に)クリティカルパス大会を開催しました。
コロナ禍でしばらくはポスター掲示方式による発表でしたが、3年ぶりの会場発表で大変盛り上がりました。
「クリティカルパス」とは、医療スタッフと患者さんが治療の情報を共有するために作成する、「入院中の予定をスケジュール表のようにまとめた診療計画書」のことです。
入院すると、手術や検査はどのようなスケジュールで行うのか、退院はいつできるのかと不安に思うことがたくさんあります。
医療従事者が予定を把握するのはもちろんですが、患者さんご自身で予定を把握することは、安心して治療や入院生活を送るために重要です。
そのため、当院では各病棟や部門が、クリティカルパスを新たに作成したり、より良くなるよう見直すなどの改善活動を行っており、年に1回、クリティカルパス大会でその成果を発表しています。


今回の発表での最優秀賞は、東6病棟の「コイル塞栓術、ステント留置術のDPCに合わせたパス日数短縮について」でした。
患者さんから術後の絶対安静が辛かったという訴えが多く聞かれていた手術ですが、今回クリティカルパスの改善を行った結果、患者さんが術後すぐに寝返りを打つことや起き上がることができるようになり入院期間の短縮につながったことが評価されました。
今後もこうした医療の質を上げるための取り組みを続けてまいります。

プラチナナースから新人看護師へメッセージ
2023年02月03日
今日は節分ですね。暦の上では明日が立春で、春の始まりとされています。
とは言え、まだしばらくはこの時期らしい寒さが続きそうです。
さて、今日は看護部のお話です。
タイトルにある「プラチナナース」とは、定年退職前後に就業している先輩看護師のことで、これまでの学習や経験で培った能力を発揮し、いきいきと輝き続けている看護師の呼称です。
新人看護師が配属されてもうすぐ1年が経ちます。
先輩看護師のサポートから離れて独り立ちする機会も増え、悩みやストレスを感じる時期です。
加えて、コロナの影響で同期・同僚との交流やリフレッシュの機会が減ってしまっています。
そこで、新人看護師研修後に当院のプラチナナースから、「若い世代に伝えたいこと」をテーマにメッセージをもらいました。

自身の経験をもとに、看護観やキャリアプラン・人生設計、そして、今まで看護師を続けてこられた理由などを熱く語ってくれました。
大先輩の話は新人看護師の心に響いたようで、受講後のアンケートには「辛いことも多いが、もう少し頑張ってみようと思った」、「努力は報われるという言葉が心に残った」といった前向きな内容が多くありました。
それぞれが目指す看護師像や看護師として働き続けることを考える良いきっかけとなりました。
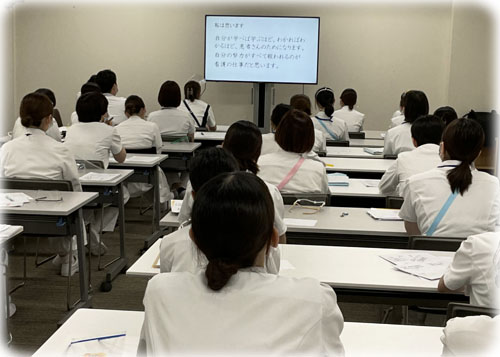
これからもベテラン職員が培った知識や技術を若い職員に伝承しながら、それぞれの職責に応じて、やりがいを感じながら仕事ができるよう、職場づくりをしていきたいと思います。
看護助手研修を実施しました
2023年01月27日
新しい年が始まり早くも1ヵ月が過ぎようとしています。
今週は今冬最強の寒波が到来し各地で厳しい寒さとなりました。
さて、今日は看護助手研修のおはなしです。
看護助手は、医療行為を行わないものの、看護師と一緒に患者さんの入院生活に必要なケアや安全に治療が受けられるようお手伝いを行う大切な職種です。
当院では、看護助手独自のラダー研修を行い、段階を重ねて知識・技術を高めています。
今回は大人用おむつメーカーの担当者を招いて、おむつ介助の研修を行いました。

おむつの選び方やあて方についての講義の後、実際に練習を行いました。
おむつが緩かったり、サイズやあて方が間違っていたりすると、安心して排泄ができなくなるうえに、皮膚トラブルを引き起こす原因にもなってしまいます。
この研修では、実際に自分自身が患者さん役になりおむつ交換の体験をしながら、介助のコツを学ぶことができました。
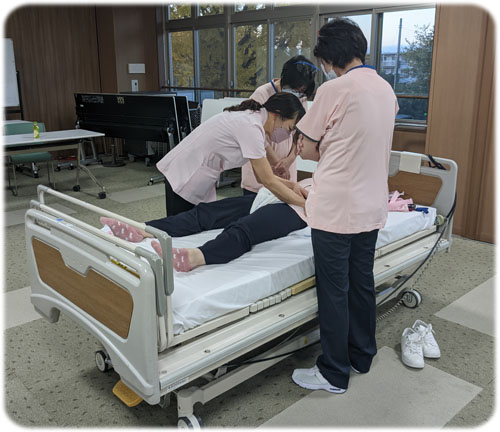
今後も患者さんが快適な入院生活を送れるように看護助手研修を行っていきます。
過去のブログ 看護助手の食事介助の研修(ペースト食ってどんな味?)もご覧ください。
BLS(一次救命処置)講習を実施しています
2023年01月20日
暦の上では大寒を迎え、1年で最も寒い時期になりました。
今週末以降はこの冬一番の寒波襲来との予報が出ています。
2020年以降大きな流行がなかったインフルエンザも今年は感染者が増えています。
引き続き手洗い等の感染対策、咳エチケットを心掛けたいですね。
さて、当院では希望する職員を対象に「BLS:Basic Life Support」と呼ばれる心肺停止または呼吸停止に対する一次救命処置の講習を定期的に実施しています。
この講習はAHA(アメリカ心臓協会)認定インストラクターの資格を持つ当院職員が講師を務めています。
今年度は約60名が受講し、心臓マッサージや人工呼吸(換気バックを用いた呼吸の補助)、AEDの扱い方などの訓練を行いました。

通勤通学中の電車やバス、スポーツ中でも心臓発作や頭を強く打つなど、日常生活のさまざまなシーンで救命処置が必要になる場合があります。
BLSは一般の講習会場でも受講が可能な資格ですが、当院では医療従事者としてより適切な救命処置が行えるよう、院内で講習を実施し、新人からベテラン職員まで幅広く講習に参加しています。
また、BLSのガイドラインは5年ごとに改定が行われるためインストラクターも繰り返し指導を行うことでスキルを磨いています。
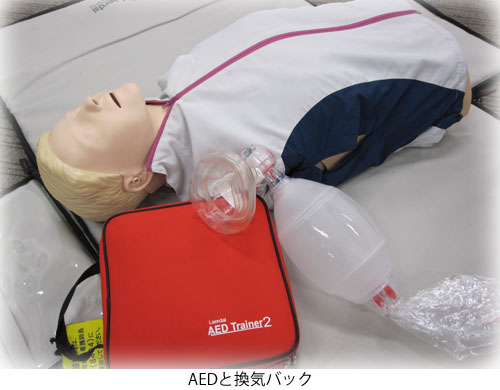
これからも知識・技術のアップデートを行い、救命の現場で適切に対応できるようこうした講習を実施していきます。
脳神経外科の動画「下垂体のおはなし」を配信中!
2023年01月13日
今年度開設した当院YouTubeチャンネルでは、当院医師が専門の疾患について解説していく予定ですが、第一弾として、脳神経外科の動画を配信しました✨

脳神経外科の瓜生医師と鈴木医師が、人の頭の中にある「下垂体」について、その機能や下垂体疾患の症状、治療法などを解説します。
下垂体って何だろう?難しそう…と思いますが、かわいいキャラクターが登場したり、実際に視野が欠けていくイメージを体感できたりと、一般の方でも楽しく見ていただける内容となっています。
撮影中はとても和やかな雰囲気で、広報スタッフ含め終始笑顔で行われました。
横浜医療センターを代表する仲良しの先生お二人を是非YouTubeでご覧ください!
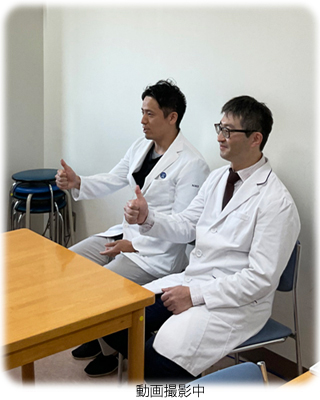

オミクロン株対応ワクチン接種について
2023年01月06日
今日は二十四節気の「小寒」ですね。
新年を迎えて本格的に寒さが訪れ、朝夕の冷え込みが身に沁みます。
昨年後半から飲食や旅行、イベントに関する行動制限が緩和され、コロナ禍以前の日常が少しずつ戻ってきました。
一方、人の動きが活発になり、感染者数が増加しています。
職員の感染による医療ひっ迫の恐れもあることから、当院では昨年11月からオミクロン株対応ワクチンの院内接種を実施しています。
接種後の副反応を考慮して、金曜日に接種を希望する職員が多く、接種会場前に長い列ができました。
現在供給されているオミクロン株対応ワクチンは、オミクロン株に対して、従来型ワクチンを上回る重症化予防効果とともに、感染予防効果や発症予防効果も期待されています。
未接種の方はぜひ接種をご検討ください。
感染対策が緩和される傾向にありますが、当院を受診いただく際や面会等で院内に入る場合は、検温、手指消毒、マスク着用をお願いします。
もちろん職員も引き続き感染対策を実施します。

横浜医療センターのお正月🐇
2023年01月04日
明けましておめでとうございます🎍
本年も病院ブログをよろしくお願いします。
当院では毎年、正面玄関に門松を飾り付けています。

年末年始、入院患者さんに提供された特別メニューをご紹介します。

大晦日には年越しそばを、三が日にはおせち料理をご用意して、病棟スタッフとともに新年をお祝いしました。
栄養管理室では、栄養バランスを考えながら、このように季節が感じられるメニューを提供しています。
皆さんも写真で楽しんでいただけると嬉しいです😊



今年も当院の様々な情報を毎週発信していきます。
皆さんにとって良い一年となりますように…。
院長メッセージはこちらをご覧ください。

本年最終ブログです!
2022年12月26日
先週末はクリスマス寒波でした。
大雪が降っている場所もありますので、年末年始、帰省等で外出の際にはお気を付けください。
栄養管理室では、クリスマスイブにサンタクロースに扮した職員が入院患者さんに夕食をお届けしました🎅
配膳車もクリスマスのデコレーションがされています。


~メニュー~
えびピラフ
フライドチキン
添え)ベジタブルソテー
ポトフ
彩ピクルス
クリスマスケーキ
フルーツ盛り合わせ
患者さんたちにとても喜んでいただくことができました。
院内保育園では恒例のクリスマス会が行われました。

きれいに飾り付けられた部屋で、クリスマスにちなんだお話を聞いたり、歌を歌ったりと盛り上がったところでサンタさんがプレゼントを持って来てくれました🎁

サンタさんを初めて見た子どもたちはびっくりして泣き出す子もいましたが、一人ひとりプレゼントを手渡されて嬉しそうでした。
サンタさんと一緒の楽しいクリスマス会になりました🎀

当院は年内28日まで、新年は4日から通常診療を行います。
皆様良いお年をお迎えください。
クリスマスイルミネーション2022in横浜医療センター🎄✨
2022年12月23日
昨日は1年で夜が最も長くなる冬至でした。
街の様々な場所で長い夜の時間をキラキラしたイルミネーションが彩っています。
当院でも例年クリスマスの時期に、ロータリーのシンボルツリーにイルミネーションを実施しています。
今年はSDGsの取り組みの一環として、新たにソーラーパネルを設置し、太陽光発電で点灯しています。
院内でもいろんな場所でクリスマスムードを盛り上げているのでご紹介します。
待合室には恒例の大きなツリーがあります。
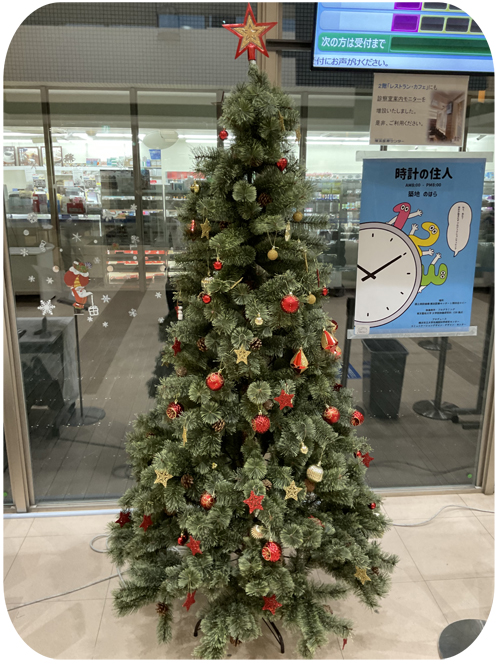
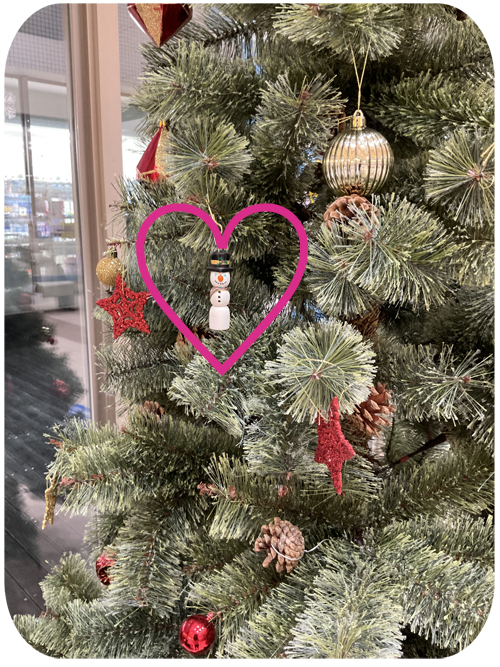
来院された方が手作りの素敵な飾りをつけてくれました。 ありがとうございます😊
小児科病棟ではリースとツリーが飾られています。

受付にもかわいい飾りがありました!

栄養相談室の装飾には、通りかかった子どもたちが指を指して喜んでいる姿がありました。
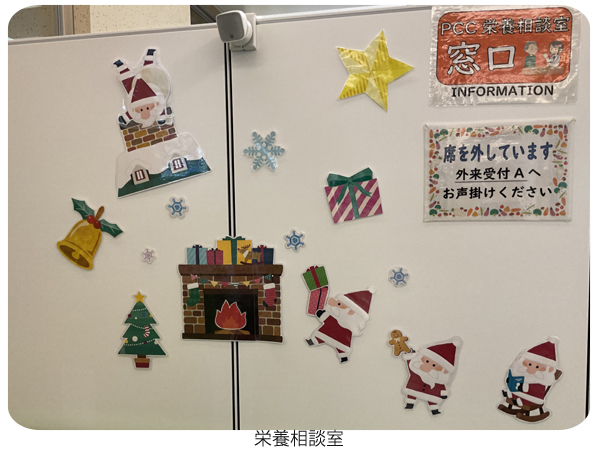
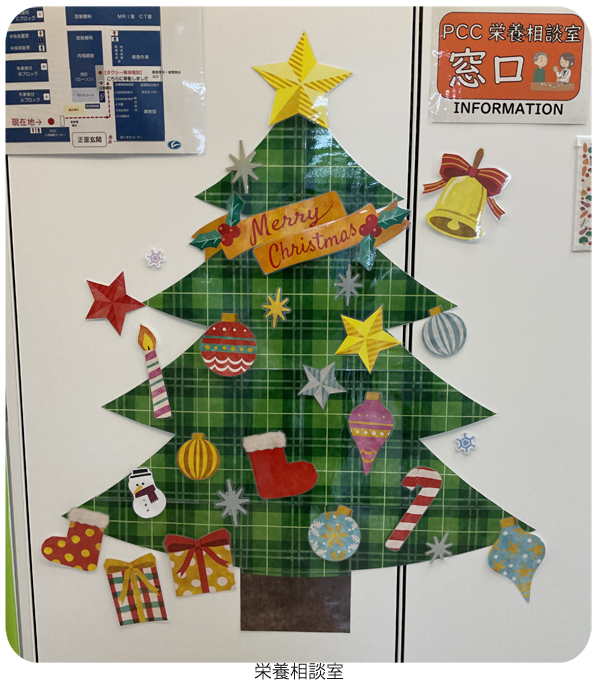
クリスマスが終わると今年もあとわずかですね!
皆さん、楽しい週末をお過ごしください🎅
【チーム医療の活動紹介7-1】ラピットレスポンスチームの活動
2022年12月16日
「多くの急変には前兆がある」という言葉はご存知でしょうか。
当院では、患者さんの状態変化にいち早く気づいて早期対応する院内対応システム(RRS:Rapid Response System)を今年度より導入しました。
救急科医師、ICU・救急病棟の看護師で構成された「ラピットレスポンスチーム」がその対応を担っています。

看護をしていると、「何かいつもと様子が違うな…」という具体的な言葉にはできない直感や嫌な予感のようなものを感じることがあります。
目立った症状が現れていなくても、その予兆を見逃さずにチームが介入することで患者さんの急変を未然に防ぐことができます。
また、院内で急変が起きた際、主治医がすぐに駆け付けられない場合であっても、診療科を越えてチームが対応します。
今回チームの立ち上げにあたって、各病棟フロアのラウンドを行い、チームの目的や活動内容についての周知を行いました。
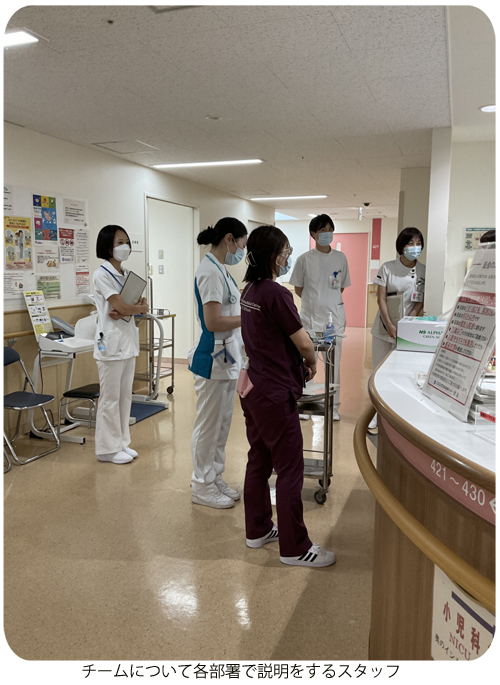
院内でチームの存在を周知することで、どんな些細なことでも気になることがあれば要請を受け、必要に応じて治療方針を再検討し、患者さんの急変を防げるように活動を行っていきます。

看護部の紹介動画を作成中❣
2022年12月09日
寒い日が続きますね。
皆さんはサッカーW杯をご覧になりましたか?
選手たちの熱い姿に感動された方も多いのではないでしょうか。
また4年後の開催が楽しみですね!
さて、何度かブログでもお伝えしましたが、当院では9月にYouTubeチャンネルを開設し様々なコンテンツを更新しております。ご覧いただけましたか?
先日、新しいコンテンツとして看護部の紹介動画の撮影を行いました。
最前線で働く看護師の勤務の様子やインタビューを中心に構成しているほか、ドローンを使用した病院景観や、ドクターカー出動の様子など普段見ることができないような場面も紹介しています。

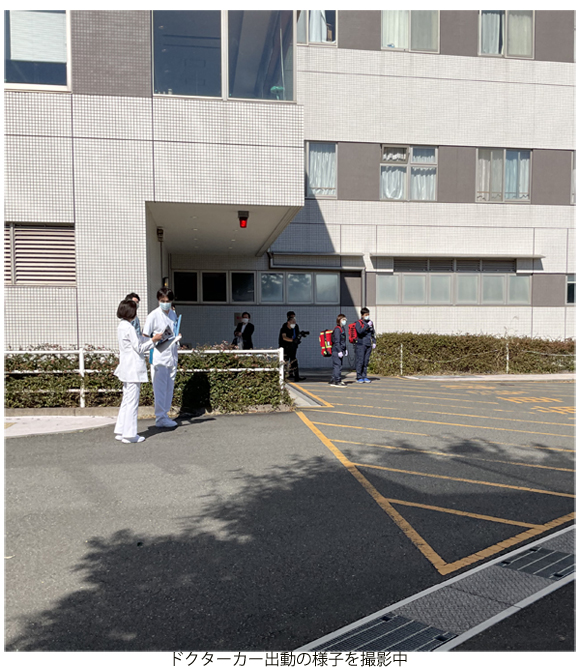
ただいま12月中の公開を目指して編集作業の真っ最中です!
完成後にはお知らせいたしますので、ぜひご覧ください😊

【チーム医療の活動紹介6-2】骨粗鬆症チームの活動
2022年12月02日
早いもので師走となりました。月日が流れるのは早いですね。
年末に向け、体調には気を付けてお過ごしください。
さて、今回は前回に続き骨粗鬆症チームの活動を紹介します。
当院の骨粗鬆症チームメンバーである診療放射線技師より骨粗鬆症の予防と検査について説明していただきました。
骨密度は一般的に10代で蓄えられ、20代で最大となり、40代まで維持され、その後減少していきます。
特に女性では閉経を境に骨密度が著しく低下する傾向があり、骨折リスクが高まります。
他にも喫煙や過度なアルコール摂取が危険因子となり、骨粗鬆症発症と骨折リスクを高めます。
骨粗鬆症の予防のためには骨密度の減少者を早期に発見することや、骨密度の値を把握し、減少を食い止めることが重要です。
骨密度の評価にはDXA(二重エネルギーX線吸収測定)法による腰椎と大腿骨頸部での測定が推奨されています。
当院での検査時間は5分程度で、胸部X線検査より少ない被ばく線量で検査を行うことができます。
当院のDXA法骨密度検査装置は、骨粗鬆症由来の骨折により当院で手術をされた患者さんの治療後経過観察での利用などに加え、地域の皆様が定期的に骨密度検査を行えるように地域連携医療機関との共同利用を行っています。

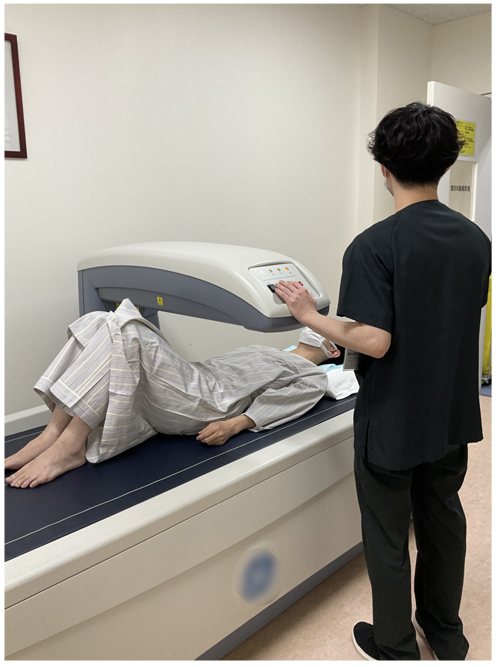
こうした骨密度検査を通して、骨粗鬆症の予防や診断、治療に努めています。
また、様々な媒体を通して骨粗鬆症についての啓発も行っています。
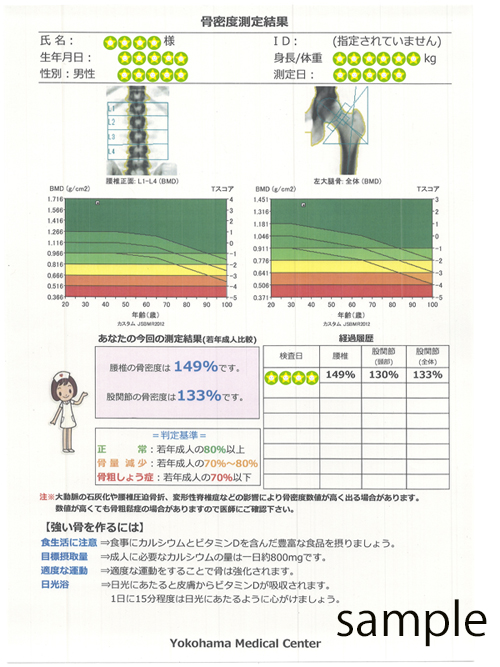
【チーム医療の活動紹介6-1】骨粗鬆症チームの活動
2022年11月25日
今回は骨粗鬆症チームについてのご紹介です。
骨粗鬆症とは、骨強度(骨の強さ)が減って骨が弱くなり、骨折しやすくなる病気です。
日本には1000万人以上の患者さんがいると言われ、高齢化に伴って増加傾向にあります。
当院では、多職種(医師、看護師、放射線技師、薬剤師、管理栄養士、ソーシャルワーカー)による専門のチーム【OLS(Osteoporosis Liaison Service):骨粗鬆症チーム】でこの病気に関わっています。

骨粗鬆症と聞くと、直接命に関係しないように思えますが、骨折を繰り返して寝たきりとなり介護が必要になってしまうと、死期に関わる場合があります。
そのため、チームでは骨折を未然に防ぎ、二次骨折など回復に時間がかかる骨折を食い止めるための活動やサポートを行っています。
骨粗鬆症では長期的な薬での治療を行う場合もありますが、薬の服用を途中で止めてしまう患者さんも少なくありません。
そこで、お薬手帳のような「骨粗鬆症連携手帳」を活用して、他の医療機関を受診した際に、治療経過や薬の情報が引き継がれるよう、データの管理を行っています。
患者さんの環境が変わっても治療が継続できるよう、チームで連携して活動を行っています。
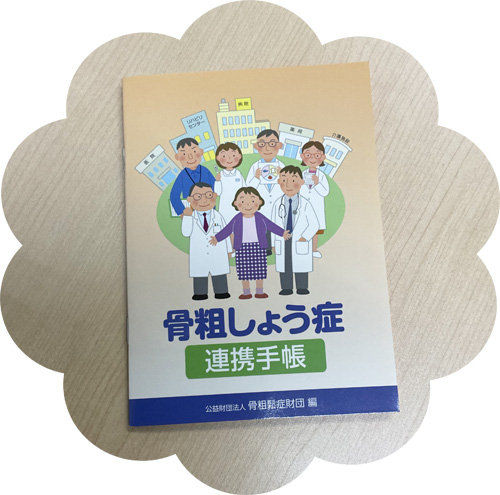
職員研修を行いました②📝
2022年11月18日
日が暮れるのが一段と早くなり、朝晩冷え込むようになりましたね。
当院の屋上からは富士山の雪化粧が見られ、もう冬が近づいているなぁと感じます。
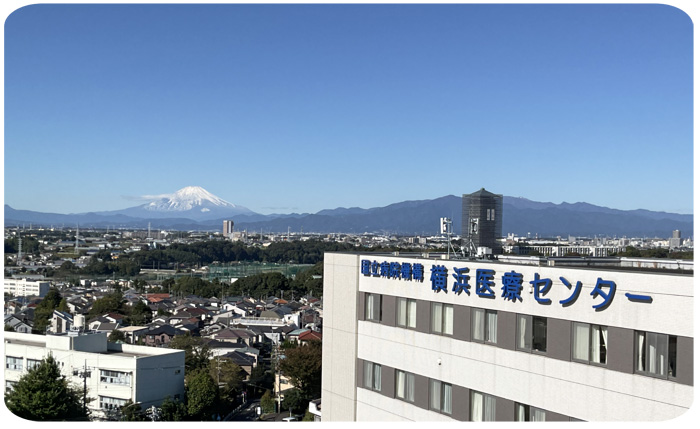
今日は職員研修のお話です。
医療安全と感染防止対策に関する今年度2回目の研修を10月に行いました。
(第1回目のブログはこちらをご覧ください。)

今回は、「医薬品の適正使用」について当院副薬剤部長からの講義に加えて、「新型コロナウイルスの流行と地域連携 感染症に強い社会をめざして」というテーマで沖縄県立中部病院感染症内科副部長の高山義浩先生にお越しいただき、ご講演いただきました。

新型コロナウイルス感染症は発生から3年近く経過して、ワクチンや治療薬の開発などが進みましたが、医療施設や高齢者施設でのクラスター発生が後を絶ちません。
ウイルスを持ち込まれても、そこから感染を広げないということが医療機関の命題です。
高山先生からは、在宅患者や日本語が分からない方などにも、地域と連携して感染対策の指導を行っているという沖縄県の取り組みをご紹介いただきました。
当院でも地域への感染対策の指導を行っておりますが、その重要性を改めて実感しました。
医薬品の適正使用では、一部の抗菌薬が不足した場合での適正使用、医療用麻薬の取り扱いについての適正使用の内容について学びました。

今後も、全職員が医療職としての知識のアップデートを行い、学ぶことの重要さを再認識できるように定期的に研修を実施していきたいと思います。
看護師1年目研修
2022年11月11日
11月11日はゾロ目ということもあって様々な記念日があるようです。
皆さん、いい(11)日をお過ごしください😊✨
さて、今日は先日行われた新人看護師研修のお話です。
当院で働く新人看護師は、新人教育プログラムとして毎月1回(8月を除く)研修を受けていますが、今年も後半戦に入りました。

10月は人工呼吸器の使い方について基礎を学ぶ研修でした。
人工呼吸器は急性期病院ではよく使われる機器ですが、病棟によって使う機会に差があります。
当院ではICUや、救急病棟、SCU、CCUでの使用が多く、一般病棟では少ないため、使用に不安を感じる看護師も少なくありません。
研修を通して知識や技術を身につけることで、恐怖心を無くし、他の病棟に行っても医療機器全般を抵抗なく扱えるようにするためにイメージトレーニングの教育は必要です。
※SCU:脳卒中集中治療室、CCU:冠疾患集中治療室
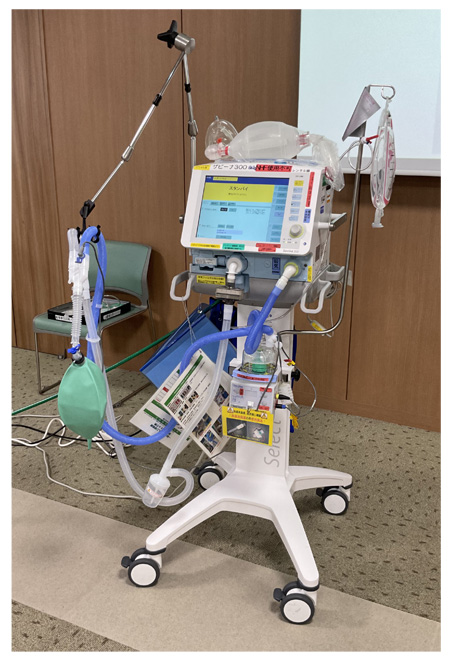
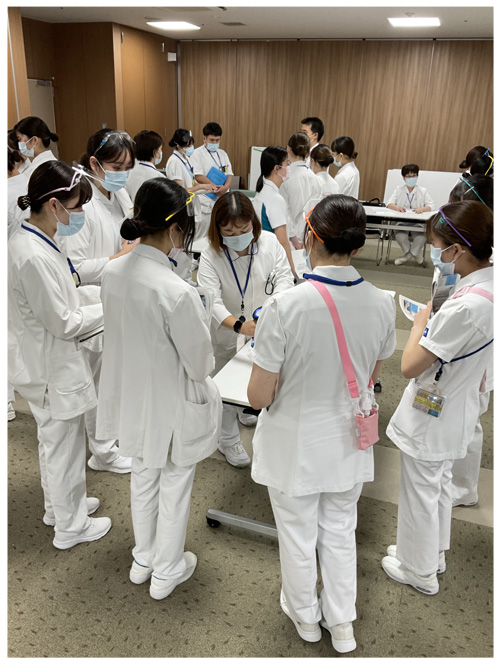
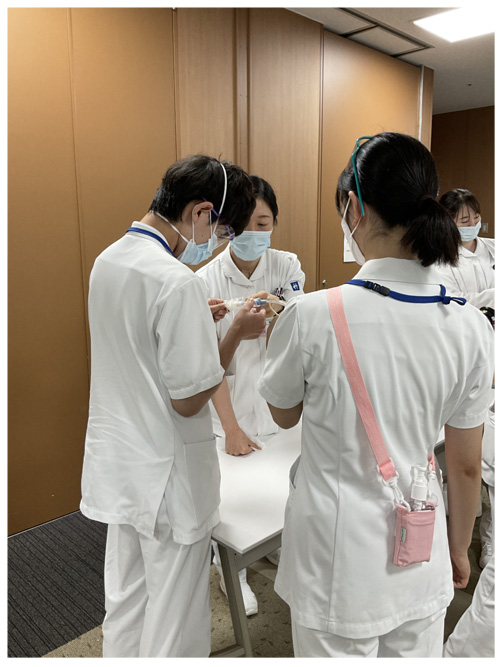
また、日頃なかなか会えない同期と顔を合わせることで、リフレッシュにもつながります。
研修中には、仲間同士笑顔で会話する場面も見ることができました。
仲間たちと研修の場を通して知識・技術を高め合い、日々患者さんの看護に取り組んでいます。
J.M.S(ジャパン・マンモグラフィー・サンデー)の終了報告
2022年11月09日
こんにちは、寒暖差が大きく、皆様体調を崩しておられませんか。
夜はすっかり秋の虫の声になりましたね。月もきれいに見える気がします。
さて、今回のブログは10月16日に行われたJ.M.Sについて紹介します。
J.M.S(ジャパン・マンモグラフィーサンデー)とは、子育て・介護・仕事など多忙な平日を過ごす女性のために「10月第3日曜日全国どこでもマンモグラフィー検査が受診できる環境作り」を目指し、日本乳がんピンクリボン運動(認定NPO法人J.POSH)が全国の医療機関に呼びかけ、2009年から開始した取り組みです。
当院はこの取り組みに賛同し、昨年から実施しています。
昨年より受診希望の方や、乳腺エコーを同時に希望される方も増えています。
乳がんは検診で早期発見できる病気です。
この取り組みが実を結び、一人でも多くの笑顔が守られますように…

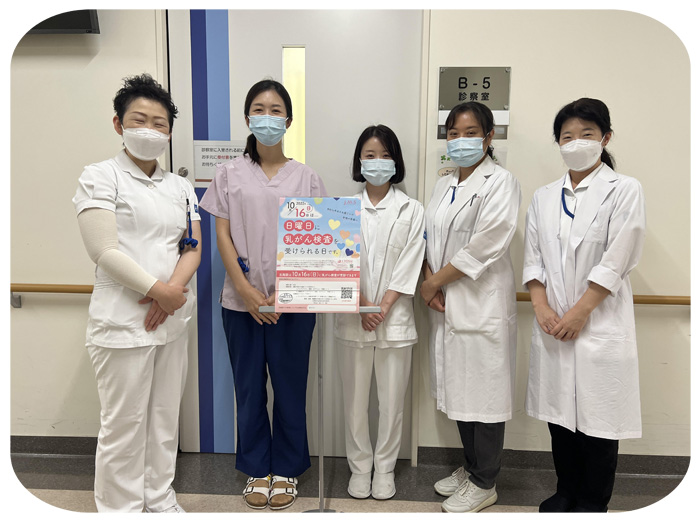
ハッピーハロウィン2022🎃
2022年11月04日
10月31日はハロウィンでしたね👻🍭
街中でもハロウィンの装飾や、地域の子どもたちが仮装してお菓子を持っている姿を見かけました。
当院でも外来ホールと小児科病棟でハロウィンの飾り付けを行いました。


また、入院中の患者さんにはハロウィンの行事食を提供しました。
◇米飯
◇鶏ももチーズ焼き ボイルキャベツ添え
◇サラダ 袋ドレッシング付
◇彩りピクルス
◇パンプキンポタージュ
◇スイートポテト
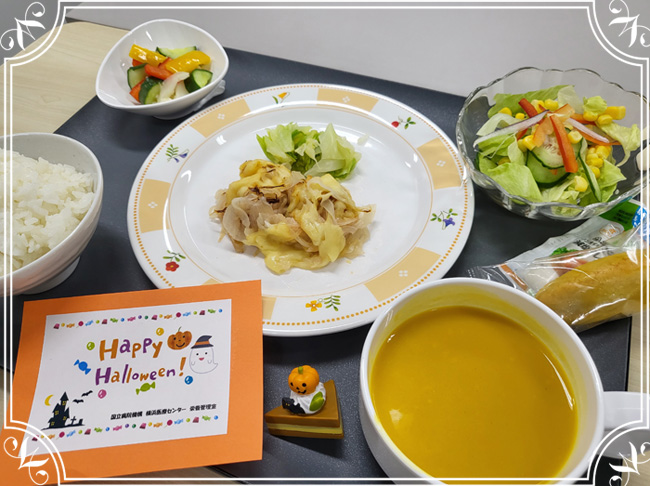
栄養管理室長よりコメントをいただきました🎃❣
「ハロウィンとは、かぼちゃの飾り物「ジャック・オー・ランタン」がお馴染みですが、これはお守りの意味があります。
また、秋の収穫を祝う習慣があります。
ハロウィンといえば、やはりかぼちゃ料理は外せない物です。
かぼちゃは、緑黄色野菜の代表的な野菜ですが、糖質も多く含まれます。
かぼちゃ90g(約1/8個)には糖質が、米飯50g(コンビニおにぎり半分程度)に相当します。
かぼちゃに含まれるβカロテンやビタミンC・Eは、皮膚や粘膜を正常に保つ作用が期待されています。
栄養管理室では、入院中でも患者さんが様々な行事を楽しんでいただけるように工夫して食事を提供しております。
今回のハロウィンの夕食も喜んでいただけました😊」
日本ではまだ歴史が浅いハロウィンですが、皆さんもかぼちゃ料理やお菓子を食べてハロウィンを楽しまれたでしょうか?
人工心肺装置とは?
2022年11月02日
11月1日は「いい医療の日」でした。
そこで今回は、今年新しく導入された「人工心肺装置」についてご紹介します。

人工心肺装置とは、一時的に心臓と肺の機能を人工的に代行する装置のことです。
なぜそのような装置が必要なのかというと、心臓の中にある弁などに疾患がある患者さんは状況によって外科的な治療を行うことがあります。
その際に心臓を一時的に停止させて心臓内を治療することになります。
その間に人工心肺装置を用いて患者さんの心臓と肺の機能を代行する為です。
この人工心肺装置は臨床工学技士という国家資格の専門家が操作します。
彼らは病院内の医療機器のほとんどを管理している専門家であり、医療機器の操作及び点検や修理も行います。病院内のエンジニアのような仕事で、メディカルエンジニア(ME)などと呼ばれております。

使用する場面はほとんどが心臓血管外科の開心術で使用しますので、麻酔がかかった患者さんがこの装置に気が付くことはほとんどありません。
人工心肺装置は写真にあるように多くのスイッチ類、パネル類、センサー類が搭載されています。
操作する際はこれら様々な機械に囲まれて操作することになり、まるで飛行機や車の操縦席のような感じです。
新しい人工心肺装置ではスイッチが電子スイッチになり、液晶がタッチパネルになり、多くのセンサーにより自動制御を行うなど様々な機能が搭載されるようになり、以前の装置よりも、安全性能が高くなっております。

また、多機能になり操作が難しいのではと思われがちですが、最新の車の「進む、曲がる、停まる」といった機能と操作方法も昔の車と大きく変わっていないのと同様に、人工心肺装置の基本的な機能と操作方法も大きく変わっておりませんので操作に関してはそれほど違和感なく使用できます。
当院では今後もより安全性の高い医療を患者さんに提供していきます。
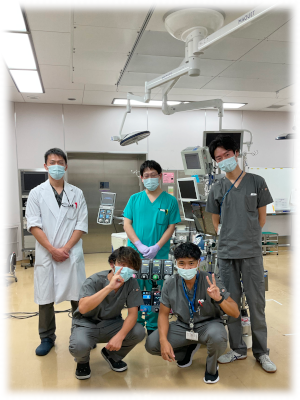
秋のイベントが実施されました🎈
2022年10月28日
秋冷が日増しに加わり、落ち葉が足元を埋め、冬の前触れを感じる季節となりました。
先日当院では、病院正面のロータリー脇に植樹を行いました。
ソヨゴ、ヤマボウシ、ムクゲ、サルスベリの4種類です。
若い木々が育ち、花をつける時期まで成長を見守っていきたいと思います。

さて今日は、先日行われたイベントの様子をお伝えしたいと思います。
雨続きの週でしたが秋晴れの週末となりました!
10月15日(土)、院内保育園にて「親子レクリエーション」が行われました。

感染対策に配慮し、クラスごとに入れ替え制での実施となりました。
コロナで様々なイベントが中止になっている中で、子ども達のために保育士の皆さんが知恵を振り絞ってできる範囲の中で企画してくれました。
子ども達はいつもと違う雰囲気に緊張しながらも、保護者と保育士に囲まれてとても嬉しそうでした。保護者の方々からは、
「手作りで愛情こもった親子レク、子どもたちの笑顔がたくさん見ることができた」
「朝の会や絵本の読み聞かせなど、どのように過ごしているのかがわかりとてもよかった」
「日頃使用している教室でリラックスして友だちと競技に参加している様子が見ることができて嬉しかった」などの感想が寄せられました。
保育士の皆さん、企画・運営をありがとうございました😊

10月16日(日)、当院公開空地にて3年ぶりに「とつか原宿ふれあい祭り」が開催されました🎊
地域から様々なブースが設置され、フリーマーケットや、近隣の中学校・カルチャースクールの発表が行われました。
特にフリーマーケットは毎年皆さん楽しみにしていたイベントで、会場は子どもから年配の方までたくさんの人達で賑わっていました。

また、感染対策を行いながら軽食の販売もあり、少しずつ落ち着きを取り戻しつつあると感じることができました。
これからも院内のスペースを提供して地域活性化に貢献していきたいと思います。
国立病院総合医学会に参加しました
2022年10月26日
10月7日~8日にかけて、国立病院総合医学会が熊本で開催されました。
毎年開催されているのですが、対面方式は3年ぶりです。
しっかりとした感染対策がなされ、安心して参加することができました。

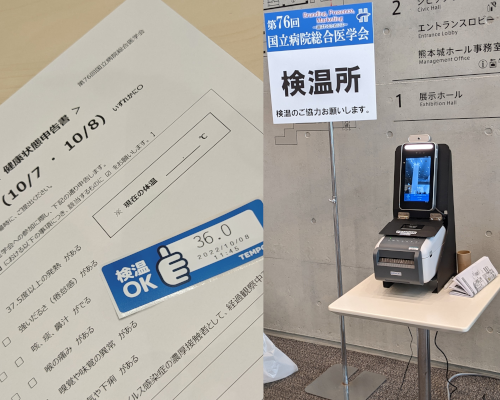
国立病院機構は日本最大の病院ネットワークであり、北海道から沖縄まで140の医療施設を擁します。
また、附属の看護学校もあるため、医療現場に限らず教育に関する研究など学会発表のテーマは多岐に渡っています。
今年は「Brandeing,Presence,Marketing ~選ばれるためには~」と言うテーマで、特別講演では一般の企業活動における経験や反省から「ニーズに応え、選ばれるため」のお話しがありました。
シンポジウムやパネルディスカッション、一般演題口演、ポスター発表では、日ごろの業務に関する調査や分析、経験に基づく研究発表が分刻みのスケジュールで開催されました。
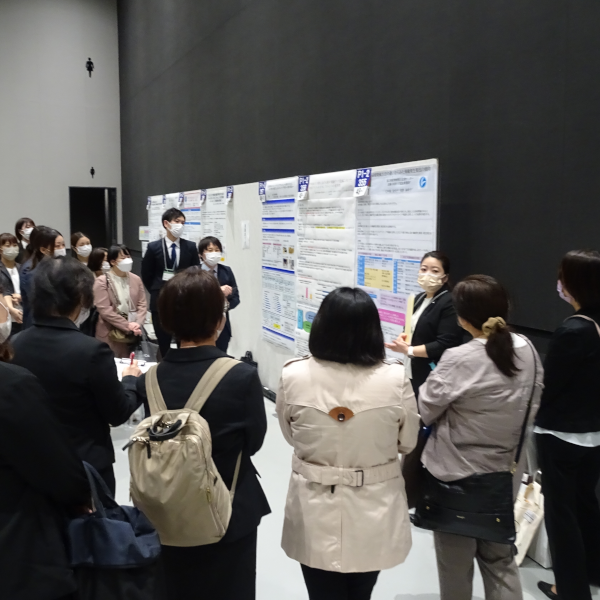
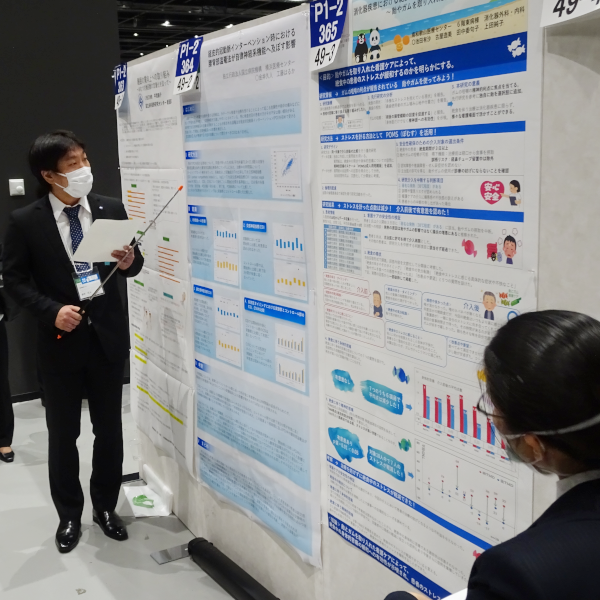
発表を聞くと、多くの仲間たちが色々な思いを持って仕事に向き合っていることが伝わってきます。
医師による疾患研究、看護研究、リハビリ、薬剤、栄養、経営等の事務部門・・・日ごろ課題になっていたことに対する答えのヒントがみつかったり、まったく違う角度からみたりすることができるなど、気付きの多い発表が多くありました。
国立病院総合医学会ではベスト口演賞とベストポスター賞が選出されます。
当院からもベスト口演賞2名、ベストポスター賞6名の発表が選ばれました!
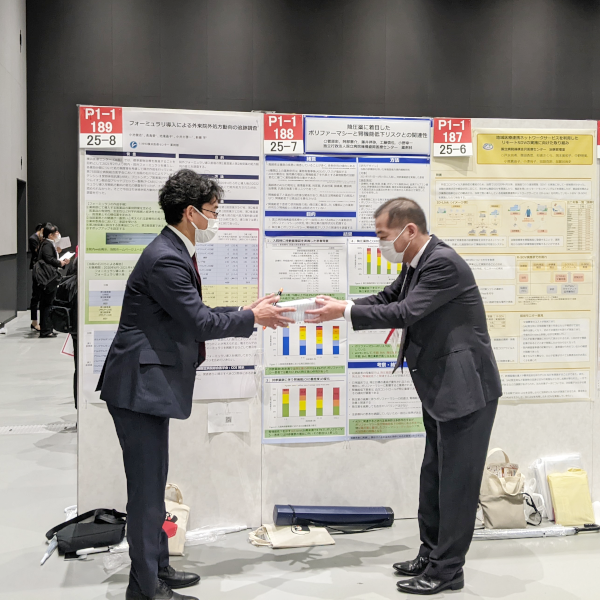
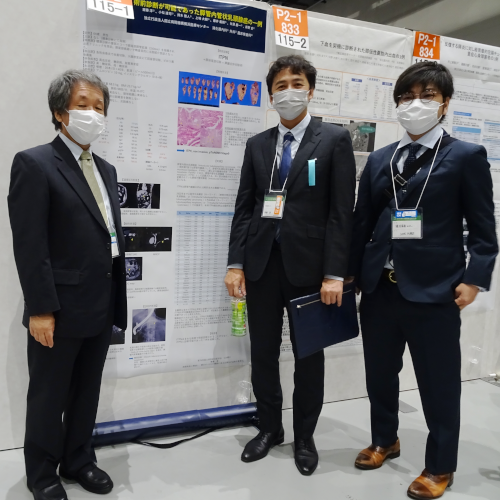
2日目には「くまモン」が忙しいスケジュールの合間を縫って、メインホールに来てくれました!くまモンは2010年から熊本県PRマスコットキャラクターとして活躍していて、認知度が非常に高くブランディングとして大成功していると思います。
多くの企業とコラボがあるのは、まさに選ばれているからなのでしょう。
医療従事者として「選ばれるために」何ができるか、私たち職員もアップデートを繰り返しながらあゆみを進めていこうと思います。
看護部長のお話~戴帽式を終えて~
2022年10月21日
9月30日、横浜医療センター附属横浜看護学校にて戴帽式が行われました。
戴帽式とは1年生が病院実習に入る前に行われるセレモニーで、男性にはエンブレム、女性にはキャップが授与され、ナイチンゲールの「心の灯」を継承し「看護の誓詞」を宣誓します。
戴帽式の様子はこちら(看護学校ホームページ)
戴帽式に参加した藤澤看護部長にお話を伺いました。
🔶今年の戴帽式の様子はいかがでしたか?
「3年ぶりに来賓や保護者の方々にも参加していただけて良かったです」
🔶戴帽式の思い出を教えてください
「戴帽式でナースキャップをもらうまでは三角巾をかぶって実習していたので、ナースキャップをもらえて嬉しかった記憶があります(三角巾が嫌だったので…)」
🔶現在はナースキャップが廃止となっていますが、当時はどのように感じましたか?
「ナースキャップをつける時は髪型もピシッとセットしていたので、気持ちも引き締まる気がしていました、実際の現場ではナースキャップが物にぶつかることもなく楽に感じます。」
🔶当院の看護部の特徴を教えてください
「やる気やパワーがある人、勉強家でやると決めたらやり遂げる人が多いです😊」
🔶患者さんの看護で印象に残っている思い出を教えてください
「ターミナルケア(終末期医療の看護)を担当していたとき、肺がんで苦しんでいる患者さんに一晩中付き添って背中をさすって、患者さんと夜明けを迎えたことです。当時の医療では肺がんの苦しさを緩和する治療がなかったのでとても苦しんでいました。背中をさすることしかできなかったけど、一緒に患者さんと「もう夜が明けますね」と話したことを思い出します。」
🔶これから看護師を目指している方や看護学生に向けて、今できること・やっておくべきことがあれば教えてください
「医療に限らず様々なジャンルのドラマを見てほしいです。ドラマには人の気持ちが関係してくるので、自分以外の人の気持ちが理解できるといいと思います。生活のメリハリもつくのでお楽しみのドラマを見つけてほしいです」
新たなステップに進んだ看護学生の皆さん、これから病院実習、頑張ってくださいね✨
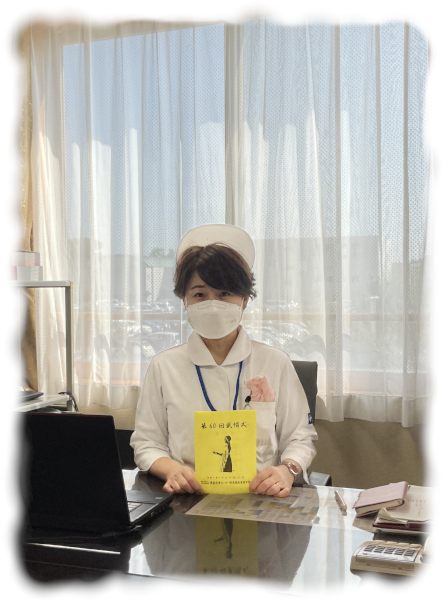
当院医師の論文が『Nature』に掲載されました📰
2022年10月14日
当院の糖尿病内分泌内科部長・田島一樹医師らが執筆した研究論文が、英国科学雑誌『Nature』(2022年9月1日号)に掲載されました。
【論文のリンク先:https://www.nature.com/articles/s41586-022-05067-4】
『Nature』とは医学界のみならず、国際的な総合科学ジャーナルとして、世界中に届けられているとても有名な雑誌です。医療は日進月歩で発展していますが、その発展にはこのような医療従事者による研究が大きく貢献しています。
田島医師にこの研究論文の要旨を以下のとおりまとめてもらいました。
本研究は、褐色脂肪の新たな制御メカニズムを調べた研究です。
人間のからだには、2つの脂肪細胞が存在します。一つは白色脂肪、もう一つが褐色脂肪です。私達が、肥満と関連して思い浮かべるのが、白色脂肪であり、皮膚の下や内臓にあり、体の中の余分なエネルギーを脂肪として溜め込む役割を担っています。
一方で、褐色脂肪は、エネルギーを作り出すミトコンドリアが多く存在しているため、脂肪を熱に変える働きをもっています。
以前まで、この褐色脂肪は、乳幼児のときに多く見られるものの、成長とともに減少し、成人になるとほとんど存在しないものと考えられていました。
しかし、最近の研究で、成人にも褐色脂肪が存在することが明らかとなりました。そのため、熱を産生して、脂肪エネルギーを消費する褐色脂肪の働きを高めることが出来れば、肥満や糖尿病の治療につながるのではないかと期待されています。
今回の研究では、褐色脂肪の分化・機能維持に重要である転写因子PRDM16の安定化に重要な制御メカニズムを明らかにしました。将来、褐色脂肪の研究がさらに進むことで、肥満および糖尿病の新しい治療法へと発展することが期待されます。

職員研修を行いました📝
2022年10月07日
10月に入りました🍁
行楽にスポーツ、読書と何をするにも良い季節ですね。
皆さんもこの秋を楽しんでください。
さて、当院では9月15日に医療安全と感染防止対策の取り組みにおいて、より質の高い医療を提供するため、全職員を対象とした研修を実施し、多くの医師をはじめ様々な職種の職員が参加しました。
ひとつ目のテーマは「診療用放射線の安全利用の基礎知識と考え方」です。
放射線被ばくによる健康被害には、皮膚障害や発がん性のリスクがあります。
医療安全の側面においても、患者さんへの被ばくを最小限にすると同時に放射線リスクを考慮した放射線検査の適正利用が重要です。
今回は、北里大学医学部の井上優介教授に講師としてお越しいただき、放射線検査による不利益を常に考慮しつつ検査適応を慎重に検討することや、検査前の患者さんとの対話によって安全に行うことの重要性について講義していただきました。

続いて「当院の抗菌薬使用状況を踏まえた抗菌薬適正使用」について、当院救急科医師が講義をしました。
薬物療法を行う上で、感染防止対策の基本である抗菌薬の適正使用は欠かせません。
細菌感染症の治療において、病原体も含めて的確に感染症の診断を行い、適切なタイミングで最も効果的な抗菌薬を投与することが重要となります。
そのためには、抗菌薬の必要な病態かどうかを見極め、必要であれば最大限の治療効果を引き出すように使用するとともに、患者さんに害を与えることなく耐性菌を増やさないことが重要です。

こうした研修を通じて、今後も患者さん一人ひとりにあった治療計画のもと安全な医療の提供に努めてまいります。

「ペースト食」ってどんな味?
2022年09月30日
台風が過ぎ去り、季節の変わり目を感じられている方も多いのではないでしょうか。
秋晴れが気持ちいい時季となってきましたね。
今日は看護助手研修のお話です。
病棟で看護師の補助業務を行う大切な役割を担っている看護助手の研修として、栄養管理室の監修のもと、食事介助に関する研修を行いました。
入院患者さんの食事は、通常食以外に、噛む力や飲み込む力が弱くなった方でものどごし良く食べていただくため、「全粥食」「3分菜」「ペースト食」など、一人一人の状態に合わせて形態を変えて提供しています。
しかし、食事の形態を変えてしまうと、患者さんはメニューの内容が分からないため、食事の楽しみや食欲が減ってしまうことがあります。
そこで、普段提供している食事がどのようなものであるかを知るために、入院食を看護助手の皆さんに試食してもらいました。

ペースト食は、一見、ドロドロであまり食欲が湧かなさそうですが、とてもいい匂いです。実際に食べてみるとしっかり味があってとてもおいしく、おかわりしているスタッフもいました。
「もうすぐお食事の時間ですよ!」「今日はこんなメニューですよ、おいしそうですね!」などのお声がけもプラスして、食事介助に役立てていただきたいと管理栄養士からアドバイスがありました。

患者さんの入院生活がより快適になるよう、今後も様々な研修を行ってまいります。
ジャパン・マンモグラフィー・サンデー(J.M.S)をご存知ですか?
2022年09月22日
「ジャパン・マンモグラフィー・サンデー(J.M.S)」とは、平日に仕事や介護、子育てなどに忙しく、検診を受けにくい女性が、10月第 3日曜日に乳がん検診を受診できるようにしましょうという活動です。当院でもこの活動に賛同し、10月16日(日)に乳がん検診を実施します(今年で2回目の実施です)。
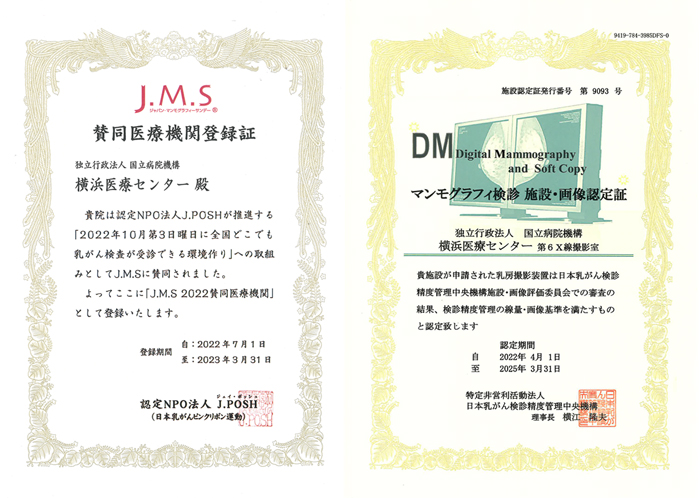
平日に実施している検診は40歳以上を対象としていますが、今回の検診では20歳以上を対象にするとともに、従来の検査(視触診とマンモグラフィー検査)に加えて乳腺エコーも選択して受診できるようにしています。
日本人女性の9人に1人が乳がんになると言われています。早期発見で適切な治療を受ければ生存率が高いがんなのですが、検診率は5割以下という状況です。
今まで忙しくて乳がん検診を受けたことがない方、ここ何年か乳がん検診を受けていない方、この機会にいかがでしょうか。
当院では新型コロナウィルス感染対策として、患者さんごとの機器のアルコール消毒はもちろんのこと、できるだけ待ち時間を少なく、また検査時間が重ならないようにしています。
また、医師・検査スタッフは全員女性です。

🎞案内動画はこちらからご覧ください。
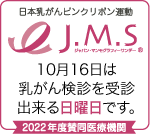
BCP対策訓練を行いました
2022年09月16日
外に出るとまだまだ汗ばむ日もあり、夏と秋のせめぎ合いが続いています。
さて、当院では8月23日に停電によるシステムダウンを想定したBCP対策訓練を行いました。
緊急時において病院が早期に医療機能を回復できるようにするための計画をBCP(Business Continuity Plan:事業継続計画)といい、災害などの緊急事態に備え当院では定期的に訓練を行っています。
訓練は、電子カルテや医療モニターが突然使用できなくなった場合を想定して、患者さん対応の流れを理解するためシミュレーション形式で行いました。
職員は、ホワイトボードで入院患者さんの状況を把握して、必要な対応の確認を行うなどの対応を行っていました。様々なマニュアルがある中で、今回の事象に該当するマニュアルが見つからず苦戦する場面などもありましたが、職員は慌てることなく対応策を確認するため真剣に取り組んでいました。
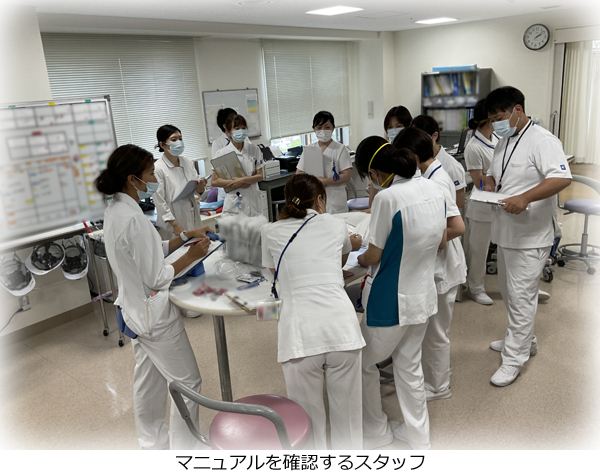
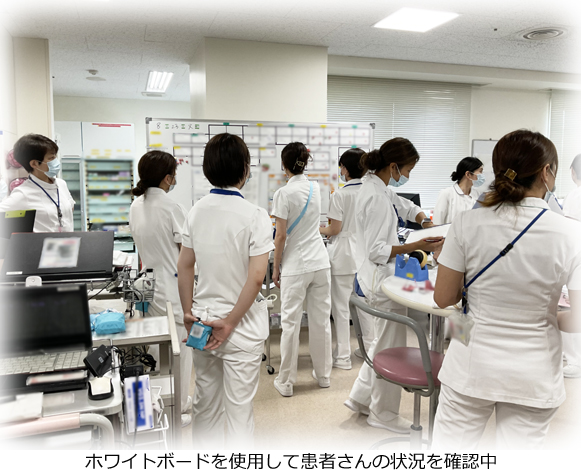
訓練後、参加した看護師にインタビューをしました。
🔶Q1.実際に訓練を行ってみた感想はいかがですか?
「災害はいつでも起こり得る可能性がありながらも、滅多に起こることではないので、現場で必須となっている医療機器や電子カルテが実際に使用できないという想定での訓練ができて良かったです。」
「訓練にも事前準備が大切だと思いました。初めて参加する職員への指導や各職種との調整をして成立する訓練だと思いました。」
🔶Q2.訓練を行ってみてどんなところが大変でしたか?
「通常業務では、マニュアルというものに意識が向きにくいので、今回の事象に該当するマニュアルを探すのが大変でした。」
「電子カルテが使えない場合、各部門や担当者への連絡や引継ぎ方法が大きく変わるのですが、実際対応するとなったときどのような流れで確認が必要か分からなくなってしまいました。」
🔶Q3.災害が実際に起きた場合、今回の訓練は役立ちますか?また、今後に向けての改善点はありますか?
「緊急時に適切な対応を行うためには、このような機会は重要で、繰り返し行うことで実際の災害に備えることができると思います。」
「緊急時だからこそ、誰が見ても、すぐに理解できるようにマニュアル表示を改善する必要性を感じました。」
どのような状況であっても医療の継続ができるように、今後も様々な訓練を行ってまいります。
順調に撮影中です!
2022年09月09日
こんにちは。蝉の声と入れ替わるように、夜には虫たちが歌いはじめました。
明日、9月10日は中秋の名月です。秋を色濃く感じる今日この頃です。
さて、現在広報部では当院のYouTubeチャンネル開設に向けて、準備をしています。

この日は院長の屋外ロケもあり、迷走台風の影響が心配されていました。
ところが、私たちの心配をよそに風もおだやかで、ちょうど雲が切れて晴れるというミラクル。
幸先よいスタートです。

撮影は3時間の予定でしたが、予想以上に順調でなんと1時間半で終了。
ほとんどNGなく撮影を終えました。
広報スタッフにより、ただいま編集作業中です。どんな仕上がりになるか、楽しみです!
この動画を皮切りに、さまざまなコンテンツを発信していきます。
チャンネルが開設されましたら、こちらでもお知らせしたいと思います。
その際はぜひ、ご覧になっていただけると嬉しいです。
【チーム医療の活動紹介5-2】呼吸ケアサポートチームの活動
2022年09月02日
初秋の時期となりました。
日中はまだ残暑が残りますが、しのぎやすい日が続いていますね。
今日は前回に続き呼吸ケアサポートチームの活動を紹介します。
当チームでは、急性期の入院患者さんを対象に毎月第2・第4水曜日に回診を行っています。
人工呼吸器の装着状況や機械の管理、十分な加湿ができているかの観察を行い、必要時に病棟スタッフと連携して対応しています。
また、今後どのようなリハビリを行っていくかの検討を行い、患者さんに適切なケアがなされているかを各職種の視点から状況を把握して、患者さんの回復に向けてサポートしています。
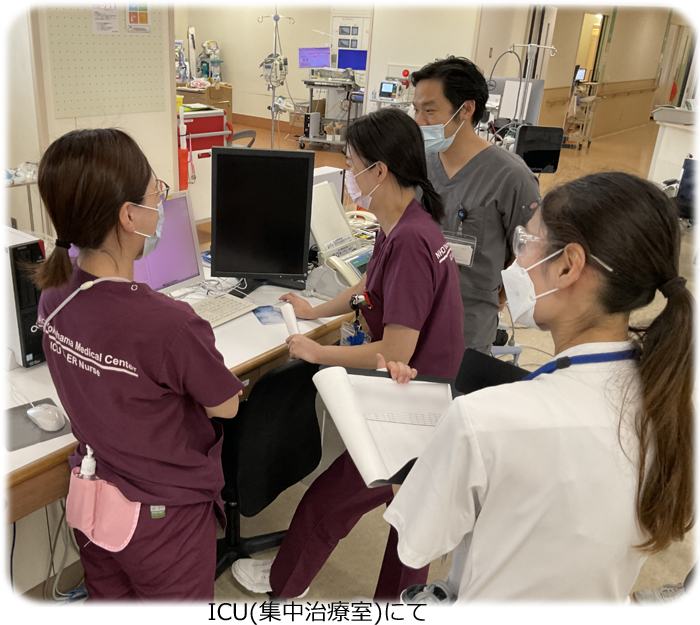


また、人工呼吸器ハンズオンセミナーや早期離床リハビリテーションなどに関する勉強会を定期的に開催し、病棟スタッフの知識や技術の向上に努めています。
人工呼吸器を装着したまま自宅に退院される、患者さん・ご家族のご相談をお受けしています。
ご不安なことがございましたら、ぜひお気軽にお声がけください。
今後も随時、チーム医療のご紹介をしていきます。
【チーム医療の活動紹介5-1】呼吸ケアサポートチームの活動
2022年08月26日
8月も残りわずかですね。
ジリジリとした暑さが和らいで朝晩は少し涼しくなり、ようやく秋の気配が感じられるようになりました。
さて今回は「呼吸ケアサポートチーム」についてのご紹介です。
当院の「RST(Respiratory Support Team):呼吸ケアサポ-トチーム」は医師・看護師・理学療法士・臨床工学技士など多職種で構成されるチームで、主に人工呼吸器を装着している患者さんに適切なケアの提供・安全管理ができるようサポートを行っています。

人工呼吸器は患者さんの呼吸を助けてくれる一方、装着期間が長くなると、肺炎や安静による全身の筋力低下、せん妄と呼ばれる一過性の意識精神障害などの多くの合併症を起こしやすくなります。
患者さんの入院環境を整え、人工呼吸器を装着している時からリハビリを行い、口腔のケアや痰の除去などの適切なケアを実施することが、患者さんの早期回復や退院につながります。

そのため、当チームは患者さんが人工呼吸器を装着せずに日常生活が送れるようにするための早期改善に向け、患者さんやご家族に適したサポートを行う活動をしています。
次回は当院の呼吸ケアサポートチームの活動の様子を紹介します。
広報誌をリニューアルしました✨
2022年08月24日
こんにちは。
二十四節気の処暑を過ぎ、だんだんと日の入りが早くなってきましたね。
ヒグラシの鳴く夕暮れには夏の終わりが近いな、と感じるようにもなりました。
さて、当院では広報誌「はらじゅくかわら版」を年4回、発行しています。
ご覧になったことはありますか?
今月発行の「2022年夏号」から、「はらじゅくかわら版」をリニューアルし、内容を充実させるとともにデザインを刷新しました🌻

当院管理栄養士が監修する「ハマの健康レシピ」、リハビリスタッフが健康トレーニングをご紹介する「リハビリ通信」など、皆さんの健康管理のお役に立てるコンテンツを新たに追加しています。
表紙もちょっとオシャレな感じになっています✨
そのほか、「医師が語る疾患」「病診連携施設紹介」などの連載は継続し、医療情報や地域連携、イベントなど、これからも様々な情報を発信していきます。
「はらじゅくかわら版」は1階ロビーで配布していますので、当院にお越しの際にお手に取っていただけると嬉しいです。
ホームページからもダウンロードできます(ホームページはこちら)。
また、広報誌には各種QRコードも記載していますので合わせてご利用ください。
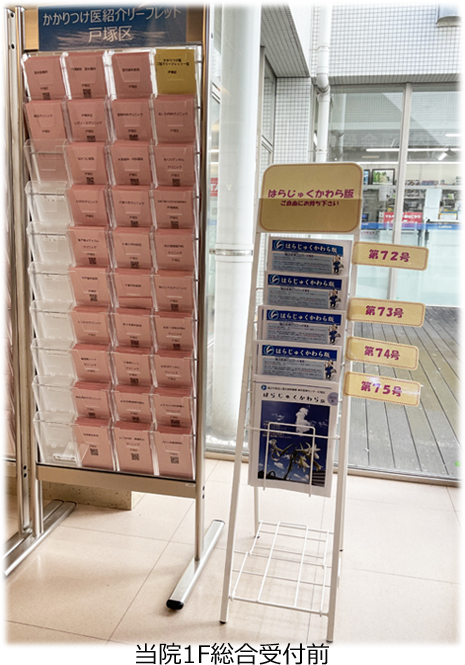
新人看護師研修中!
2022年08月19日
暦の上では秋となりましたがまだまだ暑い日が続いていますね。
夏の疲れが出やすい時期ですので、引き続き体調管理に気を付けてお過ごし下さい。
さて、今日は先日行われた新人看護師研修のお話です。
当院では4月に配属された看護師を対象に年間の教育プログラムを通して看護の基礎研修を実施しています。
今回はその一部の研修内容についてのご紹介です。

まず、医療機器の扱い方について講義を受けたあと、実際の機器を使って演習します。
皆さん緊張しながらも、先輩看護師の指導のもと焦らずにしっかり手順を確認しながら訓練をしていました。
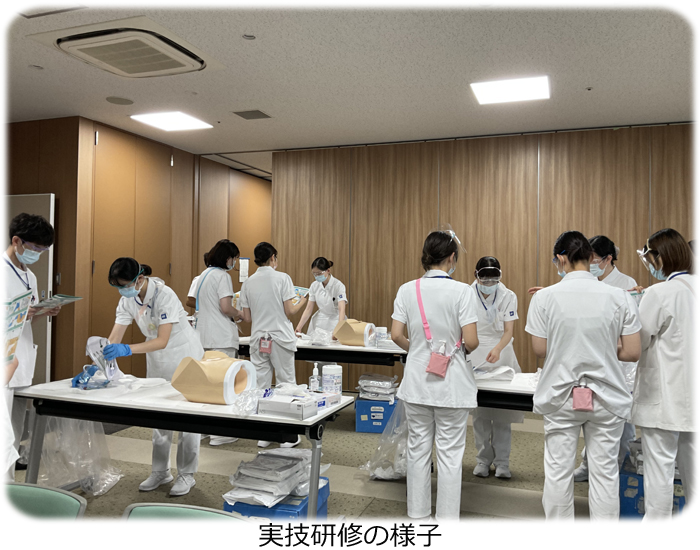
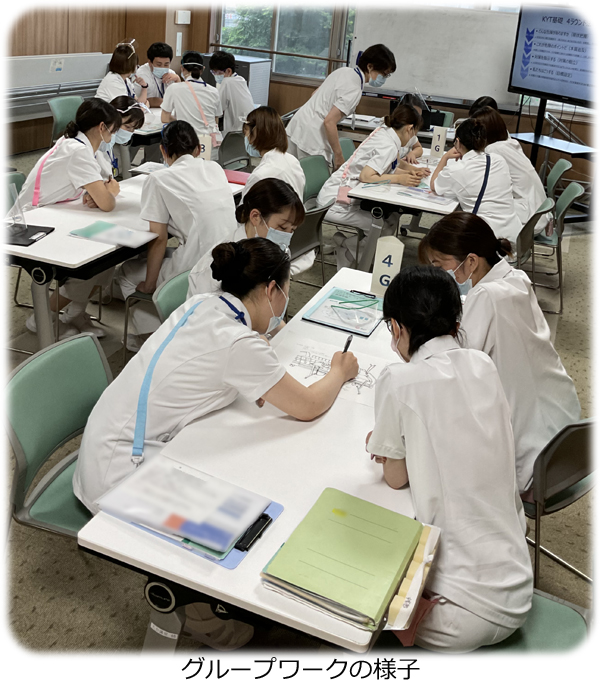
グループワークでは、医療現場におけるインシデントを未然防止するための訓練が行われました。
目の前の光景から危険を察知するための感受性を育てることが目的です。
新人看護師の皆さんは、一つの事象にはたくさんの危険が潜んでいることを学んでいました。
(※インシデント:重大な事故に発展する可能性を持つ出来事)
後日、看護師免許証の交付が各病棟にて行われました。

先輩看護師にお話を伺ったところ、「命を預かる場所でもありますが、患者さんの人生を預かる気持ちで日々患者さんと向き合って欲しいと思います」と新人看護師に向けてコメントをいただきました!
これから悩んだり苦労をすることもあると思いますが、安全でより良い看護が提供できるように頑張ります😊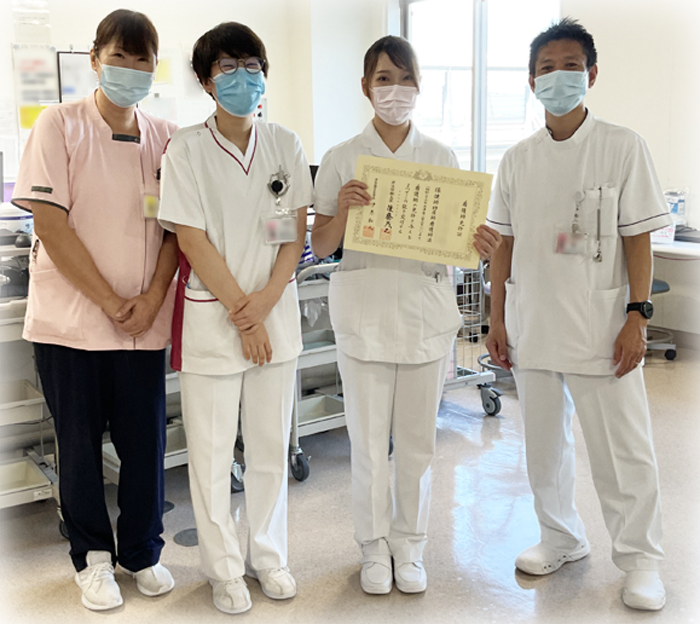
土用の丑の日!おいしいウナギ食べましたか?
2022年08月05日
暦では立秋を迎える時期となりましたが、暑さはピークですね。
今年のお盆シーズンは新型コロナウイルス感染拡大前と同じような激しい混雑が予測されているようですので、お出かけされる方は感染対策に気を付けてお過ごしください。
さて、今日は土用の丑の日のお話です。
土用の丑の日は季節の変わり目の準備期間の意味が込められており、立春・立夏・立秋・立冬の直前にあります。
今年は7月23日と8月4日の2回ありました。
土用の丑の日にはウナギが有名ですが、実はウナギ以外にも「う」のつく「うどん」「梅干し」「胡瓜(ウリ科の食材)」を食べることも良いとされています。
「暑くて食欲がわかない時でもうどんならツルンとおいしく食べることができますね。」と管理栄養士の先生が教えてくれました!
当院では、土用の丑の日(7月23日と8月4日)に特別メニューを提供いたしました。

~メニュー~
◇鰻ちらし寿司 米飯200g
◇冬瓜そぼろ煮
◇即席漬け(キュウリ・シソ)
◇清汁(ミョウガ・はんぺん)
◇カットパイン
暑さで食欲が落ちやすい夏ですが、患者さんに喜んでいただくことができました。
皆さんもさっぱりしたメニューやのど越しの良い食材を選ぶなど工夫をして、しっかり食事を摂りましょう!

【院内保育園】夏祭り
2022年07月29日
早いもので7月ももう終わりですね。
背の伸びたひまわりの先に青空が広がり、強い日差しと厳しい暑さが続いています。
先日、当院の院内保育園にて夏祭りイベントが開催されたのでその様子をお伝えしたいと思います。
夏祭りの午前中は、横浜を中心に活動する和太鼓チーム「昇龍」の方々に和太鼓を演奏してもらい、盆踊りを踊りました。
子どもたちは和太鼓の音を生で聴いたり、叩かせてもらったり貴重な体験ができました。


午後は夕涼み会と題して縁日のお店屋さんごっこです。
保育士さんたちが手作りで色鮮やかなおもちゃをたくさん準備してくれました!





今回は感染対策として、子どものお迎えの時間から順次参加という形での開催だったので全員一緒に…というわけにはいきませんでしたが、親子で一緒に夜店での買い物を楽しむことができ、夏祭り気分を味わった一日でした。
夏祭りなどのイベントはここ数年自粛が続いていたので、子どもたちが浴衣や甚兵衛に着替えてお祭りに参加できる機会ができたことに保護者の皆さんはとても喜んでいました。
来年はもっと賑やかにできるといいですね!
テレビドラマの撮影が行われました!
2022年07月22日
こんにちは。ここしばらく戻り梅雨でジメジメとした日が続いていましたね。
太陽が顔を出すとグッと気温が上がり、厳しい暑さでまさに夏本番です。
さて今回は「ドラマ撮影」情報です!
7月16日土曜夜10時から放送されている日本テレビ系ドラマ「初恋の悪魔」に、当院が撮影協力しました。
捜査中の病院という設定で当院救急外来出入口でのシーンが放送されました。
事件の鍵となる部分に何度か使用されておりましたが、ご覧になられた方お気づきになりましたか?
今回はストーリーが完結していたので、今後の当院の登場シーンはありませんが、第1話での仲野太賀さんの名言セリフやミステリアスコメディーの脚本内容に反響が相次ぎ、トレンドニュースや口コミで注目を集めています。是非皆さんもご覧ください!
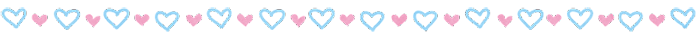
◆番組情報
番組名:日本テレビ 「初恋の悪魔」
放送時間:2022年7月16日スタート 毎週土曜日 夜10:00から
出演者:林遣都、仲野太賀、松岡茉優、柄本佑、伊藤英明、安田顕、田中裕子ほか
◆番組ホームページ
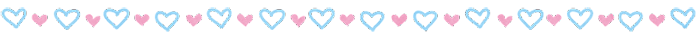

敷地内の草刈りを行いました
2022年07月15日
日差しが強くなり、本格的な夏がやってきました。
今年の夏も厳しい暑さが予想されますが、元気に乗り切りたいですね。
さて、当院では6月下旬に環境整備として職員による「草刈り」が行われました。
昨年(2021年06月16日)も行ったのですが、今年は梅雨の間の晴れ間が多かったので草の成長がとても早く感じます。

◆◆作業前◆◆
左側:正面玄関前、右側:救急車専用入口付近

◆◆作業中◆◆
左側:正面玄関前、右側:救急車専用入口付近
職員からのコメント
「この蒸し暑さの中での草刈り作業は大変だが敷地内が綺麗になるのは気持ちいいです!」

◆◆作業後◆◆
左側:正面玄関前、右側:救急車専用入口付近
ご来院いただく皆さまに気持ちよくご利用いただけますよう、今後も定期的に環境整備を行っていきます。

短冊に願いを込めて
2022年07月08日

暦のうえでは昨日から「小暑」に入りました。「小暑」とは、だんだんと暑さが増していく時期とされていますが、今年は既に記録的な猛暑日が続いています。
病院の正面玄関では、風に揺られた風鈴が音色を響かせており、「五感の涼」を感じることができます。
さて、昨日7月7日は七夕でしたね。
当院では外来ホールにて七夕の飾り付けを行いました。短冊には患者さんや職員の願い事が込められています。
今年の願い事には昨年に引き続きコロナ渦の収束を願うものや、世界平和を願うものが多く見られました。

また、入院中の患者さんにも七夕を楽しんでいただけるように行事食を提供いたしました。

~メニュー~
◇散らし寿司
◇ハンバーグ和風おろし添え・いんげんとコーンのソテー
◇冬瓜くず煮
◇おくら梅酢和え
◇すいか
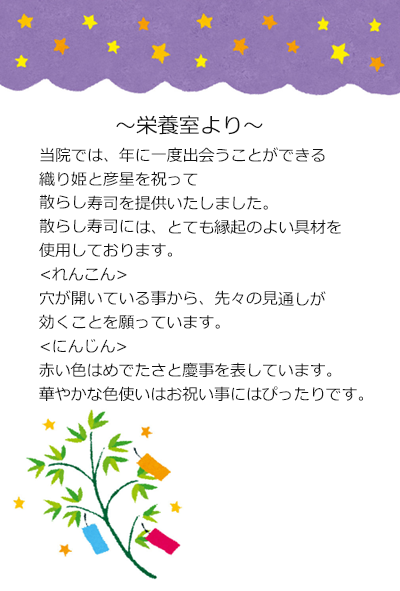
今年は中止が続いていた夏のイベントが開催される地域が多くあるようで、人出も増えています。
引き続き感染対策に気を付けながら夏を楽しみたいですね。
皆さんは七夕にどんな願い事をしましたか?
皆さんの願い事が届きますように…✨


【院内保育園】じゃがいも堀り
2022年07月01日
今週はじめに梅雨が明けました。関東では史上最短の梅雨期間だったそうです。
異例の暑さで既に猛暑日も記録し、長く厳しい夏になりそうですね。
さて、今回は当院の院内保育園のお話です。
毎年、地域のボランティアの方が育てたじゃがいもを、ご厚意で保育園の子どもたちに掘らせていただいています。
今年は地域のボランティアの方が畑の砂利を取り除き、きれいに整備してくださったので、とてもたくさんのじゃがいもが採れました。
保育士さんも「ここ数年の中で一番の豊作です!!」と仰っていました。


掘ったじゃがいもを小さな手で何度も運ぶ園児の姿がとてもかわいいですね。
たくさん採れたのでじゃがいも堀りにはまだ行けない小さな子どもたちのクラスにもお裾分けしました♪

保護者の皆さんも立派なじゃがいもを見て驚き、笑顔で喜んでくれました。
皆さん各家庭でおいしくいただいたそうです。
来年の収穫も楽しみですね!


「看護の日」川柳結果発表🎊
2022年06月24日
敷地内に咲く紫陽花がひと雨ごとに色を変えていて、その変化を見ることが日々の楽しみになっています。
さて、先日5月20日のブログ「看護の日」にて「看護川柳」についてご紹介させていただきました。
今日はその投票結果を発表します。
表彰された上位2チームの看護川柳はこちらです。
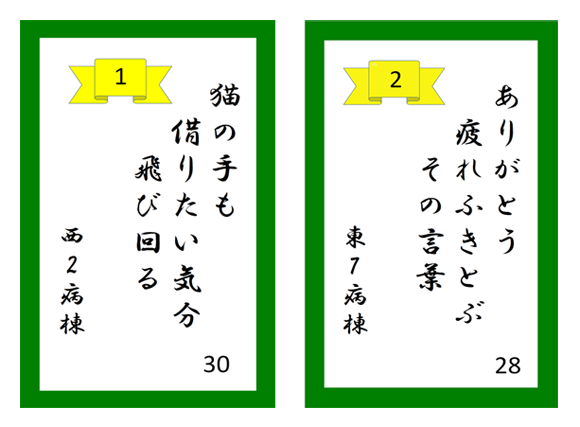
今回1位に選ばれたチームにインタビューをしました。
🔶Q1 看護川柳はどんなお気持ちで作成されましたか?
「患者さんのもとへ今すぐにでも行きたい!ベッドサイドへ今すぐ行きたい!でもナースコールが鳴ってすぐには行けないので、飛び回るように走っている様子を書きました。そんな時、もっと人手があるといいなぁ、猫の手も借りたいなぁという気分です。」
🔶Q2 看護の魅力について教えて下さい!
「看護師の表情や接し方や、技術によって患者さんが笑顔になり、元気ややる気につながることが魅力です。そして、患者さんからの「ありがとう」という言葉とともに、元気で退院される姿を見ることが嬉しいです。」
今回の看護川柳を通じて、改めて多岐にわたる看護業務を垣間見ることができました。
今後も患者の皆さんに安心の看護を提供できるよう取り組んでまいります。
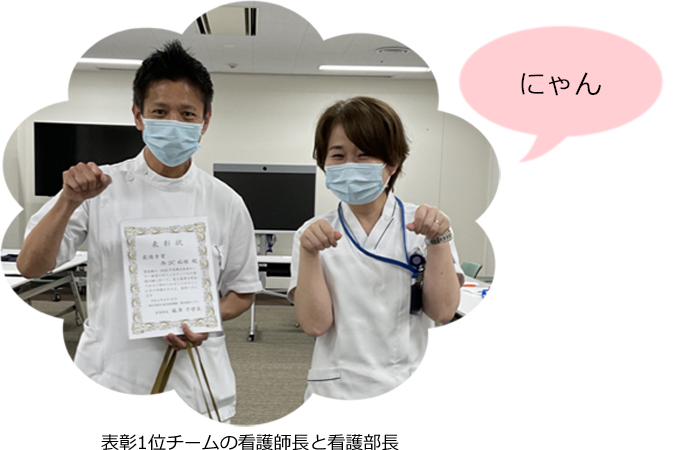
嬉しいメッセージが届きました
2022年06月23日
梅雨の晴れ間の青空は、すっかり夏色になりましたね。
さて、当院では、患者さん、ご家族を中心に様々なお便り、お問い合わせを頂くことがあるのですが、先日、近隣の大正小学校の児童から当院あてに感謝のメッセージをいただきました。
内容は当院の職員への応援の言葉と共に、当院に対する信頼と期待について書かれたものですが、当院の存在が地域に安心を届けられていると知り、とても嬉しく、励みになりました。
ありがとうございました。
なお、このメッセージは当院外来ロビー(1階エスカレーター付近)に掲示させていただいております。
これからも地域の期待(安心を届ける)に応えられるために、地域の皆さんと共に、当院職員も成長していきたいと思います。
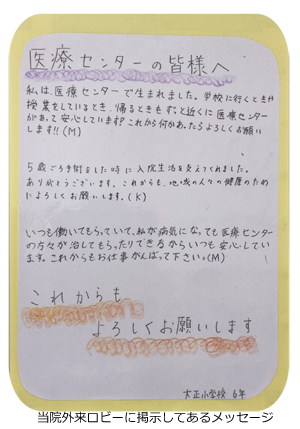
永年勤続表彰伝達式
2022年06月17日
先週、関東では昨年より早く梅雨入り発表がされましたね。
しばらく洗濯に悩む日が続きます。
先日、当院職員の永年勤続表彰伝達式が行われ、勤続30年の方が6名、20年の方が11名表彰されました。
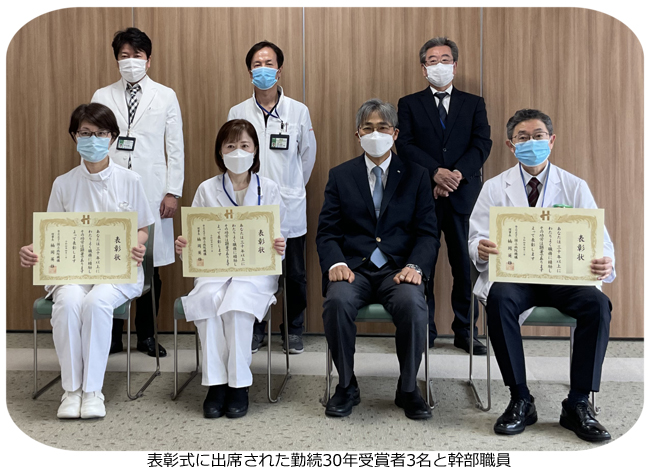
鈴木院長からは「30年前、20年前から医療は大きく進歩し、社会には大きな変化がありました。その中で勤務を継続されたことは大変素晴らしく輝かしいことだと思います。おめでとうございます!」とお祝いのメッセージが贈られました。

今回、表彰された勤続30年の職員3名にインタビューし、「30年」を振り返っていただきました。
🔶Q1これまでの勤務で一番嬉しかったことは何ですか?
「診療関係で一つだけ挙げるのは難しいですが、それ以外では平成22年3月の病院の更新築に関われたことです。周囲に助けられて30年間続けられたこと自体がとても嬉しく思います。」
「患者さんから「看護師さん」ではなく、名前で呼ばれたことや退院時にお礼のお手紙をもらったことです。ここまで勤務できたのも、諸先輩方やスタッフの支えのおかげです。」
「多職種で取り組んだ料理教室で、最初は不安な顔をされていた患者さんが、日々抱えている不安や疑問が解消し、笑顔で「ありがとう」と言ってもらえたことです。これまで沢山の方々に支えて頂き今日がありとても嬉しく思います。」
🔶Q2 横浜医療センターの職員としてのやりがいは何ですか?
「患者さんと気持ちの通じるやりとりができた時に“医療という仕事”にやりがいを感じることができます。」
「管理職ですが、上司は自分に仕事を任せてくれます。任せられた仕事の成果を認められた時や目標を達成した時にやりがいを感じます。」
「定期的な栄養指導により、食生活が良い方向に変わり、検査結果に成果がみられ、今までよりも元気になったとき、やりがいを感じます。」
表彰された皆様、このたびは誠におめでとうございます。今後もさらなる活躍を期待しています。
【チーム医療の活動紹介4-2】糖尿病チームケアユニット
2022年06月10日
今日は前回に続き、糖尿病チームケアユニットの活動をご紹介します。
週1回開催される糖尿病チームケアユニットのカンファレンスでは、患者さんの生活習慣や家庭環境などを、皆で情報共有し、退院後の生活を見据えた治療を検討しています。
現代はストレス社会といわれていますが、糖尿病患者さんにおいても、まわりには言えない、家族にも相談しづらいなど、糖尿病という病気自体にストレスを感じる方が少なくありません。
そのため、通院をやめてしまう方もいます。ただ血糖値を良くするだけでなく、患者さんの負担となっている感情についても意識し、出来る限りストレスが少なくなるような生活習慣の提案、治療法を心がけています。
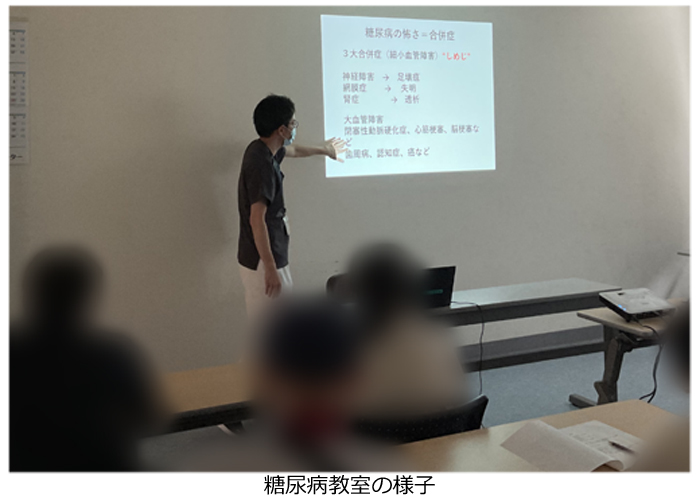
また週1回、患者さんを対象に「糖尿病教室」を開催しています。
糖尿病は患者さんがご自身の病状を把握して、どのような食事・運動習慣がいいか、使用している薬についても理解して頂くことが重要です。
そのため、少しでも患者さんの知識が深まり、病気とうまく付き合うきっかけとなりえるように、各職種がお話しします。
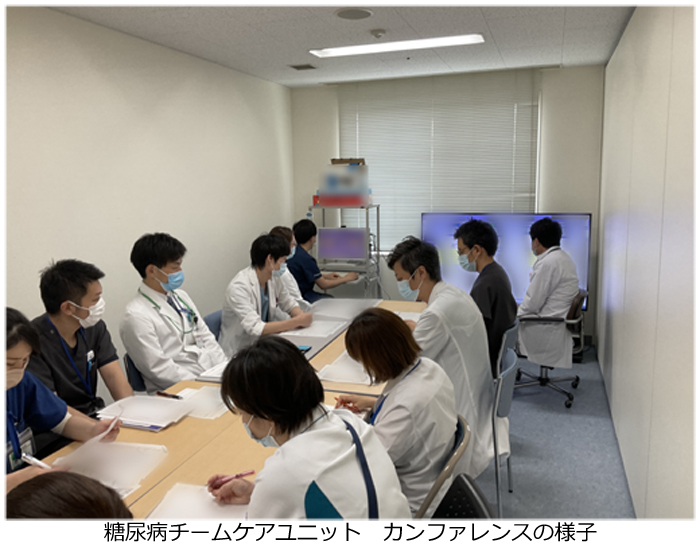
患者さんが当院の入院を通じて、糖尿病という病気に関して少しでも気持ちの負担が少なくなり、うまくつきあえることを目指して、これからもチーム一同努力していきます。
今後も随時、チーム医療の紹介をしていきますのでご期待ください。
【チーム医療の活動紹介4-1】糖尿病チームケアユニット
2022年06月03日
だんだんと日差しの強さが増し、夏の足音が近づいてきました。
先月にくらべて湿度が上がってきたように感じます。
今回は「糖尿病チームケアユニット」についてのご紹介です。
当院では、「糖尿病チームケアユニット」と呼ばれる、看護師、管理栄養士、薬剤師、臨床検査技師、理学療法士、医師で構成されるチームで、糖尿病診療における様々な活動をおこなっています。

糖尿病は、インスリンというホルモンが十分に働かないために、血液の中の糖(ブドウ糖)がふえてしまう病気です。
この病気の怖いところは、自覚症状がほとんどないことです。知らぬ間に、病状が進行し、神経や眼、腎臓などの内臓、そして心臓、脳などの血管までも、むしばんでいきます。
この糖尿病は、現代医学では、完治することはない病気ですが、正しい治療を続けていけば、糖尿病でない人と変わらない生活を送ることができます。
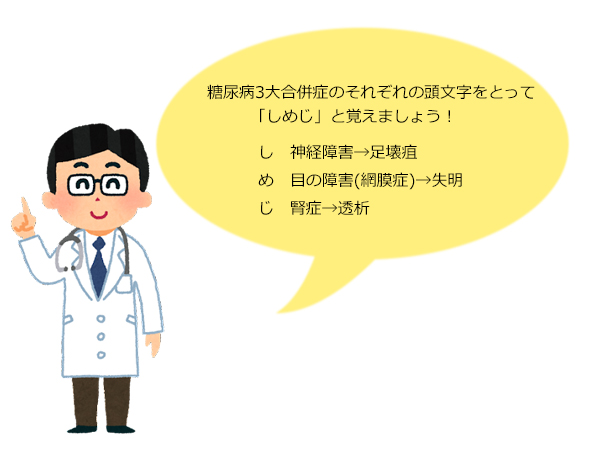
糖尿病の治療は、食事や運動をふくめた生活習慣の振り返りが重要となります。
糖尿病の治療の主役は、患者さんであり、医療者の役割は、患者さんがうまく病気と付き合えるようにサポートすることにあります。
次回は、当院の糖尿病チームケアユニットの入院診療における活動をご紹介します。
おいしいドリンクをいただきました
2022年05月27日
こんにちは。病院周辺の木々の緑も深みを増してきました。
時々吹き抜ける風がとても心地よく感じられます。
先日、日本コカ・コーラ株式会社より、新型コロナウイルスと戦う医療従事者への支援として、「おいしいオーツ麦ミルク」をいただきました。
業務の合間に皆でおいしく飲ませていただきました。
豆乳に似た味ですが、豆乳が苦手な方でもクセがなく飲みやすいという感想が多くありました。
温かいご支援に職員一同心より感謝申し上げます。ありがとうございました。
なお、本件は西横浜国際総合病院理事長 高木様からのご紹介でお話をいただいております。
合わせて御礼申し上げます。

「看護の日」イベント実施中です
2022年05月20日
こんにちは。今日は現在実施中(5月12日から5月31日)のイベントについてご紹介します。
5月12日は「看護の日」です。近代看護の母「ナイチンゲール」の誕生日にちなんで制定され、各地でさまざまなイベントが行われています。
当院では看護の日のイベントとして、当院の看護師が看護業務への思いを五七五の川柳にした「看護川柳」を掲示し、人気投票を行っています。
看護業務のやりがいや患者さんへの思いなど、看護師の気持ちが詰まった個性的な作品がたくさんあり、とても感慨深いです。
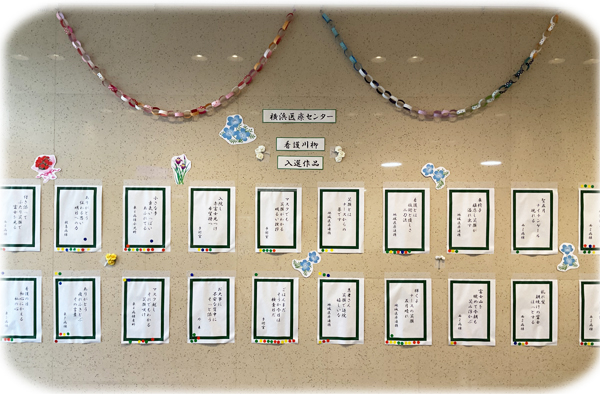
なお、投票していただいた方には、看護の日グッズ(写真)を配布しています。
(配布数には限りがあります)

また、看護師の仕事をもっと皆さんに知って頂くために、専門・認定看護師の仕事内容をご紹介するポスターの掲示もしています。
以前にブログでふれた専門・認定看護師の掲示もあります。
※専門・認定看護師とは?
特定の看護分野において、複雑で解決困難な看護問題への対応が可能な、熟練した看護技術と知識、優れた実践能力のある人に対して、日本看護協会から認定を受けた看護師
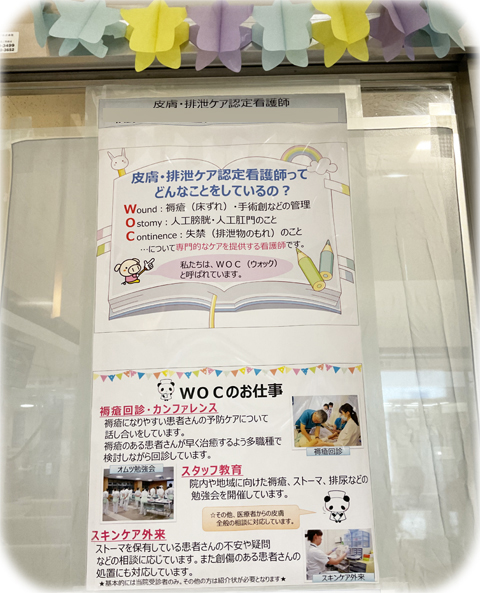
関連記事:当院ブログ「WOCナースの活躍」もご覧ください。
いずれも当院の1階ロビーにて、5月31日(火)まで実施していますので、ご来院の際にはぜひご覧ください。
横浜医療センター版 「大改造!!劇的ビフォーアフター」
2022年05月13日
こんにちは。さわやかな季節がやってまいりましたね。
今回は、当院の小さな「大改造!!劇的ビフォーアフター」の紹介です。
当院の医師等の執務室(病院では通称、「医局」と呼んでいます)がここ数年医師の増員により手狭となっておりました。
そこで今回職員用図書室を改修しスペースの半分を医局にしたうえで「研修医の医局」としました。

実際に利用している当院の研修医にインタビューしたところ「研修医同士でコミュニケーションを図りながらともに学べる環境」と好評でした。

なお、少し狭くなってしまった図書室ですが本棚を減らしたり、デッドスペースとなっていたスペースを削減しているので図書閲覧や自習等、図書室としての大きな機能は損なわず利用できています。
良いコミュニケーションや職場環境づくりはより良い病院運営にとってとても大切なことだと考えています。
今後も「働きやすい病院」を目指して取り組みを行っていきます。
研修医の日々の様子「教育研修部ニュースレター」も是非ご覧ください。
こどもの日(その2)
2022年05月11日
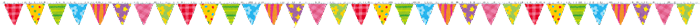
こんにちは。
5月5日は「こどもの日」でしたね。関東地方は爽やかに晴れて外出される方が多く感じました。
小児病棟の飾り付けに続いて、今回は当院で提供した「こどもの日」の特別メニューを紹介します。

~メニュー~
◇たけのこご飯
◇鶏木の芽焼き 付け合わせ ベジタブルソテー
◇田楽(さといも・こんにゃく)
◇白菜人参生姜和え
◇甘夏柑
◇和菓子(緋鯉)
当院ではこのように季節の行事に合わせてお食事を提供していますが、いつも患者さんからご好評をいただいています。入院中でもお食事から季節や行事を感じていただけたらと思います。
二十四節気の立夏を迎え、暦の上では初夏の季節となります。気温が高くなってくる時期なので、水分補給も忘れずにしてください。
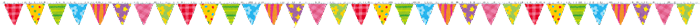
こどもの日
2022年04月28日

こんにちは。ゴールデンウィーク目前ですね。
街中のあちこちでこいのぼりが泳いでいるのを見かけます。
当院小児科病棟スタッフがこどもの日に向けて、病棟の壁面にこいのぼりの飾り付けをしました。
飾り付けは退職したスタッフから贈られたものもあります。
コロナ禍以前では、保護者の方と一緒に描いた絵を飾ることもありました。
入院中のお子さんたちは、こいのぼりの飾り付けを喜んで見ています。

こどもの日にこいのぼりを揚げる由来としては諸説ありますが、「強く流れが速い川でも元気に泳ぎ、滝をものぼってしまう鯉のように子どもたちがたくましく元気に大きくなること」を願う意味が込められているそうです。
小児科病棟のスタッフたちは入院しているお子さんたちの「寂しい」気持ちを和らげたり、楽しいことを考えたりと工夫しています。
これからも季節に合わせた飾り付けなどで子どもたちに笑顔を届けたいと思っています。


横浜市医師会より学術功労賞の表彰をいただきました
2022年04月22日
このところ天気が不安定な日が続きますね。時折、晴れ間に見上げる木々の若葉がまぶしいです。
さて、先日当院副院長の宇治原医師が横浜市医師会の「学術功労賞」を受賞しました。
「医学、医術の研究又は地域における医療活動により、医学、医療の発展又は社会福祉の向上に貢献し、特に功績顕著なる功労者」に贈られる賞です。
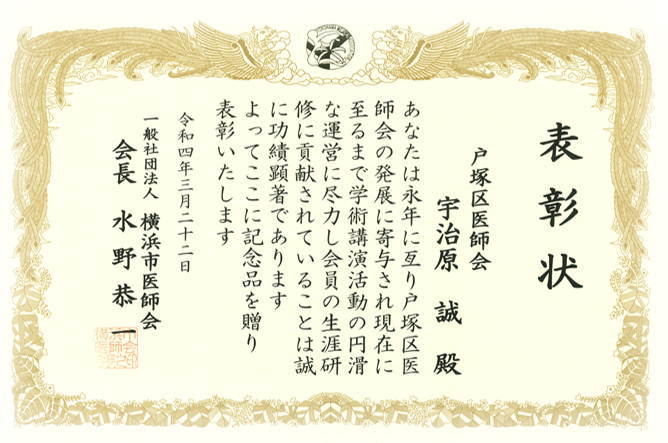
宇治原副院長は、常に地域の先生方との関わりを大切にし、これまで多くの講演会や研究会などで講師を務めています。
コロナ禍によりオンライン中心になった現在でも、日々変化をしていく医療や、医療を取り巻く環境について地域の先生方との情報共有や意見交換を行っています。
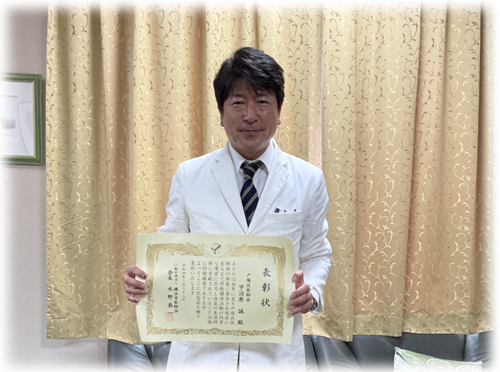
地域医療の質の向上に貢献することは当院の使命であり、病院としても今回の受賞を嬉しく思っています。今後とも地域医療への貢献に取り組んでいきます。
マンモグラフィ検診施設・画像認定を取得しました
2022年04月15日
こんにちは。
春風に吹かれて、桜の樹も若葉を揺する季節となってきましたね。
さて、今日は乳がん検診で使用するエックス線撮影装置「マンモグラフィ」についてのお話です。
NPO法人『日本乳がん検診精度管理中央機構』ではマンモグラフィ検診および診療の精度を高め、維持するために、一定の基準を満たした施設を「マンモグラフィ検診施設・画像認定施設」として認定しています。このたび当院はこの認定を取得しました。
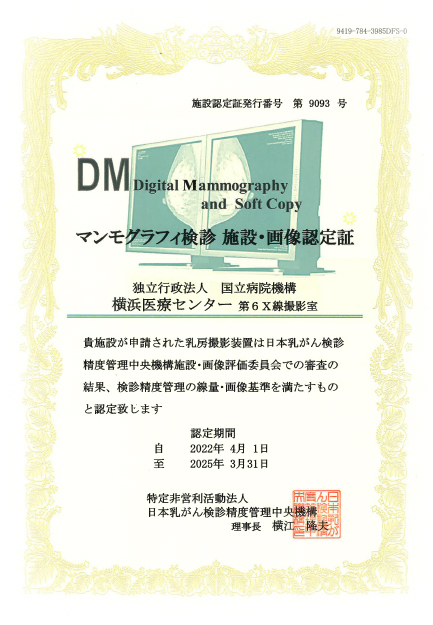
質の高い検診を受けるには、撮影装置が仕様基準を満たしているだけでなく、撮影装置の精度管理が適切に行われていることが重要であり、今回の認定は当院の設備・運用が適切であると評価されたものです。

乳がん検診は40歳以上の女性に、2年に1回の受診が推奨されています。
当院では上記のとおり精度の高い設備のもと、撮影技術や精度管理の講習を修了した女性技師が対応していますので、早期発見のためにもぜひ受診をご検討ください。
【乳がん検診の申し込み】
総合受付[初診窓口](受付時間 平日14:00~17:00)
TEL 045-851-2621(代表)
※詳細はこちらをご覧ください。
関連記事:当院ブログ「J.M.Sプログラムに参加しました」をご覧ください。
「こすずめ号」のバス停ができました
2022年04月13日
こんにちは。早くも初夏の空気になってきましたね。
今日は4月から始まった新しい事業のご紹介です。
戸塚区小雀町周辺を運行する小型乗合バス「こすずめ号」の運行ルートが、4月1日から当院まで延伸され、当院敷地内にバス停が設置されました。
このバスは、道幅が狭く路線バスが通らない小雀浄水場付近を周回し、大船駅東口を発着する13人乗りの小型バスです(運行事業者:株式会社共同)。
小雀町内会の皆さんが中心となって事業を開始し、地元企業が協賛、横浜市が運営支援をしています。1日12便運行されており、そのうち昼間の5便が当院に発着しています。

今回の延伸により、小雀町から原宿エリアへのアクセスが向上します。
小雀町にお住まいの方は、当院への通院はもちろん、原宿エリアでのお買い物やご用事の際にもぜひご利用ください。
※こすずめ号について(横浜市道路局ホームページ)
気持ちも新たに新年度を迎えました
2022年04月08日
今週はじめに降った冷たい雨で、桜の花は舞い落ちて、若葉の緑が覗いています。
新年度を迎え、当院では4月1日に辞令交付式を行いました。
コロナ禍ですので、感染防止対策を十分に行ったうえで実施しました。
院長からは医療従事者としての心構え、地域における当院の果たすべき役割などについて訓示がありました。
心機一転、さまざまな場所から当院へ配属された職員からは、少しだけ緊張が伝わってきました。

辞令交付式後は、新採用者・転入者向けのオリエンテーションが行われました。
院長の講義では、今年の大河ドラマの舞台は鎌倉ですが、現在の戸塚区にあたる地域は1939年に横浜市に編入する前は「鎌倉郡」でした・・・という、旬な話題も盛り込みながらの戸塚区の紹介もありました。
ここ戸塚は鎌倉に由来のある土地だったのですね!
これからたくさん戸塚と当院の良さを知って欲しいと思います。
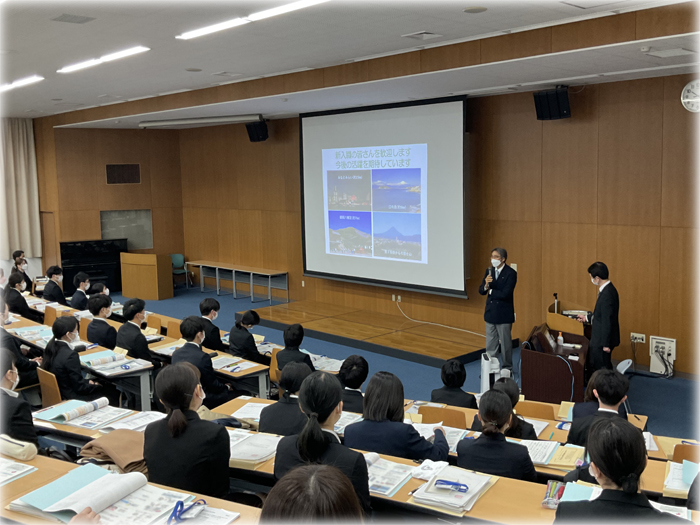
また、4月4日~6日には看護部のオリエンテーションが行われました。
「感染管理」や「感染防止に必要な看護技術」など、現在のコロナ禍における重要な内容も含まれていました。
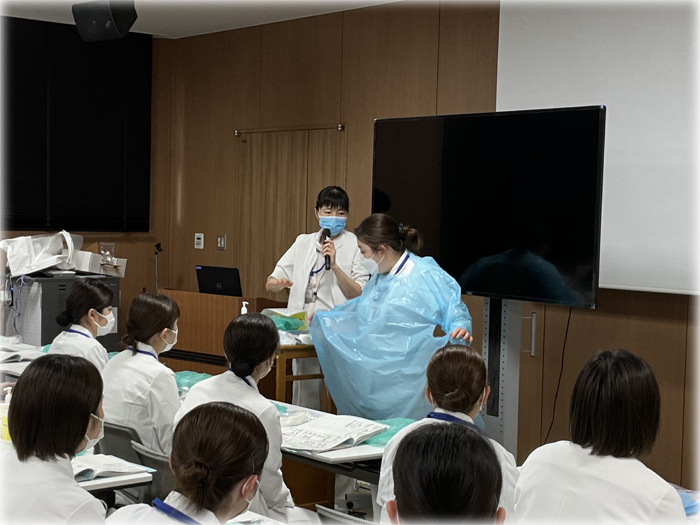
初日の研修を終え、帰宅時に院内の桜をバックに写真を撮る新入職員を見かけました。
嬉しいこと、楽しいことがたくさん待っていると思います。もしかしたら、辛いことがあるかもしれません。同期や先輩との絆を深めつつ、今の気持ちを忘れずに頑張って欲しいと願います。
しばらくは不慣れなところもあるかもしれませんが温かく見守ってくださるとうれしいです。
横浜医療センター敷地内の桜が満開です🌸
2022年04月01日
こんにちは。今週始めに当院敷地内の桜が満開となり、見ごろを迎えました。

横浜では平年より4日早く、昨年より1日遅い満開となるそうです。
コロナ禍で迎える3年目のお花見シーズンとなりますが、去年に比べて制限が緩和されているお花見スポットもあるそうです。
当院のお花見スポットを少しご紹介します。
看護学校近くにある桜です。立派に咲き誇っている姿に思わず足を止めてしまいました。
桜に負けじと、その存在感をアピールする松の木も風情があります。

桜ハンティングをしていたら、お散歩中の方がきれいに咲く桜を写真に撮る姿が見られました。

毎年桜が咲くと、春が来たことを実感します。
淡いピンクに色づく花の見ごろは短いですが、感染予防の工夫をしつつ、お花見を楽しみましょう。
災害への備え
2022年03月25日
こんにちは。この時期らしく寒暖差が大きい日が続いています。気温の上昇に伴って、桜の開花が例年より早くなったそうです。本格的な春の足音が聞こえてきます。
先週は東北地方で大きな地震がありました。被害に遭われた方に心よりお見舞い申し上げます。
当院は「災害拠点病院」として、日頃から災害対応訓練を実施したり、被災地に医療チーム(DMAT)を派遣したりして、災害への備えを行っています。
このたび、当院では災害医療機能の更なる強化のため、災害用簡易ベッドを購入しました。
折り畳み式で簡単に持ち運びができるので、発災後に素早く設置できます。外来ロビーなどに展開し、患者さんの受け入れを行います。また、寝袋などの災害備蓄品も合わせて充実させています。


災害時、当院を含め市内に13か所ある「災害拠点病院」では重症の患者さんを受け入れます。
一方、中等症は「災害救急病院」、軽症は「診療所」と役割を分けています。
これは、一度にたくさんの負傷者が発生する災害では、大病院に軽症の患者さんが集中すると、すぐにパンクし、助かる命が助けられなくなることがある、ということでトリアージ(傷病者の振り分け)がとても大事だからです。
皆さんも、災害への備えとして、ケガをしたときにどの医療機関にかかれば良いのか、あらかじめ調べておくことをお勧めします。
【参考】横浜市ホームページ「災害時の医療提供体制」
第28回クリティカルパス大会を開催しました(その2)
2022年03月18日
今日は前回お知らせしたパス大会の「最優秀賞」をご紹介します。
今回のパス大会には全8チームが参加し、「最優秀賞」は1チーム、「優秀賞」は2チームが受賞しました。
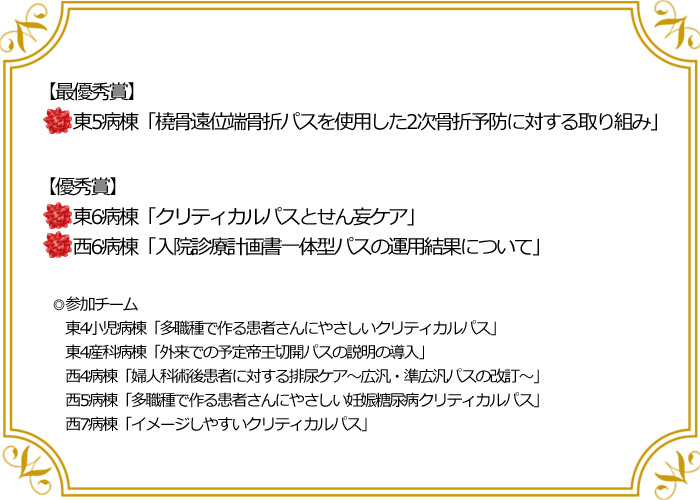
最優秀賞は、骨折した人(特に骨粗鬆症の人)が、当院の治療後に再度骨折しないよう予防(2次骨折予防)する取り組みを行った東5階病棟のチームでした。
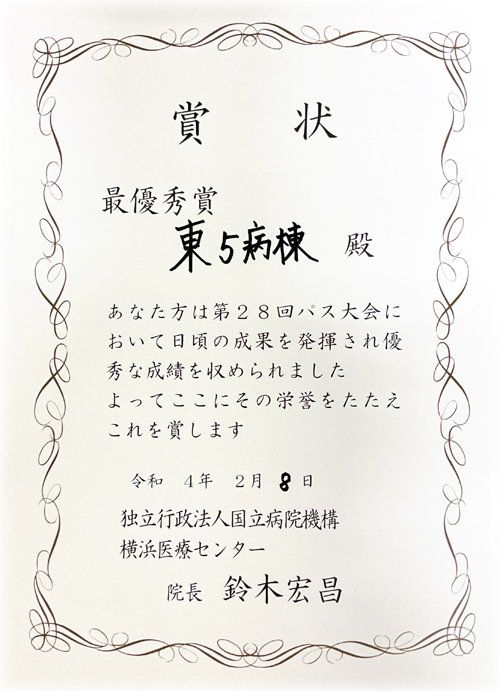
当チームは多職種で連携しながら、対象の患者さんに対して、骨折の治療だけでなく、骨粗鬆症や生活習慣の指導などの働きかけを積極的に行っています。
そして今回、橈骨遠位端骨折のパスを見直して、退院後でも骨粗鬆症の検査やその治療につながるようにするなど、患者さんへの指導内容をさらに充実させました。こうした取り組みが評価され、受賞となりました。
院長講評より引用となりますが、このコロナ禍は「効率的な医療の流れ」を求めています。今後も効率と医療の質を上げるよう、更なる改善を実施してまいります。
第28回クリティカルパス大会を開催しました(その1)
2022年03月11日
2月上旬~中旬に「第28回横浜医療センタークリティカルパス大会」を開催しました。
「クリティカルパス(略してパス)」とは、医療スタッフと患者さんが治療の情報を共有するために作成する、「入院中の予定をスケジュール表のようにまとめた診療計画書」のことです。
パスは大きく分けて2種類あり、院内のみで利用するパスを「院内パス」、地域にまたがって利用するパスを「地域連携パス」と呼んでいます。
パスは一度作成して終わりではなく、効率的で安全な医療の提供を目指し、パスの質の向上のために改善活動を行います。当院では各病棟や部門が、新規のパスや改善したパスの運用について発表する場として、毎年「クリティカルパス大会」を開催しています。

今年で28回目となり、「地域連携パスを意識した院内パス大会」という位置づけで行いました。
なお、例年は発表形式で行われていましたが、コロナ禍となり昨年と今年は掲示形式で開催しました。
パス大会の「最優秀賞」は次回のブログでご紹介したいと思います!
病院機能評価の認定を受けました
2022年03月09日
こんにちは。3月に入ってから、日中はだいぶ暖かくなり過ごしやすくなりましたね。
病院からきれいに見えていた富士山が霞んで見える日が増え、春が近いと感じます。
以前、病院ブログ「より質の高い医療を届けるために(2021年09月10日)」でご紹介しましたが、当院は2021年9月に病院機能評価を受審し、2022年2月4日付で「日本医療機能評価機構認定(一般病院2)」の更新認定を受けました。今回で4回目の認定となります。

また同時に、救急医療・災害医療分野において、より高い水準が求められる「高度・専門機能(救急医療・災害時の医療)」についても初回認定を受けることができました。
こちらは神奈川県内で初めての認定機関となります。
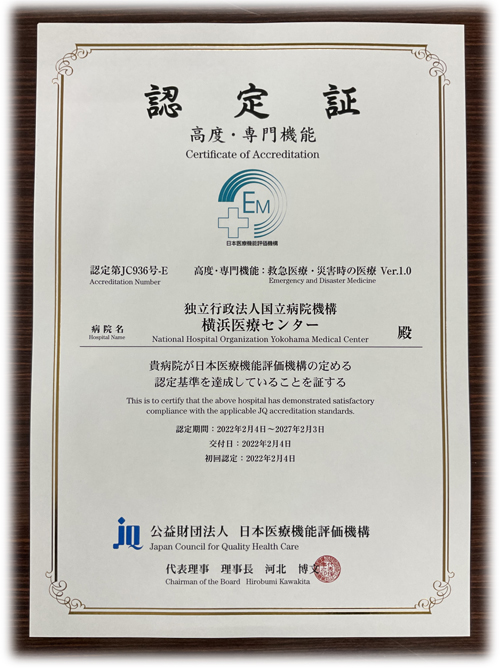
今後も患者さんにより質の高い安全で安心な医療をお届けできるよう、スタッフ一同日々研鑽してまいります。
お雛祭り
2022年03月04日
こんにちは。今週始めに河津桜が満開になりましたね。
昨年は「河津桜まつり」は中止でしたが、今年は規模を縮小して開催されました。 春はすぐそこまで来ています。
昨日(3月3日)は女の子のすこやかな成長と健康を願う「雛祭り」がありました。
今年は当院でも外来ホールに雛人形を飾りました。

雛人形を飾るときに男雛(お内裏様)と女雛(お雛様)の左右の位置を迷われる方がいるのではないでしょうか。
お雛様には「京雛」と「関東雛」があり、大きな違いはお内裏様の位置が「京雛は向かって右」、「関東雛は向かって左」になるそうです。
そのほかにお顔にも違いがあり、「京雛は切れ長の目に鼻筋の通った細面のお顔」、「関東雛は大きな目、口元がふっくらとした可愛らしいお顔」だそうです。
当院のお雛様はどちらか見分けることができませんでしたが、飾ってすぐに小さなお子さんが嬉しそうに見に来てくれました。
さて入院患者さんには、夕食に「お雛祭り特別メニュー」をご用意しました!

★メニュー:ちらし寿司、鶏風味焼き・焼き葱添え、若竹煮、菜の花のお浸し、
雛あられ、オレンジ★
入院中は外出が難しいですが、患者さんに春を感じていただけたら嬉しいです。
ジャスミン茶のご寄付をいただきました
2022年02月25日
こんにちは。2月は中学や高校、大学受験シーズンですね。
コロナ禍の受験ということで、柔軟な対応をとっているところも多く見られます。良くも悪くもコロナに慣れてきたと言うことでしょうか。
当院スタッフも第6波の中、地域医療を守るべく毎日奮闘しています。
そうした中、医療施設への支援として、株式会社ローソン様より「白葡萄ジャスミン茶」のご寄付をいただきました。
ジャスミン茶は、ベースとなる緑茶などの茶葉の部分にジャスミンの香りをつけたもので、リラックス効果、鎮静効果があると言われています。
今回ご寄付いただいたものは、ジャスミンのさわやかな香りに白葡萄のフルーティな香りがプラスされて、休憩時間にぴったりのお茶でした。みんなで美味しく頂きました。

当院には院内売店としてローソンが入っているのですが、本格的な店頭ドリンクメニューはとても人気があります。ご来院の際にはお立ち寄りください。
あたたかいご支援を糧に、引き続き頑張ります。ありがとうございました!
St Valentine's Day
2022年02月18日
こんにちは。三寒四温のうちに、季節は冬から春へと移りつつあるようです。
梅の花も咲き始め、窓から入る春めいた日ざしがうれしいこの頃です。
イベントの多い冬。今週始め(2月14日)にはバレンタインデーがありました。主に女性が恋人や友人へチョコレートを贈ることは日本ならではの文化だそうで「日本で1番チョコレートが売れる日」とも言われています。海外では異なる文化があるので、一部ご紹介します。
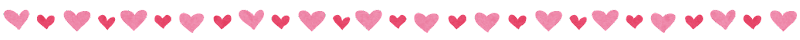
■イギリス
「想いを寄せる人にひそかに想いを伝える日」として、カードに名前を書かずに「From Your Valentine」などのメッセージを贈ります。
■アメリカ
日本とは反対に、男性から女性にプレゼントを送るのが一般的で、プレゼントの他にお芝居を観に行ったり、ディナーを楽しんだりして過ごす方も多く、街も賑わいます。
■ベルギー
「お世話になっている人に感謝を伝える日」として、恋人や夫婦でなくても贈り物をします。男性から女性へプレゼントするのが一般的です。
■イタリア
男性から女性へ贈り物をするのが主流で、バラの花が贈り物の定番です。バレンタインをきっかけにプロポーズする男性も多いようです。
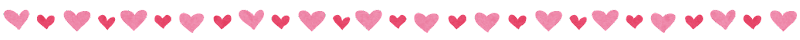
さて当院の入院患者さんには、夕食に「バレンタインデー特別メニュー」をご用意しました!

★メニュー:ごはん、さわら味噌漬け焼き・ブロッコリー添え、大根サラダ、小松菜磯和え、
キウイフルーツ、バレンタインハートプリン★
栄養管理室スタッフからの愛が、患者の皆さんへ届きますように・・・💓
感謝状をいただきました
2022年02月10日
北京2022冬季オリンピックが開幕し、連日アスリートたちが素晴らしい闘いを繰り広げています。
スキージャンプの金メダルは感動しました。今後も冬季ならではの雪上、氷上の熱い闘いに期待したいですね。
一方、半年前に開催された東京2020オリンピック・パラリンピックの日本選手の活躍や印象的なシーンが記憶に新しい方も多いと思います。
当院は同大会の事前キャンプ及び大会期間中、横浜市の依頼により、医師をはじめとしたスタッフを派遣し、医療アドバイザーとして大会関係者の傷病対応や新型コロナウイルス感染症の対応や助言を行いました。
そのことについて先日、横浜市から感謝状をいただきましたので、ご紹介させていただきます。
感染拡大による無観客開催など、異例の大会となりましたが、当院を含め横浜市内の病院が協力し合って、大会の開催に貢献することができました。
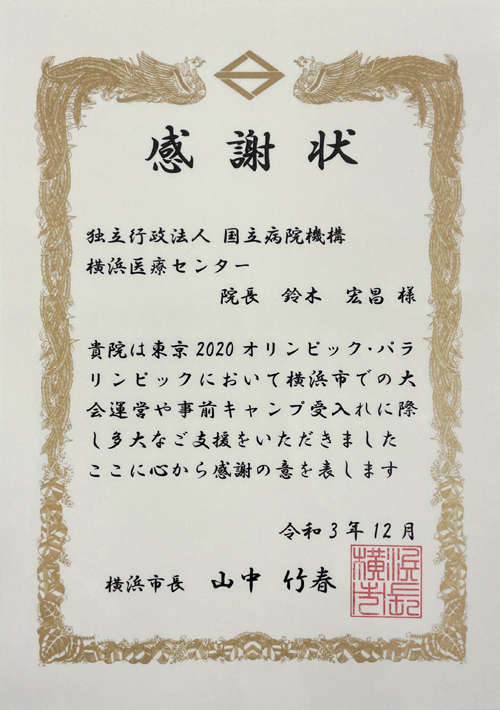
北京2022冬季オリンピック・パラリンピックでの日本選手のご活躍をお祈りします。
がんばれ!!日本!!
節分と豆まき
2022年02月04日
こんにちは。今日は立春です。暦の上では春となり、梅のつぼみが膨らんできました。
相変わらず寒い日が続いていますが、春はそこまで来ていますね。
さて、昨日は「節分」でしたね。
「季節の変わり目は邪気が入りやすい」と考えられ、邪気を祓い清め、一年間の無病息災を祈る行事です。今年は「コロナ退散」の願いを込めて、豆まきをする方も多かったのではないでしょうか。
ところで豆まきで投げる豆は、関東では炒った大豆ですが、地域によっては落花生のところがあるそうです。豆まき後の掃除が楽で、大豆に比べ落花生なら拾いやすいですね。

当院の入院患者さんには、夕食に「節分特別メニュー」をご用意しました。

★メニュー:ごはん、鯵の塩焼き・大根おろし添え、野菜豆、いんげん胡麻和え、清汁、
オレンジ、節分和菓子・赤鬼★
季節の変わり目ですので、どうぞご自愛ください。
【チーム医療の活動紹介 3-2】排尿ケアチーム
2022年01月28日
今日は前回お知らせした排尿ケアチームのラウンド(病棟回診)の様子をご紹介します。
当院の排尿ケアチームは、毎週火曜日に対象病棟(西7・東7・東6・西5・東5・西4)をラウンドしています。
泌尿器科医師・所定の研修を終えた看護師・理学療法士・皮膚排泄ケア認定看護師などの多職種で構成され、排尿障害のある患者さんの状態を把握し、適切なアドバイスや支援を行うよう努めています。
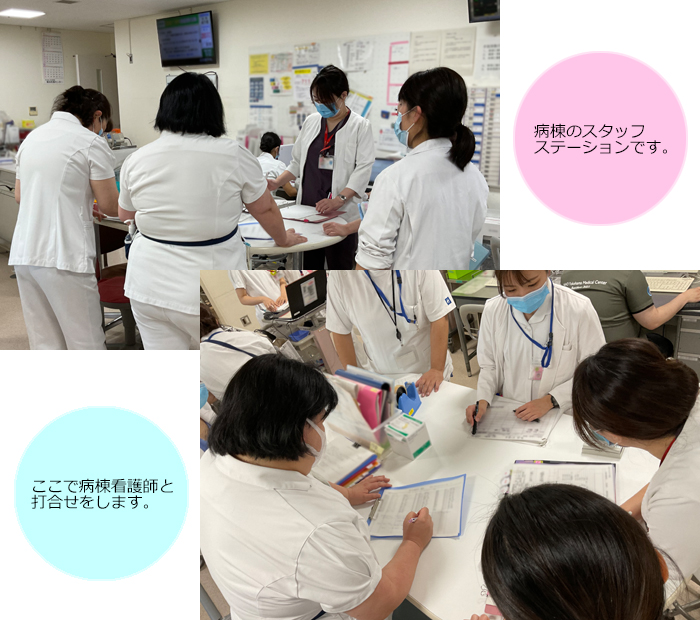
病棟看護師が、尿道カテーテル抜去後に尿が膀胱内に残っていないか残尿測定器で確認をし、排尿困難、残尿感、頻尿、尿失禁などの症状の有無を確認しています。
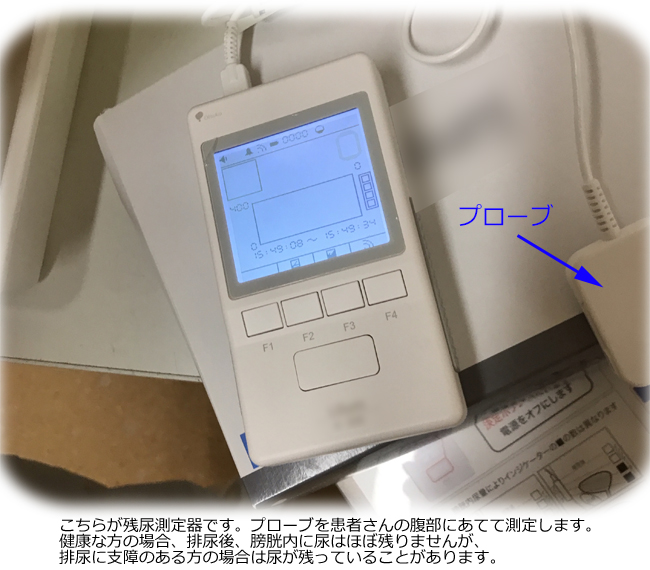
排尿ケアラウンドでは、排尿ケアチームと病棟看護師が連携し、情報を共有しながら患者さんによりよい排尿ケアを提供できるよう関わっています。
以上、活動レポートをお届けしました。
今後も随時、チーム医療の紹介をしていきますのでご期待ください。
【チーム医療の活動紹介 3-1】排尿ケアチーム
2022年01月21日
こんにちは。大寒を迎え、冷え込みがひときわ厳しくなってまいりました。
さて当ブログでは、当院の「チーム医療の活動」を紹介しています。
※医療現場でよく耳にする「チーム医療」とは、「一人の患者さんに複数のメディカルスタッフ(医療専門職)が連携して、治療やケアに当たること」です。
今回はその一つである「排尿ケアチーム」についてのご紹介です。
排尿ケアチームとは、尿道カテーテルを挿入した患者さんが元の生活へ早く復帰できるよう支援する医療チームです。

対象の患者さんは、疾患や治療、手術の為に尿道カテーテルを挿入した患者さんや尿道カテーテル抜去後に排尿障害のある方です。
患者さんにとっては、痛みやだるさなどが無くなってから尿道カテーテルを抜去してほしいと思われるかもしれませんが、尿道カテーテルを24時間留置するとカテーテルおよび膀胱に細菌が定着してしまうこと、また、長期間尿道カテーテルを留置すると自分で排尿する必要がないため、ベッド上で生活する時間が長くなり全身の筋力低下を引き起こしてしまうことから、尿道カテーテルは早めに抜去する必要があります。

そのため、患者さんが1日でも早く尿道カテーテルを抜去し、適切な排尿ケアを実施することで、尿路感染症を予防し、自立して排尿できるよう活動しています。
チームラウンド(病棟回診)の様子は、「排尿ケアチームの活動レポート」として次回ご紹介予定です。
紫外線照射ロボット活躍中!(第2弾)
2022年01月14日
お正月を過ぎてから関東地方は大雪でしたね。予報よりも雪が積もり、病院の周辺も銀世界になりました。

急激な感染拡大を見せる新型コロナウイルス。以前「紫外線照射ロボット」のご紹介をしましたが、覚えていらっしゃいますか?
当院では院内感染対策の一環として、紫外線照射ロボットを導入し消毒作業を行っています。
以前ご紹介したものとは別のロボットも頑張ってくれていて、こちらは主に救急外来で活躍しています。実際に働いている様子がこちらです。※光の点滅にご注意ください。
特殊な紫外線(キセノン紫外線)が照射されており、薬剤耐性菌やウイルスなどの消毒が1回5分という短時間で完了します。頼れる相棒です!

さらに、この一次消毒の後にドアノブやテーブルなどの環境表面をアルコール製剤で拭き取る等の二次消毒を行い、換気や空気清浄を加えて万全の態勢で次の患者さんを受け入れています。
コロナ変異株(オミクロン株)感染症が世界的に拡大している中、院内感染予防対策を徹底して実施してまいります。
横浜医療センターのお正月
2022年01月07日
新年あけましておめでとうございます。今年も病院ブログをよろしくお願いいたします。
今日は人を大切にする「人日の節句(じんじつのせっく)」です。日本の「五節句」一番目の節句で季節の変わり目の中でも、特に重要なものとされています。七草粥を食べて邪気を払い、無病息災でありたいですね。
さて、当院の年始の様子を少しお伝えしようと思います。
年神様をお迎えできるように正面玄関には門松を立て、院内には鏡餅をお供えしました。

受付や病棟のスタッフステーションなどにもお供えしています。
また、三が日の入院患者さんには「お正月特別メニュー」をご用意しました。
職員手作りの季節のカードを添えてお届けしました。お正月を感じていただけたら嬉しいです。

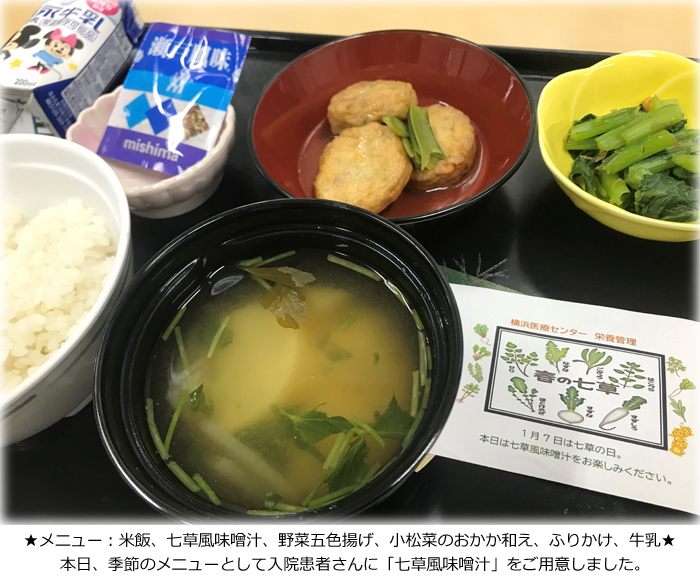
今年も毎週更新で色々なことを発信していきたいと思います。
よろしければ、またお立ち寄りください。
Happy Merry Christmas! in 横浜医療センター
2021年12月24日
今日はクリスマス・イブです。コロナ禍ではありますが街は少し賑わいを取り戻していますね。
皆さんもさまざまな形でクリスマスシーズンをお過ごしでしょうか。
当院でもご来院の方や入院患者さんにクリスマス気分を感じていただこうと、病院スタッフが色々と準備をしてまいりました!
まずはクリスマスツリーの飾りつけです。
今回は大きいツリーと小さいツリーを用意しました。

病院スタッフが飾りつけをしていると、子どもたちがツリーを見て嬉しそうにはしゃいでいました。
大きいツリーは1階正面玄関に、小さいツリーは1階夜間休日出入口付近に設置しました。
ご覧になっていただけましたか?

そして、入院患者さんにはクリスマス・イブの日の夕食に特別メニューをご用意しました。

★メニュー:えびピラフ、フライドチキン、ポトフ、彩りピクルス、
クリスマスケーキ、フルーツ盛り合わせ★
12/17~12/25までは、サンタクロースが配膳をお手伝いしてくれることになり、夕食をお届けしました。また、配膳車にもクリスマスの飾りをしました。

入院患者さんに大好評でクリスマス・イブを楽しんでいただけました。
皆さんも素敵なクリスマスをお過ごしください。
本ブログで今年最後のブログとなります。
当院では年内は12/28まで、新年は1/4から通常診療を行います。12/29から1/3までは休診となります。良いお年をお迎えください。
小児病棟(の子どもたち)への贈り物
2021年12月22日
いよいよクリスマスが近づいてきました。昨年は自粛ムードだった街のイルミネーションですが、今年は色々なところできらめいていますね。
先日、小児病棟の子どもたちへ素敵な贈り物が届きました。
ひとつは全国共済神奈川県生活協同組合様より「絵本」です。
絵本を通じて子どもたちが元気になるようにとの願いが込められています。
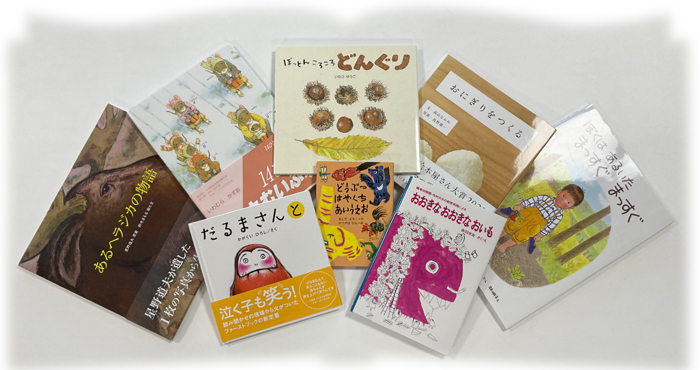
神奈川県教育委員会の推薦図書より選定された子どもたちに人気の絵本です。
もうひとつはLucaemma(ルカエマ)小児病棟プロジェクトチーム様より「アートバルーン」です。
コロナ禍で不安な想いで、病気と闘っている小児病棟の子どもたちに「ルカエマバルーン」を送って笑顔と元気を届けたい!と始められたクラウドファンディングによるプロジェクトです。


バルーンには子どもたちや医療従事者への心温まる応援メッセージが添えられていました。
小児病棟の入口に、クリスマスツリーと一緒に飾らせていただきました。
皆様からの温かいご支援に感謝申し上げます。
医療安全・感染防止対策の研修を行いました
2021年12月17日
こんにちは。街路の並木の枝々も葉を落とし、すっかり冬景色にかわりました。
当院では年2回以上、全職員を対象に医療安全と感染防止対策について研修を行っており、11月に2回目の研修を感染予防対策を徹底したうえで実施しました。
今回の医療安全のテーマは「転倒転落を起こしやすい薬剤」について、感染防止対策のテーマは「抗菌薬の適正使用(セフトリアキソン)」と「新型コロナウイルスに関する最新情報」でした。

「抗菌薬の適正使用」とは、適正に感染症診断を行い、その感染症に対して抗菌薬が必要な場合は、適正な「抗菌薬」を選択し、適正な「量」で適正な「期間」治療を行うことです。
抗菌薬を正しく使用することで、薬剤耐性菌を抑制し、院内感染を防ぐことにつながります。
そのため、抗菌薬の適正使用は院内感染対策として重要な研修の一つです。
そして今回は感染症専門医である大阪大学の忽那賢志教授にお越しいただき、新型コロナウイルスに関する最新情報について講演して頂きました。


医療提供体制等の分析データや変異株、ワクチンの感染予防効果、後遺症などについて専門家の立場から幅広くご説明いただきました。
頂いた貴重な情報は当院の院内感染対策や新型コロナウイルス感染症の予防および治療に活用していきます。
癒しの灯り
2021年12月10日
こんにちは。二十四節気では「大雪」を迎えましたね。
病院から見える富士山の雪化粧も美しいです。
11月末から、当院の冬の風物詩であるシンボルツリーのイルミネーションを点灯しています。
今年はイルミネーションのエリアを拡大し(青い照明の部分)、より幻想的な雰囲気になりました。


ドローンで撮影した、上空からの写真です。

来年1月下旬まで癒しの灯りをお届けする予定です。
皆様に楽しんでいただけたら幸いです。ぜひご覧ください。
フィブロスキャンを導入しました
2021年12月03日
こんにちは。12月に入り、今年も残すところあとわずかとなってまいりました。
このたび当院消化器内科では超音波エラストグラフィ「フィブロスキャン」を導入しました。
フィブロスキャンは超音波と振動により、肝臓の線維化や脂肪化の程度を診断することができる検査機器で、導入している病院はまだ多くありません。

肝疾患は自覚症状がないままに病状が進行するケースが多くあります。
体に負担をかけずにおおよその病期を診断することができるフィブロスキャンの登場で、肝疾患診療は転換期を迎えています。
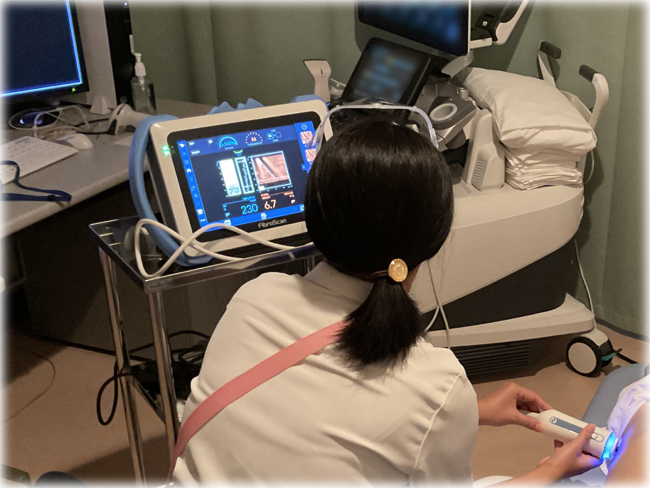
過食や運動不足を背景に増加している「非アルコール性脂肪性肝疾患」をはじめ、肝疾患全般での診療に活用していきます。
入院患者さんへの面会を一部再開しています
2021年12月02日
※本ブログの内容は2021年12月2日時点のもので、最新の情報とは異なります。
こんにちは。12月に入り朝晩の冷え込みが堪えますね。
さて、新型コロナウイルスの感染状況が落ち着いていることから、当院では11月8日(月)から面会制限を一部緩和しました。1回30分以内で、個室の入院患者さんに限り、一定の基準のもとで面会ができるようになりました(小児科を除く)。
なお、横浜市内新規感染者が3日続けて50人を超えた場合は即時に面会禁止とさせていただきますので、ご理解のほどよろしくお願いいたします。
面会受付場所は時間帯により異なります。
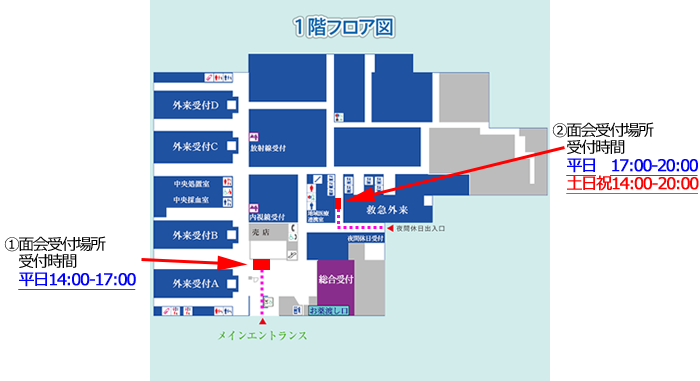
平日の診療時間中は1階正面玄関にあります。

平日夜間と土日祝日は1階夜間休日出入口付近のエレベーターホールにあります。

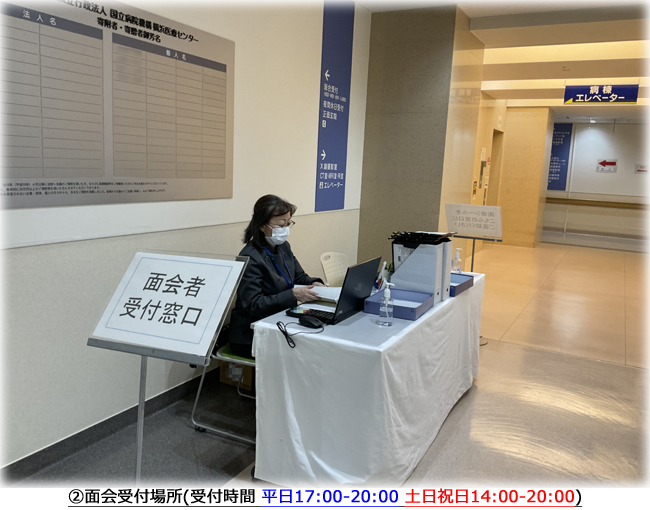
面会受付場所では面会の方には健康状態の確認をさせて頂き、入館許可シールをお渡しします。
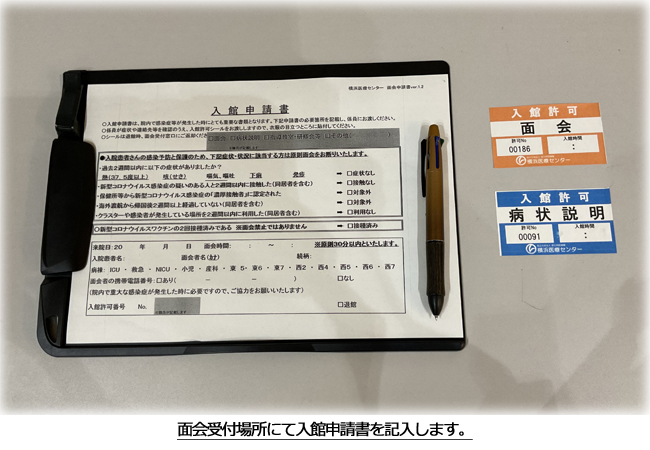
感染防止のため、必ず受付を済ませていただくよう、ご協力をお願いします。
※本ブログの内容は2021年12月2日時点のもので、最新の情報とは異なります。
【チーム医療の活動紹介 2-2】緩和ケアチーム
2021年11月26日
今日は前回お知らせした緩和ケアチームのラウンド(病棟回診)の様子をご紹介します。
カンファレンスで患者さんの情報などを共有した後、ラウンドを開始します。
病室では主治医や病棟看護師と一緒に患者さんの様子を確認しながらお話をうかがい、必要な薬剤や食べやすい食事の調整、不安や気分の落ち込みへの相談支援などをきめ細かく行っています。
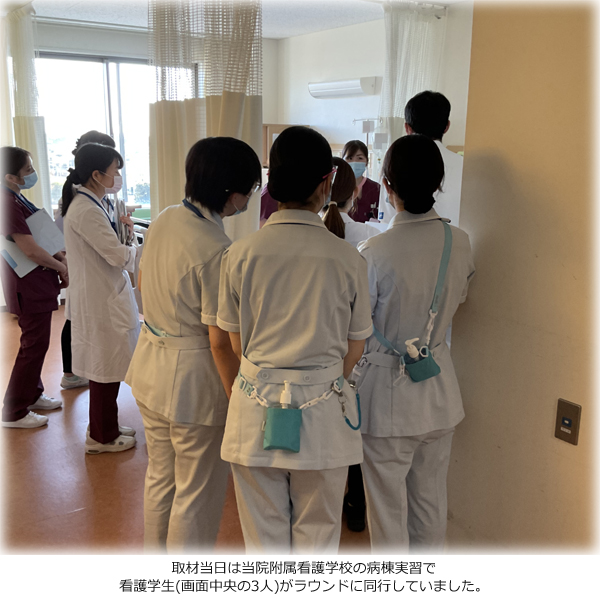
外来通院へ移行された場合にも、緩和ケア外来で同様のサポート体制をとっています。
また、緩和ケアチームはがん以外にも、心不全や重篤な肺炎などによるつらい症状に関する相談にも対応しています。
がんや心不全などで以下のような悩みを抱えている方は、担当の医師や看護師に『緩和ケアチームに相談したい』旨をお気軽にご相談ください。
・痛みや息苦しさ、しびれや吐気など 身体症状がある
・不安や気分の落ち込み、不眠など 精神症状がある
・何らかの症状があって、これまでの日常生活や通院に心配がある
今後も随時、チーム医療の紹介をしていきますのでご期待ください。
【チーム医療の活動紹介 2-1】緩和ケアチーム
2021年11月19日
先週立冬を迎え、暦の上では冬ですね。朝晩の冷え込みがぐっと増してきました。
晴れた日中は暖かい日もあり、まさに冬の入り口と言う感じです。
さて当ブログでは、当院の「チーム医療の活動」を紹介しています。
※医療現場でよく耳にする「チーム医療」とは、「一人の患者さんに複数のメディカルスタッフ(医療専門職)が連携して、治療やケアに当たること」です。
今回はその一つである「緩和ケアチーム」についてのご紹介です。
当院の緩和ケアチームは平成19年に立ち上がり、今年で14年目となります。
メンバーは医師、看護師、薬剤師、管理栄養士、公認心理師、社会福祉士の職種で構成され、総勢13名で活動しています。
『緩和ケア』と聞くと、末期がんの患者さんが受けるケアといったイメージを持っている方が多いかもしれませんが、実際に当院の緩和ケアチームが関わっている患者さんは、がんの診断を受けて間もない時期から治療中の方が大半を占めています。
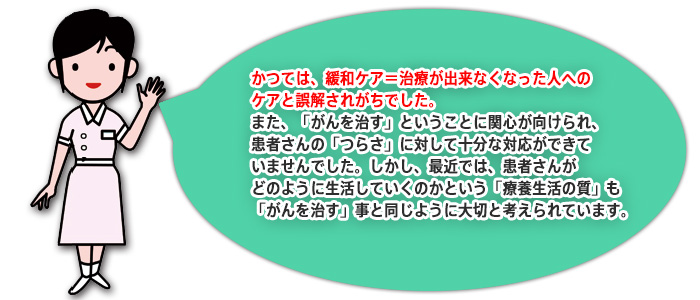
※当院ホームページ「緩和ケアチーム」のページはこちらです。
がんによって生じる痛みなどのつらい症状があっても、希望する場所で自分らしく日常生活が送れるように、多職種で専門性を生かし、患者さんおひとり、おひとりに合わせた方法で支援しています。

多職種で行うカンファレンスでは、色々な意見が出され共有されます。
カンファレンス後のラウンド(病棟回診)の様子は、次回の「緩和ケアチームの活動レポート」でご紹介します。
血管撮影装置をリニューアルしました
2021年11月17日
こんにちは。朝の最低気温が10℃を下回る日もあり、日中との寒暖差がより激しくなってきました。
晴天が続き空気が乾燥していますので体調管理に気をつけたいです。
さて、今日は「血管撮影装置」のお話です。
血管撮影装置とはカテーテルと呼ばれる細い管を血管や臓器に挿入し、造影剤を注入して血管の状態を撮影する装置のことです。
主に狭心症、心筋梗塞などの冠動脈疾患の検査や治療に使用されます。
当院でも血管撮影装置を導入しておりますがこの度リニューアルし、11月1日より稼働を開始しました。
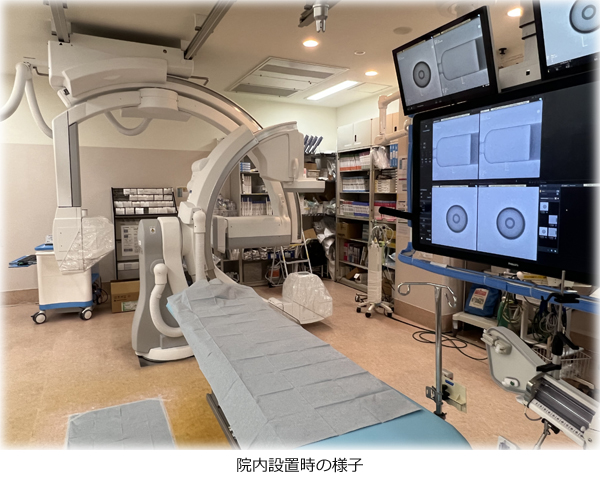
従来の装置と比べ、より少ないX線量で且つより細い血管を撮影することができます。
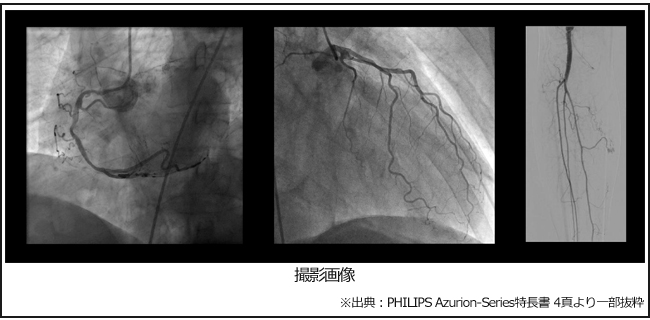
これにより、患者さんや術者の被ばく低減と検査時間の短縮ができるようになりました。
無事に停電点検が完了しました
2021年11月12日
こんにちは。遠くの山々が綺麗に色づいてきました。名所は紅葉狩りの真っ盛りですね。
さて、今日は「停電点検」のお話です。
11月6日(土)に法令に基づく年1回の電気設備定期点検を実施しました。
午前中に自家発電の点検を行って、正常に動作することを確認したうえで、午後に自家発電に切り替え、点検を行いました。

短時間ではありましたが電気が消えるととても暗く、災害等で実際に停電が起きたときの状況を体感することができました。

天井の非常灯も点いています。
入院患者さんの不安を軽減できるよう、停電箇所や作業状況などについては館内放送でお知らせしました。
ご不便をお掛けしましたが、皆さまのご協力のおかげで無事に停電点検が完了しました。お礼申し上げます。
ハッピーハロウィン♪
2021年11月05日
こんにちは。先週から気温差が大きくなってきましたね。病院のそばにある木々も少しずつ黄色やオレンジに色づいてきました。
さて、今日は「ハロウィン」のお話です。
入院患者さんに季節を感じていただきたく、ハロウィンの日の夕食に特別メニューをご用意しました。

★メニュー:ごはん、白身魚フライ・コーンコロッケ しめじとピーマンソテー添え袋ソース付き、
カリフラワーサラダ、オクラ梅酢和え、味噌汁、オレンジ★
ハロウィンらしい飾りとメッセージカード、お菓子が添えられてとてもおいしそうです!
ハロウィンは、もともとアイルランドやイギリスを発祥とし、古代ケルト、古代ローマ、キリスト教の3つの文化が融合して生まれたとされており、秋の収穫をお祝いし、先祖の霊をお迎えするとともに悪霊を追い払うお祭りです。
正確な期間は10月31日~11月2日ですが、現在は10月31日がハロウィンとして定着しています。
今年は当院スタッフが外来ホールにハロウィンの飾り付けを行いました。

患者さんたちからも大好評でした!
新型コロナウイルスが一日も早く収束するよう願いをこめて。
感染防止対策相互ラウンド
2021年10月29日
こんにちは。いつしか秋も深まり、もうじき紅葉の美しい季節がやってきますね。
さて、今日は10月15日(金)に行われた「感染防止対策相互ラウンド」のお話です。
この相互ラウンドは、年に1回以上行われ、事前にマッチングした連携病院と協力し、お互いの病院を訪問して実施します。

この連携病院は昨年も当院と相互ラウンドを実施したので、各部署を回って感染対策が正しく実施されているか、昨年の指摘事項について改善されたか等の確認を行いました。

当院では感染対策チーム(ICT(※))を配置し、週に1回、ラウンドを行っていますが、相互ラウンドでは他施設のチームが入ることで違った視点でヒアリングや評価をしています。このような活動を行うことで、お互いの良い取り組みを取り入れることができます。
新型コロナウイルスが流行している中で、患者さんの安全のためにより良い感染防止対策が出来るよう努めてまいります。
※ICT:インフェクション(Infection:感染)コントロール(Control:制御)チーム(Team)の略称で、院内の感染対策全般にわたり、感染症の治療から耐性菌対策まで現場で活動しているチームのことです。
J.M.Sプログラムに参加しました
2021年10月28日
こんにちは。寒さも次第につのり、朝夕はめっきり冷え込む今日この頃です。
さて、今日は「ジャパン・マンモグラフィー・サンデー(J.M.S)」のお話です。
J.M.Sとは、NPO法人J.POSHと全国の医療機関が協力して、平日は仕事や子育てに忙しく検診を受けに行きにくい女性が、日曜日に「乳がん検診」を受けられる環境づくりへの取り組みのことです。当院では今年初めてこの活動に参加し、10月17日の日曜日に乳がん検診を行いました。
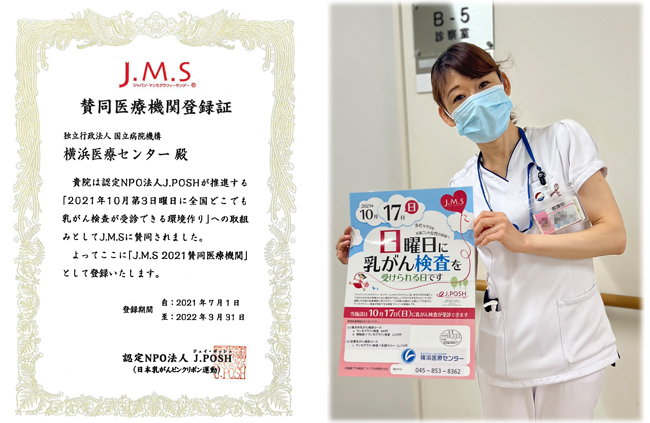
平日に実施している検診は40歳以上を対象としていますが、今回の検診では20歳以上を対象にするとともに、従来の検査(視触診とマンモグラフィー検査)に加えて乳腺エコーも選択して受診できるようにしました。予約はすぐにいっぱいになり、乳腺エコーを受診される方も多く、乳がん検診に対する意識の高さを感じました。

当日はあいにくの雨模様でしたが、受診された方から「日曜日だと助かるわ。ありがとう。」とのご感想をいただきました。当院は来年も引き続きJ.M.Sに参加する予定で、多くの方が乳がん検診を受診できる環境づくりを進めてまいります。

第75回国立病院総合医学会
2021年10月27日
こんにちは。二十四節気では「霜降」となり、12月並みの気温となる日もありました。
寒暖差で体調を崩しやすい時期なので、気を付けて過ごしたいものです。
みなさんは学会って、ご存知でしょうか?
病院やクリニックで「〇〇医師は、学会参加のため休診いたします」といった掲示を見かけた方もいらっしゃると思います。
学会とは、一般的には「学者や研究者が自身の研究成果を発表し、その妥当性を検討論議する場」なのですが、医療では数えきれない位多くの学会が存在し、医師だけでなく多くの医療従事者が学会に参加し研鑽しています。
このような医療従事者による研鑽の積み重ねが医療の発展を支えています。
さて、10月23日から国立病院機構の医療従事者の学会である『国立病院総合医学会』が開催されており、当院からも医師、看護師、薬剤師、放射線技師、救急救命士、管理栄養士、MSW等が23題の発表を行っています。2019年までは全国各地の会場で開催されていましたが、昨年からオンラインでの開催となり、全国の国立病院機構の職員が、日々の業務の成果を発表し、医療の質向上のために熱い議論を繰り広げています。
国立病院機構職員以外の方も視聴していただくことが可能ですので(有料です)、ご覧になりたい方は国立病院総合医学会ホームページで詳細をご確認ください。

ペーパーレスの取り組み
2021年10月22日
こんにちは。日曜日の雨からぐっと気温が下がりましたね。
木々の葉が色づき始め、秋を感じるようになってきました。
さて、今日は当院で実施している「ペーパーレス会議」のお話です。
ペーパーレス化は環境保全や業務効率化など、さまざまなメリットがあり各企業が取り組んでいます。
当院でも会議資料の紙節減に努めていますが更なる会議運用効率化・省資源化・経費削減のため、「ペーパーレス会議システム」を導入しました。
タブレットで発表者の資料や動画を他の参加者と同期したり、その場で書き込んだメモや撮影した写真を瞬時に共有したりと大変便利です。最大80人の同時利用ができます。


新型コロナウイルス感染対策のため使用前後の手指消毒などは欠かせませんが、オンライン会議などに加えて新たなツールが加わり、状況に応じた柔軟な対応が可能となりました。
一層の効率化と省資源化だけでなく、活発な議論や効果的なセミナーなどが実施できると期待しています。
「時計の住人 Ver.2」
2021年10月15日
こんにちは。日ごとに暗くなるのが早くなり、「秋の日はつるべ落とし」を実感する今日この頃です。
さて、今日は当院1階・外来ロビーで実施している「プロジェクション・マッピング」 リニューアルのお話です。
横浜市立大学、東京藝術大学のご協力を得て、2019年よりプロジェクション・マッピング「時計の住人」を設置しております。
アニメーション作家である築地のはらさんがデザインしたかわいいアニメーションが見る人を楽しませてくれます。
このたび、内容をリニューアルし「時計の住人 Ver.2」として更新いたしました。
上映期間は2021年10月1日~2022年3月末を予定しており、毎日8:00~20:00まで上映しております。



今回の「時計の住人 Ver.2」では、5分ごとに壁面の時計からカラフルな数字のキャラクターが現れて、いろんなかわいいしぐさを見せてくれます。
中には現れて昼寝をしてしまう数字も。こちらは不定期で現れるので、もし見ることができたらラッキーかもしれません。
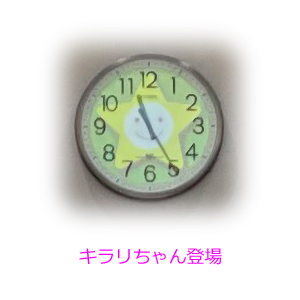
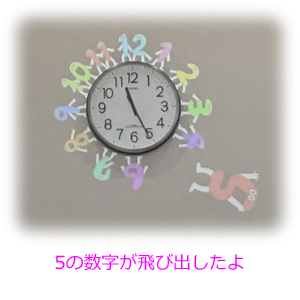
当院のシンボルキャラクターである「キラリちゃん」も登場します。
ご来院の際は、ぜひご覧ください!
*詳細につきましては、プレスリリースをご覧ください。*
看護学校で今年も戴帽式が行われました
2021年10月08日
こんにちは。10月に入り、秋空が気持ちよく、暑さが涼しさに変わってきましたね。
さて、今日は10月1日(金)に開催された当院附属横浜看護学校「戴帽式」のお話です。
戴帽式とは1年生が病院実習に入る前に行われるセレモニーで、男性にはエンブレム、女性にはキャップが授与され、ナイチンゲールの「心の灯」を継承し「看護の誓詞」を宣誓します。
ナースキャップが廃止され戴帽式を行わない学校もありますが、当校は看護学生にとって大切なセレモニーとして続けてきました。
昨年に続き、今年も新型コロナウイルス感染予防対策を徹底したうえで、式典を行いました。
残念ながら保護者のみなさんの来校は叶いませんでしたが、式の様子をオンライン配信することで、厳かな雰囲気を感じていただけたと思います。

当日は関東に台風が接近する悪天候の中での戴帽式でしたが、コロナ禍で看護の道を選んだ頼もしい学生たちは理想の看護師像を志す決意を胸に誓いを立てていました。
学生たちはこれから本格的な病院実習を開始します。
看護師としての責任と自覚を持ち、「いのち」と向き合うと誓う学生たちの背中は、4月の入学式よりも大きく見えました。
この先さまざまな壁にぶつかることもあるでしょう。そんなときは同じ看護の道を歩む仲間たちと共に、支えあって乗り越えてほしいと思います。
*戴帽式の様子は看護学校HPに掲載しております。ぜひ、ご覧ください。*
アルコール消毒用品のご寄付をいただきました
2021年10月01日
こんにちは。一雨ごとに秋が深まり、朝晩は肌寒さを感じるようになりました。
秋晴れの日はやわらかい日差しが気持ちの良い季節になりましたね。
緊急事態宣言が解除され、生活範囲が広くなってきます。
それでも、毎日の手指消毒やマスクは忘れずに行いたい感染対策です。
先日、フマキラー株式会社様より「アルコール除菌プレミアム ウイルシャット」「アルコール消毒プレミアム ウイルシャット 手指用」のご寄付をいただきました。

ドアノブや手すり、机などを拭いて使用するタイプは、ほのかにグレープフルーツの香りがします。

こちらはサラっとした使い心地のリキッドタイプです。ベタつかず手にも優しい感じがします。
病院スタッフ一同、大切に使わせていただきます。誠にありがとうございました。
何に見えますか?
2021年09月24日
こんにちは。暦の上では秋分も過ぎ、日の入りも早まってきました。
さて、今日は「十五夜」のお話です。
十五夜は1年で最も美しいとされている「中秋の名月」を鑑賞しながら、収穫などに感謝をする行事です。芋類の収穫祝いを兼ねているので、別名「芋名月」と呼ばれています。
十五夜の日は旧暦8月15日の月を指すため、毎年変わります。今年は「9月21日(火)」でした。
日本から眺めた月は「うさぎが餅つきをしているように見える」と言われています。しかし、この月うさぎは万国共通ではないそうです。(以下は一例で、同じ国でも地域によって異なるかもしれません。)

・中国:薬草を挽くうさぎ ・ベトナム:木の下で休む男性
・モンゴル:犬 ・オーストリア:男性が灯りを点けたり消したりしている
・インド:ワニ ・北ヨーロッパ:本を読むおばあさん
・中南米:ロバ ・南ヨーロッパ:大きなはさみのカニ
・東ヨーロッパ:女性の横顔 ・インドネシア:編み物をしている女性
・ドイツ:薪をかつぐ男

月の模様をどう捉えるかは国によって様々で面白いですね!
当院では入院患者さんに十五夜を楽しんでいただけるよう、十五夜の日の夕食に特別メニューをご用意いたしました。

★メニュー:ごはん、ぶりの塩焼き・おろしソースがけ、五目きんぴら、
白菜ごま酢和え、お月見大福、梨★
コロナ禍で慌ただしい世の中ですが、月を見て静かに過ごすのも良いですね。入院患者さんにお月見気分を楽しんでいただきました。
救急車型ドクターカーがニュースに!
2021年09月17日
こんにちは。秋の長雨とはいいますが、最近雨の日が多いですね。晴れた日はさわやかな秋晴れの空が広がって過ごしやすい季節となりました。
さて、7月に当院ブログにて「救急車型ドクターカーを導入しました!」をご紹介いたしましたが、この度、タウンニュース戸塚区版(2021年8月26日号)に掲載されました。
医療行為できる車両導入(タウンニュース戸塚区版)
ぜひ、ご覧ください!
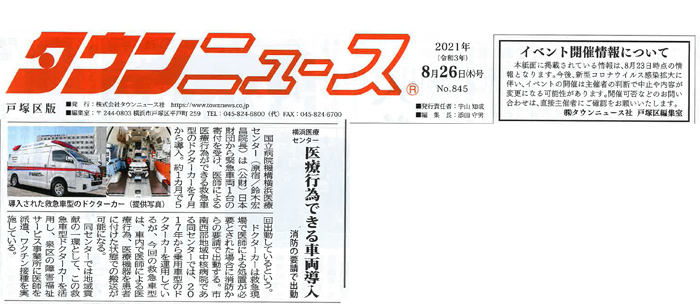
より質の高い医療を届けるために
2021年09月10日
こんにちは。昼間の日差しはまだ厳しいですが、朝夕は涼しい風が吹き、気持ちの良い季節になってきました。
当院は9月6~8日に病院機能評価を受審しました。
病院機能評価とは、全国の病院の運営管理や提供される医療について、公益財団法人日本医療機能評価機構が客観的な立場(第三者の立場)で中立的、科学的・専門的な見地から評価を行うものです。患者中心の医療の推進、良質な医療の実践などの様々な評価項目について審査を受け、一定の水準に達している病院が認定されます。
当院は2006年に認定を受けてから5年ごとに更新認定を受けており、今回で4回目の受審となります。今回は初めて、通常の審査に加えて「高度・専門機能(救急医療・災害時の医療)」も受審しました。


なお、審査の結果が出ましたらまたご報告させて頂きます。
審査でのご指摘等を踏まえ、患者さんが安全で安心な医療を受けられるよう、病院体制のより一層の充実や医療の質の向上に努めてまいります。
※病院機能評価事業(公益財団法人日本医療機能評価機構)
【チーム医療の活動紹介 1-2】認知症ケアチーム
2021年09月03日
こんにちは。8月は厳しい残暑が続いていましたが、9月に入り徐々に暑さが落ち着いてきました。秋はすぐそこまで来ていますね。
今日は前回お知らせした認知症ケアチームのラウンド(※)の様子をご紹介します。
ラウンドでは患者さんの療養環境を確認し、一人ひとりの状況に応じてより良い環境づくりを検討しています。
あらかじめ病棟スタッフと患者さんの様子や病状などの情報を共有してから、ラウンドを開始します。

ラウンドは、常に患者さんと認知症ケアチームメンバーとの会話が中心です。「ココはどこか分かりますか?」「何かお困りのことはありませんか?」など、色々なことを患者さんに聞きます。また、その時々で色々な『道具』を利用します。
例えば…何か看護師が手に持っていますね。お分かりでしょうか。

そう、時計です。近くにはカレンダーもあります。
病室にいると、日付や時間の感覚が鈍ってきます。 これらを使って、患者さんに日付や時間を確認してもらい感覚を刺激します。
次に、メガホンです。反応がない、適切な返答ができないのは、認知症のためではなく、単に聞こえていないだけかもしれません。メガホンを利用することで、声が耳にダイレクトに伝わります。新型コロナ対策で病室では大声が出せないこともあり、重宝しています。

認知症ケアチームは、このような質問や道具を使いながら、認知症状のある患者さんが安心して治療を受けられる環境を提案し、疾患の治療を円滑に受けられることを目指して、活動しています。
以上、活動レポートをお届けしました。
今後も随時、チーム医療の紹介をしていきますのでご期待ください。
※ラウンド:医師や看護師などが病棟や病室内を見回ること
【チーム医療の活動紹介 1-1】認知症ケアチーム
2021年08月27日
こんにちは。まだまだ蒸し暑い日が続きますが、暗くなるのが早くなってきました。
8/23から二十四節気の「処暑」となり、秋の気配も感じられますね。
さて当ブログでは、今後、当院の「チーム医療の活動」を紹介していきます。
※医療現場で良く耳にする「チーム医療」とは、「一人の患者さんに複数のメディカルスタッフ(医療専門職)が連携して、治療やケアに当たること」です。
今回はその一つである「認知症ケアチーム」についてのご紹介です。メンバーは医師、看護師、社会福祉士、リハビリなど様々な職種で構成され、認知症状のある患者さんが安心して治療を受けられるよう、入院療養の環境調整、入院中の患者さんへの関わり方や薬物療法などに関する相談・助言を病棟スタッフへ行うなどの活動をしています。

なお、今年度は特に患者さんの状態を把握し、認知症状が悪化しない関わりの強化を行っています。

最後に認知症ケアチームメンバーから、患者さんへのメッセージです。
「認知症状のある患者さんも安心して治療を受けられるようケアの充実、環境調整に力を入れています。患者さんを中心とした看護の提供、より質の高い看護の提供ができるよう取り組んでいます。」
次回は、「認知症ケアチームの活動レポート」として、工夫を凝らした具体的な活動内容をご紹介します。
ミストと風鈴で「涼」をお届けしています
2021年08月20日
こんにちは。
関東地方では先週から雨が続き、半袖ではヒンヤリするほど気温の低い日が続きました。
今回の雨は、太平洋高気圧が弱く前線が停滞したために長く続いたそうです。
8月後半はこの高気圧が関東に張り出してくるため、厳しい残暑となる予報がでています。
気温の変化が大きいと、身体に堪えますね。
そんな暑さ対策として、当院では正面玄関横にミストシャワーを設置しています。

ミストシャワーは、屋外では2~3度程度、冷却効果があると言われています。
見た目も涼し気ですよね。

そして、お気づきいただけますか??

そう!風鈴です。風が吹くと、リンリンと音を奏でて涼しさアップ 
日本の夏は古くから打ち水や風鈴など、五感で涼を楽しむ工夫がありますね。
古くからの涼の知恵、当院にお越しの際には、ぜひ感じてみてください。
うれしい贈り物が届きました
2021年08月06日
こんにちは。暦の上では立秋を迎えますが、この暑さは一向に衰える気配がないですね。
引き続き、熱中症に気をつけて過ごしましょう。
先日、医療施設への支援の一環ということでうれしい贈り物が2つ届きました。
ひとつ目は看護職員に向けて、神奈川県を通じて株式会社ファンケル様より「パウダーファンデーション」です。
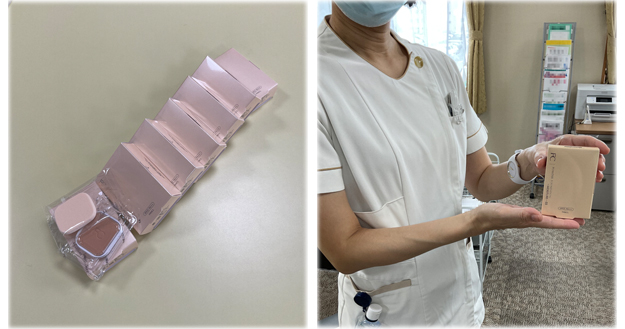
マスクの着用は感染予防に欠かせませんが、マスクによる摩擦(こすれ)や蒸れ、乾燥により肌荒れを起こしがちです。毎日使うものなので、無添加化粧品はとてもうれしい贈り物でした!
もうひとつは、有楽製菓株式会社様より「ブラックサンダー」。

小腹が空いたときの頼もしい味方で、大人も大好きな定番お菓子。
オリジナルのブラックサンダーのほかに、期間限定の「カスタードアップルパイ」「濃密くるみのガトーショコラ」「しっとりプレミアム」をいただきました。こちらは全職員に配布。どれもおいしくて、大満足です!
先週あたりから感染者数が増加傾向にあります。みなさんも基本的な感染対策を引き続き行って、
しっかり予防していきましょう。当院では今後も継続して、新型コロナウイルス感染症への対応に努めます。
あたたかいご支援をいただき、心より感謝申し上げます。
※来週のブログはお休みさせていただきます。
夏バテにはやっぱりこれです!
2021年07月30日
こんにちは。夏本番になり、蒸し暑い日々が続いていますね。
さて、今日は「土用の丑の日」のお話です。
年によっては夏に土用の丑の日が2回訪れることがあるのですが、今年は7月28日の1回だけですね。
土用は、季節の変わり目の約18日間のことで、体調を崩しやすい時期と言われています。
そして、「土用の丑の日」と言えば、やはり「うなぎ」ですね!
一昔前は、庶民的な食べ物であったうなぎですが、漁獲量減少によりすっかり高級品となりました。そんなうなぎですが、ビタミンAやビタミンB群など、疲労回復や食欲増進に効果的な成分が多く含まれており、夏バテ防止にはピッタリの食材です!
当院でも入院患者さんのご夕食に、特別メニューをご用意いたしました。

★メニュー:米飯、うなぎ蒲焼き、冬瓜そぼろ煮、胡瓜即席漬け、パイン、ぶどうゼリー★
「うなぎを食べて精をつけ、暑さに負けずに夏を乗り切ってほしい」との願いを込めて、メニューに加えました。入院患者さんにとても喜んでいただけました!
救急車型ドクターカーを導入しました!
2021年07月21日
こんにちは。関東は梅雨が明けましたね。空を見上げると夏空がまぶしいです。
さて、当院では公益財団法人日本財団からのご寄付により、救急車型のドクターカーの運用を開始しました。
現在運用中の「乗用車型」ドクターカーに加えて、患者さんを搬送することができる「救急車型」ドクターカーが新たに導入されたことで、救急現場における活動の幅が大きく広がります。車内での医療行為やECMO(エクモ)などの医療機器を患者さんに付けた状態での搬送ができるようになります。
地域の皆様が安心して医療を受けられるように、引き続き地域中核病院としての役割を果たしてまいります。
(公財)日本財団からは、当該車両に加えて災害時の通信手段として「設置型衛星電話(衛星IP通信サービス)」もご寄付いただきました。誠にありがとうございました。
*詳細につきましては、プレスリリースをご覧ください。*

※ドクターカーとは、救急現場などにおいて医師による処置が必要と判断された際に、消防からの要請により、医師・看護師等が医療器材を載せて現場に急行するための緊急自動車です。(一般の方からの出動要請は受け付けておりません。)
新人看護師、奮闘中!
2021年07月16日
こんにちは。急な雷雨が増えてくると、梅雨明けも間近だなと感じます。
気温と湿度が高くなっているので、引き続き熱中症には気を付けて過ごしたいですね。
さて、今日は7月9日に行われた新人看護師研修のお話です。
入職して3か月が過ぎ、看護師としての一歩を踏み出したところです。
先輩看護師の優しく、ときに厳しい指導のもと日々奮闘しています。
そして研修前に、看護師免許証の交付が行われました。
合格してから手元に届くのが、待ち遠しかったですよね。
看護部長からそれぞれに手渡され、受け取る皆さんの表情からは嬉しさとともに決意のようなものも伝わってきました。
看護部長から「皆さんは看護師としてまだ一歩を踏み出したばかり。もしかしたら、まだ片足をあげたくらいで地にも着いていないくらいの時期。看護師の道のりは長いので、そんなに焦らずに頑張れば大丈夫」と、激励の言葉がありました。

免許証を受け取った皆さんに、今の気持ちをインタビューしてみました。
「3年間の看護学校を経て、やっとここまできました。免許証をもらって、改めて自覚を持ちました。」
「3か月働いてみて、まだまだ勉強不足なところがあるけれど、先輩に助けてもらいながら、同期と支えあって頑張れています!」
と、とても嬉しそうに話してくれました。
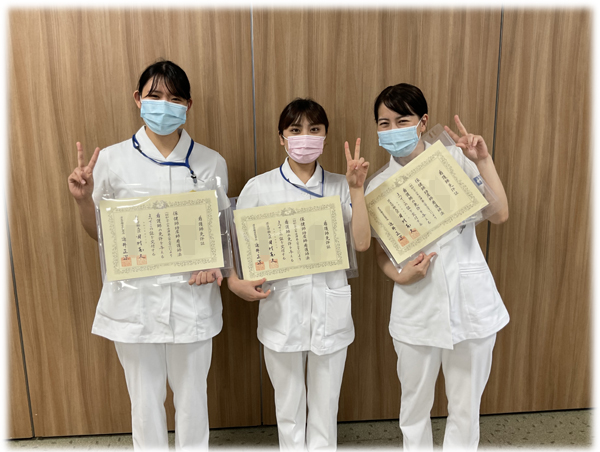
その後の研修では、責任の重さを感じながら、真剣に取り組む新人看護師の姿がありました。

看護師として、チームの一員として活躍できる看護師を目指し、私たちと一緒に歩んでいきましょう!
RSウイルスが流行しています
2021年07月09日
6月下旬からRSウイルスが流行しています。
当院でも小児科の入院患者さんが増えてきました。
ここ数年は7月頃から流行が始まるとされていましたが、今年は例年よりも早く増加しており、横浜市からは感染症臨時情報が出ています。
RSウイルスは、発熱や鼻汁などの症状が数日続き多くは軽症ですが、特に乳児では肺炎などの重篤な症状を起こすことがあります。
飛沫、接触により感染するため手洗い、マスク着用の基本的な感染防止対策が大切です。
乳幼児がいる場合はおもちゃの消毒も対策となります。
横浜市からの最新情報はこちらで確認できます。
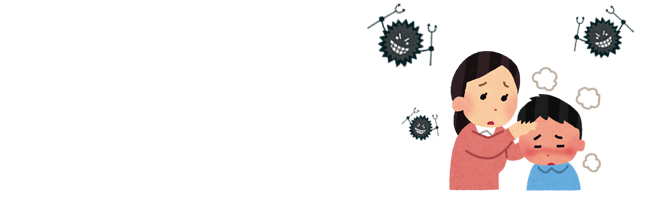
2021年七夕 ~短冊に願いをこめて~
2021年07月07日
こんにちは。今日は七夕です!
「雨が降ると天の川が渡れない」ともいわれていますが、今年は織姫さまと彦星さまは出会えるといいですね。
今年もコロナ禍での感染リスクを考慮し、病院スタッフが短冊を書き、飾りつけを行いました。

いろいろな願い事が書かれていますが、コロナ終息がやはり多いでしょうか。
一日も早く、新型コロナウイルス感染症が終息することを願います。
そして、入院患者さんの本日のご夕食ですが、七夕特別メニューをご用意いたしました!

オクラ醤油和え、七夕タルト、西瓜★
とっても美味しそうですね!当院の調理師が腕を振るって作りました!
みなさまにとって、素敵な七夕になりますように。
ワクチン接種会場に医師・看護師を派遣しています
2021年07月06日
現在、高齢者の新型コロナウイルスワクチン接種が急ピッチで進んでいます。
当院では横浜市からの依頼に基づき、大規模接種会場(横浜ハンマーヘッド)に6月6日から毎日医師2名(午前・午後各1名)、看護師4名(同2名)を派遣しています。また、戸塚区の集団接種会場にも週1回程度、医師を派遣しています。
コロナに打ち克つ未来に向けて、国・県・市と各医療機関が協力しながら、少しでも早くワクチン接種が進むように全力で取り組んでいます。

※当院の役割である高度・急性期医療の提供を優先するため、当院での患者さん向け接種は行っておりません。
※横浜市のワクチン接種に関する情報やお問い合わせ先はこちらです。
WOCナースの活躍
2021年07月02日
こんにちは。7月に入り、季節はいよいよ夏へ近づいてきました。
気温が徐々に高くなってきていますので、こまめに水分補給をしましょう。
さて今日は、当院で活躍しているWOCナース(※)のご紹介です。
当院には3名のWOCナースが在籍しております。
先週のブログで「高機能エアマットレス」をご紹介しました。自分で体を動かすことが難しい方に、様々な機能を持つマットレスやクッション等を準備するのもWOCナースのお仕事の一つです。
患者さんの状態を見て、使用するマットが適正か等を検討し、その評価を毎週行っています。
もちろん、新製品のトライアル導入や病院スタッフへの勉強会を開催するなど、教育・指導に抜かりありません。
最後にWOCナースより「皆様の生活がより良いものになるよう、一緒に考えさせていただきます。スキンケア関連で困った時にはご相談ください。」
当院では、より質の高いケアが実践できるよう取り組んでまいります!


※WOCナース:W(Wound)=創傷(きず)・O(Ostomy)=ストーマ(人工肛門、人工膀胱)・C(Continence)=失禁(尿や便の漏れ)看護の分野において、熟練した看護技術と知識を用いて水準の高い看護実践ができる看護師のことです。
環境整備を進めています!
2021年06月30日
こんにちは。
梅雨時期は洗濯物がなかなか乾かず、家の中もジメジメ。
晴れると気温は上がりますが、時々顔を出す太陽のありがたみを感じています。
さて、6月中旬に前回(6/16のブログ)に続いて、駐車場の草刈りを行いました。
植栽エリアには植木があるのですが、植木がわからないくらい草が伸び放題。
(特に今の時期は 雑草の生育の速度が早く1日で最大3センチ伸びる草もあるそうです。)
◆◆作業前◆◆

◆◆作業後◆◆

スッキリと刈り取られて見通しも良くなりました!さっぱりしましたね。
来院される方を気持ちよくお迎えできるよう、院外環境も整えてお待ちしています。
高機能エアマットレスってなに?
2021年06月25日
こんにちは。梅雨入り早々、ものすごいゲリラ豪雨がありましたね。
梅雨の時期は、雨が降っていなくても傘を持ち歩くと安心です。
今日は高機能エアマットレスのお話です。
入院中の患者さんで、自分で体を動かすことが難しい方に、病院スタッフは数種類のマットレスやクッションを用意し、患者さん一人ひとりに適したものを選んで使っています。
その中でもお猿さんの絵がとっても可愛いバナナ型クッションと高機能エアマットレスが現場で大活躍しています。
高機能エアマットレスを使うと、頭を上げたときにお尻の圧を自動的に調整してくれるので、お尻が痛くありません。バナナ型クッションと併せて使うと、より褥瘡(※)を予防できます。
この高機能エアマットレスを2021年5月に追加導入しました。
これからも、患者さんが安全・安楽に過ごせるように療養環境の整備に努めていきます!


※褥瘡:寝たきりなどによって、体重で圧迫されている場所の血流が悪くなったり滞ることで、皮膚の一部が赤味をおびたり、ただれたり、傷ができてしまうことです。一般的に「床ずれ」ともいわれています。
「勇気のパス」を受け取りました
2021年06月18日
こんにちは。今日はうれしいお知らせです。
2021年6月に医療従事者への支援に取り組んでいるラグビーエイド(※)活動で集められた「医療用ガウン」のご寄付をいただきました。ラグビーキッズから、かわいらしい手書きの応援メッセージも添えられていました。
受け取った私たちも思わず「すごい!」と声が漏れました。
新型コロナウイルス感染症対策として、活用させていただきます。
日々現場で対応に当たるスタッフは、暖かいメッセージにパワーをもらいました。ありがとうございます!みなさんから受け取った「勇気のパス」は私たちがスクラムを組み、トライを目指していきます。


※ラグビーエイド
ラグビーを愛する人たちが、コロナ禍での医療現場の最前線で働く医療従事者に対するサポートを目的とした活動。クラウドファンディングで支援金を募り医療物資とエールを届けている。
当院敷地内の側溝清掃作業を実施しました
2021年06月16日
こんにちは。ついに関東甲信も梅雨入りしましたね。
これからジメジメした日が続きそうです。
さて、5月末に当院建物東側の側溝清掃と草刈りを行いました。
作業前は、側溝が見えないくらい草が生い茂っておりました。
◆◆作業前◆◆ 左側:正面玄関前、右側:救急車専用入口付近

◆◆作業後◆◆ 左側:正面玄関前、右側:救急車専用入口付近

とっても、キレイになりました!
当院を気持ちよくご利用いただけるように、環境整備に努めてまいります。
横浜医療センター附属横浜看護学校(1年生)の病棟見学
2021年06月11日
こんにちは。一段と気温が上がり、蒸し暑い日が多くなってきましたね。
今日は当院附属の看護学生の様子をご紹介したいと思います。
6月2日に1年生が初めての病棟見学を行いました。
今回は「日常生活の援助技術Ⅰ(生活環境)」という科目で、入院患者さんの療養環境の実際を理解し、患者さんに必要な生活環境の調整を考えることが目的です。
見学者は合計79名ですが、感染対策として5~6名ずつのグループを編成。
各グループに1名の教員が付き添って、いよいよ病棟の見学です。
学生の皆さんは初めての白衣に身を包み、とても緊張した面持ちで教員の説明を熱心に聞き、メモを取っていました。
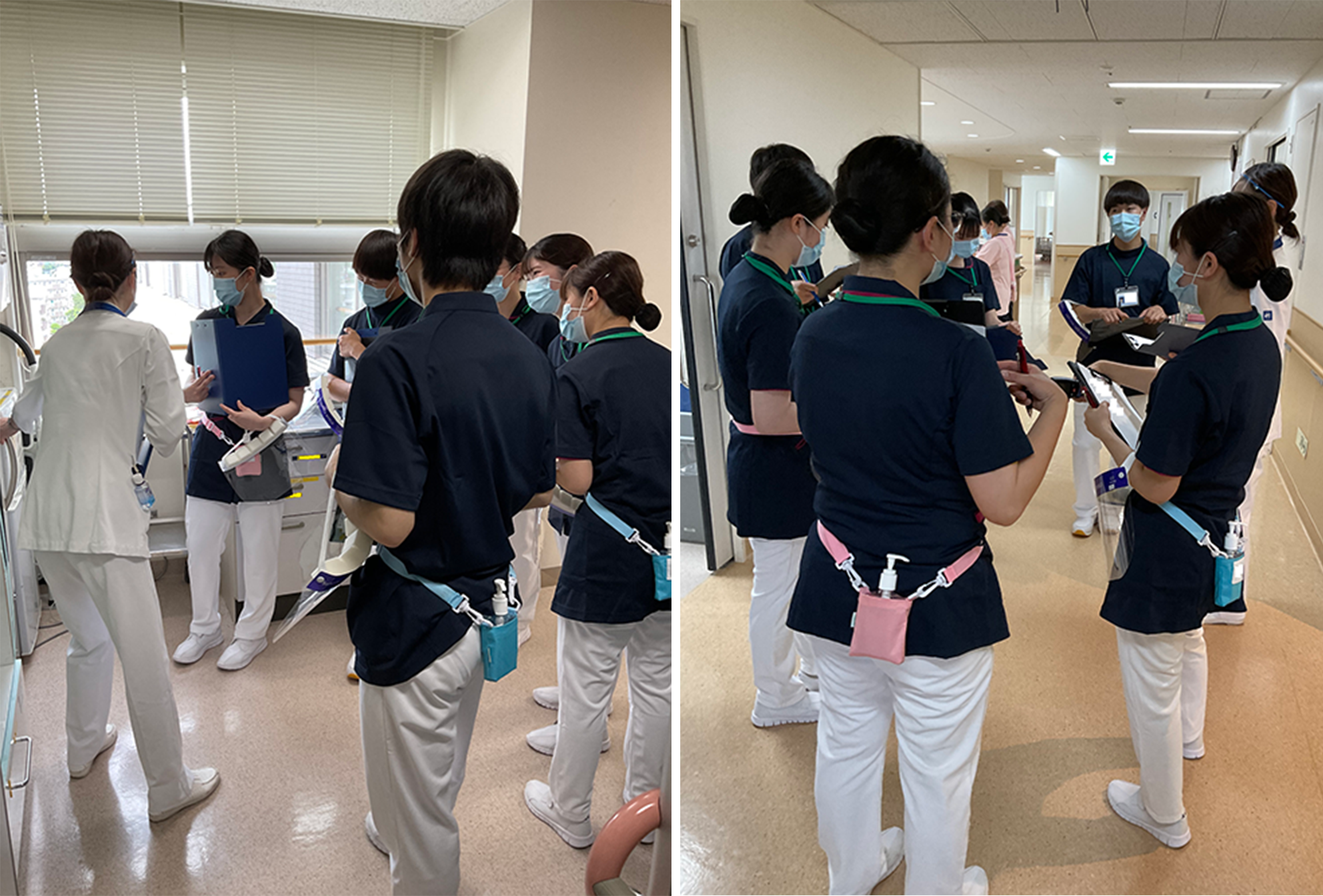
そんな姿が印象的な学生の皆さんに、病棟見学について聞いてみました。
「学んでいる内容を実際の現場で見ることになって、はじめてだったので驚くことが多かったけど、学んだことをより理解することができた。」
「こういうところで将来働くことになると思うと、もっと勉強しなければならない。」
と、より一層、気持ちを引き締めているように感じました。

そして、どんな看護師になりたいかについて聞いてみると、
「ありがちだけど、患者さんの顔色一つひとつ、少しの変化でも気づくことができる看護師になりたい。」と、凛とした眼差しの中に、強い信念を感じる言葉が返ってきました。
コロナ禍ではありますが看護の道を目指し、日々勉学に励む皆さんを応援しています!
Googleストリートビューを制作しました。
2021年06月03日
2021年5月に来院者の方々向けにGoogleMapストリートビューを制作いたしました。
当院ホームページのトップページにございます「■横浜医療センター Googleストリートビュー」から、総合受付および食堂、スタッフステーション、特別室E、CT室等をストリートビューにて閲覧できます。
当院の院外・院内の様子を知っていただくためにぜひ、ご活用ください。

紫外線照射ロボット活躍中!
2021年05月28日
当院では、院内感染対策として、自動走行式の紫外線照射ロボット(※)を2021年3月より導入し、職員の清掃消毒作業の負担が大きく軽減されました。
※紫外線で殺菌、消毒噴射で除菌をします。
なお、ロボットでは対応できない細かな場所については、職員が手による消毒作業を行っております。
入院患者様や来院者様が安心してご利用いただけるように、日々、感染対策に努めてまいります。
新しいユニフォームです。
2021年05月21日
こんにちは。
今週に入ってから、ムシムシとした日が続いていますね。
しばらくは傘が手放せない天気予報です。
さて、4月からICU(集中治療室および救急外来)のユニフォームがえんじ色主体のスクラブ(※)に変わりました。

かっこいいですね!!
以前は個々に違うものを着用していました。
揃いのユニフォームでキビキビ業務をこなす姿がまぶしいです。
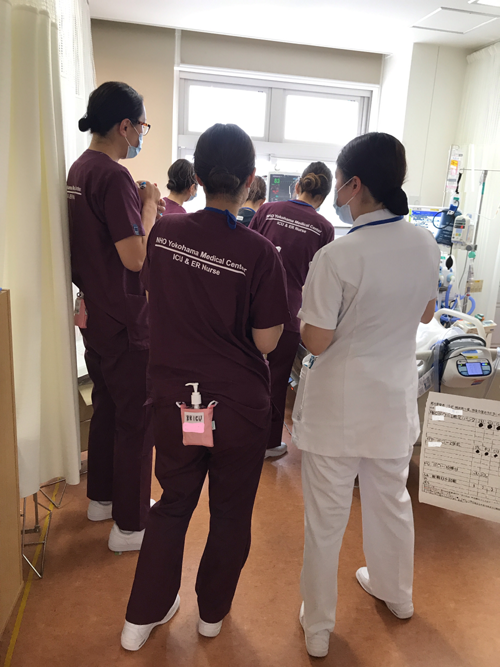
4月から仲間入りしたスタッフも、少しずつ慣れてきたようです。
ICUの師長は「視認性もあるし、気が引き締まる」と話していました。
(管理職は白衣を着用しています)
感染対策にも一層気を配りつつ、今日も当院スタッフは頑張っています!
※スクラブ=半そでで首回りがⅤネックの医療用白衣
クールビズ実施中。
2021年05月17日
5月1日から「夏の軽装(クールビズ)」を実施しています。
当院では一層の省エネルギー推進のため、職員の服装について、暑さをしのぎやすい軽装(ノーネクタイ・半袖シャツ・ポロシャツ等)を励行しております。
ご理解ご協力のほど、よろしくお願いいたします。
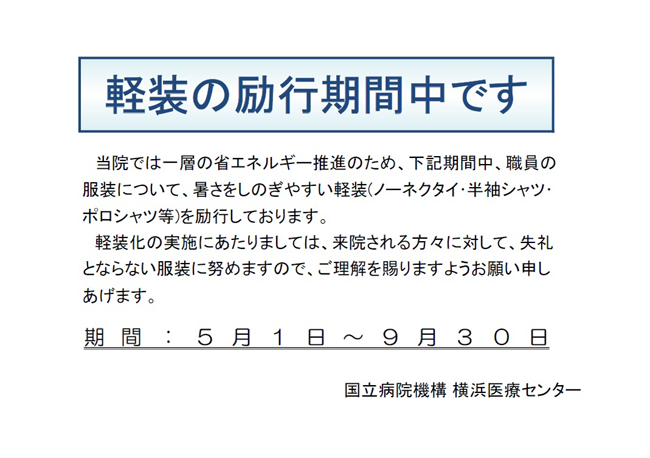
感染対策、再確認。
2021年04月26日
こんにちは。病院周辺の新緑が眩しく感じられる今日この頃です。
朝晩と日中の気温差が大きい日が続いているので、体調を崩さないようにしたいですね。
さて横浜医療センターでは、今月から大型の検温モニターを導入しました。

これまでは、お一人ずつの体温チェックでしたが、一度に複数の方のチェックが可能になりました。
入館者が集中する時間帯でもスムーズに体温チェックを行うことができます。
発熱の疑いがある方は、個別に再検温をさせていただきます。
また、非接触型の「手指消毒用アルコール自動ディスペンサー」を設置しました。

マスクの着用・検温・手指消毒は基本的な感染対策です。
慣れてくると、おざなりになりがちですが
横浜医療センターでは、引き続き感染対策をしっかり行ってまいります。